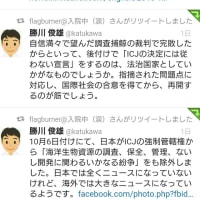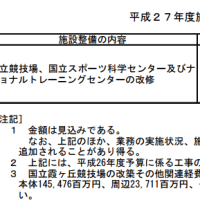今月15日になって、文化庁(Agency of Cultual Affairs)が『国語に関する世論調査』の結果を公表してたのだが・・・。
・国語世論調査:「寒っ」8割以上の人が気にならないと回答(2011年9月15日 毎日jp)
そもそも、この手の世論調査については文化庁の意向が透けて見える気がしないでもない俺。
さしあたっては、2011年9月15日分毎日jp『「寒っ」8割以上の人が~』から、前半部分を(略
---- 以下引用 ----
冷たい外気に触れた際の感覚を表現する言葉「寒(さむ)っ」について8割以上の人が気にならないと考えていることが15日、文化庁の10年度国語に関する世論調査で分かった。
「姑息(こそく)」は本来と違う意味にとらえる人が多数派を占め、「声を荒(あら)らげる」などの慣用句も誤認が多い。
いわゆる「ら抜き言葉」については使う人が増えていた。
「寒っ」については、「冬に暖房の利いた建物から気温の低い外に出た」との状況で当てはまる選択肢の回答を求めた。
冗談がつまらなかったような状況について尋ねたわけではない。
「自分も使うし、他人が言うのも気にならない」が62.8%、「自分は使わないが、他人が言うのは気にならない」が22.2%で、計85%が気にならないと答えた。
同様に形容詞を短縮させる言い方の「すごっ」「短っ」「長っ」「うるさっ」についても6割以上が気にならないとした。
形容詞「寒い」の語幹である「さむ」の用例は19世紀初頭の江戸時代からあるが、今回の調査結果について、同庁の氏原 基余司・主任国語調査官は「使われる形容詞が広がっている。テレビでもよく使われ、抵抗感がなくなっている」と話している。
(以下略)
---- 引用以上 ----
「寒っ」って、冗談がつまらない状況でも使う言葉じゃね~の?(違)
・・・話を世論調査の結果に戻す。
この調査では、密かに無視できない重要な話題も質問していた。
↓は調査結果。
・国語に関する世論調査(2010年度)(2011年9月15日 文化庁;.pdfファイル)
俺が気になったのは、『7. 国内で消滅の危機にある言語や方言』という項目。
ここでは、日本国内にある方言の認知状況について質問していたが・・・。
まずは、2011年9月15日分文化庁『国語に関する~』から、『7. 国内で消滅の危機にある言語や方言』問9 と回答を(略
---- 以下引用 ----
(中略)
ユネスコが指摘した国内で消滅の危機にある言語や方言について知っていたか<問9>(P.40)
―「知らなかった」が過半数―
〔全体〕
平成21年2月,ユネスコ(国連教育科学文化機関)が,世界で2,500に上る言語が消滅の危機にあると指摘
した際,日本国内では,アイヌ語,沖縄県の八重山語,与那国語,沖縄語,国頭(くにがみ)語,宮古語,鹿児島県奄美諸島の奄美語,東京都八丈島などの八丈語がその中に含まれていたが,日本国内にこのような消滅の危機にある言語や方言があることを知っていたかどうかを尋ねた(選択肢の中から一つ選択)。
「知らなかった」(52.6%)の割合が最も高く,「聞いたことがある」(26.6%),「知っていた」(20.1%)の順となっている。
(以下略)
---- 引用以上 ----
ちなみに、UNESCO が公開してる『世界消滅危機言語地図(Atlas of the World's Languages in Danger)』だと、アイヌ語(Ainu)は消滅の危険が非常に高い(Critically Endangered)言語になっている。
また、八重山語(Yaeyama)と与那国語(Yonaguni)は消滅の危険が割と高い(Severely endangered)言語になっている。
↓参照
・Atlas of the World's Languages in Danger(2011年9月20日最終アクセス日 unesco.org)
そもそも、俺自身こアイヌ語以外存在自体を「知らなかった」のだが(馬鹿)
・・・こういう消滅の危機にある言語についてどう考えてるかについても、例の世論調査は質問していた。
以下、2011年9月15日分文化庁『国語に関する~』から、『7. 国内で消滅の危機にある言語や方言』問10 と回答を(略
---- 以下引用 ----
(中略)
国内で消滅の危機にある言語や方言についてどのように考えるか<問10>(P.42)
― 約半数の人が「消滅しないような対策が必要である」と回答―
〔全体〕
日本国内で消滅の危機にある言語や方言について,どのように考えるかを尋ねた(選択肢の中から一つ選択)。
「そのような言語や方言が消滅しないような対策が必要である」(49.6%)の割合が最も高く,「言語や方言が消滅するのは仕方がないことなので特に対策は必要ない」(17.8%),「どちらとも言えない」(29.5%)の順となっている。
(以下略)
---- 以下引用 ----
消滅の危機にある言語や方言を保存するのかしないのかってのは、実の所簡単に答えを出せる問題じゃないんだよな。
つーのも、この問題については、「誰が」「どうやって」「誰に対して」言語や方言を伝えるのかという面を無視できないからで・・・。
これについては、問10 のおまけ(問10付)で回答者に質問していた。
以下、2011年9月15日分文化庁『国語に関する~』から、『7. 国内で消滅の危機にある言語や方言』問10付 と回答を(略
---- 以下引用 ----
どのような対策が必要だと思うか<問10付>(P.42)
― 「指導者や後継者の育成」「現状の調査」「言語や方言を知ってもらう催し」の回答が多い―
〔全体〕
問10で「そのような言語や方言が消滅しないような対策が必要である」を選択した人(49.6%)に,どのような対策が必要だと思うかを尋ねた(当てはまるものは全て選択)。
「指導者や後継者の育成」(54.0%)と答えた人の割合が最も高く,以下,「現状を把握するための調査」(47.1%),「その言語や方言を知ってもらうための催し」(44.4%)の順となっている。
・指導者や後継者の育成:54.0%
・現状を把握するための調査:47.1%
・その言語や方言を知ってもらうための催し:44.4%
・地域や民間による方言教室などの取組:32.5%
・学校教育での指導:32.0%
・優れた取組に対する国からの経済的支援:15.2%
・優れた取組に対する国からの表彰:5.6%
・「方言の日」等の制定:5.6%
(以下略)
---- 引用以上 ----
学校教育で、か。
確かに、消滅する危険のある言語や方言の存在を伝えるという意味では有効な手段と言える。
が、同時に、そうした言語や方言の歴史的文脈や文化的背景も伝えなければ、知ってもらうという面では不十分かと。
となれば、学校教育でそれを伝えるには相当の努力が必要になりそう・・・。
一方、そうした言語や方言を保存するといっても、現実社会で使われ続けない限り独特の世界で生き続ける言語や方言になる可能性が大きいわけで。
しかし、それは、本当の意味で言語や方言を保存することになるのか?
俺には見当がつかない・・・。
それはそうと。
この世論調査について、天下の3K新聞は不思議な見解を示していた。
・国語世論調査 日本語の「性差」を大切に(2011年9月20日 MSN産経ニュース)
タイトルオチという気がするこの論説。
だが、後半になると、世論調査で男女間で言語の使用状況に差がなくなっていることを指摘した上で、頭が痛くなるような論を展開していた。
以下、2011年9月20日分 MSN産経ニュース『国語世論調査 日本語の「性差」を大切に』から、終盤部分を(略
---- 以下引用 ----
(中略)
昨今は女性タレントらがテレビ番組で「お前」「腹減った」などと口にし、その影響だろうか、電車内でも女子高生らが実に乱暴な言葉遣いをして周りの顰蹙(ひんしゅく)を買っている。
男女には肉体や声質の違いがあるのと同様に、それぞれの性に備わった精神的個性がある。
日本語の大きな特色でもある性差に基づいた言葉遣いも個性の一つで、それが繊細にして豊かな情感をもたらしてくれる。
男女同一の言葉はむしろ、互いの美質を尊重する男女共生の精神に反しよう。
言葉は歴史と文化そのものである。
男女の「らしさ」を失った深みのない言葉遣いこそ「日本語の乱れ」であると、深刻に受け止めるべきではなかろうか。
---- 引用以上 ----
・・・こっそりと性差別を助長する論を展開するなよ(怒)
・国語世論調査:「寒っ」8割以上の人が気にならないと回答(2011年9月15日 毎日jp)
そもそも、この手の世論調査については文化庁の意向が透けて見える気がしないでもない俺。
さしあたっては、2011年9月15日分毎日jp『「寒っ」8割以上の人が~』から、前半部分を(略
---- 以下引用 ----
冷たい外気に触れた際の感覚を表現する言葉「寒(さむ)っ」について8割以上の人が気にならないと考えていることが15日、文化庁の10年度国語に関する世論調査で分かった。
「姑息(こそく)」は本来と違う意味にとらえる人が多数派を占め、「声を荒(あら)らげる」などの慣用句も誤認が多い。
いわゆる「ら抜き言葉」については使う人が増えていた。
「寒っ」については、「冬に暖房の利いた建物から気温の低い外に出た」との状況で当てはまる選択肢の回答を求めた。
冗談がつまらなかったような状況について尋ねたわけではない。
「自分も使うし、他人が言うのも気にならない」が62.8%、「自分は使わないが、他人が言うのは気にならない」が22.2%で、計85%が気にならないと答えた。
同様に形容詞を短縮させる言い方の「すごっ」「短っ」「長っ」「うるさっ」についても6割以上が気にならないとした。
形容詞「寒い」の語幹である「さむ」の用例は19世紀初頭の江戸時代からあるが、今回の調査結果について、同庁の氏原 基余司・主任国語調査官は「使われる形容詞が広がっている。テレビでもよく使われ、抵抗感がなくなっている」と話している。
(以下略)
---- 引用以上 ----
「寒っ」って、冗談がつまらない状況でも使う言葉じゃね~の?(違)
・・・話を世論調査の結果に戻す。
この調査では、密かに無視できない重要な話題も質問していた。
↓は調査結果。
・国語に関する世論調査(2010年度)(2011年9月15日 文化庁;.pdfファイル)
俺が気になったのは、『7. 国内で消滅の危機にある言語や方言』という項目。
ここでは、日本国内にある方言の認知状況について質問していたが・・・。
まずは、2011年9月15日分文化庁『国語に関する~』から、『7. 国内で消滅の危機にある言語や方言』問9 と回答を(略
---- 以下引用 ----
(中略)
ユネスコが指摘した国内で消滅の危機にある言語や方言について知っていたか<問9>(P.40)
―「知らなかった」が過半数―
〔全体〕
平成21年2月,ユネスコ(国連教育科学文化機関)が,世界で2,500に上る言語が消滅の危機にあると指摘
した際,日本国内では,アイヌ語,沖縄県の八重山語,与那国語,沖縄語,国頭(くにがみ)語,宮古語,鹿児島県奄美諸島の奄美語,東京都八丈島などの八丈語がその中に含まれていたが,日本国内にこのような消滅の危機にある言語や方言があることを知っていたかどうかを尋ねた(選択肢の中から一つ選択)。
「知らなかった」(52.6%)の割合が最も高く,「聞いたことがある」(26.6%),「知っていた」(20.1%)の順となっている。
(以下略)
---- 引用以上 ----
ちなみに、UNESCO が公開してる『世界消滅危機言語地図(Atlas of the World's Languages in Danger)』だと、アイヌ語(Ainu)は消滅の危険が非常に高い(Critically Endangered)言語になっている。
また、八重山語(Yaeyama)と与那国語(Yonaguni)は消滅の危険が割と高い(Severely endangered)言語になっている。
↓参照
・Atlas of the World's Languages in Danger(2011年9月20日最終アクセス日 unesco.org)
そもそも、俺自身こアイヌ語以外存在自体を「知らなかった」のだが(馬鹿)
・・・こういう消滅の危機にある言語についてどう考えてるかについても、例の世論調査は質問していた。
以下、2011年9月15日分文化庁『国語に関する~』から、『7. 国内で消滅の危機にある言語や方言』問10 と回答を(略
---- 以下引用 ----
(中略)
国内で消滅の危機にある言語や方言についてどのように考えるか<問10>(P.42)
― 約半数の人が「消滅しないような対策が必要である」と回答―
〔全体〕
日本国内で消滅の危機にある言語や方言について,どのように考えるかを尋ねた(選択肢の中から一つ選択)。
「そのような言語や方言が消滅しないような対策が必要である」(49.6%)の割合が最も高く,「言語や方言が消滅するのは仕方がないことなので特に対策は必要ない」(17.8%),「どちらとも言えない」(29.5%)の順となっている。
(以下略)
---- 以下引用 ----
消滅の危機にある言語や方言を保存するのかしないのかってのは、実の所簡単に答えを出せる問題じゃないんだよな。
つーのも、この問題については、「誰が」「どうやって」「誰に対して」言語や方言を伝えるのかという面を無視できないからで・・・。
これについては、問10 のおまけ(問10付)で回答者に質問していた。
以下、2011年9月15日分文化庁『国語に関する~』から、『7. 国内で消滅の危機にある言語や方言』問10付 と回答を(略
---- 以下引用 ----
どのような対策が必要だと思うか<問10付>(P.42)
― 「指導者や後継者の育成」「現状の調査」「言語や方言を知ってもらう催し」の回答が多い―
〔全体〕
問10で「そのような言語や方言が消滅しないような対策が必要である」を選択した人(49.6%)に,どのような対策が必要だと思うかを尋ねた(当てはまるものは全て選択)。
「指導者や後継者の育成」(54.0%)と答えた人の割合が最も高く,以下,「現状を把握するための調査」(47.1%),「その言語や方言を知ってもらうための催し」(44.4%)の順となっている。
・指導者や後継者の育成:54.0%
・現状を把握するための調査:47.1%
・その言語や方言を知ってもらうための催し:44.4%
・地域や民間による方言教室などの取組:32.5%
・学校教育での指導:32.0%
・優れた取組に対する国からの経済的支援:15.2%
・優れた取組に対する国からの表彰:5.6%
・「方言の日」等の制定:5.6%
(以下略)
---- 引用以上 ----
学校教育で、か。
確かに、消滅する危険のある言語や方言の存在を伝えるという意味では有効な手段と言える。
が、同時に、そうした言語や方言の歴史的文脈や文化的背景も伝えなければ、知ってもらうという面では不十分かと。
となれば、学校教育でそれを伝えるには相当の努力が必要になりそう・・・。
一方、そうした言語や方言を保存するといっても、現実社会で使われ続けない限り独特の世界で生き続ける言語や方言になる可能性が大きいわけで。
しかし、それは、本当の意味で言語や方言を保存することになるのか?
俺には見当がつかない・・・。
それはそうと。
この世論調査について、天下の3K新聞は不思議な見解を示していた。
・国語世論調査 日本語の「性差」を大切に(2011年9月20日 MSN産経ニュース)
タイトルオチという気がするこの論説。
だが、後半になると、世論調査で男女間で言語の使用状況に差がなくなっていることを指摘した上で、頭が痛くなるような論を展開していた。
以下、2011年9月20日分 MSN産経ニュース『国語世論調査 日本語の「性差」を大切に』から、終盤部分を(略
---- 以下引用 ----
(中略)
昨今は女性タレントらがテレビ番組で「お前」「腹減った」などと口にし、その影響だろうか、電車内でも女子高生らが実に乱暴な言葉遣いをして周りの顰蹙(ひんしゅく)を買っている。
男女には肉体や声質の違いがあるのと同様に、それぞれの性に備わった精神的個性がある。
日本語の大きな特色でもある性差に基づいた言葉遣いも個性の一つで、それが繊細にして豊かな情感をもたらしてくれる。
男女同一の言葉はむしろ、互いの美質を尊重する男女共生の精神に反しよう。
言葉は歴史と文化そのものである。
男女の「らしさ」を失った深みのない言葉遣いこそ「日本語の乱れ」であると、深刻に受け止めるべきではなかろうか。
---- 引用以上 ----
・・・こっそりと性差別を助長する論を展開するなよ(怒)