白百合と菊Lys et Chrysanthèmeさんの、ビルコック(Billecocq)神父様による哲学の講話をご紹介します。
※この公教要理は、 白百合と菊Lys et Chrysanthèmeさんのご協力とご了承を得て、多くの皆様の利益のために書き起こしをアップしております
Billecocq神父に哲学の講話を聴きましょう
ルソーに関する講話を続けましょう。
今晩は、ちょっと特別な著作に関することをご紹介したいと思います。『エミール』です。これを中心にお話しします。この本の副題は「教育について」です。比較的に長い著作ですから、手元にお配りした資料に、今回、多く引用を載せました。もっと多くの引用をご紹介したかったのですが時間の問題で絞りました。
『エミール』は長い分、それだけ面白い点も多くあります。ご紹介に当たって、お配りした資料を読みながら、『エミール』におけるルソーの思想をよく把握するために一番役立つ点を取り上げます。
1756年、ド・シュノンソ(de Chenonceaux)婦人より、ルソーは教育に関する質問を受けていました。その依頼に応じるために、ルソーは『エミール』を書きました。
数年後、それを出版します。ルソーは次のようにこの著作を紹介します。自分で書いた面白い紹介文です。
「これから、教育論みたいな本を出版することになり、その中で私がいつも夢見ている空想を盛り込んだ。」(Jacob Vernetへの書簡、1760年11月29日)これは、ルソーによる『エミール』についてのまさに完璧な要約です。「いつも夢見ている空想を盛り込んだ」と。
教育論の依頼は1756年でしたが、『エミール 教育について』の出版は1762年5月でした。出版されてすぐ、話題となり、論争の対象となります。その著作はかなり批判されました。政府は書籍の在庫を没収し、ソルボンヌ大学は1762年6月、『エミール』を正式に否認しました。
1762年5月に出版され、同年6月7日ソルボンヌ大学からの否認に続いて、二日後、パリ高等法院(国王の権威を代理する裁判所)も『エミール』を否認する、と発表します。なかなかの大騒ぎであるのも想像に難くありません。
そこでルソーは逃げざるを得なくなります。ヌフシャテル(Neufchatel)へ避難することになりました。しかしながら、世間では『エミール』による余波は4年間ほど、1766年まで続きました。
さて1766年、ルソーが英国へ移住すると、一旦『エミール』に関する世間の動揺は落ち着きます。そういえば、ヴォルテールは全力を尽くしてルソーを非難し、ルソーへの害を図りました。というのも、ヴォルテールは、自分の広い人脈を活かして、諸国のあちこちの裁判所でルソーを告訴させるように、厳しい判決が下るように全力を尽くしたからです。ヴォルテールにはルソーによる「教育論」が気に入らなかったようです。
ある意味では信じられないことかもしれませんが、それほど世間は動揺しており、正面から非難されたにもかかわらず、『エミール』は後世においてかなりの影響を及ぼすようになりました。その意味で、ルソーが夢見て訴えている教育論からの支配を、現代でも私たちはかなり受けているといわざるを得ません。
また、『エミール』は単なる教育論にとどまらず、ルソーの全思想を総括するような著作でもあります。その意味で、面白いことに『エミール』を検討することによって、前にすでにご紹介したいくつかの要素・特徴が再確認されます。
ルソーの思想の諸原理が『エミール』において、もう一度、主張されていることは明らかです。さらに言うと、『エミール』においては、ルソーの思想が教育について適用されているので、ほかの著作よりもその分、より具体的に紹介されて分かりやすいかもしれません。
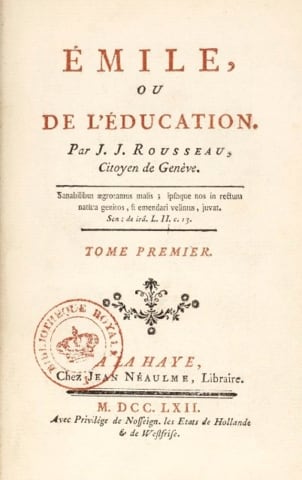
『エミール』はまた、『社会契約論』の続きでもあります。というのも、『社会契約論』において、ルソーは社会を対象に検討し、全人類に関することについて論及するのに対し、『エミール』では、教育論として、個人を中心に検討して論及していきます。
つまり、『社会契約論』と同じ人間観をもって個人の教育が論じられ、『社会契約論』において紹介されている社会の中で、個人がいずれか生活せざるを得ないという観点からも書かれています。
ある面、逆説的に見えます。ルソーは社会を否定していますが、『エミール』においては、教育論の目的として、社会とは非常な悪であるが、それでも個人が社交生活し、社会において何とか生きていけるように助けるべきであるとします。
しかし、問題はそこから出てきます。社会において生きる必要があるという前提に立つならば生徒を社会において教育すべきなのに、ルソーはその社会を否定して、社会の外での教育を提案し、これを「自然な教育」と呼ぶからです。ただし、「自然な教育」なのに、その教育の目的の一つは一応社交のできる大人になるように、社会において何とか活きられるようにとの教育論でもあります。
長い著作なので、多くの意見が出たりしまして、時々自ら矛盾している論及も少なくありません。Jean de Viguerie著の『教育論者』という立派な著作において、ルソーに関する章があります。ぜひとも、それを読んでいただけたらと思っております。というのも、10枚数だけで、今晩の一時間ぐらいの講話のすべてを要約してあります。
では、ルソーの教育論の問題点を取り上げましょう。まず、ルソー自身はまともな教育を受けていません。自分の母をほとんど知らなかったのです。母は家を出て、ルソーを見捨てましたから。また、ルソーには何人の子供が生まれましたが、生まれてすぐの自分の子を見捨てて教育しなかったのです。
また、一応、ルヴァサー(Levasseur)という女性と結婚していましたが、ルソーは、人生において付き合った女性たちと一緒に、本物の家庭や夫婦的な愛を経験したことはありませんでした。ルソーは付き合っていても、あまり真面目になれず、軽い恋愛の連続ばかりです。つまり、教育について説明するには、ルソーの立場は非常に悪いわけです。
次にJean de Viguerie氏を引用します。
「これは、教育論の中でも一番驚くべき本でしょう。著者は子供を育てた経験もありません。ルヴァサー(Levasseur)との間に5人の子供が生まれましたが、全員を保護所へ預ける形で見捨てました。非常勤という形での家庭教師の少ない経験を除けば、教師の経験は全くありません。ルソー自身、家庭教師の仕事が提案されたときに拒否したと自分自身が認めて次のように明かしています。「私には家庭教師の職に向いていない」と。」
『エミール』は文章としてはよくできています。書きぶりはやはり上手で、ルソーの筆は達者です。抒情的な文章だといっても過言ではありません。
『エミール』は小説であることを忘れてはいけません。教育に関する小説です。つまり、ルソーは夢の中でだけ経験した理想的な教育を描いている小説なのです。ルソーは現実に経験したことがない夢を教えようとしています。あえて言えば、『エミール』はルソーのダメな悲しい人生を埋め合わせるための空想論だといえましょう。このような思考様式で『エミール』を書くのです。
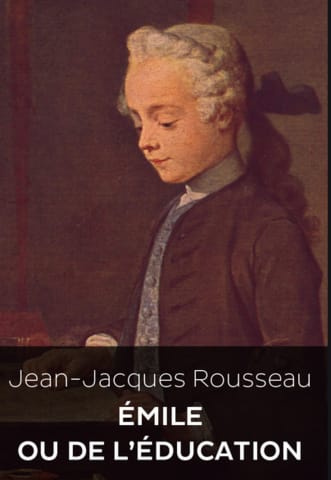
それから、著作の構造を見ましょう。五編からなっています。ルソーに言わせれば、編は人生の一般の五段階の一つ一つの段階により構成されています。つまり、ルソーは人生を五つの時期に分けます。生まれてから結婚までに人生を五つの時期に分けます。
小説の最後、エミールは結婚して父となって社会において生活しており、そこまでです。五編です。一遍ずつご紹介できればと思っておりますが、主に第一編から第三編までを中心にご紹介します。
教育論でいうと、一番大事なのは最初の二編です。そこに、ルソー思想のすべての諸原理が収まっているからです。第四編は宗教論を中心に語るのですが、次回にそれを中心に紹介する予定です。ルソーの宗教論に関する『サヴォアの主任司祭の信仰宣言』という大事な文書は、第四編にあるからです。
最後に、第五編についてほんの少しだけ触れることになりますが、ルソーの教育論においていよいよ一人の女性、唯一の女性が登場する場面です。エミールの結婚のために登場せざるを得ないのですが、ルソーは女性の教育に関してそもそも興味がありません。第五編は小説であって、次に書く『新エロイーズ』へとつながる結びだといってもよいでしょう。
要するに、五編からなっています。登場人物は厳密にいうと二人ですが、結局、三人です。これは面白い現象です。主人公はフィクション上のエミールという子供です。それから、エミールの家庭教師という人物も登場します。ですから、『エミール』は二人だけの登場人物の演劇なのです。
しかしながら、もう一人の登場人物も出てきます。それはルソー自身です。というのも、頻繁に家庭教師の代わりに、ルソー自身が宣言したりします。「家庭教師は」と言わないで、よく「私は」と書くのですから。要するに、登場人物は二人いて、見方によって三人がいます。
小説の目的は幼いエミールを育てることにあります。そして、エミールを大人にすることが目的です。ルソーに言わせれば、「大人にする」のはどういう意味なのかというと、「よく生きる」ようにするということです。これが、小説の目的です。
ルソー曰く「生きるとは職業だ。」 また「(生きるとは)体の器官や感覚やすべての能力を作用することだ 。生きることは感じること 。」また「生きることだけを望む人は幸いになる。」と。
エミールという子供は家庭教師の完全な支配の下に置かれていて、家庭教師はいつも彼のそばにいます。家庭教師はエミールが自由であることをエミールに思い込ませながら、実際にはエミールは自由ではないというのが小説の中心テーマです。
それでは、第一編に入りましょう。幼児期前期についてです。お配りした引用は編ごとに纏まってあります。多すぎてすべてを読めないのですが、ご参考のまで、編ごとに、『エミール』の流れに沿って引用を纏めました。
『エミール』の第一編の最初の文書から引用します。
「万物を創る者の手をはなれるときすべては良いものであるが、人間の手にうつるとすべてが悪くなる。」
『社会契約論』を思い出してみると、この二行でもうルソーの思想のすべてですね。この二行に『社会契約論』が要約されています。万物を創る者は良く万物を創り、自然は良いが、「人間の手にうつるとすべてが悪くなる」ということで、人間は自然を堕落させるということを言います。
前回に見たように、ルソーの第一の前提は「人間の本性は善である」です。従って、これの単なる帰結ですが、教育論では、「子供も生まれながら自然に善良な者」という前提を置きます。そして、これの対称となるもう一つの前提は「社会は堕落をもたらす」です。つまり、社会において生きている人間は社会によって堕落させられているということを前提にしているのです。
この二つの前提を見るだけで矛盾があります。もしも本当に人間が生まれながら自然に良ければ、つまり、人間本性が絶対に善だったら、一体どうやって社会は人間を堕落させうるのでしょうか、それは不明のままです。
というのも、社会は人間より前に存在しないのなら、また人々の集まりによって構成されていないのなら(それはもちろんあり得ない仮説ですが)、そもそも良い人々を堕落させることはあり得ないはずです。
なぜかというと、社会はそもそも人々の結合ですから。そもそも良い人々ばかり集まったら、一体なぜ良い人々のままにいられなくなるでしょうか?あるいは、一体なぜ本当に良い人々は集まるだけで必ず悪くなれるでしょうか。どう見ても、結局、逆説的な前提です。
共同生活しているせいで、人々は悪くなるとは?ルソーはそのあたりについて明らかにしていないのです。社会から生じる悪はどこに由来するのでしょうか?『社会契約論』においては「所有権」に由来していると言っていました。根拠はそれだけです。ルソーはほかに理屈を見つけていません。結局、人間はそもそも良い存在なのに、悪い存在になっているという矛盾があります。
「人間の手にうつるとすべてが悪くなる。人間はある土地にほかの土地の産物を作らせたり、ある木に他の木の実をならせたりする。風土、環境、季節をごちゃまぜにする。犬、馬、奴隷をかたわにする。すべてのものをひっくりかえし、すべての物の形を変える。人間はみにくいもの、怪物を好む。何一つ自然がつくったままにしておかない。人間そのものさえそうだ。人間も乗馬のように調教しなければならない。庭木みたいに、すきなようにねじまげなければならない。」
人間はそもそも良いものでありながら、社会は人間を堕落させているという前提に立つルソーは、人間を教育するために、大人にするためにどうすべきかというと次のようにいいます。すなわち、社会から子供を離れて彼を一人にして、社会抜きに教育すべきだという対策を打ち出します。そうしながらも、いずれか社交がでてくるから、子が社交できるようにすべきだと。
「こんにちのような状態にあっては、生まれた時からほかの人々の中にほうり出されている人間は、誰よりもゆがんだ人間になるだろう。偏見、権威、必然、実例、私たちを押さえつけているいっさいの社会制度がその人の自然をしめころし、そのかわりに、何ももたらさないことになるだろう。」
このようにして、ルソーは、社会において子供を教育すると子供は堕落するとします。
「自然はたまたま道のまんなかに生えた小さな木のように、通行人に踏みつけられ、あらゆる方向に折り曲げられて、間もなく枯れてしまうだろう。」
したがって、人間を教育するために社会から離れる必要があるとします。次の引用を飛ばしますが、そのあとの引用はこうです。
「この教育は、自然か人間か事物から私たちのところに来ている。」
つまり、人間を教育するために社会から離れ、子供の教育者とは、次の三つの現実だとします。
第一、自然。それは「人間の本性」という意味で、自分の本性です。
第二、人間。理想的な教育を受けているエミールでさえ、ある種の社会から逃れようがない、これはルソーでさえ認めていることです。教育を受けるために、最低限、家庭教師が必要とされているから、どうしても社会はいつのまにか再登場します。従って、社会から子供を完全に離れることは不可能です。ルソーは最低限の社会にすることにしています。子供ともう一人と二人きりの社会にします。そういえば、小説のすべてはエミールとその家庭教師の関係を語ることになっています。ちなみに、その家庭教師には名前がないのです。ルソー曰く、「私だ」ということで、実際、ルソーです。
第三、事物。それは、エミールの周辺にある環境を指します。周辺の自然です。
要するに、第一、自分自身の内面にある本性(自然)。第二、家庭教師、第三、周辺の自然です。
「私たちの能力と器官の内部的発展は、自然の教育である。この発展をいかに利用すべきかを教えるのは人間の教育である。私たちを刺激する事物について私たち自身の経験が獲得するのは事物の教育である。」
これは非常に面白いことです。ルソーにとって第一、発展すべき能力と器官とは、自分自身の中にあるのですね。ですから、結局、第一の教育者は自分自身だということです。
それから、それらの能力をいかに「利用すべきか」は他人から教わるということになっています。ここは要注意です。ルソーは能力をいかに「利用」するかということだけを取り上げます。いかに利用するか。しかし能力は何を対象にしているかあるいは他の対象にすべきか否かに関しては、全く無視されています。
ご存じのように、私たちのすべての能力は、ある特定の対象のために備わっているわけです。つまり、私たちには多くの能力があります。例えば、知性や意志や諸感覚などは備わっています。能力と呼ばれています。これは「何かを知る機能」あるいは「何かを作用する(働く)機能」という意味での能力です。
そして、それらの能力はある対象を目的にしています。つまりある対象に従っての能力です。例えば、知性という能力は本性的に真理に向かわせてあります。意志なら、善に向かいます。それより簡単な例を挙げると、「目」は視覚のためにあります。つまり、色のついた物体を見るためです。「聴覚」は「音」という対象に向かわせてあります。
しかしながら、『エミール』において、教育者の仕事はそれぞれの能力にふさわしい対象を与えることではありません。しかし能力を養う相応しい対象を与えるのは本来の教育であるはずです。
しかしながら、『エミール』においてそうではなく、教育者は能力の利用だけを指導しますが、能力の対象を全く与えないのです。それは自然が自然に対象を与えられているから、です。ルソーはその理屈を出します。少しずつ見えてきたでしょうか。
また後述しますが、これはルソーの教育論の基盤です。つまり、ルソーの教育論では、「教育者」は対象を「教えない」のです。いや、さらに言うと教えてはならないのです。指導するにとどまるべきだと。
「教える」と「指導する」という違いは非常に大事です。一言でいうと、教育者は「真理を教える」ことではなくして、「子供が自分の力で真理を見つけるべきだ」と。本来の教育の完全な転倒です。
御覧の通り、現代ではどれほど一般の教育論はルソー主義になっているかは自明でしょう。
「ですから、この本来の傾向にすべて(の能力)を結び付けなければならないのだが」
要するに、ある種の主観主義です。「ある種の」ですけど、そこまで言わなくても、少なくとも個人主義であることは確かです。こういったような原理に基づくと、必然的に、人々は「私だけの真理を作る」と言い出すことになってしまうしかありません。
こういった教育論の遠い帰結は「真理を相対化する」ということです。一人一人がそれぞれ違う真理を持つことになります。その結果、真理という概念自体は破壊されています。なぜかというと、すべての真理は相対的なものだったら、あることとその逆のことを同時に肯定できるということになりからです。
ですから、真理自体という概念を否定することになりますし、また実際において、いずれか現実にぶつかります。当然、相対化には限界があるのです。矛盾している「真理」が同時に二つあるのはあり得ないからです。それぞれの人々に違う真理がある、と思い込んでしまうと、真理は相対化されて、「真理は存在しない」と断言することと同然になります。
また、人は真理を決めることができるということを断言するようなことですから、「人は神になる」ということをも意味しています。従って、ルソー論だと、自分にとって自分は神です。それから、必然的に、自分が神ならば、神なる自分を他人に無理やりに認めさせるようになるしかありません。ですから、その時、確かに社会は息苦しくなってもおかしくありませんね。
要約すると、自然すなわち能力。人間すなわち家庭教師。それから事物がルソーの教育の三つの先生でした。
・・・続く
※この公教要理は、 白百合と菊Lys et Chrysanthèmeさんのご協力とご了承を得て、多くの皆様の利益のために書き起こしをアップしております
Billecocq神父に哲学の講話を聴きましょう
ルソーに関する講話を続けましょう。
今晩は、ちょっと特別な著作に関することをご紹介したいと思います。『エミール』です。これを中心にお話しします。この本の副題は「教育について」です。比較的に長い著作ですから、手元にお配りした資料に、今回、多く引用を載せました。もっと多くの引用をご紹介したかったのですが時間の問題で絞りました。
『エミール』は長い分、それだけ面白い点も多くあります。ご紹介に当たって、お配りした資料を読みながら、『エミール』におけるルソーの思想をよく把握するために一番役立つ点を取り上げます。
1756年、ド・シュノンソ(de Chenonceaux)婦人より、ルソーは教育に関する質問を受けていました。その依頼に応じるために、ルソーは『エミール』を書きました。
数年後、それを出版します。ルソーは次のようにこの著作を紹介します。自分で書いた面白い紹介文です。
「これから、教育論みたいな本を出版することになり、その中で私がいつも夢見ている空想を盛り込んだ。」(Jacob Vernetへの書簡、1760年11月29日)これは、ルソーによる『エミール』についてのまさに完璧な要約です。「いつも夢見ている空想を盛り込んだ」と。
教育論の依頼は1756年でしたが、『エミール 教育について』の出版は1762年5月でした。出版されてすぐ、話題となり、論争の対象となります。その著作はかなり批判されました。政府は書籍の在庫を没収し、ソルボンヌ大学は1762年6月、『エミール』を正式に否認しました。
1762年5月に出版され、同年6月7日ソルボンヌ大学からの否認に続いて、二日後、パリ高等法院(国王の権威を代理する裁判所)も『エミール』を否認する、と発表します。なかなかの大騒ぎであるのも想像に難くありません。
そこでルソーは逃げざるを得なくなります。ヌフシャテル(Neufchatel)へ避難することになりました。しかしながら、世間では『エミール』による余波は4年間ほど、1766年まで続きました。
さて1766年、ルソーが英国へ移住すると、一旦『エミール』に関する世間の動揺は落ち着きます。そういえば、ヴォルテールは全力を尽くしてルソーを非難し、ルソーへの害を図りました。というのも、ヴォルテールは、自分の広い人脈を活かして、諸国のあちこちの裁判所でルソーを告訴させるように、厳しい判決が下るように全力を尽くしたからです。ヴォルテールにはルソーによる「教育論」が気に入らなかったようです。
ある意味では信じられないことかもしれませんが、それほど世間は動揺しており、正面から非難されたにもかかわらず、『エミール』は後世においてかなりの影響を及ぼすようになりました。その意味で、ルソーが夢見て訴えている教育論からの支配を、現代でも私たちはかなり受けているといわざるを得ません。
また、『エミール』は単なる教育論にとどまらず、ルソーの全思想を総括するような著作でもあります。その意味で、面白いことに『エミール』を検討することによって、前にすでにご紹介したいくつかの要素・特徴が再確認されます。
ルソーの思想の諸原理が『エミール』において、もう一度、主張されていることは明らかです。さらに言うと、『エミール』においては、ルソーの思想が教育について適用されているので、ほかの著作よりもその分、より具体的に紹介されて分かりやすいかもしれません。
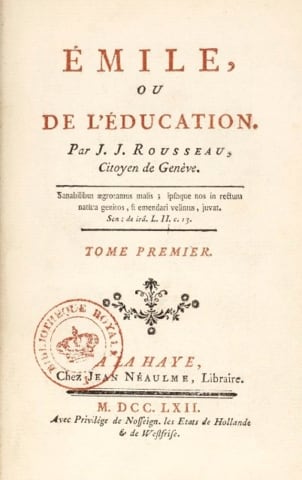
『エミール』はまた、『社会契約論』の続きでもあります。というのも、『社会契約論』において、ルソーは社会を対象に検討し、全人類に関することについて論及するのに対し、『エミール』では、教育論として、個人を中心に検討して論及していきます。
つまり、『社会契約論』と同じ人間観をもって個人の教育が論じられ、『社会契約論』において紹介されている社会の中で、個人がいずれか生活せざるを得ないという観点からも書かれています。
ある面、逆説的に見えます。ルソーは社会を否定していますが、『エミール』においては、教育論の目的として、社会とは非常な悪であるが、それでも個人が社交生活し、社会において何とか生きていけるように助けるべきであるとします。
しかし、問題はそこから出てきます。社会において生きる必要があるという前提に立つならば生徒を社会において教育すべきなのに、ルソーはその社会を否定して、社会の外での教育を提案し、これを「自然な教育」と呼ぶからです。ただし、「自然な教育」なのに、その教育の目的の一つは一応社交のできる大人になるように、社会において何とか活きられるようにとの教育論でもあります。
長い著作なので、多くの意見が出たりしまして、時々自ら矛盾している論及も少なくありません。Jean de Viguerie著の『教育論者』という立派な著作において、ルソーに関する章があります。ぜひとも、それを読んでいただけたらと思っております。というのも、10枚数だけで、今晩の一時間ぐらいの講話のすべてを要約してあります。
では、ルソーの教育論の問題点を取り上げましょう。まず、ルソー自身はまともな教育を受けていません。自分の母をほとんど知らなかったのです。母は家を出て、ルソーを見捨てましたから。また、ルソーには何人の子供が生まれましたが、生まれてすぐの自分の子を見捨てて教育しなかったのです。
また、一応、ルヴァサー(Levasseur)という女性と結婚していましたが、ルソーは、人生において付き合った女性たちと一緒に、本物の家庭や夫婦的な愛を経験したことはありませんでした。ルソーは付き合っていても、あまり真面目になれず、軽い恋愛の連続ばかりです。つまり、教育について説明するには、ルソーの立場は非常に悪いわけです。
次にJean de Viguerie氏を引用します。
「これは、教育論の中でも一番驚くべき本でしょう。著者は子供を育てた経験もありません。ルヴァサー(Levasseur)との間に5人の子供が生まれましたが、全員を保護所へ預ける形で見捨てました。非常勤という形での家庭教師の少ない経験を除けば、教師の経験は全くありません。ルソー自身、家庭教師の仕事が提案されたときに拒否したと自分自身が認めて次のように明かしています。「私には家庭教師の職に向いていない」と。」
『エミール』は文章としてはよくできています。書きぶりはやはり上手で、ルソーの筆は達者です。抒情的な文章だといっても過言ではありません。
『エミール』は小説であることを忘れてはいけません。教育に関する小説です。つまり、ルソーは夢の中でだけ経験した理想的な教育を描いている小説なのです。ルソーは現実に経験したことがない夢を教えようとしています。あえて言えば、『エミール』はルソーのダメな悲しい人生を埋め合わせるための空想論だといえましょう。このような思考様式で『エミール』を書くのです。
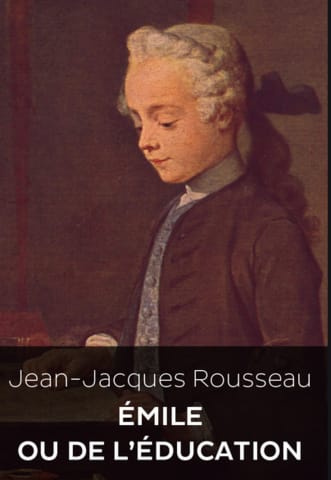
それから、著作の構造を見ましょう。五編からなっています。ルソーに言わせれば、編は人生の一般の五段階の一つ一つの段階により構成されています。つまり、ルソーは人生を五つの時期に分けます。生まれてから結婚までに人生を五つの時期に分けます。
小説の最後、エミールは結婚して父となって社会において生活しており、そこまでです。五編です。一遍ずつご紹介できればと思っておりますが、主に第一編から第三編までを中心にご紹介します。
教育論でいうと、一番大事なのは最初の二編です。そこに、ルソー思想のすべての諸原理が収まっているからです。第四編は宗教論を中心に語るのですが、次回にそれを中心に紹介する予定です。ルソーの宗教論に関する『サヴォアの主任司祭の信仰宣言』という大事な文書は、第四編にあるからです。
最後に、第五編についてほんの少しだけ触れることになりますが、ルソーの教育論においていよいよ一人の女性、唯一の女性が登場する場面です。エミールの結婚のために登場せざるを得ないのですが、ルソーは女性の教育に関してそもそも興味がありません。第五編は小説であって、次に書く『新エロイーズ』へとつながる結びだといってもよいでしょう。
要するに、五編からなっています。登場人物は厳密にいうと二人ですが、結局、三人です。これは面白い現象です。主人公はフィクション上のエミールという子供です。それから、エミールの家庭教師という人物も登場します。ですから、『エミール』は二人だけの登場人物の演劇なのです。
しかしながら、もう一人の登場人物も出てきます。それはルソー自身です。というのも、頻繁に家庭教師の代わりに、ルソー自身が宣言したりします。「家庭教師は」と言わないで、よく「私は」と書くのですから。要するに、登場人物は二人いて、見方によって三人がいます。
小説の目的は幼いエミールを育てることにあります。そして、エミールを大人にすることが目的です。ルソーに言わせれば、「大人にする」のはどういう意味なのかというと、「よく生きる」ようにするということです。これが、小説の目的です。
ルソー曰く「生きるとは職業だ。」 また「(生きるとは)体の器官や感覚やすべての能力を作用することだ 。生きることは感じること 。」また「生きることだけを望む人は幸いになる。」と。
エミールという子供は家庭教師の完全な支配の下に置かれていて、家庭教師はいつも彼のそばにいます。家庭教師はエミールが自由であることをエミールに思い込ませながら、実際にはエミールは自由ではないというのが小説の中心テーマです。
それでは、第一編に入りましょう。幼児期前期についてです。お配りした引用は編ごとに纏まってあります。多すぎてすべてを読めないのですが、ご参考のまで、編ごとに、『エミール』の流れに沿って引用を纏めました。
『エミール』の第一編の最初の文書から引用します。
「万物を創る者の手をはなれるときすべては良いものであるが、人間の手にうつるとすべてが悪くなる。」
『社会契約論』を思い出してみると、この二行でもうルソーの思想のすべてですね。この二行に『社会契約論』が要約されています。万物を創る者は良く万物を創り、自然は良いが、「人間の手にうつるとすべてが悪くなる」ということで、人間は自然を堕落させるということを言います。
前回に見たように、ルソーの第一の前提は「人間の本性は善である」です。従って、これの単なる帰結ですが、教育論では、「子供も生まれながら自然に善良な者」という前提を置きます。そして、これの対称となるもう一つの前提は「社会は堕落をもたらす」です。つまり、社会において生きている人間は社会によって堕落させられているということを前提にしているのです。
この二つの前提を見るだけで矛盾があります。もしも本当に人間が生まれながら自然に良ければ、つまり、人間本性が絶対に善だったら、一体どうやって社会は人間を堕落させうるのでしょうか、それは不明のままです。
というのも、社会は人間より前に存在しないのなら、また人々の集まりによって構成されていないのなら(それはもちろんあり得ない仮説ですが)、そもそも良い人々を堕落させることはあり得ないはずです。
なぜかというと、社会はそもそも人々の結合ですから。そもそも良い人々ばかり集まったら、一体なぜ良い人々のままにいられなくなるでしょうか?あるいは、一体なぜ本当に良い人々は集まるだけで必ず悪くなれるでしょうか。どう見ても、結局、逆説的な前提です。
共同生活しているせいで、人々は悪くなるとは?ルソーはそのあたりについて明らかにしていないのです。社会から生じる悪はどこに由来するのでしょうか?『社会契約論』においては「所有権」に由来していると言っていました。根拠はそれだけです。ルソーはほかに理屈を見つけていません。結局、人間はそもそも良い存在なのに、悪い存在になっているという矛盾があります。
「人間の手にうつるとすべてが悪くなる。人間はある土地にほかの土地の産物を作らせたり、ある木に他の木の実をならせたりする。風土、環境、季節をごちゃまぜにする。犬、馬、奴隷をかたわにする。すべてのものをひっくりかえし、すべての物の形を変える。人間はみにくいもの、怪物を好む。何一つ自然がつくったままにしておかない。人間そのものさえそうだ。人間も乗馬のように調教しなければならない。庭木みたいに、すきなようにねじまげなければならない。」
人間はそもそも良いものでありながら、社会は人間を堕落させているという前提に立つルソーは、人間を教育するために、大人にするためにどうすべきかというと次のようにいいます。すなわち、社会から子供を離れて彼を一人にして、社会抜きに教育すべきだという対策を打ち出します。そうしながらも、いずれか社交がでてくるから、子が社交できるようにすべきだと。
「こんにちのような状態にあっては、生まれた時からほかの人々の中にほうり出されている人間は、誰よりもゆがんだ人間になるだろう。偏見、権威、必然、実例、私たちを押さえつけているいっさいの社会制度がその人の自然をしめころし、そのかわりに、何ももたらさないことになるだろう。」
このようにして、ルソーは、社会において子供を教育すると子供は堕落するとします。
「自然はたまたま道のまんなかに生えた小さな木のように、通行人に踏みつけられ、あらゆる方向に折り曲げられて、間もなく枯れてしまうだろう。」
したがって、人間を教育するために社会から離れる必要があるとします。次の引用を飛ばしますが、そのあとの引用はこうです。
「この教育は、自然か人間か事物から私たちのところに来ている。」
つまり、人間を教育するために社会から離れ、子供の教育者とは、次の三つの現実だとします。
第一、自然。それは「人間の本性」という意味で、自分の本性です。
第二、人間。理想的な教育を受けているエミールでさえ、ある種の社会から逃れようがない、これはルソーでさえ認めていることです。教育を受けるために、最低限、家庭教師が必要とされているから、どうしても社会はいつのまにか再登場します。従って、社会から子供を完全に離れることは不可能です。ルソーは最低限の社会にすることにしています。子供ともう一人と二人きりの社会にします。そういえば、小説のすべてはエミールとその家庭教師の関係を語ることになっています。ちなみに、その家庭教師には名前がないのです。ルソー曰く、「私だ」ということで、実際、ルソーです。
第三、事物。それは、エミールの周辺にある環境を指します。周辺の自然です。
要するに、第一、自分自身の内面にある本性(自然)。第二、家庭教師、第三、周辺の自然です。
「私たちの能力と器官の内部的発展は、自然の教育である。この発展をいかに利用すべきかを教えるのは人間の教育である。私たちを刺激する事物について私たち自身の経験が獲得するのは事物の教育である。」
これは非常に面白いことです。ルソーにとって第一、発展すべき能力と器官とは、自分自身の中にあるのですね。ですから、結局、第一の教育者は自分自身だということです。
それから、それらの能力をいかに「利用すべきか」は他人から教わるということになっています。ここは要注意です。ルソーは能力をいかに「利用」するかということだけを取り上げます。いかに利用するか。しかし能力は何を対象にしているかあるいは他の対象にすべきか否かに関しては、全く無視されています。
ご存じのように、私たちのすべての能力は、ある特定の対象のために備わっているわけです。つまり、私たちには多くの能力があります。例えば、知性や意志や諸感覚などは備わっています。能力と呼ばれています。これは「何かを知る機能」あるいは「何かを作用する(働く)機能」という意味での能力です。
そして、それらの能力はある対象を目的にしています。つまりある対象に従っての能力です。例えば、知性という能力は本性的に真理に向かわせてあります。意志なら、善に向かいます。それより簡単な例を挙げると、「目」は視覚のためにあります。つまり、色のついた物体を見るためです。「聴覚」は「音」という対象に向かわせてあります。
しかしながら、『エミール』において、教育者の仕事はそれぞれの能力にふさわしい対象を与えることではありません。しかし能力を養う相応しい対象を与えるのは本来の教育であるはずです。
しかしながら、『エミール』においてそうではなく、教育者は能力の利用だけを指導しますが、能力の対象を全く与えないのです。それは自然が自然に対象を与えられているから、です。ルソーはその理屈を出します。少しずつ見えてきたでしょうか。
また後述しますが、これはルソーの教育論の基盤です。つまり、ルソーの教育論では、「教育者」は対象を「教えない」のです。いや、さらに言うと教えてはならないのです。指導するにとどまるべきだと。
「教える」と「指導する」という違いは非常に大事です。一言でいうと、教育者は「真理を教える」ことではなくして、「子供が自分の力で真理を見つけるべきだ」と。本来の教育の完全な転倒です。
御覧の通り、現代ではどれほど一般の教育論はルソー主義になっているかは自明でしょう。
「ですから、この本来の傾向にすべて(の能力)を結び付けなければならないのだが」
要するに、ある種の主観主義です。「ある種の」ですけど、そこまで言わなくても、少なくとも個人主義であることは確かです。こういったような原理に基づくと、必然的に、人々は「私だけの真理を作る」と言い出すことになってしまうしかありません。
こういった教育論の遠い帰結は「真理を相対化する」ということです。一人一人がそれぞれ違う真理を持つことになります。その結果、真理という概念自体は破壊されています。なぜかというと、すべての真理は相対的なものだったら、あることとその逆のことを同時に肯定できるということになりからです。
ですから、真理自体という概念を否定することになりますし、また実際において、いずれか現実にぶつかります。当然、相対化には限界があるのです。矛盾している「真理」が同時に二つあるのはあり得ないからです。それぞれの人々に違う真理がある、と思い込んでしまうと、真理は相対化されて、「真理は存在しない」と断言することと同然になります。
また、人は真理を決めることができるということを断言するようなことですから、「人は神になる」ということをも意味しています。従って、ルソー論だと、自分にとって自分は神です。それから、必然的に、自分が神ならば、神なる自分を他人に無理やりに認めさせるようになるしかありません。ですから、その時、確かに社会は息苦しくなってもおかしくありませんね。
要約すると、自然すなわち能力。人間すなわち家庭教師。それから事物がルソーの教育の三つの先生でした。
・・・続く









