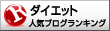・食欲Appetite しょくよく 4月には、ストレスや環境の変化、基礎代謝、空腹時のホルモンの分泌の変化などにより食欲に変化が現れることがあります。季節によっても食欲に変化が起きているようです。
人体で正常な状態では副交感神経優位になると、心拍数が落ち着き、胃腸がよく活動して、胃液の分泌もよくなり食欲が沸いてきます。
交感神経優位に働いてくると胃腸の働きが鈍くなり食欲がなくなりセーブして、対応しているといえます。
食欲とは、脳の摂食中枢と満腹中枢が刺激されることで、「空腹:お腹がすいた」「満腹:お腹がいっぱい」と感じることを指しています。
季節によって気温が下がると、体温保持のため身体の熱産生が高まり、基礎代謝が上がる事により、エネルギーを多く利用しますので、その分を補給しようと一般には空腹感を感じてきます。
よく食欲の秋といいますが、春もちょうどいい気候で過ごしやすいイメージでカラダがリラックスしやすいこの季節は副交感神経優位になりやすいといえるでしょう。副交感神経優位になるとカラダは胃液の分泌を促して食欲がでてくるということが起こります。刺激とリラックスのメリハリをつけてバランスの良い日々を過ごすことが大切のようです。
以前より人は青色波長の多い朝日を浴びると、眠りを誘うホルモン「メラトニン」の分泌 が減少して目を覚まし、夕日を浴びると分泌が増加して眠くなることが以前から知られます。
さらにメラトニンは概日リズムCircadian rhythm(がいじつりずむ: 体内時計)に深く関係し、深部体温を低くする作用があります。メラトニンは0~5歳くらいまでに多く放出しているのですが成長ホルモンと同じく、朝日を浴びて15~16時間位すると出始め遅くまで起きているとあまり出なくり、さらに、歳を重ねるほど減ってくるようです。
メラトニンMelatoninはトマト、バナナ、春菊、アメリカンチェリー、
ケールなどに含む成分です。脳内でトリプトファンより体内でセロトニンを昼に生成し、そのセロトニンを経てメラトニンを生成しています。
脳の松果体に存在する睡眠・休養を促進、成熟を抑制する松果体ホルモンの一種で夜になると分泌が多く昼は少なくなります。
ビタミンB6が安眠、鎮静を促すセロトニンSerotonin の原料となる必須アミノ酸トリプトファンの生成を助けます。ビタミンB12がメラトニンの分泌を調節し睡眠と目覚めのリズムを整えます。夕方にメラトニンを投与すると不眠の人もよく眠れることがわかっています。しかし1000ルクスもの強い照明を浴びれば、夜間であってもメラトニン分泌量は低下するようです。
脳内で作られるセロトニンには、食欲抑制作用があり、その分泌量は日照時間に比例すると言われます。セロトニンSerotonin は、神経伝達物質で血管収縮性を有し感情の情報をまとめるホルモンHormoneとして存在しています。ビタミンB6、ナイアシン、マグネシウムとトリプトファン(必須アミノ酸、カツオ、蓄肉の赤みに多い)より合成しています。摂食抑制にも関与して、冬眠体質(疲れやすい・だるい・無気力・熟睡が出来ない)をかえる物質としています。
太陽の光を浴 びること、リズム運動(咀嚼・ウオーキングなど)でセロトニン神経が活性化し、セロトニンを分泌するのです。
脳内ホルモンとして濃度が高まると、代謝を促進し、満足感、充実感がえられノルアドレナリンNoradrenaline(不快感で増加)、ドーパミンDopamine(興奮状態で増加)の分泌を抑制するのに働いています。セレトニンの欠乏することによりいらいら、感情をおさえられず不安感がつのり鬱(うつ)の状態に陥(おちい)るといいます。セロトニンは脳の松果体によって、メラトニンに変換します。
これまでもよく言われているのが気温の低下による基礎代謝の変化です。 気温が下がると、体温保持のためからだの熱産生が高まり、基礎代謝が上がることは良く知られています。 基礎代謝が上がれば、それだけエネルギーを多く使ってしまうため、空腹を感じ、食物を食べる願望です。 新陳代謝を維持する為に充分なエネルギーを取り入れるのに役立ち、胃腸の消化管、皮下脂肪組織と脳との間の密接な関係にあり相互作用で調節が行われているのです。
胃の中に食べ物のない空腹状態になると、胃から脳の視床下部に情報が伝わり、摂食中枢の働きが強くなり、「食べたい」という食欲の欲求を生じさせます。 一方、空腹感は、消化によって胃の中に食べ物が消化を受けてなくなり、存在する胃液などの消化液や酵素が、食べ物を分解のために働き始めることによって生じます。
脳の視床下部には2つの中枢があり、空腹・満腹などの信号をキャッチし、視床下部に摂食中枢と満腹中枢があり、摂食中枢が働いて食欲がわきます。
空腹感は、栄養が届かなくなった細胞の中で、自分で自分の細胞を包み込み分解するAuto:自ら、Phagy:食べる=自食作用、これを「オートファジー(自食)」といわれています。
更には空腹ではないにもかかわらず、食欲が止まらない原因として挙げられるのは、ストレスや睡眠、栄養不足などです。 食欲を調整するホルモンバランスが崩れ、食欲が増加します。 女性の場合は、生理前後のホルモン変動が食欲増加に影響を与えているようです。食後にもかかわらず、空腹を感じるのには血糖値の乱高下が原因となっている場合も考えられます。 血糖値が急に上昇すると、身体はインスリンを分泌し、血糖値を下げようとします。 その結果、血糖値の急降下が起こり、食欲を調整しているホルモンのバランスが崩れて、病的状態の空腹感が生じることがあるようです。
生活習慣の崩れ寝不足、ストレス、運動不足、加齢などで恒常性の維持を意味するホメオスタシスHomeostasis機能の乱れが生じてくるものです。
食欲を抑えられないのは、脳内で食欲の制御に働く「レプチン」というホルモンの作用が不足していることも考えられています。
食欲を促すためにできる習慣として適度な運動、十分な休養と睡眠、規則正しい生活ルーティンとして行うことは、ストレス・イライラをため込まない、自律神経のバランスを整える、タバコ・アルコールを控えめに、食事ではよく噛んで、盛り付けを工夫するなどです。.
わたしたち人間は、食べ物がなくても3週間程度生きることができるといわれています。 そのため食べ物がなくても、人が一滴もの水を口にできないと数日、72時間ほどで息絶えてしまうとさえいわれ十分な水が確保されていれば2週間から一月はいきながらえるといいます。3週間程度は生きることができるのです。
ストレスを感じると甘いものが食べたくなるとしていますが、ストレスへの対処法は人それぞれです。副腎皮質から分泌されるステロイドホルモンでストレスから体を守り、糖利用の調節、血圧を正常に保つ糖質コルチコイドの一種で必要不可欠なホルモンとして存在の一般には朝、起床したときが最も多く、午後から夜にかけては徐々に減少するのですがコルチゾールには様々な機能があります。ストレスホルモンとしてよく知られ強い不安感が高まったりすると分泌量が増えます。コルチゾールが増えると空腹を感じたり、脂肪を蓄積したり、食欲を調節する脳の領域への血流が減ったりする。食べる量が増えたり、高カロリーで糖分や塩分、脂肪分が多い食べ物が欲しくなる人もいれば、逆に食欲減退に陥る人もいます。
食欲に関連する主の病気には、摂食障害(拒食症・過食症)、甲状腺機能亢進症、クッシング症候群(Cushing症候群)、バセドウ病(Basedow病)、睡眠時無呼吸症候群、甲状腺機能亢進症、脳腫瘍、糖尿病などがあります。
春は気分のムラも激しくなりがちです。 また環境の変化がイライラや不安などのストレスをより高めますので、空腹を招いたり、食欲旺盛になっている場合があります。
よく食欲は健康のバロメーターと一般にいわれていますので、原因不明で食が進まない、過食症気味の場合など、何らかの不調を抱えている可能性もあります。 食欲不振・過食の原因は様々ですが、緊張感、疲れなどによって一時的に食欲が落ちるという経験は誰にでもありますが、長く続くような場合は医療機関での検査を受けるのもよいでしょう。