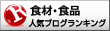・果実の気温差Fruit temperature difference かじつのきおんさ 一般に果樹の栽培適地は、その果樹の原産地、あるいは原産地の土地に似た風土に改良したところであるといえます。果樹の生育に最も大きく影響するのは気象条件、なかでも年間の平均気温と降水量といわれます。
気温差によって収穫するフルーツの種類、北部温帯果樹では年間平均気温が7~12℃で🍎リンゴ、🍒オウトウ、🍐セイヨウナシなどがよく育ちます。
中部温帯果樹では年間平均気温が11~15℃でナシ、🍇ブドウ、🍑モモ、スモモ、ウメ、カキ、🌰クリ、イチジク、🥝キウイフルーツなどなどがよく育ちます。
南部温帯果樹では年間平均気温が15~18℃で🍊カンキツ、ビワなどがありよく育ちます。
北欧気温では北部の平均気温は夏が12.8度、冬は-13度、南部では夏が17.2度です。
夏には太陽が沈まない白夜(びゃくや)、冬には太陽の出ない極夜(きょくや)となります。 暖流の影響を受けるノルウェーは比較的気温は高いのですが、スウェーデンは山脈で隔てられた分その影響は少なくなります。
南部以外は夏でも冷涼、冬の寒さをスウェーデンの気候としては、おおまかに3つのタイプに分類でき、南部は海洋性気候、中部は大陸性湿潤気候、北部は亜寒帯気候になります。北欧原産のビルベリーの甘味はありません。
日本で栽培している果物では1位ウンシュウミカン、2位リンゴ、3位ナシ(ニホンナシ)、4位カキ、5位ぶどうの生産量です。
日本における代表的なフルーツの温度について調べてみました。
今回はさくらんぼ、もも、スイカ、バナナ、和梨についてです。
◇🍒さくらんぼ(西南アジア原産)
山形県東根市は、夏は暑く年間降水量は870.0mm前後、梅雨時も雨が少なく、さくらんぼ栽培に適した気候で、生産量も日本一です。さくらんぼ栽培には、年間平均 気温11~13度で寒暖があり、開花期には風のない温暖な気候が適しています。苗を植え付け4年目ごろより開花して実をつけ、成木には10年といいます。山形県で全国出荷量の70%を占めます。
冬眠が必要な樹木で、5月に入りかなり気温が高くなって上旬に一気に花が咲き始めます。夏期に行われる花芽形成には、夜間低温であることが不可欠ですが、開花期の低温と霜は厳禁で、かといって、気温が常に高ければ枝だけが伸び、結実しなくなります。
14~25℃の開花期に雨の多い地域では、気温と同様に受粉がしにくくなってしまいます。収穫期の雨は、実割れや病気発生の原因となり、梅雨に比較的雨の少ない風土を好みます。実の締まったさくらんぼを朝5~7時くらいまでに朝採りします。
耐水性の弱い根をもつため、水はけのよい礫質(れきしつ)の多い扇状地等が適しています。
現在の日本では、さくらんぼの栽培できる南限は山梨といわれます。
◇🍑桃(中国原産)
2023年(令和5年)都道府県別桃(もも)収穫量ランキング 1位 山梨県 33,400t、2位 福島県 28,500t、3位 長野県 9200t、順に山形県、和歌山県と続いています。 山梨県の気候は、①「昼と夜」の一日の気温差が大きい、②年間の日照時間が日本一長い、③年間の降水量が少ない、という内陸性気候で水はけのよい土壌です。
生育に最適なph 5.5~6のほぼ中性の土壌で年間の平均気温12℃以上の場所がよく 年間降水量は1,300mm以下としています。特に旬の夏場は日中の気温は35度以上、朝晩は20度という気温差が桃の糖度を上げる好条件になっています。
ブドウ収穫量の地図とよく似ています。
◇🍉スイカ(アフリカ原産)
スイカの生産量は2020年(令和2年)で中国が世界の約60%、6億0246万888トンにも なります。2位以下は1桁減りトルコ(テゥルキエ)、インド、アルジェリアと続きます。日本は約309.402トンで14位です。日本の全国収穫量は、362.5千トンで日本一は熊本県の16.3%に、2位 千葉県12.16% 、3位 山形県の順に新潟県 、 鳥取県、長野県と続いています。スイカの生産地としては上記のほか北海道や山形県と日本の北から南まで、全国各地さまざまな土地で栽培しています。
熊本県熊本市北区植木町は、果物や花などのハウス栽培が盛んなところでもあり江戸時代からスイカの名産地として知られスイカは全国有数の名産地です。熊本県北西部に位置し、すいかのトンネル・ハウス栽培の普及で、昭和30年代にすいかづくりが始まったと言われています。小玉西瓜は、2月下旬より6月いっぱいまで出荷しています。
温暖で一日の寒暖の 差が激しい盆地性の昼は暑くて夜はぐっと冷え込むという 気候のおかげで、糖度が10%以上と高く美味しい真っ赤な果肉のスイカに育ちます。
果物の糖度は、夜の気温と昼の気温の差が高ければ高いほど甘くなります。気象条件は平均気温15.3℃、平均年間降雨量2,006mm、初霜10月15日 、晩霜5月6日と比較的温暖な気候ですが、ここ植木町では、4月から6月くらいまでの天候がまさにこの糖度の高い西瓜を作るのに適した気候風土であり、そこから生まれた実の固さが特徴で、ぎっしりつまったシャリシャリの食感は、日本一の味とも称されています。
連棟加温式より始まり種まきを10月下旬から11月に行い、 挿し木、その後苗を育て定植、12月10日くらいに、苗の植え付けをします。ハウス、トンネル栽培ともに1月中旬頃より、栽培方法により4月下旬頃まで開花の時期を迎え受粉し、生育させ、南から北へと順次収穫の時期となります。
西瓜の日を7月27日として27を「つ(2)な(7)」(綱)とよんで特徴とする縞模様を綱にみたて夏の綱と成る スイカの消費拡大を願い制定です。
◇🍌バナナ(熱帯アジア原産)
熱帯生まれの作物のバナナは、温暖・湿潤という気候を好みますが、一方で比較的乾燥した地域でも栽培しているなど、かなり広範囲の気候条件に適応します。FAO(国連食糧農業機関)の統計では約130カ国もの国々でバナナを生産しているようです。とくに生産が盛んなのは赤道を中心に緯度が南北緯30℃以内までの一帯で、バナナの生産量が多い国々はインド、ウガンダ、エクアドルなどで、この範囲に含みます。この一帯はその「バナナ・ベルト」と呼ばれています。
アフリカへのバナナの伝播経路について諸説ありますが、紀元前1000年頃からといいます。1500年前後のポルトガル人による西アフリカ地域へのバナナの導入などがあり継続的、重層的なものであったと推定しています。アフリカに渡ったバナナは、品種レベルで多様化して栽培と伝播によって独自のバナナ栽培が生みだされていったようです。
熱帯の地域では大型の多年草で年間を通して花が咲き実をつけ特に旬という時期は定まっていません。果実は最初は下向きですがやがて空に向かって反り返って成長、開花から一月ほどで収穫しています。アフリカ中部は雨が多く熱帯林地帯です。一方で堪水条件には弱く排水されない土壌では根腐れをおこし枯死してしまいます。排水性がよく有機物に富んだ土壌が適しています。
実験でカリウムやカルシウム、リンといったミネラルは昼間の気温が30℃を超える高温条件下でより多く吸収したという結果があります。
赤道から離れるに従い気候が乾燥していきますがバナナ栽培に適しました。
気候条件として 一年中暖かいことでおよそ14~38℃の広い範囲で最適気温が26~30℃、降雨が一年中で100~200mm/月 程度です。台風の通り道でないこともあげられています。
バナナ輸出量世界第1位の南アフリカの西部エクアドル共和国です。日本への輸入先はフィリピン8~9割、エクアドル0.85%前後、台湾が0.14%前後です。
フィリピン諸島で2番目に大きな島ミンダナオ島では日本に輸入しているバナナの9割程度がこの島で熱帯性気候であり年間を通し高温多湿です。平均気温は26~27℃、6月を中心に年間2,000~2,500mmの雨が降ります。
台湾はバナナ生育の条件である気候的には低温ですが、フィリピンでは8ヵか月で収穫できるのに 台湾では収穫まで12ヵ月~13ヵ月かかるものもあり、促成栽培でなくじっくり成長 するため味、香りが濃くなっているようです。
◇和梨 (中国原産)
中国や朝鮮半島、日本の中部地方以南に 自生する野生種ヤマナシが基本種としています。丸い和梨には皮の色で大きく2種類の赤梨系と青梨系タイプに分かれます。
現在では青梨系20世紀梨などはあまり出回らなくなりました。和梨と言って、日本だけの品種です。明治時代には、現在の千葉県松戸市において1888年に二十世紀が、現在の神奈川県川崎市で明治26年に長十郎をそれぞれに発見しています。
和梨の収穫量全国第1位の千葉県は県内産地は白井市・市川市・鎌ヶ谷市 ・船橋の順です。
千葉県に多い火山灰土壌は、排水性が良いことから梨の栽培に向いており、ナシ栽培地帯の気象条件は、年平均気温15.5℃~16℃、雨量は1,200mm~1,500mmです。
台木には和なしの他、マンシュウマメナシやチュウゴクナシ、マルバカイドウも用いられています。本来ナシは高さ10m程になる高木ですが、栽培の際には台風などの風害を避け、十分な日照を確保するの理由によりぶどう棚のような棚仕立てで作られています。
4月中旬、天気がよく気温が15℃以上ある日に交配作業を行います。おいしい梨に育つには、昼と夜の気温差が大きく、メリハリのある天候が望まれます。
千葉県は全国一の梨生産地であり、現在の市川から船橋にかけての江戸近郊では江戸時代後期頃には、既に梨の栽培が盛んだった事がわかっています。遅霜や降雹(こうひょう)等の被害も少なく、7月に気温が高くなり、たっぷりの日差しを浴び甘い梨ができます。
ナシは沖縄県を除く日本各地、北海道から鹿児島県まで広く栽培しています。そのため、主産県でも収穫量におけるシェアはそれほど高くなく、上位10県合計でも全体の7割弱となっています。
梨特有のシャリシャリとした食感とみずみずしさ、糖度の高さで 人気があり、全国に広く出荷しています。梨の収穫時期は品種により7月中旬~10月上旬ごろで、品種は幸水→豊水→あさづき→新高、二十世紀などがあります。幸水(生産量の35%)は多汁で 特有の風味があり特に夏の盛り出荷される為需要も多くある品種です。 豊水は水分豊富で糖度は13度と高く、若干酸味のある和梨です。
梨は、
リンゴや
ミカンと違い、日持ちしにくい果物です。リンゴや
カキと同様、果頂部といわれる尻の方が甘みが強くなります。
7月4日は梨の日です。
さくらんぼ栽培には、雨が少なく、年間平均 気温11~13度で寒暖があり、開花期には風のない温暖な気候が適し冬眠を必要としています。
桃の結実栽培には年平均気温12℃以上の場所がよく 年間降水量は1,300mm以下としています。特に旬の夏場は日中の気温は35度以上、朝晩は20度という気温差が桃の糖度を上げる好条件になっています。
西瓜の気象条件は平均気温15.3℃、平均年間降雨量2,006mm、初霜10月15日 、晩霜5月6日と比較的温暖な気候です。
熱帯産のバナナの気象条件は一年中暖かいことでおよそ14~38℃の広い範囲で最適気温が26~30℃、降雨が一年中で100~200mm/月 程度です。
ナシ栽培地帯の気象条件は、年平均気温15.5℃~16℃、雨量は1,200mm~1,500mmです。
果実は、夜間の寒さによって糖度を増し、寒さに耐え、収穫時期の降水量の少ないことが、甘みの強い、おいしい果実を育ててます。熱帯産の
西瓜、
バナナは、高い気温が必要ですが、最近ではハウス栽培によって適温、水量の調節が行われ、安定した供給策の進展が見られているようです。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。