前回の記事(2019/10/28)の続きで、エーテル("Luminiferous_aether")の属性がどのように消えていったかの詳しい経緯です。ただし以下で速度の変化が誘電率や透磁率の変化を意味する点の考察は私が調べた限りの歴史文献では触れられてはいませんでした。その部分は「当然そういう論理になるだろう」という話であり、実際に過去の科学者達が考えた筋道とは違うかも知れません。
前回の記事(2019/10/28)で強調しておきたいのが、マイケルソン・モーリーの実験ではエーテルの存在は否定されてはいないという点です。実際にその後に提案されたローレンツ理論はエーテルの存在を否定していません。マイケルソン・モーリーの実験で示されたのは地球に対しては"エーテルの風が吹かない"ことです。エーテルの存在が否定されたのは、ローレンツ理論が最終的に定式化された1905年のまさに直後に特殊相対性理論によってなのです。それも積極的に否定されたというよりは、無視されたという方が実態に近いでしょう[*1]。ニュートンの万有引力理論が場の正体を必要としていないように、マクスウェルの電磁波理論もエーテルを必要としていないことが明らかになったというべきでしょうか。
ここで基本的なことを確認しておきましょう。電場と磁場は運動する系から見ると相互に変換されて見えるということです。例えば運動する電荷は静磁場の中でローレンツ力を受けます。これを運動する電荷自身の系から見れば、静止している電荷が力を受けている、すなわち電場があるということになります。つまり電場と磁場は実は同じものであり、見る立場により磁場の側面が強く見えたり電場の側面が強く見えたりするということです。このことはマクスウェル理論の中ではスカラーポテンシャルとベクトルポテンシャルを合わせた電磁ポテンシャルという本体?の観測量が電場と磁場であるという表現になります。そして特殊相対性理論の中では、スカラーポテンシャルとベクトルポテンシャルとは4元ベクトルという1つのものに統一されます。本体?の電磁ポテンシャルや4元ベクトルは同じであっても異なる座標系では異なる座標値(電場と磁場)になるというわけです[*2]。
さて電磁波の速度は(誘電率*透磁率)-1/2となります。それまでの常識だった速度のガリレイ変換によれば、ある速度の電磁波に対して運動している観測者からその電磁波を見ると速度が変化している、すなわちその場所の誘電率や透磁率が変化していることになります。これはすなわち、電磁波を構成する変化している電場と磁場とが運動速度の異なる系からは別の大きさに見えるということから導かれるはずです。電磁波はともかくとして光の場合にはそのような変化が観測されていたのでした。それがフィゾーの実験(Fizeau experiment)です。この実験では水中を伝わる光の速度は、媒質である水の運動速度により変化することが示されました。ただしその変化の大きさはガリレイ変換から予測される単純な加成則ではありませんでした。フィゾーが得た実験式を下記に示しますが、これは実は特殊相対性理論の速度加成則から水の速度が光速より小さい場合の近似として得られるものでした。
フィゾーの実験式 ω=c/n+v(1-(1/n2))
ω: 水中の光速度
v: 水の速度
n: 屈折率=真空中の光速度/水中の光速度
注目すべきはこの実験式から、もし運動する媒体(フィゾーの実験では水)が真空中と同じ速度で光を伝播するものであれば、その媒体が運動していたとしても伝播する光の速度は外部から見ても変化しないことが外挿されることです。つまりフィゾーの実験式をn=1に外挿すればエーテルの風は光速度の変化からは観測できないという結論が生まれ、マイケルソン・モーリーの実験結果が予想されるのです[*3]。アシンシュタインがフィゾーの実験と光行差の測定とを重要な実験として挙げていてマイケルソン・モーリーの実験結果を挙げていないというのは、このような事情もあるのだと思います。3つの実験はアインシュタインが最も創造性を発揮したと言われる特許局勤務時代(1902-1909)より何十年も前の有名な実験なので「マイケルソン・モーリーの実験を知らなかった」という噂は誇張でしょうけれど[*4]。
静止した水中の光速度(電磁波速度)はマクスウェル理論から(水の誘電率*水の透磁率)-1/2になります。フィゾーの実験により運動する水の誘電率や透磁率は確かに変化することがわかったのです。しかもその変化は速度方向による異方性を持つはずです。運動する水に入っていく光の屈折は静止した水へ入る場合とは異なるということも起きるでしょう。しかし、どの方向から来る電磁波(光波)の速度もその地点での水の誘電率と水の透磁率とで決まります。そしてそれは真空中でも同じことです。
観測量としては、誘電率とはクーロンの法則で示される電荷と電場との関係の係数であり、透磁率とは電流と磁場との関係の係数です。誘電率も透磁率も水などの媒質の各位置の関数ですから、その位置を通る電磁波(光波)の速度は方向にも光源にもよらないはずです。まさしく電磁波(光波)の水中の伝播は水という媒質の性質である水の誘電率と水の透磁率とで決まるのです。そして媒質である水に対して相対運動する系から見れば、確かに水の誘電率と透磁率とは変化しており、結果として光速も変化していたのです。すると水も空気もない真空においても、電磁波が飛んでいる真空、すなわち変動する電場と磁場とが存在する真空に対して運動する系から見れば、真空の誘電率と透磁率とが変化して見え電磁波(光波)の速度が異なったとしてもおかしくはありません。しかし物質のないはずの真空に対する運動などということがありうるのでしょうか?
それは可能です。なぜなら真空と言えども各座標位置には電場や磁場や誘電率や透磁率という属性が付随していて、各座標位置は区別可能な異なる性質を持っているからです。すると区別可能なその点に対する運動は観測可能なものになるはずです。しかしそうなった場合、異なる運動系から見る真空は異なるものとして見えることになります。仮に遠くの恒星系から見た真空が真に均一で、どの位置でも同一の誘電率と透磁率とを持っていたとすれば、恒星系に対して年周運動する地球から見た真空は異なる誘電率と透磁率とを持つでしょう。以上の考察は光の正体とは関わりなく、マクスウェル理論が予測する電磁波の伝播から導かれることには注意しましょう。現実の歴史では光の電磁波説はほとんど疑われることはなく、マイケルソン・モーリーの実験が運動する地球から見ても電磁波(光波)の速度は変化しない、すなわち真空の誘電率や透磁率は変化しないことを示したのです。
ここで真空という言葉をエーテルと言い換えれば、実際の歴史で科学者たちが考えていたこととかなり似たものになるでしょう。ただし真空に対する運動なら怪しまれたでしょうが、エーテルに対する運動はむしろ当然視されました。そしてローレンツ理論ではエーテルの短縮と時間の遅れを持ち込むことにより、エーテルに対して運動する観測者から見てもエーテルの誘電率や透磁率は変化しないようになっていたものと考えられます。それは等速運動をするどの観測者から見てもエーテルは同質に見えるということです。そしてアインシュタインはここで、どの観測者から見ても物理法則は不変であるという考え方を持ち込むことにより、理論を極めて簡明なものとしたのです。すなわちどの観測者から見ても不変に見えるエーテルという存在しないも同然のものを排してどの観測者から見ても不変な物理法則という一段深いものに置き換えたのです[*1]。
そしてエーテルから物理法則への置き換えは相対性理論の適用範囲をローレンツ理論よりも自然に広げています。具体的には速度の上限である真空中の光速度は物質固有の性質ではなくなりました。光でもニュートリノでもグラヴィトンでも、また粒子であれ波であれ情報であれ、cという上限速度を定数とした方程式に従うのであり、どの観測者から何を見てもcを越える速度では観測されないのです。
アインシュタインは光行差(Aberration)も重要だったと述べています。光行差はブラッドレーが初めて検出し光速度を求めたことはよく知られていますが、その正確さ(現代の測定値との差)は1849年のフイゾーによる地上での測定値を上回るものでした。数値は東北大・光物性物理研究室・吉澤グループ「光速度測定の歴史」や「光速測定の歴史と天文学」天文教育2008年9月号,P40-45にまとめられています。
恒星の光行差 (ブラッドレー、1725) 299042km/s
回転歯車 (フィゾー、1849)地球上での初めての測定 315300±500km/s
回転鏡Ⅰ(フーコー、1862) 298000±500km/s
回転鏡Ⅱ(マイケルソン、1926)299796±4km/s
現代の値 299792.458 km/s
実は光行差の値は相対性理論によりきちんと説明できるものです。それはwikipedia英語版にも書かれていますが、FNの高校物理「アインシュタインの特殊相対性理論(1905年)」の「(9)光行差 Sommerfeld文献402」にも詳しく書かれています。またFNの高校物理「ブラッドリーが光行差を見付けた方法(1727年)」には光行差の測定と年周視差の測定の違いを含めてブラッドリーの観測の話が書かれています。それによれば1725年はブラッドリーらが恒星の謎の周年変化を見つけた年であり、それが光行差によると見抜いたのは1728年のことのようです。ブラッドリーは素晴らしい観測家であり理論家でもありますね。
これらの記事に述べられているように年周視差は地球からの距離が異なる恒星同士の方角のずれとしても観測されますが、光行差はすべての恒星について赤経と赤緯のずれ、すなわち地球の自転軸を基準とした方角のずれとして観測されます。実はブラッドリー以前は年周視差を赤経と赤緯のずれから求めようとしていてブラッドリーも年周視差を見つけようとして天頂儀(zenith telescope)での観測を行ったのですが、それで光行差による変化に埋もれているはずの「年周視差による変位が1秒以下」ということを見出し、恒星同士の相対位置の変化から求めた方が良いと結論付けたようです。
さてブラッドリーの観測結果でひとつの重要なポイントは観測したどの恒星からの光の速度も同じとなったことです。光行差はただ黄道面に対する方向、つまりは地球の公転面に対する方向だけに依存していました。これは地球から見た光速度は光源の運動にはよらず、また太陽系に対してはエーテルの風は吹いていないことを強く示唆しています。むろんブラッドリーの時代では多くの恒星の固有運動は見つけられてはいませんし、全天の恒星の光行差データには程遠かったでしょうが、19-20世紀ともなればさらに観測データも積み重ななっていたはずです。これがアインシュタインが光行差の観測が重要だったと述べた理由だと思います。
ではエーテルが消えていった過程をまとめてみましょう。
1.最初は、光波を伝える、密度、弾性などを持つ物質と考えられた。ここで観測されていた性質は光波を伝えることだけであり、他の属性は振動波の媒質である通常物質からの類推だった。
2.光の電磁波説により、光波および電磁波を伝える性質と共に、電磁場を担うという性質が加わった。密度、弾性、圧力などの機械的性質はなくてもよくなった。
3.光行差、フィゾーの実験、マイケルソン・モーリーの実験により、運動性が通常物体とは異なる奇妙なものであることがわかった。つまりエーテルの風は奇妙な性質があるとわかった。その奇妙な性質を数学的に定式化したのがローレンツ理論だった。
4.どの慣性系でも物理法則は不変であるという相対性原理を仮定すればエーテルの存在は不要とわかった。それが特殊相対性理論である。
特殊相対性理論の内容は速度の異なる慣性系の間の時空座標変換が、上限速度cを定数としたローレンツ変換になるということに尽きます。またどの慣性系から見ても不変な速度cがあるという仮定からはローレンツ変換が導かれるので、数学的にはどちらを原理としても等価です。重要なことは、この仮定には光の固有な性質も、ましてやその媒質の性質も必要とされないことです。上限速度が光速度と一致するのは、たまたま光が静止質量ゼロであるからに過ぎず、他の粒子でも波でも、古典的なガリレイ変換とは異なる奇妙な運動性を共有しているのです。そのために、後に一般相対性理論で予測された重力波も光と同じ速度を持つと予測することができたのです。
そして特殊相対性理論が理論からエーテルを消した時には、「電磁波の媒質はどうなったんだ?」という反論をする者はいませんでした・・たぶん。電磁場の振動であることが明確である以上は、その他の余計な仮想物質など不要であることに誰もが気付いていたからでしょう。
そして量子力学においてもっと奇妙な波である物質波が登場しました。この波は誕生当初から媒質など必要としていませんでした。次回はその話に入ります。
----------------------
*1) アインシュタインは1909年の講演で[Ref-A1]、自らが相対性原理に基づいてエーテルを否定した経緯を話している。
「If that is so, we can just as well imagine the ether is at rest relative to K' not K. It is completely unnatural to distinguish the two reference frames K' and K by introducing an ether that is at rest in one. A satisfying theory can only be reached if we dispense with the ether hypothesis.」
「もしそうならば、我々はエーテルはKではなく、まさにK'に対して静止しているとイメージすることができる。2つの基準系KとK'とを、その一つに対して静止しているエーテルを導入することで区別することは、まったく不自然である。」
*2) 異なる慣性系から見た違いを単なる座標変換だけで考える方法も特殊相対性理論がローレンツ理論と違うところだと思うがどうなんだろう。ただ「本体は不変」と考えれば、いわゆる相対性理論のパラドックスは起きるはずがないということは納得しやすいのではないだろうか。
*3) エーテルを流す手段がないのでフィゾーの実験をエーテルを媒体として行うことはできない。水流の中でマイケルソン・モーリーの実験を行ったという話は聞かないが、水流で装置が動いたりしてとても困難だということは予想できる。
*4) 実際、アインシュタインは[Ref-A1]ではマイケルソン・モーリーの実験に触れている。
----------------------
Ref-A1) "On the Development of Our Views Concerning the Nature and Constitution of Radiation" アインシュタイン(1909)
Ref-A2) アインシュタイン「エーテルと相対性理論」(1920/05/05)
Ref-A2-1) ドイツ語原本、印刷イメージ
Ref-A2-2) 英訳版、印刷イメージ
Ref-A2-3) 英訳テキスト
Ref-A2-4) 湯川秀樹(監修);内山龍雄(訳)『アインシュタイン選集 2 ―一般相対性理論および統一場理論―』共立出版 (1970/12/05),ISBN-13: 978-4320030206 ([A10] エーテルと相対性理論)
Ref-A2-5) 石原純(訳)。日本語が難解。Ref-A2-3やRef-A2-4の英訳の方がむしろわかりやすいかも知れない。
前回の記事(2019/10/28)で強調しておきたいのが、マイケルソン・モーリーの実験ではエーテルの存在は否定されてはいないという点です。実際にその後に提案されたローレンツ理論はエーテルの存在を否定していません。マイケルソン・モーリーの実験で示されたのは地球に対しては"エーテルの風が吹かない"ことです。エーテルの存在が否定されたのは、ローレンツ理論が最終的に定式化された1905年のまさに直後に特殊相対性理論によってなのです。それも積極的に否定されたというよりは、無視されたという方が実態に近いでしょう[*1]。ニュートンの万有引力理論が場の正体を必要としていないように、マクスウェルの電磁波理論もエーテルを必要としていないことが明らかになったというべきでしょうか。
ここで基本的なことを確認しておきましょう。電場と磁場は運動する系から見ると相互に変換されて見えるということです。例えば運動する電荷は静磁場の中でローレンツ力を受けます。これを運動する電荷自身の系から見れば、静止している電荷が力を受けている、すなわち電場があるということになります。つまり電場と磁場は実は同じものであり、見る立場により磁場の側面が強く見えたり電場の側面が強く見えたりするということです。このことはマクスウェル理論の中ではスカラーポテンシャルとベクトルポテンシャルを合わせた電磁ポテンシャルという本体?の観測量が電場と磁場であるという表現になります。そして特殊相対性理論の中では、スカラーポテンシャルとベクトルポテンシャルとは4元ベクトルという1つのものに統一されます。本体?の電磁ポテンシャルや4元ベクトルは同じであっても異なる座標系では異なる座標値(電場と磁場)になるというわけです[*2]。
さて電磁波の速度は(誘電率*透磁率)-1/2となります。それまでの常識だった速度のガリレイ変換によれば、ある速度の電磁波に対して運動している観測者からその電磁波を見ると速度が変化している、すなわちその場所の誘電率や透磁率が変化していることになります。これはすなわち、電磁波を構成する変化している電場と磁場とが運動速度の異なる系からは別の大きさに見えるということから導かれるはずです。電磁波はともかくとして光の場合にはそのような変化が観測されていたのでした。それがフィゾーの実験(Fizeau experiment)です。この実験では水中を伝わる光の速度は、媒質である水の運動速度により変化することが示されました。ただしその変化の大きさはガリレイ変換から予測される単純な加成則ではありませんでした。フィゾーが得た実験式を下記に示しますが、これは実は特殊相対性理論の速度加成則から水の速度が光速より小さい場合の近似として得られるものでした。
フィゾーの実験式 ω=c/n+v(1-(1/n2))
ω: 水中の光速度
v: 水の速度
n: 屈折率=真空中の光速度/水中の光速度
注目すべきはこの実験式から、もし運動する媒体(フィゾーの実験では水)が真空中と同じ速度で光を伝播するものであれば、その媒体が運動していたとしても伝播する光の速度は外部から見ても変化しないことが外挿されることです。つまりフィゾーの実験式をn=1に外挿すればエーテルの風は光速度の変化からは観測できないという結論が生まれ、マイケルソン・モーリーの実験結果が予想されるのです[*3]。アシンシュタインがフィゾーの実験と光行差の測定とを重要な実験として挙げていてマイケルソン・モーリーの実験結果を挙げていないというのは、このような事情もあるのだと思います。3つの実験はアインシュタインが最も創造性を発揮したと言われる特許局勤務時代(1902-1909)より何十年も前の有名な実験なので「マイケルソン・モーリーの実験を知らなかった」という噂は誇張でしょうけれど[*4]。
静止した水中の光速度(電磁波速度)はマクスウェル理論から(水の誘電率*水の透磁率)-1/2になります。フィゾーの実験により運動する水の誘電率や透磁率は確かに変化することがわかったのです。しかもその変化は速度方向による異方性を持つはずです。運動する水に入っていく光の屈折は静止した水へ入る場合とは異なるということも起きるでしょう。しかし、どの方向から来る電磁波(光波)の速度もその地点での水の誘電率と水の透磁率とで決まります。そしてそれは真空中でも同じことです。
観測量としては、誘電率とはクーロンの法則で示される電荷と電場との関係の係数であり、透磁率とは電流と磁場との関係の係数です。誘電率も透磁率も水などの媒質の各位置の関数ですから、その位置を通る電磁波(光波)の速度は方向にも光源にもよらないはずです。まさしく電磁波(光波)の水中の伝播は水という媒質の性質である水の誘電率と水の透磁率とで決まるのです。そして媒質である水に対して相対運動する系から見れば、確かに水の誘電率と透磁率とは変化しており、結果として光速も変化していたのです。すると水も空気もない真空においても、電磁波が飛んでいる真空、すなわち変動する電場と磁場とが存在する真空に対して運動する系から見れば、真空の誘電率と透磁率とが変化して見え電磁波(光波)の速度が異なったとしてもおかしくはありません。しかし物質のないはずの真空に対する運動などということがありうるのでしょうか?
それは可能です。なぜなら真空と言えども各座標位置には電場や磁場や誘電率や透磁率という属性が付随していて、各座標位置は区別可能な異なる性質を持っているからです。すると区別可能なその点に対する運動は観測可能なものになるはずです。しかしそうなった場合、異なる運動系から見る真空は異なるものとして見えることになります。仮に遠くの恒星系から見た真空が真に均一で、どの位置でも同一の誘電率と透磁率とを持っていたとすれば、恒星系に対して年周運動する地球から見た真空は異なる誘電率と透磁率とを持つでしょう。以上の考察は光の正体とは関わりなく、マクスウェル理論が予測する電磁波の伝播から導かれることには注意しましょう。現実の歴史では光の電磁波説はほとんど疑われることはなく、マイケルソン・モーリーの実験が運動する地球から見ても電磁波(光波)の速度は変化しない、すなわち真空の誘電率や透磁率は変化しないことを示したのです。
ここで真空という言葉をエーテルと言い換えれば、実際の歴史で科学者たちが考えていたこととかなり似たものになるでしょう。ただし真空に対する運動なら怪しまれたでしょうが、エーテルに対する運動はむしろ当然視されました。そしてローレンツ理論ではエーテルの短縮と時間の遅れを持ち込むことにより、エーテルに対して運動する観測者から見てもエーテルの誘電率や透磁率は変化しないようになっていたものと考えられます。それは等速運動をするどの観測者から見てもエーテルは同質に見えるということです。そしてアインシュタインはここで、どの観測者から見ても物理法則は不変であるという考え方を持ち込むことにより、理論を極めて簡明なものとしたのです。すなわちどの観測者から見ても不変に見えるエーテルという存在しないも同然のものを排してどの観測者から見ても不変な物理法則という一段深いものに置き換えたのです[*1]。
そしてエーテルから物理法則への置き換えは相対性理論の適用範囲をローレンツ理論よりも自然に広げています。具体的には速度の上限である真空中の光速度は物質固有の性質ではなくなりました。光でもニュートリノでもグラヴィトンでも、また粒子であれ波であれ情報であれ、cという上限速度を定数とした方程式に従うのであり、どの観測者から何を見てもcを越える速度では観測されないのです。
アインシュタインは光行差(Aberration)も重要だったと述べています。光行差はブラッドレーが初めて検出し光速度を求めたことはよく知られていますが、その正確さ(現代の測定値との差)は1849年のフイゾーによる地上での測定値を上回るものでした。数値は東北大・光物性物理研究室・吉澤グループ「光速度測定の歴史」や「光速測定の歴史と天文学」天文教育2008年9月号,P40-45にまとめられています。
恒星の光行差 (ブラッドレー、1725) 299042km/s
回転歯車 (フィゾー、1849)地球上での初めての測定 315300±500km/s
回転鏡Ⅰ(フーコー、1862) 298000±500km/s
回転鏡Ⅱ(マイケルソン、1926)299796±4km/s
現代の値 299792.458 km/s
実は光行差の値は相対性理論によりきちんと説明できるものです。それはwikipedia英語版にも書かれていますが、FNの高校物理「アインシュタインの特殊相対性理論(1905年)」の「(9)光行差 Sommerfeld文献402」にも詳しく書かれています。またFNの高校物理「ブラッドリーが光行差を見付けた方法(1727年)」には光行差の測定と年周視差の測定の違いを含めてブラッドリーの観測の話が書かれています。それによれば1725年はブラッドリーらが恒星の謎の周年変化を見つけた年であり、それが光行差によると見抜いたのは1728年のことのようです。ブラッドリーは素晴らしい観測家であり理論家でもありますね。
これらの記事に述べられているように年周視差は地球からの距離が異なる恒星同士の方角のずれとしても観測されますが、光行差はすべての恒星について赤経と赤緯のずれ、すなわち地球の自転軸を基準とした方角のずれとして観測されます。実はブラッドリー以前は年周視差を赤経と赤緯のずれから求めようとしていてブラッドリーも年周視差を見つけようとして天頂儀(zenith telescope)での観測を行ったのですが、それで光行差による変化に埋もれているはずの「年周視差による変位が1秒以下」ということを見出し、恒星同士の相対位置の変化から求めた方が良いと結論付けたようです。
さてブラッドリーの観測結果でひとつの重要なポイントは観測したどの恒星からの光の速度も同じとなったことです。光行差はただ黄道面に対する方向、つまりは地球の公転面に対する方向だけに依存していました。これは地球から見た光速度は光源の運動にはよらず、また太陽系に対してはエーテルの風は吹いていないことを強く示唆しています。むろんブラッドリーの時代では多くの恒星の固有運動は見つけられてはいませんし、全天の恒星の光行差データには程遠かったでしょうが、19-20世紀ともなればさらに観測データも積み重ななっていたはずです。これがアインシュタインが光行差の観測が重要だったと述べた理由だと思います。
ではエーテルが消えていった過程をまとめてみましょう。
1.最初は、光波を伝える、密度、弾性などを持つ物質と考えられた。ここで観測されていた性質は光波を伝えることだけであり、他の属性は振動波の媒質である通常物質からの類推だった。
2.光の電磁波説により、光波および電磁波を伝える性質と共に、電磁場を担うという性質が加わった。密度、弾性、圧力などの機械的性質はなくてもよくなった。
3.光行差、フィゾーの実験、マイケルソン・モーリーの実験により、運動性が通常物体とは異なる奇妙なものであることがわかった。つまりエーテルの風は奇妙な性質があるとわかった。その奇妙な性質を数学的に定式化したのがローレンツ理論だった。
4.どの慣性系でも物理法則は不変であるという相対性原理を仮定すればエーテルの存在は不要とわかった。それが特殊相対性理論である。
特殊相対性理論の内容は速度の異なる慣性系の間の時空座標変換が、上限速度cを定数としたローレンツ変換になるということに尽きます。またどの慣性系から見ても不変な速度cがあるという仮定からはローレンツ変換が導かれるので、数学的にはどちらを原理としても等価です。重要なことは、この仮定には光の固有な性質も、ましてやその媒質の性質も必要とされないことです。上限速度が光速度と一致するのは、たまたま光が静止質量ゼロであるからに過ぎず、他の粒子でも波でも、古典的なガリレイ変換とは異なる奇妙な運動性を共有しているのです。そのために、後に一般相対性理論で予測された重力波も光と同じ速度を持つと予測することができたのです。
そして特殊相対性理論が理論からエーテルを消した時には、「電磁波の媒質はどうなったんだ?」という反論をする者はいませんでした・・たぶん。電磁場の振動であることが明確である以上は、その他の余計な仮想物質など不要であることに誰もが気付いていたからでしょう。
そして量子力学においてもっと奇妙な波である物質波が登場しました。この波は誕生当初から媒質など必要としていませんでした。次回はその話に入ります。
----------------------
*1) アインシュタインは1909年の講演で[Ref-A1]、自らが相対性原理に基づいてエーテルを否定した経緯を話している。
「If that is so, we can just as well imagine the ether is at rest relative to K' not K. It is completely unnatural to distinguish the two reference frames K' and K by introducing an ether that is at rest in one. A satisfying theory can only be reached if we dispense with the ether hypothesis.」
「もしそうならば、我々はエーテルはKではなく、まさにK'に対して静止しているとイメージすることができる。2つの基準系KとK'とを、その一つに対して静止しているエーテルを導入することで区別することは、まったく不自然である。」
*2) 異なる慣性系から見た違いを単なる座標変換だけで考える方法も特殊相対性理論がローレンツ理論と違うところだと思うがどうなんだろう。ただ「本体は不変」と考えれば、いわゆる相対性理論のパラドックスは起きるはずがないということは納得しやすいのではないだろうか。
*3) エーテルを流す手段がないのでフィゾーの実験をエーテルを媒体として行うことはできない。水流の中でマイケルソン・モーリーの実験を行ったという話は聞かないが、水流で装置が動いたりしてとても困難だということは予想できる。
*4) 実際、アインシュタインは[Ref-A1]ではマイケルソン・モーリーの実験に触れている。
----------------------
Ref-A1) "On the Development of Our Views Concerning the Nature and Constitution of Radiation" アインシュタイン(1909)
Ref-A2) アインシュタイン「エーテルと相対性理論」(1920/05/05)
Ref-A2-1) ドイツ語原本、印刷イメージ
Ref-A2-2) 英訳版、印刷イメージ
Ref-A2-3) 英訳テキスト
Ref-A2-4) 湯川秀樹(監修);内山龍雄(訳)『アインシュタイン選集 2 ―一般相対性理論および統一場理論―』共立出版 (1970/12/05),ISBN-13: 978-4320030206 ([A10] エーテルと相対性理論)
Ref-A2-5) 石原純(訳)。日本語が難解。Ref-A2-3やRef-A2-4の英訳の方がむしろわかりやすいかも知れない。










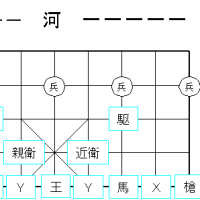
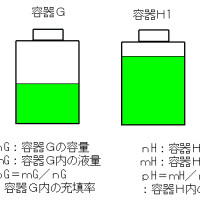
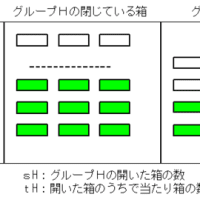
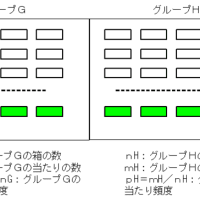
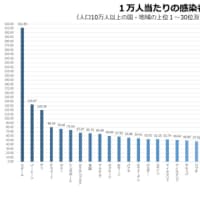
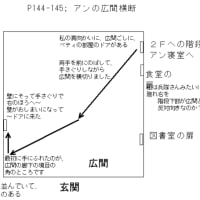
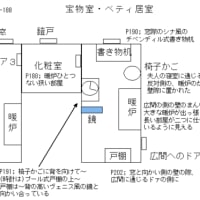

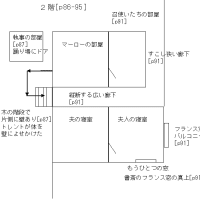
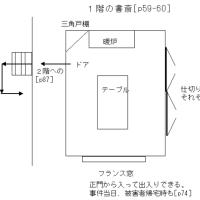






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます