日本付近の雨はどのようにして降るか

日本付近の雨(=冷たい雨)は、氷晶と過冷却水滴が混在する氷点下の雲の中で、氷晶の独占的な成長が発生する特殊な仕組みにより雨が降る。
過冷却水に対しては飽和していないが、氷に対しては飽和しているという中間の状態。
過冷却水滴→水蒸気が飽和していないので、蒸発進み、水滴は小さくなる。
氷晶→水蒸気が過飽和なので、水蒸気は氷晶にどんどん昇華凝結し、急速に成長していく。
⇒氷晶が周囲多数の過冷却水滴の雲粒を消費しながら独占的に成長していく過程=氷晶過程
大きくなった氷晶は、衝突併合過程を経て、雪やあられに成長。→溶けて雨粒になって地上に降りそそぐ。
対流雲(積乱雲、積雲)から冷たい雨が降るのは上記の通り。層状雲から冷たい雨が降る場合は、上層の巻雲から氷晶が落下し、中層、下層雲のなかで、雪に成長し、下層で溶けて雨になるという流れ。











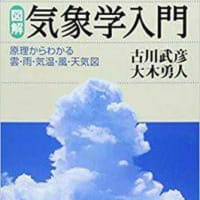
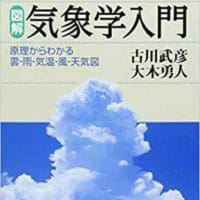
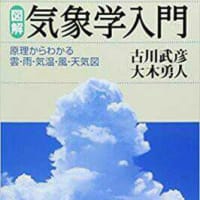
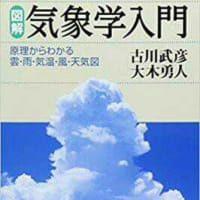
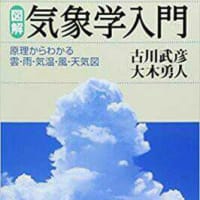
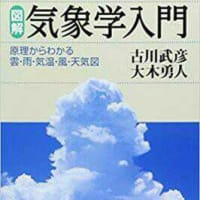
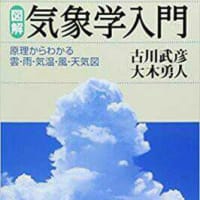
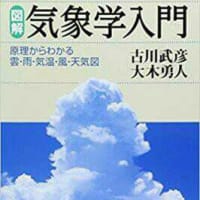
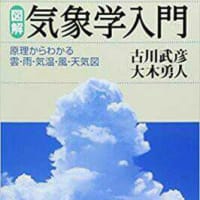
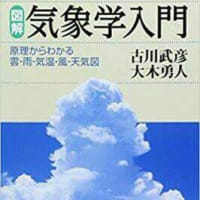
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます