
工芸科の課題研究の生徒12人は徹夜で穴窯実習を行いました。
(ちゃんと交代で仮眠するそうです)
実習の内容は、炉に薪を入れること。
朝9時半から翌朝の10時半まで、およそ25時間をかけ、炉内の温度を1250度まで上げる
という内容のものです。穴窯の前がマシニングセンター実習室。
ちょうど、マシニングセンターの使い方の勉強をしたかったため、
同じ時間に合わせて活動をしました。
電気炉やガス炉がある中、あえて「薪」で行う理由があるとのこと。
どうやら中のO2やCOやCO2等の雰囲気の状態で
「酸化反応」や「還元反応」が起こるようです。
どっちがどっちか忘れましたが、電気炉とガス炉は逆の
反応を示すそうで、1つの炉で両方できる「ハイブリッド炉?」もあるとか。
薪で行うのは酸化・還元どちらも交互になることと
(薪を入れた直後は不完全燃焼、その後は完全燃焼に移行)、
「灰」もかぶることで、独特の模様がでるとのことでした。
工芸科の子どもたちは工芸科のたくさんの先生と外部の作家の先生の指導の下、
窯の温度をリアルタイムで測定しながら、薪を入れるタイミング、投入する場所を
工夫して温度をあげていました。
実際、簡単に温度が上がりません。2時間交代で2~4人チームで始めていますが、
交代した時が大変の様子。
せっかく30分で30度上げたのに、交代したら20度下がっちゃった!
ということもしばしば見受けられました。
毎年準備して指導している、ベテランの先生も
「俺に代わったら温度下げちゃった、むむむ。」と、
温度を上げる方法はいくつかあるような様子でしたが、
その時の燃焼状態によって、適切な方法があるような
感じでした。
炉内の薪や炉自身のつもりになって、どうなっているのだろうかと
推測しながら適切な判断が必要な様子。
そのためには上・中・下の温度の時間的推移と
薪を投入した時に、明るい炉の中を一瞬で観察する力、
そして、煙突から出る蒸気、炎、すすの量や様子を観察する
そして判断する力、薪を入れる技量が要るようでした。

窯の温度は「上」「中」「下」の3か所で測定している様子です。
20時頃は800度くらいだったかな?上と下の温度差が80度近くありました。
24時ごろは1000度を超え、温度差は50度以下に収まり、
28時頃は1100度。温度差は30度以下。
翌朝8時ごろには1200度、温度差は20度以下、
終わる直前の10時ごろには1250度!温度差は5度以下。
機械の重要部品(精度が1/1000mm以下)の測定前に
「温度ならし」が24時間必要ということも納得!でした。
伝熱工学を体験的に理解できる、貴重な体験ですね。
24時間経過して、子ともたちの心理的変化には驚きです。
一生の良き思いでになるのでしょうね。












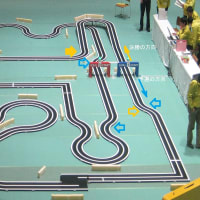
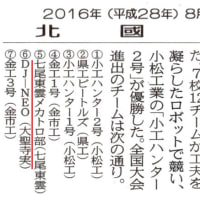
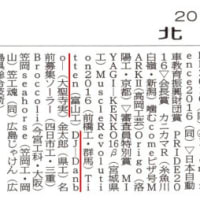





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます