
八中の同期生である川本(旧姓糸賀)悦子さんのグループ「オルタフルートアンサンブル」
の第22回定期演奏会が来る11月4日(日)に以下の演目で催されます。
・ディヴェルティメント=ジャズ(R.ギヨー)
・トリオ・ソナタ ロ短調 op.7/2(J.B.de ボワモルテイエ)
・3つの小品(E.ボザ)
・碧い月の神話(石毛里佳)
・ディヴェルティメント KV439b/4(W.A.モーツァルト)
・ロマンス op.5(P.I.チャイコフスキー)
・サウンド・オブ・ミュージック(R.ロジャース)
場所は、京急仲木戸駅から連絡橋「かなっくウォーク」で徒歩1分のところにある「かなっく
ホール」。開場13:30、開演14:00。入場無料です。
明るい色彩のリーフレット。僕の拙いパステル画の背景に合わせてくれました。
この絵、竹内栖鳳の「散華」という日本画を一部パクって制作。
名刺を一回り大きくしたぐらいの小さな図版を虫眼鏡で見ながらスケッチ。構図を考えて、
A4を一回り小さくしたサイズにして、背景を光明に変えて、描いたものです。
「散華」は、仏を供養するために蓮華の花びらを声明に合わせながらまき散らすことを云い、
竹内栖鳳の絵にも風に舞う花弁が描かれてあります。
でも僕の絵には一片の花びらも無し。なぜなら題名が「華音」と書いて「カノン」だから。
三人の菩薩が手にするフルートが奏でる調べがカノン。輪廻の伴奏曲。
このリーフレット(色彩はも少し鮮やか)、15,6枚手持ちがありますので、同期会の会場に
持参しますね。演奏会に興味のある方は、お持ち帰りください。
ブログトップへ戻る



















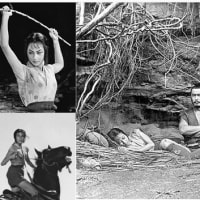
昨日(9/27)からスイスのジュネーブでお披露目された「若きモナリザ」ですが、
その真贋で喧々諤々のやりとりがなされているとか。
本物だとするのは、この絵を所有するスイスの財団「モナリザ基金」。
1913年に英国のアイルワース(ロンドン西郊)で見つかったので、「アイル
ワースのモナリザ」と呼ばれているのですが、米国人の絵画収集家らの手を経て
「モナリザ基金」が2010年に購入するまで、財団の専門家らが35年間にも
わたってダビンチ作である根拠を探すためにアレコレ調べていたようです。
そして今回の一般公開にあたって、300ページにも及ぶ調査報告書も公表した
とのこと。
それによると、レオナルド・ダビンチが51歳~54歳のころに手がけたものの
未完に終わったのが、この「若きモナリザ」で、その10年後に描き直したもの
がルーブルの「モナリザ」だと。
その根拠として
(1)同じルネサンス期の巨匠ラファエロがダビンチの作業場で模写したとされる
「モナリザ」の背景には柱が描かれており、「若きモナリザ」にも柱がある
(ルーブルの「モナリザ」には柱はない)。
(2)モデルとされるイタリア・フィレンツェの商人の妻リザ・ゲラルディーニは
1479年生まれで、作製時の年齢は25歳前後のはずである。
(3)同時代の美術評論家、ジョルジョ・ヴァザーリの記述には「(モデルの)婦人
は若く、唇は赤みを帯びている」とある。
(4)X線調査などでも、下図の筆致にダビンチの特徴がよく表れていた。
反論としては、
(1)「モナリザ」は、これまでにも多くの模写や模倣作を生んできているので、その
可能性がある。
(2)「若きモナリザ」は木の板に描かれた「モナリザ」と違って、ダビンチがほと
んど使わなかったキャンバスに描かれている。
(3)英国で20世紀になって発見されるまでの経緯が不明である。
僕に云わせると、根拠の(2)、本末転倒の最たるもの。だって「若きモナリザ」が
本物との前提にたって、25歳前後(20歳代前半の女性に見えるから)と云って
いるわけですから。
それに10年後に何故、同じ構図、同じ衣装で顔だけ老けたリザをダビンチが描こ
うとしたのか、その説明が付かないと思うのだけど。
反論(3)にあるように、ダビンチは「モナリザ」(「岩窟の聖母」も)をたいへん
大事にしていて、死ぬまで(1519年、67歳で歿)自分で持っていたと云われ
ていますので、それなら「若きモナリザ」も未完であるが故に未練をもって大切に
していた筈で、若き日から名声を博していたダビンチのそのような作品がどこに
どう流れたのかその経緯が不明というのは解せません。
根拠(1)は、ラファエロがいつ模写したのか証明されればハッキリすることですが、
それが示されていません。
根拠(3)も「モナリザ」(30歳代)のことを指していてもおかしくはありません。
根拠(4)に至っては、極めて精巧な模写を行えるだけのテクニックを有している者
であれば、当然の事です。
というわけで、僕は偽物説です。
うーむ、随分と長いタイトルだ。
今回は、10名いるメンバーのうち自他が原因の2名が欠けて
8名での、そしてピアノも欠けてフルートの音色だけの演奏会
となりました。
日本フルート協会常任理事でもある指揮者加藤克朗氏による
それぞれの曲についての解説が「プログラムノート」として、
平明な文体で書かれてあるのも大変有り難いですが、そこで
漏れたことを指揮棒を振る前に軽妙な語り口で語り伝えてく
れるのも中々に味わい深いものがあって好かったですね。
「ディヴェルティメント」というイタリア語が何か知らなかった
のですが、「喜遊曲」というものであり、現在のBGMのように
気楽に聴くものなんですって。
僕が調べたところでは、18世紀後半にオーストラリアを
中心に流行した、メヌエット・行進曲・舞曲などの多楽章
から成る、セレナードに類似した室内楽曲だそうです(あー
小難しい)。ハイドンやモーツァルトがその代表的な作曲家
だそうです。
演奏会でもモーツァルトの「Divertimento KV439b/4」という曲
が演奏されました。
上記ディヴェルティメントが3重奏であるのに対して、現代の
アーティストであるR(レイモン).ギヨーのそれは、アルト・
フルートを加えた4重奏曲。
モーツァルトのものは8人全員で、R.ギヨーのものは4人で
演奏。さてその醸し出す音色は?
僕が最も気に入ったのは、日本人好みのメランコリックなメロ
ディーラインであるチャイコフスキーの「ロマンス」。
この曲、彼の若き日の年上の恋人であるオペラ歌手のデジレ・
アルトーに捧げられたのだとか。でもその恋は破局した。
だってチャイコフスキーは女性よりも男性の方がスキーだった
から。
アンコールに応えて、「ふるさと」と「サウンド・オヴ・ミュージック」
の中から「エーデルワイス」を演奏。
180~190名ほどの聴衆が喧騒を一時逃れて憩うたオアシス。
今朝の朝日新聞の「声」に『集団的自衛権とは「参戦権」だ』と題する
ものが掲載されていました。
この20歳の大学生の論旨を要約すると、集団的自衛権が認められると、
同盟国(米国を指しているのでしょう)が他国と戦争を起こしたときには
日本も参戦することになりかねず、自衛とは別のものである、と云うもの
ですが、「自衛」を狭義にしか捉えていませんね。
自衛権は、急迫不正の侵害を排除するために、武力をもって必要な行為を
行う国際法上の権利であるとされています。現在の日本国憲法では、
自国に対する侵害を排除するための行為を行う権利である個別的自衛権は
認められているものの、相手国の先制攻撃を受けてからでないと反撃(それ
も自国領域内に限定)ができない専守防衛しか認められません。
この制約があるが故に日米安全保障条約が必要になっているわけですが、
例えば昨今騒がしくなってきた尖閣諸島の一件も、某国が軍事行動を起こ
して尖閣を占領した場合、米国海兵隊が日本の自衛隊と共にその奪還に動
いてくれるかと云うと、日本が某国から攻撃を受けたことが前提でないと
米国は軍事行動を起こせないでしょう。つまり日本側に被害が出て、初めて
共同の軍事行動に移ることができるわけです。
そこで自らが自国のために積極的な防衛をなすためには、専守防衛ではなく、
自衛権の発動(先制的自衛)を行えるように憲法の一部改正が必要になります。
さらに集団的自衛権が加えられることにより、相手国は同盟国である米国も
相手にすることになりますので、安易な軍事行動はとれなくなります。
以上のことは、第二次世界大戦後の1945年(昭和20年)10月に発効した以下の
国連憲章第五十一条で国際的に認められているものです。
「 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した
場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとる
までの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。」
ただし、武力攻撃の定義が曖昧であるがために、侵略的軍事行動等が自衛権と
いう美名にかくれてなされる(イラクのケースなど)こともあり得ますので、
憲法改正のときには縛りをかける必要があります。
某国が自国領とする尖閣に日本が建造物を造ったり、人を住まわせたりした
場合、自衛権と称して軍事行動を起こすことは十分考えられるのです。それを
恐れて何もせずほったらかしにしておくというのが民主党のとった戦略(?)
ですが、そのまま未来永劫均衡が保てるという保障は全くありません。むしろ
日米同盟の間隙をついて、そして日本が現憲法下では手も足も出せないことを
利用して、軍事力を背景に様々な圧力をかけて譲歩(屈服)させる手段を採る
でしょう。
そのようなことを防ぐ目的からも「自衛」とは何か、どのような手段でそれを
確かなものにすることが出来るか、等々を能々吟味した上で、必要であれば
憲法改正も拒むべきものであってはなりません。
20歳の学生は、憲法9条を持つのが、日本の誇りであり、ブランドである旨
を述べていますが、戦争放棄が戦勝国によって押付けられた手枷足枷でることは、
それら戦勝国によって設けられた国連において戦争放棄が謳われていないこと
からも明らかです。
徹底的に無力化を図ったにも係わらず、予想を覆して日本の戦後復興は目覚ましく、
国力も発言力も増し、国際的に果たす役割もそれに応じたものを求められるよう
になってきました。
その求められているものが終戦直後のものと大きく乖離している以上、過去の
ブランド(?)なぞに縋っているだけでは、日本の将来は暗澹たるものになると
言わざるを得ません。
♪まわるまわるよ時代は回る
別れと出逢いをくり返し
今日は倒れた旅人たちも
生まれ変わって歩きだすよ
未明(午前2時頃)まで選挙速報を見ていましたが、
一点を除いて、大勢が決したこともあって、寝床
に入ったのです。
その一点ですが、民主党の獲得議席がその時点で
56議席だったのが、今朝の新聞では57議席とな
っていたいたので、嗚呼滑り込みセーフかよ、と
云うものです。
お遍路で、4年間をかけて全国行脚というパフォ
ーマンスが見られず仕舞いになってちょっぴり残念。
でも極めて下卑た新潟のおばさんが、バラマキの
元祖未来の党の有象無象が、消滅してくれて溜飲
が下がる思いをしていたから、寝覚めは悪くない。
今回の自民党の大勝の原因は、敵失にあるという
のが、ジャーナリストらの大半の見方ですが、そう
いった引き算的な判断だけで無いのは、第三局の
日本維新の会やみんなの党が左程の議席数獲得に
至らなかったことからも明らか。
閉塞感でうつむき加減の日本の現状を打破するのは、
ムードという実体の伴わないものではなくて、真の
政治力であり、そういった力を備えていると云うより、
そういった時代がかってあったと云う経験則から、
そこへの回帰を望んだからではないかしらん。
首相に安倍晋三が付くということになると話は別です。
それで、タイトルの「約束の日」となるわけですが、
同名の書籍(幻冬舎、小川榮太郎著)では、平成18年
9月から翌19年9月までの一年間に安倍政権が成し遂
げたこと、成し遂げようとしていたこと、が文芸評論家
の目を通して事細かく、ドキュメンタリーとして記述
されています。
龍馬が「日本を今一度せんたくいたし申候」と、身命を
賭した革命とも呼べる改革に匹敵することを安倍首相
が目指していたことがよく分かる一冊です。
安倍首相退陣の引導を渡したマスコミ、就中朝日新聞
や週刊朝日は、安倍の「戦後レジーム(体制)からの脱却」
としての、憲法改正や対外(特に中国)政策、公務員
制度改革、教育基本法改正といったものが気に入らな
かったようで、安倍が二度と立ち上がれないようにと
叩きに叩いて“お坊ちゃん政治家の政権放り出し”と
まで貶めたのです。
で、「約束の日」。
同書で著者は
“私は、切望している。この終わりなき敗北から、
日本が、自立した国家の物語を取り戻し、希望を
取り戻す日が一日も早く訪れることを。そして、
安倍晋三が、「果し得ていない約束」を果すために、
今こそ、執念の炎を燃やし、政権を再度奪還して
くれることを。(中略)
安倍晋三内閣総理大臣が再び誕生する日。尖閣や
竹島、震災復興や原発問題で動揺し続ける日本国の
リーダーに、世界中が注視する就任記者会見。膨大
なカメラの放列が放つフラッシュの閃光とシャッター
音をしたたか浴びる安倍首相が、今こそ再び「戦後
レジームからの脱却」を、国民と世界に宣言する
その日。―その日こそ、前回不本意極まる辞任を
した安倍が、国民に対して内心密かに期待してきた
「約束の日」に違いない。
そして、第二次安倍政権の挑戦が、国民共有の物語
になった時、我々は胸を張って「日本人」に戻る
ことができるだろう。”
と締め括っています。
その「約束の日」が間近に迫っています。
以前(1999年)には、ノストラダムスの大予言とか云うものがあって、
今回は、マヤ文明で使用されていた長期歴という暦が2012年12月21日
から12月23日頃(要するに冬至)で終わっていることから、2012年
12月21日に人類が滅亡すると云うもの。
その長期歴ですが、ある起点日から13バクトゥン(1バクトゥン=144,000日)、
すなわち187万2000日(マヤでは1年を360日としていたので、5200年に当たる)
で表現されていて、2012年12月21日がその187万2000日目に当るそうです。
その起点日を逆算して確かめたのでしょう、2007年に英国のホゼ・アグエイアス
が自著『マヤンファクター』の中で、また2009年には米国のエイドリアン・
ギルバートの著書『マヤの予言』によって、2012年12月21日がその日とされる
ようになりました。
今年の冬至の日には、銀河系の中心とされている(飽く迄地球から見ての話で
すが)いて座、それと太陽と地球とが一直線に並ぶそうで、それだけのことなら
毎年起こっていることなので別に珍しいことではないのですが、地軸(黄道面に
対し約23.4度傾いている)の垂直真正面に太陽が向く(夏至と冬至)ときに、
いて座までが並ぶのは、約13,000年に一度という希少現象。
また、太陽そのものの活動極大期が2012年頃に当たっていて、太陽嵐が発生して
地球に何らかの影響を及ぼすと考えられています(エイドリアン・ギルバートは
このことと関連付けている)。同じことは1957年にも起こっていて、その時には
何ともなかったので大丈夫、と云いたいところですが、前回と違って今回の場合
には、地球を取り巻く磁気圏に巨大な穴が発見(2008年12月)されているので、
そこから大きな被害に結びつくと云われたりしています。
マヤ文明では、天文学が発達していましたが、人類の環境破壊による磁気圏の
綻びまでを予測することができる筈は無く、先に挙げた『マヤンファクター』
において2012年12月21日に「新しい太陽の時代」が始まるとされているように、
また5200年だけでなく、周期には26000年、52000年、260000年といったもの
まで考えられていたことから、5200年はある周期の単位と捉えるべきもので、
決して世界の終末を意味するものではありません。
終末論は、宗教にとっては信者獲得の常套手段で、…信じる者は救われる…
何から?…世界の終焉から…、といったノアの箱船。
仏教ですら、現世を語らず、来世を説く。これを末世と云う。
「あら何ともなや昨日は過ぎて河豚汁」(芭蕉)
今年のノーベル文学賞は、中国の莫言(ばくげん)が受賞したものの、
中国政府の検閲を容認する「体制側の作家」との批判を受けるなど、
色々と物議を醸したことは記憶に新しいですね。
その選考過程は、受賞後50年経たないと、ノーベル財団の守秘義務
といった厄介なものがあって、明らかにならないのですが、少なくとも
村上春樹が候補に挙がっていたという事実は無いと思います。
さて、タイトルの「コーボー」ですが、紛れも無く受賞確実であった
安部公房のことです。
なぜ「筆を選ばず」なのかは、さて置いて、安部公房が日本人で二人目
のノーベル文学賞を目前に急死したことで、大江健三郎に転がり込んで
きたのは、今年3月の読売新聞の取材に対して、“急死しなければ、
ノーベル文学賞を受けていたでしょう。非常に、非常に近かった”と
ノーベル文学賞を選考するスウェーデン・アカデミーのノーベル委員会
のペール・ベストベリー委員長が答えていることからも容易に察しが付
きます。
安部公房が亡くなった後にノーベル賞委員会の食堂にサミュエル・
ベケット(1969年受賞)と安部公房の写真が並べて飾られていたのは有名
な話で、今度は君(安部)の番だったのに、とでも云いたかったのかし
らん。
大江健三郎自身も、受賞時(1994)に、“もっと長生きしていれば、自分
ではなくて、彼らが受賞したであろう”と述べていますし。
彼らとは、安部公房(1993.1.22歿)、大岡昇平(1988.12.25歿)、井伏
鱒二(1993.7.10歿)の三人。
大江健三郎ですが、僕は彼の作品は『個人的な体験』しか読んでいない
ので何とも評価し難いのですが、肌が合わないとしか言いようが無く、
だから他の作品も読みたいとは思わなかったのですが、それに対して、
安部公房は大変魅力的というか魅惑的な作家でした。
僕が安部公房に初めて触れたのは大学生のときで、確か『他人の顔』だった
と思うのですが、理系の作家らしい表現が至る所にちりばめてあって、
それが難解とも評される所以でもあるのですが、理系の学生にとっては
かえってそこに面白みを感じてしまうのです。
な原作を―脚本が安部公房本人ということも手伝っているのでしょう―よくぞ
ここまで捨象して映像化できたものだと感心しきり。
それで、原作を40数年振りに読み返してみました。
安部公房の作品に共通しているのは、暗喩や直喩などの修辞が多用されていて、
それがミルフィーユ―練り羊羹のように様々な味覚が均一化されたものとは
違って―のような味の厚みや深みになっていて、物語の伏線にもなっている
のです。
例えば、
“地上に、風や流れがある以上、砂地の形成は、避けがたいものなのかもしれ
ない。風が吹き、川が流れ、海が波うっているかぎり、砂はつぎつぎと土壌の
中からうみだされ、まるで生き物のように、ところきらわず這ってまわるのだ。
砂は決して休まない、静かに、しかし確実に、地表を犯し、亡ぼしていく…
その、流動する砂のイメージは、彼に言いようのない衝撃と、興奮をあたえた。
砂の不毛は、ふつう考えられているように、単なる乾燥のせいなどでなく、その
絶えざる流動によって、いかなる生物をも、一切うけつけようとしない点にある
らしいのだ。年中しがみついていることばかりを強要しつづける、この現実の
うっとうしさとくらべて、なんという違いだろう。
たしかに、砂は、生存には適していない。しかし、定着が、生存にとって、絶対
不可欠なものかどうか。定着に固執しようとするからこそ、あのいとわしい競争
もはじまるのでなかろうか?もし、定着をやめて、砂の流動に身をまかせてしま
えば、もはや競争もありえないはずである。現に、沙漠にも花が咲き、虫や
けものが住んでいる。強い適応能力を利用して、競争圏外にのがれた生き物
たちだ。たとえば、彼のハンミョウ属のように…”。
とか高校とか、何の教科とかは一切不明。安部公房にとっては教師という職業の
プロトタイプに意味がある。彼の作品にしては珍しくこの主人公に仁木順平と
いう名があることを読者は最後の最後に知ることになる)が妻にも同僚にも行き先
を告げずに沙漠に棲むハンミョウ属の変種を採集しに目的地(映画では静岡県の
浜岡砂丘がロケ地として使われた)に着いたときの語り。ですから、物語の出だし
の部分なのですが、見事なプロローグになっていて、主人公の男の来し方ばかり
でなく、行く末、つまりエピローグまでを暗示している。
「砂の女」なんてあるものだから、つい砂かきで糧を得ている、主人公が搦め捕ら
れた三十前後の女(映画では岸田今日子)のことだと思ってしまい勝ちですが、小説
でも映画でも添え物としての役割しか与えられていない。で、思うに、擬人化して
いるのですよね、砂をね。
映画(1964年製作)は、練り羊羹にはならず、削ぎ落としても、しっかりしたミル
フィーユの形を留めている。
名ピアニストであったカナダ人のグレン・グールドは、殊の外、この映画がお気に
入りであったようで、百回以上も観たと、そして、“カラーでは見たくない”と
語っています。
確かに、無機質の砂が主人公の映画ですから、モノクロじゃないと…なんて断定
したら大きな間違い。安部公房の作品は含みが多いから、カラーで限定してしまうと
その魅力が半減どころか台無しになってしまうのです。
その好例が、『燃えつきた地図』。『砂の女』に引き続いて安部公房が手がけた
書下ろしですが、これも映画化(1968年製作)されました。監督(勅使河原宏)も、
脚本(安部公房)も、音楽(武満徹)も、すべて『砂の女』と同じ。ただし、映像
がモノクロではなく、カラー。
『砂の女』がキネマ旬報ベストテン1位、第17回カンヌ国際映画祭審査員特別賞に
輝いたのに対して、『燃えつきた地図』の方は鳴かず飛ばずといった有様なのも
納得。
『燃えつきた地図』の不可思議な世界へもう一度どっぷり浸かり、それから未読の
晩年の作品を購入してじっくり味わってみようと。
安部公房のことを理系の作家と云いましたが、彼、東大の医学部卒なんです。でも
医者にはならずに作家になった(途中から作家に転身した例はありますが、彼は
一度も医者であったことが無い)。
なぜって?卒業試験に二度までも落ちそうになったから。そこで安部公房が奥の手
を。“医者になるつもりはありません!”。これで恩情あるはからいがとられて
無事卒業。だから、医師国家試験も受験せず。
でも医学は一通り学んでいる筈。なのに、1992年(平成4年)12月25日の深夜、執筆中
に脳内出血で倒れ、退院後も自宅療養を続けていたのに、悪化しての再入院後、急性
心不全のため死去(享年68)―高熱と意識障害があったのに、翌日には回復、でも
翌々日の早朝に亡くなった―というのは何か納得が行かない。
愛人のところで腹上死という風説があったけど、愛人からの連絡を受けて、慌てて
病院に運んで、そのように取り繕ったと云うのは十分あり得そう。(何かの映画で
同様のストーリーがあった。)
腹上死でノーベル賞を逃した、という方が安部公房らしくって好いけど。
で、タイトルの「筆を選ばず」。これから購入して読もうと思っている晩年の二作
(『方舟さくら丸』1984年、『カンガルー・ノート』1991年)だけど、いずれも
ワープロで執筆されているのです。未完に終わった『飛ぶ男』などの遺作も、死後、
ワープロのフロッピーディスクから発見されていますし。
『燃えつきた地図』には「“燃えつきた地図”をめぐって」と題する8頁ほどの付録
が付いていて、そこでは、初めの100枚が作者自身によりボツにされ、全てが書き
直しになったり、ゲラの段階でも、ただ書き込むだけでなく、ある部分を切り取り、
そこへ新しい原稿が入り、切り取った部分が後半に行く…やっと初校が終わり、再校
になってまた結末のところが全部変わった、と編集部が苦心譚を語っていますが、
おそらくそのようなやり方が公房流なのでしょう。
ですから、まだ出たてのワープロ(専用機)ですが、ちょっと高価であっても、直ぐに
飛びついたのでしょう。何たって切り貼りが自在ですからね。
で、公房は筆を選ばず、理系らしく文明の利器に乗り換えた。