
八中の同期生である川本(旧姓糸賀)悦子さんのグループ「オルタフルートアンサンブル」
の第22回定期演奏会が来る11月4日(日)に以下の演目で催されます。
・ディヴェルティメント=ジャズ(R.ギヨー)
・トリオ・ソナタ ロ短調 op.7/2(J.B.de ボワモルテイエ)
・3つの小品(E.ボザ)
・碧い月の神話(石毛里佳)
・ディヴェルティメント KV439b/4(W.A.モーツァルト)
・ロマンス op.5(P.I.チャイコフスキー)
・サウンド・オブ・ミュージック(R.ロジャース)
場所は、京急仲木戸駅から連絡橋「かなっくウォーク」で徒歩1分のところにある「かなっく
ホール」。開場13:30、開演14:00。入場無料です。
明るい色彩のリーフレット。僕の拙いパステル画の背景に合わせてくれました。
この絵、竹内栖鳳の「散華」という日本画を一部パクって制作。
名刺を一回り大きくしたぐらいの小さな図版を虫眼鏡で見ながらスケッチ。構図を考えて、
A4を一回り小さくしたサイズにして、背景を光明に変えて、描いたものです。
「散華」は、仏を供養するために蓮華の花びらを声明に合わせながらまき散らすことを云い、
竹内栖鳳の絵にも風に舞う花弁が描かれてあります。
でも僕の絵には一片の花びらも無し。なぜなら題名が「華音」と書いて「カノン」だから。
三人の菩薩が手にするフルートが奏でる調べがカノン。輪廻の伴奏曲。
このリーフレット(色彩はも少し鮮やか)、15,6枚手持ちがありますので、同期会の会場に
持参しますね。演奏会に興味のある方は、お持ち帰りください。
ブログトップへ戻る



















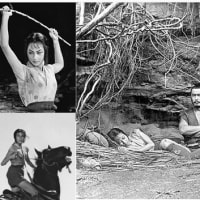
われ先と競ってほころび、はや満開の風情の桜花ですが、
漢字都都逸なるものがあって、
「櫻という字を分析すれば、二階の女が気にかかる」
昔の漢字は難しいものが多かったので、都都逸仕立てにして
覚えたのですが、都都逸というだけあってお堅いかんじも実に
たおやかで色っぽいですね。
本家本元には
「君は吉野の 千本桜 色香よけれど 気が多い」
なんて云うのがある。
「可愛いお方に 謎かけられて 解かざぁなるまい しゅすの帯」
「主と私は 玉子の仲よ わたしゃ白身で 黄身を抱く」
なんて艶っぽいものがあれば、
「遅い帰りを かれこれ言わぬ 女房の笑顔の 気味悪さ」
「おまはんの 返事一つで このカミソリが 喉へ行くやら 眉へやら」
と強持てのものもあります。
都々逸は基本的には「七七七五」調ですが、最後の例のように
五字冠りと呼ばれる「五七七七五」のものもあります。
中でも好きなのが、恬淡とした
「たんと売れても 売れない日でも おなじ機嫌の 風車」
俳句にも
「街角の 風を売るなり 風車」(三好達治)
と中々に味わい深いものがあります。
風車が春の季語になったのは、風車売によって春に多く売られたから
ですが、春の薫りを売るというところがいかにも詩人らしい。
花見もここ数日が見ごろでしょうか。で、
「桜花 仕舞も艶(あで)に 風車」(鈍末)
今日は、春分で、お彼岸の中日。お彼岸と云えばボタモチが付き物。
子供の頃、オハギと云っていた気がするけど…、呼び方には諸説紛々あって、
いずれが正しいのか分からないのだけど、一番ポピュラーなのが、春は牡丹に
なぞらえてボタモチ、秋は萩の花に見立ててオハギと呼ぶもの。作り方は同じ
だとする説もあれば、いやそうじゃないとする意見もあって、もち米で作った
ものがボタモチで、うるち米(普通の米)で作ったものがオハギだ、いやいや
もちで作ったものがボタモチでもち米で作ったものがオハギだ、なんて云う。
中身の作り方じゃなくて、あんをまぶしたものがボタモチで、きな粉をまぶした
ものがオハギだとする説もある。いやいやあんが問題で、こしあんがボタモチ
で、つぶあんがオハギだ、いやその逆だ、なんて何が何だかわけのわからない
説まであって、さらに追い打ちをかけるようにして、皆殺しにしたものがボタ
モチで、半殺しにしたものがオハギだと、甚だ物騒な説まで飛び出してくる。
でも、このボタモチ(オハギと呼べばいいのかな)、彼岸に食べるから春と秋の
ものだけかというと、そうじゃない。夏には「夜船」(よふね)、冬には「北窓」
(きたまど)と呼ばれていたらしいから。
もちのように臼と杵でペッタンペッタンと搗くわけではないので、音がしない。
で、周りのひとに知られずに作ることができるから「搗き知らず」。これが
同音異義の「着き知らず」―多分「白河夜船」から来ているのでしょう。京
を見たふりをした者が、京の白河(地名)のことを問われ、川の名と思って、
夜船で通ったから知らないと答え、うそがばれたという話から、何が起こって
も気が付かないほど、ぐっすり寝込むことのたとえとなったこと―から「夜船」
となった。
また、搗きが入らないから「搗き入らず」となって、そして「月入らず」―月の
光が入らない北側の窓―から「北窓」となった。
要するに、もち米、うるち米を等分に合わせて蒸し、すり鉢で粗ずりしたものを
団子にして、あん、きな粉、ごまなどをまぶした鎌倉時代の掻餅(かいもち)を起源
とするもので、呼び名が違うだけ。
掻餅がボタッとした大振りのものになって、ボタモチ。それに、ことわざでも
ボタモチを使ったものはあってもオハギは見かけたことが無いから、「棚から牡丹餅」
ならぬ、やはり「はなからボタモチ」だったのだと…。(そして季節ごとに優雅な
名が付けられていったのだと…。)
お彼岸には、
殺生は禁物で
「彼岸とて 袖に這いする 虱かな」(一茶)
と、痛し痒しの人情あれば、
「病牀に 日毎餅食ふ 彼岸かな」(子規)
と、心(うら)悲しい此岸(しがん、この世)がある。
最近は、和菓子屋だけじゃなく、スーパーやコンビニでも購入することができて
重宝していますが、昔ながらに手作りする場合は、ボタモチをオハギより大きめに
作るのが作法らしい。で、
「童(わらわ)らの 頬ゆるめらむ 春彼岸」(鈍末)
註)「彼岸」だけで春の季語(秋の場合には秋彼岸とする)だけど、
春を強調したいから、あえておきて破り。
ソメイヨシノが東京都心で開花したと、気象庁が今日発表。
でも、僕のところの横にある木々は発芽はあるものの、固く
閉じたまま。もっとも気象庁による定点観測地点の一つである
靖国神社の標本木だって、5、6輪ちょっとが咲いている
だけらしい。
例年より10日も早いとのことなので、例の『ことばの歳時記』
で26日のところを見てみたら、「山が笑う」の内題が。
そこには“『臥遊録』(がゆうろく)という本に「春山は笑って
いるよう、夏山は滴るよう、秋山は装うよう、冬山は眠るようだ」
と評したのがはじめという。自然や風景を擬人化する点では中国
にしばしばたくみな表現に出会うが、日本では珍しい。”とある。
で、日本の書かと思って調べてみたら、中国は南宋の呂祖謙なる
人物の手になる物。
さらに調べると(『広辞苑』)、“画品、郭煕四時山「春山淡冶に
して笑うが如く、夏山蒼翠として滴(したた)るが如し、秋山
明浄にして粧うが如く、冬山惨淡として睡(ねむ)るが如し”と
ある。
“画品”って、絵画の品位のことですから、そういった書の中で、
北宋の画家郭煕が“四時”(四季)の山の絵について語ったこと
らしい。
いずれにせよ、原典が中国であろうが、「山笑う」「山滴る」「山装う」
「山眠る」は俳句の季語として、しっかり日本に根付いている。
「故郷や どちらを見ても 山笑ふ 」(子規)
で、僕はと云うと
「山笑ひ 吾は長閑に 欠伸(けんしん)す」(鈍末)
今日(3/12)は、旧暦の2月1日に当たります。
昔々の大昔(天平勝宝4年、752年)のこの日に始まったとされるのが、
二月堂建立に伴い行われた、東大寺の僧侶が万人の悔悛をなし国家安泰と
民の豊楽を祈願するという法要。(現在は、3/1~3/14まで行われています。)
その法要の中でも人々に親しまれているのが、今日(3/12)行われる修二会
(しゅうにえ)で、いわゆるお水取り。
呪師(ずし。陀羅尼を誦えて加持祈祷をする僧)が練行(ねりぎょう)衆の行列
を従えて「若狭の井」(若狭の国と地中でつながっているとされている)から香水
(聖なる水で、あらゆる病に効験あらたかとされている)を汲み上げる行事ですが、
午前2時ごろに行われたので、もはや過去のことなのですが。
お水取りに続き行われるのが、馬鹿でかい松明を持った練行衆が二月堂内陣を
駆け回る達陀という物騒な行事で、その火の粉を被るとその年は無病息災という
ことらしい。(その映像を以下のサイトで見ることができます。)
http://www.yomiuri.co.jp/stream/m_news/vn130304_2.htm
「水取りや 瀬々のぬるみも 此の日より」(蓼太)
江戸中期の俳人大島蓼太(りょうた)の詠んだ句にもあるように、お水取りは
古都に春の訪れたことを告げる行事でもあります。
その蓼太が慕った(芭蕉の奥の細道を辿って、その遺吟を集めた)芭蕉の句。
「水取りや 籠の僧の 沓の音」(芭蕉)
法華堂(三月堂)の北門にその句碑があるのですが、この句、本来は
「水取りや 氷の僧の 沓の音」
だったそうです。芭蕉直筆の『天理本』には「二月堂に籠りて」との前書きに
続いてこの句が認めてあったこと、そして「氷の僧」の方が芭蕉らしい切れ味
を感じさせることから、まず間違いは無いと思いますが…。
「初雪や 二の字二の字の 下駄の跡」と同様に、世人に分かり易い通り句と
なってしまったのでしょう。たぶん「こおり」が「こもり」と聞き間違えられて。
「水取りや 氷で芭蕉 くさめする」(鈍末)
早乙女主水之介の退屈の虫が騒ぐのは気まぐれのようですが、
天球上の1点から黄道に下した大円の足を、春分点から東の方へ
測った角距離である黄経がピッタリ345度となったときときっちり
決まっているのが「啓蟄」で、太陽暦の3月5日か6日に当たり
ます。(今年は今日、3月5日)
天球:観測点から眺めた、半径無限大の仮想の球面で、天体
の見かけの方向を表示する座標を決めるために想定される。
黄道:地球から見て太陽が地球を中心に運行するように見える
天球上の大円。天の赤道に対して約23.4度半傾斜する。
黄道が赤道と交わる点が、春分点と秋分点。
ま、分からないところはさて置いて、二十四節気の3番目に当たり
ます。ですから、次の春分(3/20)までの15日間がこの啓蟄の期間。
立春、雨水、啓蟄、春分、清明、穀雨、
立夏、小満、芒種、夏至、小暑、大暑、
立秋、処暑、白露、秋分、寒露、霜降、
立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒
中国の太陰太陽暦(いわゆる旧暦)では、節月は約30日だから、
1年が360日となってしまうので、閏月を設けて調整した。
そして暦と季節のずれを調整するために二十四節気が考案された。
ま、分からないところはさて置いて、「蟄虫咸動きて、戸を啓きて、
始めて出づ」を語源として成句となったもので、蟄虫(地面の中に
かくれて冬眠している蟻、ミミズなどの地虫や蛇、蜥蜴、蛙の類)
が長い冬眠から覚めて、穴から地上に出てくるさまを表わしている
そうな。
「啓蟄の 蟻が早引く 地虫かな」(虚子)
と、「啓蟄」を季題に定着させた高浜虚子が詠めば、その虚子に師事した
富安風生は、
「啓蟄の もろもろの中に 老われも」(風生)
と、身につまされるようなような句を詠む。
一茶は、
「大蛇や 恐れながらと 穴を出る」(一茶)
と、啓蟄を使わず、一茶これにありを地で行くユーモラスな句。
三月、弥生は、「弥(いや)」「生(おい)」が変化したものとされていて、
いよいよはえのびる、つまり草木が芽吹くさまを表しています。
『ことばの歳時記』(金田一春彦)によると、“「芽ぐむ」「芽ざす」とは、
木の枝の先にちょっとそれとおぼしいものが現われた状態であり、「芽ばる」
「芽だつ」は、その芽が大きくなった状態。”であり、そして“「芽吹く」
というと、遠くから見てこずえ一帯がボオッと青みをおびている感じである。”
とあり、陽気につられて、恐縮しながら大蛇もにょろりにょろりと顔を出す
のが、この時季ということになります。
「啓蟄や 鬼を追い出し 蛇が出る」(鈍末)
一難去ってまた一難、世の中複雑で、長閑な春とは参りませんようで…。
ま、分からないところはさて置いて、朝昼食兼用の僕の腹の虫は定刻に鳴る。
「春告鳥」
ここ数日、目覚めるのが早くなりました。
それまでは冬眠状態と云ってよいほどに床の中でぐずぐずしていたのに、
「春眠暁を覚えず」とはいきません。
齢の所為ではなく、やはり日差しの強さによるものだと、自分自身を納得
させているのですが…。
で、新聞に挟まれた広告を見ていたら、「鉄道お忘れ物市」なんていうのが
あって、傘とか鞄とか忘れやすいものであればなるほどと思うのですが、
ブランド時計とか指輪とかネックレスとかメガネとか、果ては衣服とか、
身に着けているものをウッカリ忘れてしまうものかな、なんて首を傾げて
しまうわけです。
しかも、忘れ物であってもその品物(の元値)によって値段に違いがある。
で、忘れ物も混じっているか知れないけど、バッタもんだとか、いわく因縁
付きだとか、なんだらかんだらも在庫一掃を兼て売り払うつもりの催し物
なのかな、なんて思ってしまうわけです。
2/28~3/2、大田区産業プラザPIOの2F小展示ホールで開催。
最終日(10:00~15:00)を除いて、10:00~18:00。いずれも超特価?
ま、物忘れは季節に関係なく、増加傾向にありますが、特にこれからの季節
は気を付けなければ。
「早春賦」の安曇野と違って、ここ大田区の梅屋敷辺りは一足早く春が訪れた
ようで、僕の住まいするマンションの庭にあるいずれかの樹木で鶯の鳴き声が。
(早起きは三文の得?)
鶯には、春鳥、花見鳥、歌詠(うたよみ)鳥、経読(きょうよみ)鳥、匂鳥、人来(ひとく)
鳥、百千(ももち)鳥など、いろいろの別名が有りますが、いちばんぴったりなのは
何と言っても「春告(はるつげ)鳥」。
それと、魚のブリとかカツオとかと同じように、鶯も成長過程によって名前が
九つも変わるそうで、卵からかえって三日目がクシ、四日目がコハリ、五日目が
オーハリ、六日目がサキシラミ、七日目がサキビラキ、八日目がコイチョー、
九日目がオーイチョー、十日目がブットー、十一日目がダチ(巣立つの意)とのこと。
人間だって、アカンボー、ニュージ、ヨージ、ガキ、アオニサイ、ワカゾウ、
オヤジ、ジジイ、オイボレ…と、鶯に負けず劣らず結構変わるけどね。
で、今朝来訪した鶯、まだ舌っ足らずな鳴き声。
「春浅し 法華経読の 覚束無」(鈍末)
註)覚束無:「おぼつかな」と読み、おぼつかないこと。
サラリーマン時代は、2月は儲け月と思っていたけど、今は何か損したような気が
します。
♪流れる季節たちを 微笑みで
送りたいけれど
:
春なのに 春なのに
ため息 またひとつ
によると、「blue rose」は有り得ないものを指す言葉でしたが、2004年6月に
遺伝子組換え技術により誕生し、今や店先に並ぶようになりました。
バラにはそもそも青の色素の遺伝子がないので、品種改良では青をつくり
出すことが出来ない。それで遺伝子組換えという荒業で、青色色素をつく
り出す遺伝子をパンジーから取り出してバラに移植した。(14年もの歳月を
要した。)
バラに遅れること8年、昨年の今頃(2月15日)に千葉大が、やはり遺伝子組換え
技術を使って、青の色素の遺伝子がない胡蝶蘭にツユクサから取り出した遺伝子
を組み込んで、青い胡蝶蘭をつくり出すことに成功しました。(こちらは4年の
歳月で済んだ。)
胡蝶の形をした紅紫色の花を付けるレンゲ草を詠んだ句に
「手にとるな やはり野におけ れんげ草」(瓢水)
があります。あるがまゝが好い、というものです。
もっとも、滝瓢水は、「ぼんち」を地で行くような放蕩人で、この句を
詠んだ切っ掛けというのも、大坂の友人松木淡淡の門人のひとりが気の
進まぬ遊女を大金を積んで身請けしようとしたのを諌めてのこと。
ギリシャ神話には、精霊が変身したレンゲ草を摘み取ってしまった姉(姉妹で
祭壇に飾る花を摘みに野にやってきていた)がレンゲ草に変えられてしまう
際に「花はみな女神が姿を変えたもの。もう花は摘まないで」と妹に言い残
す、というものがあります。
で、
「青丹よし 触らぬ神に 祟りなし」(鈍末)
これって季語がないから川柳、というより狂句。それに枕詞のようだし、諺を
取って付けたようなものだし、♪とてもブルー。
「よし」は「縦し」と書いて「ままよ」(なんとでもなれ)の意。つまり、
青だろうが赤だろうが、どうでもいいじゃないか、あるがままが一番、という
ことなのですが…。
♪だけど とてもブルー…気になるけど 知らぬふり…。
残される時が来るとしたなら
君は今よりぼくを愛して
生きて行くことが出来るかい
この世にたった一人が
残される時が来るとしたなら
君が残るかぼくが残るか
今すぐに答えられるかい
ブルークリスマス アアア…
不幸な星が一つまたたき
悲しみのメロディが
乾いた唇をふるわせる
ブルークリスマス アアア…
青い星 青い雪 青い花 青い酒
青い涙がこぼれ落ちる
この世にたった二人が
残される時が来るとしたなら
君は今よりぼくを愛して
生きて行くことが出来るかい
うーむ、不信感いっぱい。青もいっぱい。
で、映画ともどもヒットには繋がらなかった。
巡らし、その囲いの中での監視付きの振る舞いは許すものの、柵を乗り越え
ようとすると、寄ってたかって鉄槌を下す。これはかって日本が経験したこと
であり、現今は隣国がその矩を超える機会を虎視眈々と窺っている。この
DNA、おいそれと変わる筈がない。
題名に使われている「ブルー」は、ブルーマンデー、ブルーデーなどと同じ
「憂鬱」を意味するもので、そういった気分充溢の中で、青い血で大地を
塗り立てることにより、救世主の出現を待とうとする、手前勝手な、常套
手段ともいえる、蹂躙という名の神の啓示。
物語の最後は、体制側の殺戮者が、青い血の恋人を、二人で祝うためのクリ
スマスケーキにキャンドルを灯し待つ恋人を、射殺する。
その流れ出る青い血を目にして、使命感から解き放された殺戮者は、その銃口
を包囲している殺戮者たちに向けるが、直ちに射殺される。
降り積もった雪の上に広がる殺戮者の赤い血潮に恋人の青い血が流れてきて、
分離することなく、溶け合う。
この映画の挿入歌も同じ「ブルークリスマス」。
でもブルーの雪の降る有名なエルヴィス・プレスリーのものではなく、当然
ながらMADE IN JAPAN(作詞:阿久悠、作曲:佐藤勝、歌:Char)。
「BLOOD TYPE:BLUE」とあるように、この血液の色を題材にした映画
(1978年、東宝、岡本喜八監督)で、倉本聰のオリジナルシナリオによる
SF。(宇宙人だか、火星人だか、昔の想像画だとタコとイカの合の子の
ような姿をしていたから、それがヒントになって、「BLOOD TYPE:BLUE」
となったのかしらん。)
UFOの光を浴びた人間は、その血液が青く変色し、性格も穏やかなもの
に変化する(どす黒いものが無色透明なものになるということの寓意?)。
それが世界中のあちこちで起こる。しかも出産した子供に遺伝される。
つまり世界中に蔓延することがハッキリする。
で、UFOの真の目的が那辺にあるか探ろうともせず、何時の世も同じ
(DNAに刷り込まれた)異物排除の論理が働き、地球規模での国家的陰謀
として、その抹殺が謀られます。
アウシュビッツを想わせる強制収容所送りや、人体実験、ロボトミー化、
自殺に見せかけた謀殺、といった初期的排除過程を経て、最後はクリス
マス・イブの午後10時を一斉殺戮の時と決めることになる。
血液の色を借りていますが、肌の色による差別・排除の歴史を非難・批判
しようとした作品であることは確か。
その殺戮に至る経緯が中途半端なものになっているのですが、そのことに
当の倉本聰が不満を漏らしていることから、彼の意図した眼目となるシーン
がカットされていたことは確かで、それがアメリカ合衆国大統領と国務長官
による、青い血の人間の処理を画策する、ホワイトハウスのシーンである
ことに疑いの余地はありません。(直截的に過ぎるからカットされちゃった?)
イカの話の続きで恐縮ですが、イカにはなんと青い血が流れている。
なので、飛翔するイカの身体が青く光り輝いていたのもむべなるかな。
飛翔が観察されたイカの群れは、全長(ヒレの先から腕の先まで)
が約203~225mm(外套長122~135mm)なので、アカイカ科のアカ
イカ(約45cm)またはトビイカ(約30cm)の成体になる前の若体と
考えられていて、後者は青、前者は名前の通り赤みががった青
(紫)です。
タコも青い血が流れていて、紫褐色か灰色をしています。
僕ら人間に限らず、脊椎動物の血が赤い色をしているのに、軟体動物
(節足動物もそうですが)のそれが青い色をしているのは、酸素を運ぶ
物質が違うから。
前者のヘモグロビン(鉄タンパク)は、酸素と結合すると、鉄が
酸化する(サビる)と赤くなるように、血液をも赤く染めます。
後者は、ヘモシアニン(銅タンパク)がその役割をするので、銅
が酸化する(サビる)と青くなるように、青い血となるのです。
酸化していないヘモグロビンは、暗赤色ですが、ヘモシアニンの場合
は無色透明。
だから、タコは煮ると(「紫褐色-青色=赤」で)赤くなる。
イカは、「青色-青色=無色」。
人間の場合は?土気色?五右衛門はどうなったのかしらん。
昔からイカが空を飛ぶのは知られていたと云いましたが、その証拠に、凧はいかのぼり
(烏賊幟)と呼ばれていたのです。その形が烏賊に似ていたからです。
では、なぜタコとなったか。
江戸時代(明暦元年)のこと、いかのぼり禁止令なるものが布告されました。相手の凧の
糸を切る凧合戦が当時あったのかどうかまでは確かではありませんが、凧が絡み合って
喧嘩になることは江戸っ子なら十分あり得ます。時節は春のこと、酒も入っていたの
でしょう、けが人がでるような事件が頻発したことから、「いかのぼり、罷りならん」
ということになってしまった。
でも、粋でいなせな江戸っ子のこと、どうしても止められない。役人に見咎められた
とき、「イカじゃねえ、こりゃタコだ」と云って続けたのがその始まりだとか…。
凧は風に巾(細長いもの)が翻る様を表す文字ですが、これをタコとするのは関東の
方言であって、関西では今もイカと呼んでいます。
「凧 きのふの空の ありどころ」(蕪村)
「凧」をイカとしてもタコとしても字足らず。これは、いかのぼり。
凧に己自身の身の上(浮沈)をなぞっているのでしょうか。おそらく、この句を詠んだ
ときは、以前のような好い境遇にはなかったように思います。凧は勢いよく空高く揚が
っていたのでしょうね。
凧は春の季語。長閑で風が強いこれからの季節は凧あげにうってつけ。でも尖閣が、
PM2.5が…。で、
「凧 けふの隣国 空もよう」(鈍末)
ことで、じょうごのような形をした漏斗(ろうと)から噴射して助走に勢いを付ける
のですが、その際に鞍馬天狗の黒頭巾の先っぽのようなヒレと腕とをたたんで
水の抵抗の少ない姿勢をとる。で、海から飛び出すと、さらに水を噴射し続けて
(おそらくスリムな体型に戻す―体を軽くする―意味合いもあるのだと思うのです
が)加速。なんと100mを11.4~8.9秒と、ウサイン・ボルトよりも速い。
実際は約30mしか飛翔しなかったのですが、体長が約20cmセンチという
ことですから、人間に換算すると270mくらいになるわけで、そりゃボルト
も真っ青(色黒でよく分からないけど)のスピードです。
滑空姿勢はというと、ヒレと腕の間にある保護膜を広げてバランスをとりながら、
先端をやや上向き加減にして、揚力をより働かせるようにする。着水時には、水の
衝撃を少なくするために、ヒレと腕をたたんで、先端をややうつむき加減にする。
漏斗は、水だけでなく、墨も吐くし、卵や精子をも、何でも放出する。
だから、タコの口のようなものも実は漏斗。口は腕の根本にある。
イカもタコも頭足類ということで、頭から足というか腕が生えているということに
なっているのですが、イカのヒレが魚のそれと同じものだとするなら、進化論的に
みて、手足の機能とも考えられるわけで、イカ10本、タコ8本の腕と称されて
いる部分は、頭髪に相当するものではないかしらん。だから刈っても、また生える。
写真撮影は偶然だったようです。北海道大学水産学部付属の練習船「おしょろ丸」で
千葉県の東方約600キロメートルの北西太平洋を実習航海中に、船首波に驚いた約
100匹のイカの群れが2回水面から飛び出したとありますから、2回目のシャッターチャ
ンスを逃さなかったのでしょう。
予想外のことで、専門外のことだったから、論文発表までにかくまでの長き時間を
要することになったのだと。
先日(2/7)、北海道大学がPRESS RELEASEしたのが「イカはホントに空を飛ぶ:
イカの飛行行動を世界で初めて解明」と題したもの。
前半の「イカはホントに空を飛ぶ」というのは昔からよく知られていたことで、
目新しい発見でも何でも無いのですが、今回それなりに話題となったのは、
イカが水面から飛び出して着水するまでの連続写真の撮影に成功し、それを
もとに「イカの飛行行動を世界で初めて解明」したことにあるからです。
その写真撮影が行われたのは2011年7月25日午後2時25分のことと云いますから、
飛行行動の解析に何と1年半も要した、ということになります。
で、「Oceanic squid do fly(外洋性イカは本当に飛ぶ)」と題する研究論文
がドイツの科学雑誌「Marine Biology」に公表された。
それによると、飛行行動は次の4段階に分けることができるそうです。(引用)
①飛び出し:水を勢いよく吐き出し水面から飛び出す。この段階では,ヒレを
外套膜に巻き付け腕もたたみ水の抵抗を小さくする姿勢を取っている。飛び出す
前に高速で遊泳し水面へ接近してきたことを示唆している。
②噴射:水を漏斗から噴射し続け空中でも加速し,さらに揚力を発生させるために
ヒレと腕を広げる。この際,腕の間にある保護膜を広げ,腕とともに“翼”の
ような形となる。この段階における空中の移動速度は8.8-11.2 m/s(メートル毎秒)
に達する。
③滑空:水の噴射が終わると,腕とヒレを広げた状態を維持したまま滑空を開始
する。揚力はヒレや腕と保護膜の“翼“で発生させており,進行方向に向かって
やや持ち上がった姿勢(ピッチ・アップ)をし,バランスを取っている。外套膜は
緊張状態を保ち,体の前後(ヒレと腕)にかかる揚力に耐え空中姿勢を安定させて
いる。
④着水:ヒレを外套膜に巻き付け腕をたたみ,進行方向に対してやや下がった姿勢
(ピッチ・ダウン)を取る。これにより着水時の衝撃を小さくさせる。
いつの間にか、バレンタインデーやホワイトデーと並んで、業界の思う壺
商品となりましたが、結構歴史はあるのです。
江戸時代末期に大坂の商人が、七福神に因んで七種類の具を太巻きにして、
商売繁盛と厄払いとを祈願して丸かぶりしたのが事の初め。
節分の夜、その年の恵方に向かって、無言で(諸説あるようですが、これが
一般的)、願い事をしながら、太巻きを大口を開けてかぶりつく。
この習わしには、鬼の金棒に見立てた太巻きを食べつくすことで「邪気を
祓う」、切らずに食べることで「縁(今なら円の方が相応しい)を切らない」、
という霊験あらたかを込めてあるらしい。
大坂商人の習わしが全国に広まったのは、つい最近(1990年代前半)からのこと
で、セブンイレブンやダイエー、ジャスコといったスーパーが一役買ったから。
僕は、梅屋敷商店街の「ちよだ鮨」というチェーン店で海鮮太巻きを購入。
今年の恵方は南南東(「北北西に進路を取れ」というヒッチコックの映画があり
ましたが、その正反対の方角)だから、丁度テレビの置いてある向き。目を
つぶらなきゃいけないという決まりは無いようだから、テレビを見ながら行事
を進めることができます。ラッキー!
『ことばの歳時記』(金田一春彦)に
“日本の鬼は、来年のことを言うと笑い出すようにユーモアを解し、同情すべき
場面では目に涙をためるやさしさをもち、十八歳の年ごろにもなれば、ちょっと
色気も出ようといううれしい存在である”
とあるように、鬼が怖いというのは遥か遠い昔のこと。
今や、鬼の権威は地に落ちて、福だけを求める時代になっちゃった。これが
本当の「おにやらい」。
今日は、季節の変わり目ということで節分。昔は春夏秋冬の4つの
節分があったのですが、今は立春の前日の今日だけを称するように
なりました。
季節の変わり目は、とかく体調を崩しがちですが、昔のひとは邪気
が生じるからと考えたようで、その邪気を払うための行事が鬼払い。
その起源は、平安時代(8世紀初め)に中国から伝わって来て、宮中
で大晦日に行われた追儺(ついな)という行事。
舎人(下級役人)が鬼に扮して、それを方相氏(ほうそうし、軍制を
司る役人で、疫病を追い払う)役の大舎人長が手に盾と矛とを持って、
何人もの童子を従えて、内裏の四門をめぐって追い回し、最期は
殿上人(てんじょうびと。昇殿を許された堂上のこと)が桃の弓に葦の
矢をつがえて鬼を射る。
それが、節分の行事として民間に広まるようになったのですが、元々は
豆まき(鬼打)だけでなく、柊(ひいらぎ)の枝に鰯の頭を刺したもの
(鬼の嫌いなもの)を戸口に立てて、鬼を追い遣った(鬼遣、おにやらい)。
「鰯の頭(かしら)も信心から」の出所は多分これ。
宮中行事には無かった豆が使われたのは、室町時代に語呂合わせの
「魔滅」を寺社が使ったかららしい。
面白いのは、「鬼は外」のときには戸外に向かって、「福は内」のときには
戸内に向かって、豆をまきますが、この風習の初期にあっては、いずれも
後ろ向きになって豆をまいていたそうです。
家の中に居るお客を送る時、家にお客を迎える時、それぞれの手の仕草?
まいた豆は、拾って、数え年の数だけ食べて厄除けを行う。
「をさな子や ただ三つでも 年の豆」(一茶)
僕らは、さばを読んでも、たらふく食べなきゃならない。
「年の豆 数を減らせど 腹ふくる」(鈍末)
彼は黒澤作品をいくつも手掛けていますが、興行的にも作品的にも成功したのは、
全て何人かの共同脚本。
「羅生門」、「生きる」、「七人の侍」、「蜘蛛巣城」、「隠し砦の三悪人」、
「悪い奴ほどよく眠る」、「どですかでん」など。
彼ひとりで手掛けたもので話題になったものには、全て原作がある。
「真昼の暗黒」、「女殺し油地獄」、「張込み」、「切腹」、「白い巨塔」、
「上意討ち」、「日本沈没」、「八甲田山」(「砂の器」は山田洋次と共同
脚本)、「私は貝になりたい」など。
彼のオリジナル脚本(原作)は、「白と黒」、「仇討」そして「幻の湖」。
いずれも話題作とはならず、「白と黒」は観ていないので何とも云えませんが、
「仇討」(1964年11月1日公開、今井正監督、東映、中村錦之介主演)もどこか
で聞いたようなストーリーで、その割には最後は無残に(仇討として)切り殺さ
れる錦之介の無念さ、不条理さが描き切れていないのです。
つまり、オリジナル脚本家としての腕は大したことがないのに、初めて監督まで
務めた。しかも橋本プロダクションのトップ。
これって、裸の王様そのものですよね。
で、再起不能になるほどの大風邪を引いた。
最期のシーンは、その長尾の子孫(宇宙パルサーとしてNASAで働く)が
宇宙空間に居て、家伝の横笛を琵琶湖の小谷城(長政の居城)址と葛篭尾崎と
をつなぐようにして置いてつぶやく。“琵琶湖の水が枯れ果て、幻の湖と
なる遠い未来までも、笛が琵琶湖の怨念を鎮めることができるように”と。
そして“たとえ琵琶湖が無くなっても、太陽系の消滅する45億年先まで、
笛はこの幻の湖の上にある”と。
これが「幻の湖」となった由縁?特別な霊験があるとも思えない横笛に
そこまで託すのか、と…。何でそんなに針小棒大なんだと。こうなると
パラノイアとしか云いようがない。
それと衛星軌道上(地球から約185㎞のところ)としていますが、
静止していなければならないので、静止軌道でなければならない。でも
静止軌道は赤道上空高度約3万6000㎞。琵琶湖の真上でもないし、
そんな高度から琵琶湖が見えるのでしょうか。
横糸を縦糸でしっかり織り上げなければならないのですが、縦糸が横糸を
上手く結びつけることができていない。で、よく言えば「難解」、悪く言えば
「支離滅裂」、といった映画になっているのです。
この映画、1982年に東宝創立50周年記念作品(第37回文化庁芸術祭参加作品)
として作られたのです。
名脚本家として名高い橋本忍が、自らのプロダクションの3作目(1作目は
「砂の器」、2作目は「八甲田山」で、いずれも大ヒットした)として、そして
橋本忍が初めて監督としてメガホンをとった、加えて原作も手がけた、渾身の
力を込めたものだったのです。
しかし、東京でさえ公開からたったの2週間とちょっとで打ち切られ、舞台と
なった滋賀県では一度も上映されないといった散々な結果に。
渋谷の東邦生命ビルに分散されていたのですが、豊洲に新しくできた本社
ビルにそれら全員が移る(1993,4年頃)と決まったときには、大量の退職者が。
皆若手のイケイケ女性ばかり。それだけ赤坂(渋谷)の地は魅力的だったの
でしょう。なんたって遊ぶところやブティックがふんだんにありましたから。
さて、本題。
いくら怪しげだからといって、赤坂の本社ビルが、これまた何故なのか分か
らないのですが、主人公の道子(源氏名は、お市)と同じ雄琴のソープ嬢で
あったローザが実は米国の諜報員で、その諜報員の職場になっているのです。
そこを道子が訪ねていって、道子の愛犬シロを撲殺(?)した犯人の身元を
調べてもらう。そして執拗にその男を追い回す(それもどちらも趣味がマラソン
とかジョギングとかで、走り回って追い回す)。この話が横糸のひとつ。
最後には、懸命に逃げる犯人に追いついて、“シロ、長尾さん、淀さん(確か
道子の同僚?)、ローザ、それに倉田(道子の恋人)さん。勝った、あたしが
勝ったわよ”と…(マラソンの勝負に勝った、という意味)。そして“お前
なんかに、琵琶湖に沈んだ女の恨み節なんて”と、何故かみつが憑依した
かのごとき言葉とともに出刃包丁(犯人が偶然、道子の働くソープランドへ
やって来たが、目当ての女に客が付いていたため、道子が指名される。これ
幸いと道子は店にあった出刃包丁を着物の帯の背中に差して、犯人を追っかけ
回す)で刺し殺す。
もうひとつの横糸として、戦国時代、織田信長と浅井長政との戦に纏わる、
お市の方のお気に入りの侍女みつとその恋人長尾の悲恋話があります。
その長尾の末裔が吹く横笛の音に惹かれて、道子がその悲恋話を聞かされる
のですが、その場所が雄琴から大分離れた葛篭尾崎(つづらおざき)。
その地は、信長の怒りに触れて、みつが逆さ磔にされて殺されたところ。
殺される瞬間まで、船で漕ぎつけて横笛を奏でていた長尾のその後のこと
は全く不明なのですが、子孫が鎮魂の意を込めて同所で家伝の横笛を吹いて
いるところをみると、他の誰かとの間に子ができて、ということになるの
ですが…。
右手ロビーが2階分あるので、左手のコンピュータルームの上には中2F
があるのです。
ですから、この中2Fにエレベータは止まりませんので、コンピュータ
ルームの手前にある階段を利用しなければなりません。
願書を携えて人事部を訪ねたとき、なんと人事部はこの中2Fにあって、
エレベータを使った僕は辿り着けない。ウロウロ、オロオロしている学生
を見兼ねたのでしょうね、懇切丁寧に教えて頂いて、何とかその日のうちに
帰宅することができました。
そんなこともあって、なんて複雑で大きなビルなんだろ、なんて入社する
までの間思っていたのですが、入社してしばらく本社ビルにいたときに、
隅から隅まで探検し、左程のことは無いな…と。
本社ビルの辺りは、江戸の頃はお屋敷が沢山あったところです。その頃、
本社ビルの地には、下総結城藩水野日向守の上屋敷がありました。明治
の御代となってからは、初期には徳川慶喜の跡を襲った家達が住まいし、
明治10年6月に家達が長期英国留学の途に就いたため、数年後に屋敷
が取り壊されて、その跡地に九条家(とその隣に一条家。ともに五摂家)
が越してきました。
この九条道孝公爵の第四女節子(さだこ)が、大正天皇のお后。
時代は下り、終戦を迎えると、GHQにより華族制度が廃止されたため、
九条家は京都に戻ります。その跡は帝産オート(GHQ御用達のバス会社)
に引き取られ、その後、上述の昭和45年に本社ビルが建ったのです。
この本社ビルの公道を挟んで右手に氷川小学校があり、そこはかって勝
海舟の屋敷があったところ。
龍馬が行き来していたときの海舟の屋敷は、そこからほんの少し離れた
氷川神社裏手崖下にある盛徳寺の隣にあり、氷川小学校のところに屋敷
を構えたのは明治5年のこと。
本社ビルも氷川小学校も今は共に無く、前者跡地には赤坂タワーレジデンス・
トップオブザヒルという長ったらしい名前に相応しい地上45F、地下3F
のタワーマンション(2005.7竣工)が、後者跡地には特別養護老人ホーム(1993年)
が、それぞれ建てられています。
先日、日本映画専門チャンネルで何気なしに観たのが、この映画。
ストーリーは、何が何だかさっぱり分からない代物でしたが、
あるシーンで僕がかって勤めていた会社の本社ビルの外観から、受付、
コンピュータルーム、そして天井の高いロビーが映し出されたので、
ビックリ仰天有頂天。
映画で使用されているのは、今回初めて知りましたが、テレビドラマ
では結構使われていたのです。
その本社ビルは、赤坂2-17-51にあったのですが、近くにTBS
とかテレ朝とかがあったこともあって、「ザ・ガードマン」だとか
「非常のライセンス」だとか、それなりに重宝がられていました。
本社ビルがその地に建てられたのは、僕が入社する丁度1年前のS45.3
のこと。
設計者が誰だったのか、調べても分からなかったのですが、当時として
はかなり斬新なデザインで、外観は少々濃いめのブラウンで、それは金
属製のスレートが全面に貼り巡らしてあるからなのですが、日差しの
角度によって煌めくのです。
地上7F、地下3Fですが、海抜18mと小高いところでしたので、当時
は周りに高い建築物が無かったこともあって、遠くからでも頭の先や屋上
に立てられた国旗と社旗がはためく様を眺めることができました。
ビルの前にはモータープールがあって、それを囲むようにしてちょっと
した石垣もどきがあって、しゃれた常夜灯が幾つかあって、そして正面
からみて右半分は、2Fまで吹抜けの、当時1枚の面積としては我が国
最大と云われていたガラスで三方を囲まれた、広大なロビーがあったの
です。左半分はコンピュータルームがショールームを兼ねて設えてあり
ましたので、その1F部分が手前に少し出っ張っています。
当時としては珍しい黒っぽいビルで、何となく怪しげなところも好まれた
のかもしれません。
一文字が、必死に生きてきた自分の人生を表しているからだそうです。
天性だけでなく、懸命な努力でそれに磨きをかけたひとの言葉だけに
重みがあります。
さて、1960年代の子供が好きだった言葉「巨人、大鵬、卵焼き」ですが、
「団塊の世代」でお馴染み、堺屋太一が生みの親。
通産省官僚当時(1961)に、経済報告の記者会見の場で、“子供たちは
みんな巨人、大鵬、卵焼きが好き”と話したことが広まり、流行語に
なった。
丁度、高度成長期。それも「規格大量生産時代」で、その特性を表現
したそうです。
この語呂に合わせて、1980年代に流行ったのが「江川、ピーマン、北の
湖」。もっともこちらは子供の嫌いなもので、それだけに、定着する
までには至らなかった。
もっとも、大鵬自身は、「巨人、大鵬、卵焼き」と云われることに不満を
漏らした。
“(ドラフト制度の無かった当時、巨人のように)有力選手を集めれば
勝つのが当たり前。こっちは裸一貫なのに”と。
人気と「忍気」は違うのだと。
大鵬が入門した二所ノ関部屋ですが、初場所を最後に閉鎖されるとのこと。
「巨人、大鵬、卵焼き」も最早死語となりつつある。
それらを見届けることなく、旅立った。見事な引き際と云わざるを得ません。
合掌。
が“柏戸は壁にぶつかる感じ、大鵬は壁に吸い込まれる感じ”と
二人を評していますが、「柔よく剛を制す」の喩通り、大鵬が圧倒的
に強く、その余り、判官びいきが高じて大鵬が嫌いになった時期も
あったりしたのですが、柏戸が山形の豪農の出であるのに対して、
大鵬が極貧の少年期を過ごしてきたことを当時知っていれば、そう
いったことも無かったかも。
大鵬の連勝記録は、昭和以降ですが、歴代4位の45連勝。
その他、34連勝2回、30連勝1回、26連勝1回、25連勝
2回、と無類の強さ。
その45連勝を止められた対戸田戦ですが、行事軍配が差し違えと
されて黒星を喫するのですが、後でビデオを見たらなんと戸田の右足
が先に土俵を割っていた。日本相撲協会がそれまで拒んできたビデオ
映像を判定の参考にする切っ掛けとなった「世紀の大誤審」だったわけ
ですが、大鵬自身は、そのような相撲(横綱相撲で無い)を取った自分
が悪いと云ったそうです。
1968年は初場所4日目から休場し、春場所、夏場所、名古屋場所と
全休。秋場所も初日黒星。でも2日目から14連勝して27度目の
優勝。九州場所が全勝優勝。翌1969年の初場所も全勝優勝。これで
44連勝。そして迎えた春場所の初日が白星で45連勝。そして
問題の東前頭筆頭戸田との一戦。おそらくこの誤審が無ければ、
連勝記録はもっと伸びたでしょうが、大鵬にとって記録は、目的では
無く、結果でしかなかった。
目的は、横綱の名に恥じない相撲を取ることにあった。ですから、
1971年の夏場所で小結貴ノ花に敗れ、30を越えたばかりであっても、
未練がましいことなく、きっぱりと引退の道を選んだ。まことに英雄
の進退は見事なものです。
中村草田男の「降る雪や明治は遠くなりにけり」は、草田男が、
降る雪の中に見え隠れする南青山小学校の姿を見て、自身の
通ったその時代をおぼろげに想い出し、感慨を込めて、その
明治という時代が過去のものとなり、永遠に去ったことに
気付かされる様を詠ったものですが、大寒の日(1/20)に前日
大鵬が亡くなったことを知って、同様の思いを感じ得ずには
おれませんでした。
「大寒や昭和は遠くなりにけり」(鈍末)
我が家にテレビが遣って来たときは、栃若時代でしたが、
小学生を終える頃には、新入幕(1960、初場所)した大鵬が
あれよあれよという間に昇進し、初優勝(1960、九州場所)を飾り、
大関に。そして新入幕からたったの11場所で横綱(1961、秋場所後)
に上り詰めます。まさに、9万里を一っ飛びするという大鵬の名
に相応しい、記録にも記憶にも残る大横綱でした。
折角の成人式だというのに、生憎の雪。
それもかなりの積雪となりそうな気配。
またまた『ことばの歳時記』(金田一春彦)によると、
今目にしているような状態を「雪が降っている」とも
云うし、朝起きて夜に降り積もった雪を見ても「あ!
雪が降っている」と云うが、中国・四国・九州の言葉
では、前者は「雪が降りよる」、後者は「雪が降っとる」
と云う、とあります。母は香川県高松市で生まれ育ち
ましたので、確認したところ、遥か昔のことですので
曖昧ではありますが、そのような言い方をしていた
そうです。
今年(この冬)初めての雪ですから初雪と云うことに
なります。初雪と云うと、すぐに頭に浮かぶのが、
「初雪や 二の字二の字の 下駄の跡」
と云う俳句ですが、これ、芭蕉の句だと思っている
ひとが多いと思うのですが、そうでは無いのです。
もとの句は、芭蕉と同じ時代に活躍した女流俳人
田捨女(でんすてじょ。姓が「田」、名が「ステ」で、
「女」は、女流の場合に接尾語として添えるもので、
女流六歌仙のひとり)の
「雪の朝 二の字二の字の 下駄の跡」
と云うもの。
6歳の時に詠んだと云いますから、栴檀は双葉より
芳し、を地で行くようなひとであったわけです。
その元句が通り句(雑俳や万句合などの付合に応募して
選に入り、世に知られている句)となったようなのです。
「初雪」を詠んだものには、
「初雪や 一二三四 五六人」(一茶)
と、いかにも一茶らしい面白いものがあります。
どう読むのか、諸説ありますが、「はつゆきや ひぃふぅ
みぃよぉ いつむたり」が、一茶らしくてよさそうです。
一茶は信州長野に住まいしていたので、雪は生活の一部
で難儀な代物。
その難儀の始まりの印としての初雪に、村人たちがひとり
又ひとりと戸外に出てきて、忌々しく空を見やっている
様子をおどけて詠んだのではないかしらん。
一茶には「雪とけて村いっぱいの子どもかな」という
句がありますので、上記のような解釈もあながち的外れ
とは云えないように思うのですが…。
落語に「雑俳(ざっぱい)」と云うのがあります。
長屋の八五郎が、横丁の隠居の所に遊びに行って、隠居の
道楽である俳句を教えてもらうという噺なのですが、
その中に「初雪」があります。
隠居が、
「初雪や 瓦の鬼も 薄化粧」
と詠んだのに対して、
八五郎は
「初雪や これが塩なら 金もうけ」
と返す。
このようなとんちんかんなやり取りが笑いを誘う落語ですが、
八中の同級生であったO・Mくんが得意にしていた噺で、
帰り道によく聞かされました。
今でも記憶に残っているのが、八五郎の
「初雪や 塩屋転んで あっちなめこっちなめ」
と云うもの。
この句を思い出すと、ついニヤニヤしてしまいます。
この稿を書いているうちに、雨交じりの細雪に代わったようで、
積もった雪も解け始めています。
それにしても、着飾った新成人たちにとって、さぞや忌々しい
一日だったことでしょう。で、
「初雪や 元の木阿弥 濃化粧」(鈍末)
『燃えつきた地図』の不可思議な世界へもう一度どっぷり浸かり、それから未読の
晩年の作品を購入してじっくり味わってみようと。
安部公房のことを理系の作家と云いましたが、彼、東大の医学部卒なんです。でも
医者にはならずに作家になった(途中から作家に転身した例はありますが、彼は
一度も医者であったことが無い)。
なぜって?卒業試験に二度までも落ちそうになったから。そこで安部公房が奥の手
を。“医者になるつもりはありません!”。これで恩情あるはからいがとられて
無事卒業。だから、医師国家試験も受験せず。
でも医学は一通り学んでいる筈。なのに、1992年(平成4年)12月25日の深夜、執筆中
に脳内出血で倒れ、退院後も自宅療養を続けていたのに、悪化しての再入院後、急性
心不全のため死去(享年68)―高熱と意識障害があったのに、翌日には回復、でも
翌々日の早朝に亡くなった―というのは何か納得が行かない。
愛人のところで腹上死という風説があったけど、愛人からの連絡を受けて、慌てて
病院に運んで、そのように取り繕ったと云うのは十分あり得そう。(何かの映画で
同様のストーリーがあった。)
腹上死でノーベル賞を逃した、という方が安部公房らしくって好いけど。
で、タイトルの「筆を選ばず」。これから購入して読もうと思っている晩年の二作
(『方舟さくら丸』1984年、『カンガルー・ノート』1991年)だけど、いずれも
ワープロで執筆されているのです。未完に終わった『飛ぶ男』などの遺作も、死後、
ワープロのフロッピーディスクから発見されていますし。
『燃えつきた地図』には「“燃えつきた地図”をめぐって」と題する8頁ほどの付録
が付いていて、そこでは、初めの100枚が作者自身によりボツにされ、全てが書き
直しになったり、ゲラの段階でも、ただ書き込むだけでなく、ある部分を切り取り、
そこへ新しい原稿が入り、切り取った部分が後半に行く…やっと初校が終わり、再校
になってまた結末のところが全部変わった、と編集部が苦心譚を語っていますが、
おそらくそのようなやり方が公房流なのでしょう。
ですから、まだ出たてのワープロ(専用機)ですが、ちょっと高価であっても、直ぐに
飛びついたのでしょう。何たって切り貼りが自在ですからね。
で、公房は筆を選ばず、理系らしく文明の利器に乗り換えた。
とか高校とか、何の教科とかは一切不明。安部公房にとっては教師という職業の
プロトタイプに意味がある。彼の作品にしては珍しくこの主人公に仁木順平と
いう名があることを読者は最後の最後に知ることになる)が妻にも同僚にも行き先
を告げずに沙漠に棲むハンミョウ属の変種を採集しに目的地(映画では静岡県の
浜岡砂丘がロケ地として使われた)に着いたときの語り。ですから、物語の出だし
の部分なのですが、見事なプロローグになっていて、主人公の男の来し方ばかり
でなく、行く末、つまりエピローグまでを暗示している。
「砂の女」なんてあるものだから、つい砂かきで糧を得ている、主人公が搦め捕ら
れた三十前後の女(映画では岸田今日子)のことだと思ってしまい勝ちですが、小説
でも映画でも添え物としての役割しか与えられていない。で、思うに、擬人化して
いるのですよね、砂をね。
映画(1964年製作)は、練り羊羹にはならず、削ぎ落としても、しっかりしたミル
フィーユの形を留めている。
名ピアニストであったカナダ人のグレン・グールドは、殊の外、この映画がお気に
入りであったようで、百回以上も観たと、そして、“カラーでは見たくない”と
語っています。
確かに、無機質の砂が主人公の映画ですから、モノクロじゃないと…なんて断定
したら大きな間違い。安部公房の作品は含みが多いから、カラーで限定してしまうと
その魅力が半減どころか台無しになってしまうのです。
その好例が、『燃えつきた地図』。『砂の女』に引き続いて安部公房が手がけた
書下ろしですが、これも映画化(1968年製作)されました。監督(勅使河原宏)も、
脚本(安部公房)も、音楽(武満徹)も、すべて『砂の女』と同じ。ただし、映像
がモノクロではなく、カラー。
『砂の女』がキネマ旬報ベストテン1位、第17回カンヌ国際映画祭審査員特別賞に
輝いたのに対して、『燃えつきた地図』の方は鳴かず飛ばずといった有様なのも
納得。
な原作を―脚本が安部公房本人ということも手伝っているのでしょう―よくぞ
ここまで捨象して映像化できたものだと感心しきり。
それで、原作を40数年振りに読み返してみました。
安部公房の作品に共通しているのは、暗喩や直喩などの修辞が多用されていて、
それがミルフィーユ―練り羊羹のように様々な味覚が均一化されたものとは
違って―のような味の厚みや深みになっていて、物語の伏線にもなっている
のです。
例えば、
“地上に、風や流れがある以上、砂地の形成は、避けがたいものなのかもしれ
ない。風が吹き、川が流れ、海が波うっているかぎり、砂はつぎつぎと土壌の
中からうみだされ、まるで生き物のように、ところきらわず這ってまわるのだ。
砂は決して休まない、静かに、しかし確実に、地表を犯し、亡ぼしていく…
その、流動する砂のイメージは、彼に言いようのない衝撃と、興奮をあたえた。
砂の不毛は、ふつう考えられているように、単なる乾燥のせいなどでなく、その
絶えざる流動によって、いかなる生物をも、一切うけつけようとしない点にある
らしいのだ。年中しがみついていることばかりを強要しつづける、この現実の
うっとうしさとくらべて、なんという違いだろう。
たしかに、砂は、生存には適していない。しかし、定着が、生存にとって、絶対
不可欠なものかどうか。定着に固執しようとするからこそ、あのいとわしい競争
もはじまるのでなかろうか?もし、定着をやめて、砂の流動に身をまかせてしま
えば、もはや競争もありえないはずである。現に、沙漠にも花が咲き、虫や
けものが住んでいる。強い適応能力を利用して、競争圏外にのがれた生き物
たちだ。たとえば、彼のハンミョウ属のように…”。
今年のノーベル文学賞は、中国の莫言(ばくげん)が受賞したものの、
中国政府の検閲を容認する「体制側の作家」との批判を受けるなど、
色々と物議を醸したことは記憶に新しいですね。
その選考過程は、受賞後50年経たないと、ノーベル財団の守秘義務
といった厄介なものがあって、明らかにならないのですが、少なくとも
村上春樹が候補に挙がっていたという事実は無いと思います。
さて、タイトルの「コーボー」ですが、紛れも無く受賞確実であった
安部公房のことです。
なぜ「筆を選ばず」なのかは、さて置いて、安部公房が日本人で二人目
のノーベル文学賞を目前に急死したことで、大江健三郎に転がり込んで
きたのは、今年3月の読売新聞の取材に対して、“急死しなければ、
ノーベル文学賞を受けていたでしょう。非常に、非常に近かった”と
ノーベル文学賞を選考するスウェーデン・アカデミーのノーベル委員会
のペール・ベストベリー委員長が答えていることからも容易に察しが付
きます。
安部公房が亡くなった後にノーベル賞委員会の食堂にサミュエル・
ベケット(1969年受賞)と安部公房の写真が並べて飾られていたのは有名
な話で、今度は君(安部)の番だったのに、とでも云いたかったのかし
らん。
大江健三郎自身も、受賞時(1994)に、“もっと長生きしていれば、自分
ではなくて、彼らが受賞したであろう”と述べていますし。
彼らとは、安部公房(1993.1.22歿)、大岡昇平(1988.12.25歿)、井伏
鱒二(1993.7.10歿)の三人。
大江健三郎ですが、僕は彼の作品は『個人的な体験』しか読んでいない
ので何とも評価し難いのですが、肌が合わないとしか言いようが無く、
だから他の作品も読みたいとは思わなかったのですが、それに対して、
安部公房は大変魅力的というか魅惑的な作家でした。
僕が安部公房に初めて触れたのは大学生のときで、確か『他人の顔』だった
と思うのですが、理系の作家らしい表現が至る所にちりばめてあって、
それが難解とも評される所以でもあるのですが、理系の学生にとっては
かえってそこに面白みを感じてしまうのです。
以前(1999年)には、ノストラダムスの大予言とか云うものがあって、
今回は、マヤ文明で使用されていた長期歴という暦が2012年12月21日
から12月23日頃(要するに冬至)で終わっていることから、2012年
12月21日に人類が滅亡すると云うもの。
その長期歴ですが、ある起点日から13バクトゥン(1バクトゥン=144,000日)、
すなわち187万2000日(マヤでは1年を360日としていたので、5200年に当たる)
で表現されていて、2012年12月21日がその187万2000日目に当るそうです。
その起点日を逆算して確かめたのでしょう、2007年に英国のホゼ・アグエイアス
が自著『マヤンファクター』の中で、また2009年には米国のエイドリアン・
ギルバートの著書『マヤの予言』によって、2012年12月21日がその日とされる
ようになりました。
今年の冬至の日には、銀河系の中心とされている(飽く迄地球から見ての話で
すが)いて座、それと太陽と地球とが一直線に並ぶそうで、それだけのことなら
毎年起こっていることなので別に珍しいことではないのですが、地軸(黄道面に
対し約23.4度傾いている)の垂直真正面に太陽が向く(夏至と冬至)ときに、
いて座までが並ぶのは、約13,000年に一度という希少現象。
また、太陽そのものの活動極大期が2012年頃に当たっていて、太陽嵐が発生して
地球に何らかの影響を及ぼすと考えられています(エイドリアン・ギルバートは
このことと関連付けている)。同じことは1957年にも起こっていて、その時には
何ともなかったので大丈夫、と云いたいところですが、前回と違って今回の場合
には、地球を取り巻く磁気圏に巨大な穴が発見(2008年12月)されているので、
そこから大きな被害に結びつくと云われたりしています。
マヤ文明では、天文学が発達していましたが、人類の環境破壊による磁気圏の
綻びまでを予測することができる筈は無く、先に挙げた『マヤンファクター』
において2012年12月21日に「新しい太陽の時代」が始まるとされているように、
また5200年だけでなく、周期には26000年、52000年、260000年といったもの
まで考えられていたことから、5200年はある周期の単位と捉えるべきもので、
決して世界の終末を意味するものではありません。
終末論は、宗教にとっては信者獲得の常套手段で、…信じる者は救われる…
何から?…世界の終焉から…、といったノアの箱船。
仏教ですら、現世を語らず、来世を説く。これを末世と云う。
「あら何ともなや昨日は過ぎて河豚汁」(芭蕉)
首相に安倍晋三が付くということになると話は別です。
それで、タイトルの「約束の日」となるわけですが、
同名の書籍(幻冬舎、小川榮太郎著)では、平成18年
9月から翌19年9月までの一年間に安倍政権が成し遂
げたこと、成し遂げようとしていたこと、が文芸評論家
の目を通して事細かく、ドキュメンタリーとして記述
されています。
龍馬が「日本を今一度せんたくいたし申候」と、身命を
賭した革命とも呼べる改革に匹敵することを安倍首相
が目指していたことがよく分かる一冊です。
安倍首相退陣の引導を渡したマスコミ、就中朝日新聞
や週刊朝日は、安倍の「戦後レジーム(体制)からの脱却」
としての、憲法改正や対外(特に中国)政策、公務員
制度改革、教育基本法改正といったものが気に入らな
かったようで、安倍が二度と立ち上がれないようにと
叩きに叩いて“お坊ちゃん政治家の政権放り出し”と
まで貶めたのです。
で、「約束の日」。
同書で著者は
“私は、切望している。この終わりなき敗北から、
日本が、自立した国家の物語を取り戻し、希望を
取り戻す日が一日も早く訪れることを。そして、
安倍晋三が、「果し得ていない約束」を果すために、
今こそ、執念の炎を燃やし、政権を再度奪還して
くれることを。(中略)
安倍晋三内閣総理大臣が再び誕生する日。尖閣や
竹島、震災復興や原発問題で動揺し続ける日本国の
リーダーに、世界中が注視する就任記者会見。膨大
なカメラの放列が放つフラッシュの閃光とシャッター
音をしたたか浴びる安倍首相が、今こそ再び「戦後
レジームからの脱却」を、国民と世界に宣言する
その日。―その日こそ、前回不本意極まる辞任を
した安倍が、国民に対して内心密かに期待してきた
「約束の日」に違いない。
そして、第二次安倍政権の挑戦が、国民共有の物語
になった時、我々は胸を張って「日本人」に戻る
ことができるだろう。”
と締め括っています。
その「約束の日」が間近に迫っています。
未明(午前2時頃)まで選挙速報を見ていましたが、
一点を除いて、大勢が決したこともあって、寝床
に入ったのです。
その一点ですが、民主党の獲得議席がその時点で
56議席だったのが、今朝の新聞では57議席とな
っていたいたので、嗚呼滑り込みセーフかよ、と
云うものです。
お遍路で、4年間をかけて全国行脚というパフォ
ーマンスが見られず仕舞いになってちょっぴり残念。
でも極めて下卑た新潟のおばさんが、バラマキの
元祖未来の党の有象無象が、消滅してくれて溜飲
が下がる思いをしていたから、寝覚めは悪くない。
今回の自民党の大勝の原因は、敵失にあるという
のが、ジャーナリストらの大半の見方ですが、そう
いった引き算的な判断だけで無いのは、第三局の
日本維新の会やみんなの党が左程の議席数獲得に
至らなかったことからも明らか。
閉塞感でうつむき加減の日本の現状を打破するのは、
ムードという実体の伴わないものではなくて、真の
政治力であり、そういった力を備えていると云うより、
そういった時代がかってあったと云う経験則から、
そこへの回帰を望んだからではないかしらん。
今朝の朝日新聞の「声」に『集団的自衛権とは「参戦権」だ』と題する
ものが掲載されていました。
この20歳の大学生の論旨を要約すると、集団的自衛権が認められると、
同盟国(米国を指しているのでしょう)が他国と戦争を起こしたときには
日本も参戦することになりかねず、自衛とは別のものである、と云うもの
ですが、「自衛」を狭義にしか捉えていませんね。
自衛権は、急迫不正の侵害を排除するために、武力をもって必要な行為を
行う国際法上の権利であるとされています。現在の日本国憲法では、
自国に対する侵害を排除するための行為を行う権利である個別的自衛権は
認められているものの、相手国の先制攻撃を受けてからでないと反撃(それ
も自国領域内に限定)ができない専守防衛しか認められません。
この制約があるが故に日米安全保障条約が必要になっているわけですが、
例えば昨今騒がしくなってきた尖閣諸島の一件も、某国が軍事行動を起こ
して尖閣を占領した場合、米国海兵隊が日本の自衛隊と共にその奪還に動
いてくれるかと云うと、日本が某国から攻撃を受けたことが前提でないと
米国は軍事行動を起こせないでしょう。つまり日本側に被害が出て、初めて
共同の軍事行動に移ることができるわけです。
そこで自らが自国のために積極的な防衛をなすためには、専守防衛ではなく、
自衛権の発動(先制的自衛)を行えるように憲法の一部改正が必要になります。
さらに集団的自衛権が加えられることにより、相手国は同盟国である米国も
相手にすることになりますので、安易な軍事行動はとれなくなります。
以上のことは、第二次世界大戦後の1945年(昭和20年)10月に発効した以下の
国連憲章第五十一条で国際的に認められているものです。
「 この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した
場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとる
までの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。」
ただし、武力攻撃の定義が曖昧であるがために、侵略的軍事行動等が自衛権と
いう美名にかくれてなされる(イラクのケースなど)こともあり得ますので、
憲法改正のときには縛りをかける必要があります。
某国が自国領とする尖閣に日本が建造物を造ったり、人を住まわせたりした
場合、自衛権と称して軍事行動を起こすことは十分考えられるのです。それを
恐れて何もせずほったらかしにしておくというのが民主党のとった戦略(?)
ですが、そのまま未来永劫均衡が保てるという保障は全くありません。むしろ
日米同盟の間隙をついて、そして日本が現憲法下では手も足も出せないことを
利用して、軍事力を背景に様々な圧力をかけて譲歩(屈服)させる手段を採る
でしょう。
そのようなことを防ぐ目的からも「自衛」とは何か、どのような手段でそれを
確かなものにすることが出来るか、等々を能々吟味した上で、必要であれば
憲法改正も拒むべきものであってはなりません。
20歳の学生は、憲法9条を持つのが、日本の誇りであり、ブランドである旨
を述べていますが、戦争放棄が戦勝国によって押付けられた手枷足枷でることは、
それら戦勝国によって設けられた国連において戦争放棄が謳われていないこと
からも明らかです。
徹底的に無力化を図ったにも係わらず、予想を覆して日本の戦後復興は目覚ましく、
国力も発言力も増し、国際的に果たす役割もそれに応じたものを求められるよう
になってきました。
その求められているものが終戦直後のものと大きく乖離している以上、過去の
ブランド(?)なぞに縋っているだけでは、日本の将来は暗澹たるものになると
言わざるを得ません。
♪まわるまわるよ時代は回る
別れと出逢いをくり返し
今日は倒れた旅人たちも
生まれ変わって歩きだすよ
うーむ、随分と長いタイトルだ。
今回は、10名いるメンバーのうち自他が原因の2名が欠けて
8名での、そしてピアノも欠けてフルートの音色だけの演奏会
となりました。
日本フルート協会常任理事でもある指揮者加藤克朗氏による
それぞれの曲についての解説が「プログラムノート」として、
平明な文体で書かれてあるのも大変有り難いですが、そこで
漏れたことを指揮棒を振る前に軽妙な語り口で語り伝えてく
れるのも中々に味わい深いものがあって好かったですね。
「ディヴェルティメント」というイタリア語が何か知らなかった
のですが、「喜遊曲」というものであり、現在のBGMのように
気楽に聴くものなんですって。
僕が調べたところでは、18世紀後半にオーストラリアを
中心に流行した、メヌエット・行進曲・舞曲などの多楽章
から成る、セレナードに類似した室内楽曲だそうです(あー
小難しい)。ハイドンやモーツァルトがその代表的な作曲家
だそうです。
演奏会でもモーツァルトの「Divertimento KV439b/4」という曲
が演奏されました。
上記ディヴェルティメントが3重奏であるのに対して、現代の
アーティストであるR(レイモン).ギヨーのそれは、アルト・
フルートを加えた4重奏曲。
モーツァルトのものは8人全員で、R.ギヨーのものは4人で
演奏。さてその醸し出す音色は?
僕が最も気に入ったのは、日本人好みのメランコリックなメロ
ディーラインであるチャイコフスキーの「ロマンス」。
この曲、彼の若き日の年上の恋人であるオペラ歌手のデジレ・
アルトーに捧げられたのだとか。でもその恋は破局した。
だってチャイコフスキーは女性よりも男性の方がスキーだった
から。
アンコールに応えて、「ふるさと」と「サウンド・オヴ・ミュージック」
の中から「エーデルワイス」を演奏。
180~190名ほどの聴衆が喧騒を一時逃れて憩うたオアシス。
昨日(9/27)からスイスのジュネーブでお披露目された「若きモナリザ」ですが、
その真贋で喧々諤々のやりとりがなされているとか。
本物だとするのは、この絵を所有するスイスの財団「モナリザ基金」。
1913年に英国のアイルワース(ロンドン西郊)で見つかったので、「アイル
ワースのモナリザ」と呼ばれているのですが、米国人の絵画収集家らの手を経て
「モナリザ基金」が2010年に購入するまで、財団の専門家らが35年間にも
わたってダビンチ作である根拠を探すためにアレコレ調べていたようです。
そして今回の一般公開にあたって、300ページにも及ぶ調査報告書も公表した
とのこと。
それによると、レオナルド・ダビンチが51歳~54歳のころに手がけたものの
未完に終わったのが、この「若きモナリザ」で、その10年後に描き直したもの
がルーブルの「モナリザ」だと。
その根拠として
(1)同じルネサンス期の巨匠ラファエロがダビンチの作業場で模写したとされる
「モナリザ」の背景には柱が描かれており、「若きモナリザ」にも柱がある
(ルーブルの「モナリザ」には柱はない)。
(2)モデルとされるイタリア・フィレンツェの商人の妻リザ・ゲラルディーニは
1479年生まれで、作製時の年齢は25歳前後のはずである。
(3)同時代の美術評論家、ジョルジョ・ヴァザーリの記述には「(モデルの)婦人
は若く、唇は赤みを帯びている」とある。
(4)X線調査などでも、下図の筆致にダビンチの特徴がよく表れていた。
反論としては、
(1)「モナリザ」は、これまでにも多くの模写や模倣作を生んできているので、その
可能性がある。
(2)「若きモナリザ」は木の板に描かれた「モナリザ」と違って、ダビンチがほと
んど使わなかったキャンバスに描かれている。
(3)英国で20世紀になって発見されるまでの経緯が不明である。
僕に云わせると、根拠の(2)、本末転倒の最たるもの。だって「若きモナリザ」が
本物との前提にたって、25歳前後(20歳代前半の女性に見えるから)と云って
いるわけですから。
それに10年後に何故、同じ構図、同じ衣装で顔だけ老けたリザをダビンチが描こ
うとしたのか、その説明が付かないと思うのだけど。
反論(3)にあるように、ダビンチは「モナリザ」(「岩窟の聖母」も)をたいへん
大事にしていて、死ぬまで(1519年、67歳で歿)自分で持っていたと云われ
ていますので、それなら「若きモナリザ」も未完であるが故に未練をもって大切に
していた筈で、若き日から名声を博していたダビンチのそのような作品がどこに
どう流れたのかその経緯が不明というのは解せません。
根拠(1)は、ラファエロがいつ模写したのか証明されればハッキリすることですが、
それが示されていません。
根拠(3)も「モナリザ」(30歳代)のことを指していてもおかしくはありません。
根拠(4)に至っては、極めて精巧な模写を行えるだけのテクニックを有している者
であれば、当然の事です。
というわけで、僕は偽物説です。