
この写真は、慶応三年十一月十五日夜に龍馬が刺客に襲われた近江屋二階
の奥座敷の床の間に掛けられていた掛軸です。この小さな写真では判り難いと
思いますが、その下部の向かって左から右へ飛散した数滴の血痕が付着して
います。
現在、江戸東京博物館で開催中の龍馬展に実物は展示されていませんが、複
製品が展示されています。それも原寸大で再現された奥座敷の床の間に掛け
られてあります。
僕がこの再現された奥座敷に一入興味を抱いたのは、龍馬・慎太郎と刺客たち
の動き(僕が想定したもので間違い無いか)を確かめることにあったからですが、
その一環としてこの掛軸の血痕もそれがどの辺りからとばしったのか確かめる
必要がありました。
この血痕、それまでは慎太郎のものである可能性もあると思っていたのですが、
今は龍馬のものに間違いないと思っています。
先日(5/8)、フジテレビの土曜プレミアムという番組で「暗殺の4秒間、5滴の
血痕」ということで、龍馬が斬り殪されるまでの再現フィルムを流していました
が、大小合わせて三十四ヶ所もの刀傷を受けている上に、龍馬が斃れてい
たのは 奥座敷の隣の六畳間ですから、あのような単純な立廻りでなかっ
たことは確かです。
この血染掛軸、梅と椿が描かれているので「梅椿図(ばいちんず)」とか「椿花白
梅図」とか称されていますが、龍馬に贈られたときにそのような名が付いていた
わけではありません。
この絵を描いたのは板倉槐堂(かいどう)で、その本人が龍馬に贈ったのです。
龍馬の私物ですから龍馬の家系を継いだものが相続し、やがて京都国立博物
館に寄贈されて現在に至ります。重要文化財です。
画幅の上に書いてある漢文は、海援隊文司長岡謙吉の手になるもので、
「龍馬と慎太郎が灯下のもとで炬燵を囲んで閑談しているときに三人の
刺客が襲って二人を斬った。私(謙吉)の僕雲井龍藤吉もまた殺された。
私は当時大坂にいてこの変を聞き近江屋へ至ったが、辺り一面の狼藉で、
迸った血がこの絵や壁に及んでいた。当時の状況を想うことができる。
それは慶応三年十一月十五日のことであった」(意訳)といったことが記
されています。
この項で述べたいのは、暗殺の模様云々ではなくて、この画幅が龍馬の誕生
日を知る手掛かりとなるということです。
(文字数制限があるので続きはコメント欄で。)



















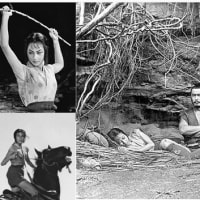
都合よく池田屋事変や禁門の変に海軍塾の門下生が関係していたことが露見、
ここぞとばかりに海舟の追い落としに拍車がかかり、ついに10月22日江戸
召還の命が神戸に達します。
そして江戸に着いた八日後の11月10日には軍艦奉行の職を解かれ、閉居謹
慎を申し付けられます。
神戸海軍操練所の廃止はもう少し先(慶応元年3月12日)ですが、海舟の庇護
を受けられなくなった龍馬らがどこに居たかといいますと、龍馬と沢村惣之丞
は江戸へ行っています。蝦夷地開拓・防衛の件で船を求める交渉を幕府と続けて
いたのでしょう。
神戸には千屋虎之助、新宮馬之助、近藤長次郎が残っていました。
高松太郎は大坂に潜んでいます。
龍馬が首尾よく船を得ることができれば、彼らは蝦夷を目指すでしょう。
土佐藩の脱藩者への追及の目を逃れながら、彼らは、固唾を呑んでいたかどうか
までは分かりませんが、ひたすら吉報を俟っていたのです。
征長の情勢を伝えたとあります。
8月3日に薩摩の吉井幸輔と一緒に上京の途に就いて以来、ずっと京都に居た
のでしょうか。
この頃、吉井の紹介だと思うのですが西郷吉之助(隆盛)と会っています。
『河原町三条下ル、龍馬暗殺』(広瀬仁紀著、文芸春秋社)によると8月5日、
場所は御所北側の今出川通の筋からやや外れた相国寺(しょうこくじ)三門の傍
らにある薩摩藩邸(二本松邸)の書院と具体的ですが、その根拠となる史料が定
かではありません。
ただし、海舟日記に龍馬の名が載る(海舟の許を訪れた)のは8月23日が最後
となりますので、在京中に西郷と会ったことは以下のことからも確かなことで
す。
明治30年に刊行された『氷川清話』(以下は昭和47年の角川版による)には、
「坂本龍馬が、かっておれに、『先生はしばしば西郷の人物を賞せられるから、
拙者もいって会ってくるにより添え書きをくれ』といったから、さっそく書いて
やったが、その後、坂本が薩摩から帰ってきていうには、『なるほど西郷という
やつは、わからぬやつだ。少しくたたけば少しく響き、大きくたたけば大きく
響く。もしばかなら大きなばかで、利口なら大きな利口だろう』といったが、
坂本もなかなか鑑識のあるやつだよ」
と、龍馬が西郷に会ったときの第一印象を語っていますが、西郷は二度の流罪
を経て薩摩藩の軍賦役を命じられたのは元治元年3月のこと。それまで龍馬ど
ころか海舟すら面識は無いのです。(海舟と西郷の初見は9月11日のこと。)
つまり、最初に西郷に会ったのは龍馬で、上記の印象を海舟に語ったのが、8月
23日に神戸に戻ったとき、となります。(明治の代になってからの海舟は大法螺
吹きで、自分を大きく見せることなら、このような歪曲もへっちゃら。)
いつ何処で会ったのか分かりませんが、そういったことを除いてはお龍一家の
アレコレや内祝言や妻となったお龍の許(寺田屋)へ通うのに結構忙しい思いを
していたように思います。
このため破獄を懼れて、大目付永井主水正、東町奉行小栗下総守、西町奉行滝川
播磨守らが相談の上、在獄中の者を斬る事に決めます。
獄に在ったのは大和義挙、生野義挙、寺田屋事変に関わった者が主で、7月20
日に近藤勇率いる数十人の新撰組により牢の外から繰り出す槍で突き殺されたの
は33人。
生野義挙の平野国臣、池田屋事変の古高俊太郎も含まれていました。もっとも類
焼を免れたとあって、守護職の松平容保から余りにも酷い不法な処分であるとし
て叱責の言葉が申し渡されることになるのですが。
長州藩を支援したとして有栖川宮熾仁(たるひと)親王ら廷臣が処分され、ついで
長州藩主毛利父子(敬親、定広)の官位が剥奪されます。
7月23日には長州藩征討の勅命が早くも出ます。幕府は直ちに山陰、山陽、四
国、九州の21藩へ出陣の準備を命じます。
そして8月7日、前尾張藩主徳川慶勝が征長総督の任命を受けます。
禁門の変に海軍塾の安岡金馬(「反魂香」など、お龍の聞書をした安岡秀峰の父)
も加わっていたことから(長州に逃げ延びて後に海援隊に加わるのですが)、海軍
塾に籍を置く者たちの調査が幕府により行われるようになります。(9月19日の
海舟日記。)
いて戦闘には加わっていません。
戦が始まって、天皇が賀茂社に避難するとの噂を聞いたとして、天皇に直訴する
と称して、賀茂に赴いて数刻も待っていたと云います。小五郎と同行した者は
戦闘に加わることを望んだ(実際に合流した)のですが、小五郎だけは一人残った
と云います。そして戦場に行ったときには既に戦闘が終わった後でした。
小五郎は5月2日に京都留守居役に任命されていますが、同役の乃美織江が
長州藩邸に居残っていて、火を放ってから逃亡したのに比べると、逸早く逃
げ出したとしか思えません。池田屋事変と云い、逃げの小五郎の本領発揮です。
小五郎は乞食に変装して二条大橋の下に潜んでいたと云います。そのとき夜密か
に握り飯を運んだのが芸妓幾松(後の松子夫人)と云うのは有名なエピソード。
本当はどうだったのでしょうか。場所は三条大橋下、握り飯は朝日を拝む
ようにして小五郎に向けて落とした、その女性は長州藩出入りの商人大黒屋
今井似幽の家の下女お里で、主人の言い付けで行っていた、というのが本当
のところ。
でも、それも僅かな間なんですよ。5日後には京都を脱出して但馬の出石へ行っ
て潜伏することになるのですから。
但馬出石へ逃げることになったのは、対馬藩邸に出入りしていた但馬出石の
商人広戸甚助の助力があってです。
乃美織江が長州藩邸に火を放ったのが午前7時頃、火は河原町御池の藩邸から
北へ向かって広がって行きます。火勢が収まりかけた午前10時頃に鷹司邸か
ら火の手が上がります。打ち込まれた砲弾による出火です。
さらに御所の西側の烏丸下長者町辺りの屋敷が、長州勢が潜むことができない
ようにと幕府軍により焼き払われたことも手伝って、燎原の火の如く東へ、西
へ、南へと燃え広がって、東は寺町、西は堀川、南は七条の果てまで焼き尽く
したとあります。二昼夜燃え続け、洛中の中心部4.9平方キロメートルが灰
燼に帰したのです。
町門へ向かったのですが、既に越前兵がしっかりと固めてあったため、横手から
鷹司邸の裏門から邸内に入り込みます。
丁度参内の仕度中であった鷹司輔煕に久坂は参内の供として嘆願したいと泣いて
縋り付くのですが、無常にも鷹司はそれを振り切って参内してしまいます。
先の関白鷹司輔煕は、長州系の公卿だった筈なのに。ま、公卿なんてこんなも
んですが。それに雨霰と弾丸が飛び交う中を参内?有り得ませんね。一蓮托生
を懼れて、一刻も早く屋敷を抜け出したかったのでしょう。
そうこうする内に鷹司邸は諸藩兵に取り囲まれてしまいます。
凝華洞に備えてあった口径15センチの大砲を鷹司邸の西北にある賀陽宮邸の前
に据えて砲撃し、くずれた塀から侵入したり、門扉を打ち破りなどして邸内に躍
り込むと、立て籠もっていた長州勢は敗走。久坂、寺島忠三郎、入江九一といっ
た松陰門下の三人は最早これまでと自刃して果てます。久坂26歳、寺島22歳、
入江27歳でした。
土佐の那須俊平(龍馬脱藩のときに途中まで道案内してくれました、享年58)、
上岡胆治*(同43)、伊藤甲之助*(同21)、中平龍之助(同22)、尾崎幸之進*(同
25)、柳井健次*(同23)も鷹司邸の戦闘で討ち死にしました。
鷹司邸から逃げ出した真木和泉(享年51)らも天王山に登って敵を迎え撃ったの
ですが、21日に17名全員が自刃して果てます。この中には土佐の千屋菊次郎*
(同28)、松山深蔵*(同28)、能勢達太郎(北添らと蝦夷地探索に出かけたメンバ
ーの一人、同22)、安藤真之助(同22)も含まれていました。
*印は、土佐勤王党員
中岡慎太郎は来島又兵衛に属して嵯峨から中立売門に進んだときに敵弾に足を撃
たれて、見物していたときに長州の流れ弾に当たって負傷したと嘘を吐いて、先
に入塾していた中沼塾で面識のあった(薩摩藩の支藩である)佐土原藩の周旋方鳥居
大炊左衛門の住居を訪れ、そこで傷の手当てを受け、長州に落ち延びています。
7月18日の戦が始まる直前に故郷北川村の父と義兄に宛てて決死の覚悟の遺書
を書き送っているのですが、身に付けていた小具足まで放擲してコソコソ戦場を
逃げ出したのは何とも情けない話です。
の率いる京都藩邸に潜む藩士と浪人組の一団が御所南側の堺町門右手にある鷹司
邸に向かい、天竜寺に陣取った国司信濃の手勢は来島又兵衛、児玉小民部らと三
手に分かれて御所西側の中立売門、蛤門、下立売門に向かいます。
いずれもが、御花畑(凝華洞)を宿所にしていた容保を目標に迫ろうとしたのです。
君側の奸とは、要するに天皇の叡慮を捻じ曲げているのは(自分らがかって遣っ
て来たことを棚にあげて)松平容保であるとして、率兵上京はそれを取り除くた
めのものだ、との理由付けが必要だったわけです。
しかし福原越後の一隊は、途中で大垣藩兵に行く手を阻まれ、負傷した福原を始
めとして山崎に退いてしまいます。この七百名を加えることが出来なかったこと
が勝敗に大きく関わったように思います。
禁門の変は、蛤御門の変とも呼ばれますが、それは会津藩の主力千五百名が守備
する蛤門での戦いがもっとも激しかったからです。
来島又兵衛率いる一隊が蛤門で会津兵と戦っているところに、中立売門へ向かっ
た国司率いる部隊が合流し大乱戦となっているところに、さらに下立売門へ向か
った児玉率いる一隊が加わったことから会津兵は挟撃を受ける形となり、ついに
は会津兵は蛤門を捨てて退かねばならなくなります。
蛤門を突破した長州勢は勢いを買って御所へ迫ろうと唐門で会津と桑名の兵と激
しく争いますが、長州勢に突破されそうになった間一髪、薩摩兵三百が駆け付け
てきて銃撃を加えたため戦況が逆転します。(ね、七百名がいたら、でしょ。)
蛤門での戦は払暁から十時頃まで続きましたが、来島が狙撃されて落命すると総
崩れとなります。(死骸は力士隊が山崎へ担ぎ去ったと云います。)
伏見口に家老福原越後を始めとする七百名が、山崎口には家老益田右衛門介、
久坂玄瑞、真木和泉、寺島忠三郎、入江九一を始めとする五百余名が、嵯峨天竜
寺には家老国司信濃、来島又兵衛、児玉小民部を始めとする九百名が、京都を三
方から包囲する形で布陣します。
武力を背景に藩主ならびに五卿(七卿のうち錦小路頼徳は死去、沢宣嘉は生野に
挙兵して行方知れずとなり、長州に囲われているのは五卿となっていた)の赦免
と入京の嘆願書を朝廷へ提出したのですが、この強行策はかえって公武合体派の
反発を招くことになり、とうとう7月17日には朝議が開かれ、「家老福原一人
を残し、全軍帰国すること。退去の期限は18日を限ること。命に違背した場合
は19日から長州軍を朝敵とみなし追討の軍を差し向けること」を通告されるこ
とになります。長州派公卿などの容認論もあったのですが、孝明天皇は長州が嫌
いなところを以ってこのような強硬手段に出たことが赦せなかったのでしょう。
天皇は慶喜に一任します。そして上記の対応を採ることにしたのです。禁裏守衛
総督としての初仕事でした。
もはやこれまでと長州軍は、期限の切れる18日深夜12時を期して、京都目指
して進撃を開始。既に九門は一橋慶喜の指揮の下、清和院門を土佐、蛤門を会津、
乾門を薩摩、今出川門を久留米、堺町門を越前、寺町門を肥後、下立売門を津、
中立売門を筑前、石薬師門を?(失念)の各藩が守備を固め、さらに禁裏の南門を
一橋家、唐門を会津藩、建春門を紀州藩、清所門を桑名藩で固めるといった万全
の体制を敷いていました。
に軍事総裁職)に就任させ、その準備を進めていたのですが、その跡(京都守護職)
を継ぐことを松平春嶽が拒んだため、結局4月7日に容保が再び京都守護職に復
帰します。同時に容保の実弟である桑名藩主松平定敬(さだあき)が京都所司代に
就任します。
それと、3月25日には慶喜が禁裏守衛総督と摂海防禦指揮を朝廷から命じられ
るとともに、それまでの将軍後見職を免ぜられています。
前年(文久3年)の長州藩による攘夷決行の報復のため四国連合艦隊が長州へ押
し寄せるとの報が伝わり、朝廷は京都に近い大坂湾を通過することを懼れ、前
年の薩英戦争でイギリス艦隊を退けた実績から島津久光を摂海防禦の職に就け
ようとする動きがありました。幕府はそれを嫌い、慶喜の方がまだ益しとのこ
とからこのようになったのですが、それまで幕府に気兼ねするところのあった
慶喜はハッキリと朝廷側に立つことになり、江戸の政権に対して一会桑(いっ
かいそう、一橋、会津、桑名の連合による京都)政権を樹立、政局は益々混迷
の度合いを増すことになります。
長州は上京して勅勘の宥しを請い、三条実美らの赦免を得ようと思っていたのに、
それどころか討伐と決まったことを知って、この京都の政治的空白期間を狙って
事を起こそうと計ります。
しかし率兵上洛に周布政之助、高杉晋作、桂小五郎は大反対。
尊攘激派の頭目の一人久坂玄瑞も無謀として反対していたのですが、藩に無断で
上京してきた晋作を久坂は連れ帰って、脱藩罪で萩の野山獄に投獄していまった
ところを見ると、その真意も推し量れそうです。
その証拠に京に再び戻った久坂は参与会議の解体により京都が空白地帯と化した
ことを絶好の機会と捉え、世子毛利定広に出京を促すべく帰国します。
周布が不始末の廉で謹慎処分を受けたりして、反対を唱える声が小さくなって
いたときに池田屋事変が起こります。このことが無くとも進発は避けられなかっ
たと思いますが、進発に強硬な藩士来島又兵衛、浪士真木和泉らにとっては恰好
の理由となったのです。
間髪を容れず6月15日に来島は遊撃隊を率いて進発し、16日には家老福原越
後が、26日には家老国司信濃が、続いて家老益田右衛門介という具合に続々と
京に向けて進発します。
前年8月18日の政変で京を追われた長州勢ですが、留守居役と添役一両人の滞
京は許されていたので、留守居役乃美織江はもとより、京坂地方に潜伏して桂小
五郎、久坂玄瑞、入江九一らが自藩の勢力挽回を図るべく暗躍していました。
そうこうしている内に、朝廷からの召命(薩摩藩の働きかけによるもの)で、島津
久光が一万五千の兵を率いて上洛します。文久3年10月3日のことです。引き
続き、越前藩松平春嶽、土佐藩山内容堂、宇和島藩伊達宗城が入京、一橋慶喜も
11月26日に入京します。
将軍家茂は海舟の指揮する幕府と諸藩との連合艦隊の旗艦翔鶴丸に搭乗し、12
月27日に江戸を出帆。折悪しく海上が荒れ気味であったため、入京は翌元治元
年1月15日と遅れます。
この間に朝廷から慶喜、容保、春嶽、容堂、宗城、久光が参与に任じられます。
公武合体派の待ち望んでいた、朝議に諸侯が加わっての政治が現実のものとなっ
たのです。(龍馬もこのことには大きな期待を寄せていました。)
議題は開鎖と長州処分についてです。初めのうちは、開国と長州討伐で意見が一
致していたのですが、将軍が到着したことにより慶喜が鎖国へと意見を変えます。
幕府にとっては、前回将軍が上洛したときには長州に攘夷を迫られ、今回の上洛
で今度は薩摩によって(既に幕府は横浜鎖港を決めていますが)開国へと翻されるこ
とになっては面目丸潰れとなってしまいます。先の政変でも薩摩にイニシャチブ
を取られた幕府としては何としてでも薩摩の出端を挫きたかったのです。
それで幕府の代表者である将軍後見職の慶喜は鎖国を押し通します。
当然のことながら朝議は紛糾し、3月上旬には参与会議は空中分解、それぞれ
国許へ帰国してしまいます。
お龍の許へヒョッコリ姿を現したというのはお龍の記憶違いの可能性が大ですね。
寺田屋は薩摩藩の定宿でしたので、龍馬(お龍)のために便宜を図った薩摩藩士が
居る筈です。それが吉井幸輔(後の友実)であることは間違いなさそうです。
龍馬が翔鶴丸で江戸から神戸に戻ったとき(7月28日)に吉井幸輔が一緒であった
ことは、神戸の海舟の許へ7月29日と翌々日の8月1日に訪れていることから
も確かなことで、江戸から一緒だったのか、27日に大坂に着いたときにそこで
同行することになったのか定かではありませんが、8月3日の海舟日記に「薩
吉井幸助(幸輔)、龍馬同道にて上京、其策を一橋公(慶喜)に建白し再び国家の
ため周旋せんと云」とあることから、この間龍馬も神戸に留まっていたと考える
べきでしょう。
そして吉井とともに上京して、それから龍馬はお龍の許へヒョコリ姿を現した
のだと思います。龍馬は吉井(薩摩藩)の建白(禁門の変で朝敵となった長州藩を討
伐することに薩摩藩も賛成で、その征討総督に禁裏守衛総督となっていた一橋慶
喜を担ごうとするもの)には反対であった筈(清国のように内戦に乗じて列強が介
入してくる虞があるため)で、吉井とは行動を共にしなかったでしょうから、恋し
いお龍の許へ(大仏騒動も聞き知っていて心配だったことも勿論ありますが)行っ
たのでしょう。
ですから、早くとも8月4日のことになります。
そしてお龍をどこへ預けるか、吉井のところ(京の薩摩藩邸)へ行って相談に乗って
貰ったのだと思うのです。そして吉井の斡旋で寺田屋を紹介して貰ったのでしょ
う。伏見の薩摩藩邸を通じての依頼となったでしょうから、寺田屋も無下に断る
ことも出来ません。やがては互い(龍馬と登勢)の人柄に惹かれ合って家族同然の
付き合いになるのですが、このときは薩摩藩の権威がものを云って、厄介になっ
たのでしょう。だから初めはお三としてであったものが、龍馬が度々寺田屋を
訪れるようになって、お龍の待遇も娘分へと改善されたように思います。
龍馬の母幸は弘化3年(1846)6月10日に亡くなっています(享年49)
ので、龍馬が12歳のとき。
寺田屋の登勢に龍馬がお龍を託したとき、龍馬30歳、登勢36歳。登勢の
写真は残っていますが、幸の写真は当然のことながら遺されていませんので、
似ていたかどうかは分かりませんが、龍馬が生まれて間もない頃の母の年齢。
龍馬が甘えるにはちと無理があるように思うのですが・・・。
母と共通するのは、享年が同じであるということくらいかな。
登勢は、近江国大津の旅籠山本重兵衛の次女として生まれ、18歳のときに
6代目寺田屋伊助に嫁ぎました。病弱だった伊助に代わって店を切り盛りし
ていましたが、伊助は元治元年9月26日に亡くなっていますので、龍馬が
お龍を託した頃にはもう重篤であったのでしょう。
お龍の回顧談「千里駒後日譚」(川田雪山、聞書)の第一回には、
「私は伏見の寺田屋へ行ったのです。此家のお登勢と云うのが中々シッかり
した女で、私が行くと襷(たすき)や前垂れやを早やチャンと揃てあって、仕
馴れまいが暫らく辛棒(辛抱)しなさいと、私はお三(女中)やら娘分やらで家内
同様にして居りました。処が此儘では会津の奴等に見付かるからと、お登勢
が私の眉を剃って呉れて、これで大分人相が変ったから大丈夫と云って笑い
ました。名も更えねばならぬが何と替ようと云っていると主人(伊助)の弟が、
京から遥るばる来たのだからお春と付けるが宜いと云ってつづまりお春と替え
ました」
とあります。
お龍は眉も剃っていませんし、名も春に替えていませんでしたね。多分、
これからもそのままなんでしょう。
「夫の苦労を自らも」と、冨も畳の上では寝なかったと云います。
♪ホーホーホタル飛んで行け、恋しい男の胸へ行け(ダッタカナ?)
獄に繋がれることのなかった土佐勤王党の同志が半平太らの救助に手を拱いて
いた訳ではなく、元治元年6月13日には大石弥太郎、門田為之助、河原塚茂
太郎、山本四郎らのおよそ30名が土佐藩庁に出頭して半平太らの寛典を願う
建白書を提出しています。でも効は無かったようで、今度は7月26日に野根
山に屯集した23名が藩庁に強訴をします。しかし反乱と看做されて大監察
小笠原唯八率いる追討兵が差し向けられます。
長州へ逃れようとしたのでしょうか、阿波路を通って脱藩しようとするのです
が、道を塞がれて阿波の蜂須賀家に抑留の後、土佐藩へ引き渡されます。
そして一度も審問されることなく奈半利(なはり)川原に曳き出されて首を刎ね
られました。9月5日のことです。
その23名は、
清岡道之助、清岡治之助、安岡鉄馬、寺尾権平、横山英吉、小川官次、
木下嘉久次、木下慎之助、柏原省三、豊永斧馬、千屋熊太郎、柏原禎吉、
岡松恵之助、宮田節斎、近藤次郎太郎、新井竹次郎、田中収吉、吉本培助、
宮地孫市、須賀恒次、宮田頼吉、檜垣繁太郎、川島総次
半平太は拷問を受けることも無く、「党与を結び人心煽動し君臣の義を乱した」
として、つまり政治犯として切腹を申し渡されます。以蔵らが打ち首にあった
と同じ慶応元年(1865)閏5月11日のことでした(享年37)。
ということは、以蔵は一連の暗殺が半平太の指図であったことを自白しなかった
と云うことになります。自分を毒殺しようとした張本人が半平太と知ってかしら
でか、かって師と仰ぎ、勤王党党首として奉った半平太の名を出すことなく、梟
首の刑に就いたのでしょう(享年28)。
土佐勤王党、文久元年(1861)8月に結成されてから、わずか4年足らずで
壊滅したことになります。
<文久2年8月2日>
土佐藩下横目の井上佐一郎を暗殺。加害者は、以蔵、久松喜代馬、岡本八之助、
森田金三郎、村田忠三郎。森田を除いて、4人はこの一件に関与した廉で慶応
元年閏5月11日に斬首の刑になります。以蔵だけは、その他の事件にも関与
していたので、晒し首になりますが。
森田だけは白状しなかったので、永牢処分となりました。
<文久2年閏8月20日>
本間精一郎を暗殺。以蔵、平井収二郎、島村衛吉、松山深蔵、小畑孫三郎、弘瀬
健太、田辺豪次郎が関与。
平井収二郎、弘瀬健太は令旨事件で切腹。島村衛吉は前出。
松山深蔵は禁門の変で自刃。小畑孫三郎は兄孫次郎とともに永牢処分となりま
すが、病を得て仮出獄したものの、その三日後に死亡。田辺は逮捕されなかっ
た模様。
<文久2年閏8月22日>
前関白九条家の諸大夫宇郷玄蕃頭重国(安政の大獄で同じ九条家の侍臣島田左近
と共に志士弾圧を行った)を殺害。以蔵、岡本八之助、村田忠三郎が関与。
<文久2年閏8月29日>
安政の大獄で島田左近の手先として多くの志士を摘発した岡っ引猿の文吉を殺
害。以蔵、清岡治之介、阿部多司馬が関与。
清岡は逮捕されなかったのですが、元治元年7月、半平太らを釈放する運動に
参加(安芸郡の同志23人)。しかし反乱とみなした藩庁が差し向けた軍勢に捕
えられ、全員が安芸郡奈半利川の河原で斬首されました(後述)。
阿部多司馬については不明。
<文久2年9月23日>
安政の大獄で長野主膳、島田左近らとともに志士摘発を行った京都町奉行所与力
の4人、渡辺金三郎、森孫六、大河原重蔵、上田助之丞を殺害。
土佐、長州、薩摩、久留米の4藩から複数の志士が参加していたとされ、半平太
の「在京日記」には土佐からの参加者として12名が記されていますが、以蔵は
その中に入っていないので、実際はどうであったか分かりません。
<文久2年11月15日>
長野主膳の妾村山加寿江の子多田帯刀を、長野とともに安政の大獄において志士
弾圧に加わったとして殺害。小畑孫三郎、河野万寿弥、依岡珍麿、千屋寅之助ら
とともに、以蔵も加わっていたとされています。
小畑孫三郎は前出。河野万寿弥は永牢処分。依岡珍麿は不明。千屋寅之助は
海舟の許に匿われていたので嫌疑を逃れた模様。
<文久3年1月22日>
安政の大獄の際に幕府に寝返って重罪を逃れたとして、儒学者池内大学を殺害。
大阪に来ていた山内容堂に招かれたその帰りを襲われました。しかもその切り取
られた両耳が、それぞれ正親町三条実愛と中山忠能の屋敷に投げ込まれ、二人の
辞職を招くこととなります。この一件が容堂をえらく刺激したことは確かです。
以蔵以外に誰が関わっていたのか、確かなところは分かっていません。
<文久3年1月29日>
安政の大獄の際に島田左近らに協力して志士弾圧に加わったとして、公家千種有
文の家臣賀川肇を殺害。
薩摩の田中新兵衛の犯行であるとされていますが、以蔵も加わっていたとする説
もあるようです。
以蔵が関係していない土佐勤王党同志による暗殺も幾つかあるようですが、割愛
します。(島本審次郎は、それらで処罰されたのでしょうか、永牢となります。)
訊問が始まったのは元治元年5月23日。なんと投獄されてから8ヶ月も経って
います。
名を変えて京坂に潜伏していた岡田以蔵が元治元年4月に捕縛されて、土佐の
山田の獄舎に繋がれたのは6月14日のこと。このことから(閏5月もあるので)
京地でかなりの詮議を受けてから送致されてきたことが分かります。ですから、
投獄されている者たちを立件するに足るとの判断が働いて、訊問が始まったの
でしょう。
8月16日付の容堂が春嶽へ宛てた手紙に「御存(知)の半平太の徒を大所置仕
り候跡は大分閑を得申すべく候」とありますので、最早決着が見えていたので
すね。
最初に取調べに遭ったのは島村衛吉(「団塊の世代雑感(44-4)」参照)で
す。その取調べは、参政吉田東洋の暗殺事件や京都を中心とする一連の暗殺事件
についてです。
龍馬伝のように、彼らの受けた拷問を獄舎の違う半平太が直接耳にすることは
ありませんが、獄外にある同志や協力者からその様子を伝え聞きます。
上士である半平太が繋がれたのは高知城のすぐ近くの南会所ですが、下士が
繋がれた山田の獄舎は、そこから1km余り離れた(江ノ口川に架かる山田橋
近くの)ところにありました。
口裏を合わせるまでもなく、島村衛吉は厳しい拷問にも耐え、決して口を割ろう
とはしませんでした。しかし、桃井道場で皆伝を授かるほどに鍛えに鍛えた身体
も度重なる拷問には耐えることができなかったのでしょう、終には吐血して果て
たと云います。翌慶応元年3月23日のことでした(享年32)。
半平太の実弟田内衛吉は、そうは行きませんでした。拷問に耐えることが出来ず
に全面自供してしまいそうになります。自らの意思でそうしたのかどうか分かり
ませんが、毒(その毒薬天祥丸は半平太の手筈で衛吉の手に渡ったと云います)を
煽って自害します。元治元年11月28日のことでした(享年30)。
岡田以蔵も拷問を受けますが、比較的早い時期に白状してしまいます。
これがために元治元年8月11日、新たに久松喜代馬、森田金三郎、村田忠三郎、
岡本八之助が逮捕されてしまいます。
龍馬伝では以蔵への拷問を聞いた半平太が「すまん」なんて云っちゃってますが、
本当のところは、以蔵が捕縛されたこと聞き知った半平太は、実家への手紙で
「あのような安方(あほう)は早々と死んでくれれば良いのに、おめおめと国許へ
戻って来て、親がさぞかし嘆くであろう」なんて云っているのです。
このことからも前述したような(京地での)以蔵の自白があって、それが半平太
の耳にも届いていたことが分かります。
アレコレ喋られては不味いと思ったのでしょう、以蔵の毒殺を謀るのですが、何
故だか上手く行きません。逆の見方をすれば、このことを知った以蔵が、この酷
い仕打ちに、何としてでも拷問に耐えてみせるといった意気地が挫けてしまった
とも考えられます。
半平太が投獄された文久3年9月21日、河野万寿弥、小畑孫次郎、小畑孫三郎、
島村衛吉、島本審次郎も獄に繋がれます。
8月18日の政変(天誅組の挙兵は8月17日)が直接の切っ掛けとなって、
「京師の御沙汰に付、天朝に対し奉りそのままには捨て置きがたく、不審の
者ども取締り申し付ける」との廉で捕縛したわけです。
半平太は、揚り屋と称される上士が入牢する南会所の獄舎に繋がれるのですが、
そこは牢番を通じて外部と連絡を取ることができるだけでなく、物の差し入れも
許されていたのか、絵(自画像や「笑泣録」と題された獄中生活の様子が遺されて
います)を描いたりもできたようです。
「笑泣録(しょうきゅうろく)」によると、藁葺き屋根の小屋の中に牢格子が
あり、そこが二つに仕切られていて、向かって左側に半平太が、右側に檜垣
清治が入っていて、和歌を交換し合ったとあります。檜垣は、文久2年の
五十人組(「団塊の世代雑感(56-7)」参照)の一人で、同年11月10日
に小田原で、同行の田内衛吉、今橋権助と三人で、足軽の坂本瀬平を偵吏と疑
って掩殺。その後自首して終身禁錮刑となって繋がれていました。
*この檜垣、龍馬の有名なエピソードの登場人物なんです。それは、龍馬が
土佐で流行っていた長い刀を差している檜垣に「今は短い刀の時代じゃ」、
檜垣が短い刀に変えたら今度は「ピストルの時代じゃ」、檜垣がピストル
を手に入れたら「今はこれじゃ」と云って万国公法を見せた、と云うもの
ですが、維新を迎えるまで牢獄に居たのですから、これは作り話。
ですから、下士が繋がれた山田の獄舎(平井収二郎が爪で引っ掻いて書いた辞世の
句を思い出してください)と比べると断然恵まれた環境だったわけで、土佐藩の
上士と下士の身分による差別がよく分かります。
土佐勤王党の獄に連座した者として、上士では前監察の小南五郎右衛門が勤事控
え、下士では島村寿之助と安岡覚之助が親類預け、と処分されています。
さらに翌22日には、岩神主一郎、鳥飼謙三郎、那須盛馬(後の片岡利和)、土方
左平、古沢迂郎、井原応輔、古沢南洋、橋本鉄猪(後の大橋慎三)、浜田辰弥(後の
田中光顕)が勤事控えとなります。
この間に脱藩する同志が相次ぎます。海舟が日記に門人と書いた田所島太郎も
その一人ですし、龍馬伝でもこれから姿を見せるであろう中岡慎太郎もそうで
す。みな尊王攘夷の総本山である長州へ、浪士たちの屯する三田尻へと一目散
に逃げ出します。
龍馬伝では、龍馬が新撰組に斬りかかろうとして桂小五郎に押し止められた、
なんて話になっていますが、そんな龍馬でないことは、以下のお龍の回顧談
(「千里の駒後日譚拾遺」川田雪山聞書)で分かろうと云うもの。
「伏見で居た時分(元治元年か翌慶応元年)夏の事で暑いから、一晩龍馬と二人
でぶらぶら涼みがてら散歩に出掛けまして、段々夜が更けたから話しもって帰
って来る途中五六人の新撰組と出逢いました。夜だからまさか阪本とは知らぬ
のでしょうが、浪人と見れば何でも彼でも叩き斬ると云う奴等ですから、わざと
私等に突当って喧嘩をしかけたのです。すると龍馬はプイと何処へ行ったか分ら
なくなったので、私は困ったがここぞ臍(ほぞ)の据え時と思って、平気な風を
して、あなた等大きな声で何ですねえ、と懐ろ手で澄して居ると、浪人は何処
へ逃げたかなどブツブツ怒りながら私には何もせず行過ぎて仕舞いました。私
はホッと安心し、三四丁行きますと町の角で龍馬が立留って待って居て呉れま
したかね、あなた私を置き去りにして余んまり水臭いじゃありませんかと云う
と、いんにゃそう云う訳じゃ無いが、あやつらに引っ掛るとどうせ刀を抜かね
ば済まぬからそれが面倒で陰(隠)れたのだ。お前もこれ位の事は平生(ふだん)
から心得て居るだろうと云いました」
君子危うきになんとやら。薩長同盟が成って直ぐに寺田屋で襲われ傷ついた
龍馬への見舞文(慶応2年2月22日付)に小五郎は「大兄は御心の公明と御量
の寛大とに御任せ成され候て、兎角御用捨これ無き方に御座候得共、狐狸の世
界か豺狼(さいろう、山犬と狼と)の世間か、更に分らぬ世の中に付、少敷(すこ
しく)、天日の光相見え候迄は、必々何事も御用心」なんて書いていますが、
龍馬自身が姉乙女に宛てた有名な「日本を今一度せんたくいたし申候」の手紙
(文久3年6月29日付)で「中々こすい(ずるい)いやなやつで死(しに)はせぬ。
(中略)けしてけして(決して決して)つけあがりはせず、ますますすみこうて(隅で
小さくなって?)、どろの中のすずめがいのように、常につちをはな(鼻)のさきへ
つけ、すなをあたまへかぶりおり申候」と告白しているように、龍馬なりに用心
深いのです。尤も「逃げの小五郎」から見ると、危うげに見えるのは致し方無い
ことではありますが。
(65-3)では「南側」とすべきところを「北側」と誤って
いたので修正しました。
(65-10)では「北」とすべきところを「南」と誤って
いたので、これも修正しました。
(その他のところは一切手を入れて居りません。)
それにしても北と南の方角を間違えるなんて、トホホ、トホホ、トホホ・・・。
第1回)だと以下のようになっています(要約)。
望月は切り抜けて土佐藩邸へ逃げ込もうとしたが、門が閉まっていて入ること
ができない。そこで引き返して長州藩邸へ行こうとするところを追いかけてきた
者(大勢であったとあります)の槍で横腹を突かれた。(そこで最早これまでと望
月は自刃するのですが。)
お龍は母貞のことが気になって扇岩を飛び出して行って見ると(これは千本屋敷
へ引っ立てられたことを知らされて、そちらへ行ったところ)、蓆を被せた望月
の死骸があった。晩に又行ってみたところ、死骸は長州藩邸に引き取られてい
てそこには無かった。
望月が自刃して果てたのは5日の午後11時を廻った頃でしょう。ですからお龍
が、その遺骸を千本屋敷で当日見たとはとても思えません。見たとすれば翌日の
ことになりますが、そうだとすると母貞が連行されたことを知ったのも翌日とい
うことになってしまいます。
大仏騒動と云うくらいですから、さほど離れていない扇岩のお龍の耳に届かぬ筈
がありません。
おそらく、母貞が連行されたのは5日で、それはお龍にも知らされた。しかし、
母が調べを終えて帰宅を許されたのは翌6日のことだったのでしょう。
中々戻って来ない母のことが心配になって千本屋敷へ行ったときに、そこに蓆で
覆われた望月の遺骸があった、ということなのでしょう。それと母とは途中で入
れ違いとなったのでしょう。
と云うことであれば、(65-9)の大高又二郎の所へ行ったのも6日のようで
す。桝屋は四条通を少し上った高瀬川べりにありましたので、そこを訪ねてから
千本屋敷へ行ったのではないでしょうか。
それと望月の逃亡経路もかなり変です。池田屋から土佐藩邸へと逃げたのであ
れば(三条から四条へと南へ下ったのですから)、土佐藩邸に入れなかったとし
ても、また元の道を引き返して池田屋の北にある長州藩邸へ向かうのは敵中突
破そのもので、有り得ません。
しかし最初から長州藩邸を目指したのであれば、桂小五郎が立寄っていたという
対馬藩別邸、加賀藩邸、その次に長州藩邸があると云う近さですから、納得が
行きます。しかも長州藩邸には同志の連中が匿われていた(その総管が小五郎)の
ですから尚更です。
つまり当時公武合体派であった土佐藩への当て付けとして創作されたものなの
です。
斯様に歴史を紐解くのは甚だ厄介なことで、紐の結び目を見極めないと冒頭の
ような破目に陥ることになります。
P.S.
どちらの回顧談でも龍馬は8月1日の夕方にお龍のところ(扇岩だと思います)に
戻ってきたことになっています。そして母貞らが金蔵寺に居ることを聞いて、
そこを訪ねたのだと思いますが、住職知足院を仲人に寺の本堂で内祝言をして、
その夜だと思うのですが初めて契ったとあります。そしていつまでもここに置い
ておけぬと云うことになり、母貞を杉坂の尼寺へ、太一郎と君江は神戸の海舟の
許へ、お龍は伏見の船宿寺田屋へ、とそれぞれ預けることになります。
光枝は公卿の伏原家へ奉公、次郎は金蔵寺に預けたままにしたのでしょう。
それにしても龍馬は7月28日に神戸に戻ってから3日後の8月1日に入京し、
2日には再び神戸に戻って、3日にはまた京へ向かって(薩摩藩の吉井幸輔とと
もに)神戸を発っているのですから、もしそれが全て事実だとしたなら、まるで
スーパーマン(古い?)。つまりどこかおかしいのです。どこかに嘘や誤解が紛れ
込んでいるのです。7月28日と8月3日の龍馬の行動は海舟の日記なので間違
い無い、と云いたいところですが、海舟もリアルタイムで日記を付けていなかっ
たそうですし、一体何を信用して良いのやら・・・。
の朝に幕府方の手入れがあり、そこに唯一居残っていた北添は慌てて逃げ出し
たのです。
お龍の回顧談(「反魂香」(安岡秀峰聞書)の第2回「大仏騒動及び内祝言」)に
よると次のようであったと云います(要約)。
(住み込みの扇岩で)朝、目を覚ますと表が騒々しいので、何だろうと思って着
替えをして門口を出る出会い頭に、大利鼎吉に思いを寄せている千本屋敷(西町
奉行所のこと、二条城西側の千本通に面したところにあったことからこう呼ば
れた)の目明しの娘お妙が君江を連れて来るのに逢い、事情を訊くと、大仏へ
会津の手の者が押し寄せてきて、母貞を縛って千本屋敷へ連行したと云う。
お龍は驚いて二人と一緒に大仏へ行って見ると、家中踏み荒らされてあって、
あちこちが槍で突かれている。
お龍が呆然としているときに、他出していた大利鼎吉が何も知らずに戻って
きたので、事情を手短に話して聞かせ、大利の身を案じて、お妙に伏見まで
逃すように頼んだ。
それからお龍は君江を隠れ家の家主河原屋五兵衛宅に預けてから、河原町の
大高某という具足師(大高又次郎のことで、播州林田藩の脱藩浪士。赤穂浪士
の大高源吾の後裔で家伝の甲冑製造を生業としていた。古高の同志で、桝屋の
道具蔵に収められた武器弾薬は、その殆どを大高が集めた)のところへ駆け付
けたと云います。
大高は宮部鼎蔵の勧めもあって、古高の宅内別棟に住んでいました。
理由は分からないのですが、「家内に秘密室を設けてあって、三藩の浪人
を潜ませて居た」と語っていることから、大高やその潜ませている誰かに
相談するために行ったものと思えます。(龍馬から言い付かっていたのかも
しれません。)
しかしそこも既に手が廻っていて、大高は斬り殺され、三人の子供は泣くは、
妻は発狂したような有様。
これもどう解釈してよいやら。大高又二郎は池田屋で即死した7名のうちの
一人です。夫の憤死の報せを聞いた妻とみは自害を計ったが死に切れず、傷
の療養をしていたとありますので、自害を計る以前に訪れたのでしょうか。
暫くその有様に呆然としていたが、漸く心を取り直して大仏へ引き返すと、
母貞が帰っていた。訳を訊くと、何も知らない者ということで放免されたと
のことで抱き合って喜んだが、ここに何時までも居るわけにゆかぬからと、
ひとまず金蔵寺へ引き移った。
ことが分かっていたからでしょう。
別れの盃と云うことで、(以前にどこかに書いたと思うのですが)皆がそれぞれ
変装(手代風に装った望月亀弥太、大店の番頭に化けた菅野覚兵衛、龍馬は易者
に、お龍は若衆姿に)して祇園の一力でドンチャン騒ぎして大仏に引き上げます。
その翌朝、望月と大利鼎吉が伏見まで龍馬を見送ったと云います。
その付き合いの好い望月が運悪くと云うか、たまたま京都に居残った北添佶摩
と二人して、池田屋事変に巻き込まれて命を落とすのです。
隠れ家に出入りしていたのは、龍馬、中岡慎太郎、北添佶摩、望月亀弥太、
大利鼎吉、菅野覚兵衛、池内蔵太、安岡金馬、山本甚馬(兼馬?)、吉井源馬、
早瀬某(?)などであったと、お龍が後に語っていますが、望月と北添以外は
皆近国や遠国へ行っていて不在だったのです。
望月、北添ともに池田屋に居たことになっていますが、北添は大仏の隠れ家に
居たところを捕り方に襲われ、着の身着のままで逃げ出したものの、おそらく
望月のことを心配してだと思いますが、安否を探りに池田屋へ向かったところ
を残党狩りにあって、殺害されたとも云われています。
望月が大仏の隠れ家に龍馬らと一緒に居たのは、北添(蝦夷地調査をして来た
中心人物)が一緒だったことからも分かるように蝦夷地の件で参加者を呼びか
けるためのものだったのでしょう。
(菅野も同様の目的で神戸海軍塾を抜け出して来ていたのでしょう。)
そして龍馬の江戸行きが決まって、その実現性が高まったことから、手分けし
て同志を募るために各地に散ったのだと思います。
望月と北添が残っていたのは京都を受け持っていたのかもしれません。そして
6月4日の夜、古高が捕えられたこと、その救出についての会合が5日夜に池
田屋であることを望月だけが知ったのだろうと思います。そして大仏には戻ら
ずに当日は池田屋もしくはその界隈に居たのでしょう。
2日の朝京を出立し、8月1日にお龍の許へ戻るまで(7月28日には神戸
の海軍塾へ帰っている)は江戸を中心に、黒龍丸(蝦夷地開拓・防衛)の一件
で活動していたので、池田屋事変にも、やがて起こる禁門の変にも巻き込ま
れることはありませんでした。
越前藩所有の黒龍丸を幕府で買い上げて操練所で使用させて欲しいと、2月
7日に海舟は二条城で閣老の水野和泉守忠精に建白書を提出しています。
龍馬は、黒龍丸を軍艦として大砲を積んで、数年交代で神戸(と江戸)とを
護ることに決したことが不満で、(蝦夷地での開拓、これは通商も含むもの
ですが、それと主にロシアを想定してのことですが、その侵略に備えた防衛
を考えていて)嘆願書を出したらしいのですが・・・(以下参考)。
5月29日に神戸海軍操練所の修行生の募集が行われますが、これに前後
して海舟は、既に練習艦と決まった観光丸だけでなく、黒龍丸も買い上げて
もらえるのであれば、両方の船に乗り込む士官、水夫、火焚どもの経費は
一年当たり1万5千両掛かるので、大坂のお蔵から渡してもらえるように
下知して頂きたいと幕府に願い出ているので、既に黒龍丸が神戸海軍操練所
で使用できる話がかなり煮詰まっていたことが分かります。
6月17日の海舟日記には、(12日に江戸を出帆した海舟の長崎丸が遠州灘
でシリンダーが故障して、14日に下田に入港し、江戸へ乗り換え用の船と
長崎丸を曳航する船を要請したところ)「乗り換え用の翔鶴丸、長崎丸を曳航
するための黒龍丸が入港。坂本龍馬は江戸へ行き、右船(おそらく黒龍丸)で
遣って来た。そのとき龍馬が云うには、京摂の過激派の数十人(傍注として
二百人程と書き込みがあるのは目標とする所要人数か)皆を蝦夷地開拓と通商
を国家の為と奮発している。この輩は皆黒龍丸で神戸から乗り回すつもりで
あり、このことは朝廷も老中水野和泉守忠精も承知のことである。且つ入費
としての三、四千両は同志の者があちこちから取り集めた。だから速やかに
この策を施すべきである、と。」(要約)。
これに続いて海舟はこのことを「志気甚だ盛んなり」と書いています。
観光丸は貸し出していた佐賀藩から戻されて7月18日に正式に神戸海軍操
練所の所属となりますが、黒龍丸は7月19日に幕府に買い上げられている
のですが、同日に禁門の変が起きて、池田屋事変だけでなく禁門の変にも海
軍塾の生徒が関わったことが幕府にも知れたことから、疑いの目を持って見
られるようになった海舟の許へ黒龍丸は引き渡されなかったものと思われま
す。
いずれにせよ、このこと(黒龍丸を幕府が買い取ったこと)をしっかり確かめた
上で龍馬は翔鶴丸で神戸へ戻ってきたものと思われます。龍馬がその間江戸
に居た傍証として、海舟日記の7月28日の条(龍馬が神戸へ帰ってきた旨を
伝えたその続き)に「江戸の大久保一翁が将軍上洛のことを論じた一件(政権を
朝廷が委任してくれないのなら、将軍職を一切返上して云々ということだと
思いますが)で、(21日に任命された勘定奉行を)退職したことを龍馬が伝え
た」(要約)とあります。辞職が認められたのは25日のことですから、(龍馬
にとってパトロン的存在であった大久保一翁の失脚は、江戸に留まってもそれ
以上の進展が望めないという見切りをつけることにもなったと思いますが)その
辺りで江戸を発って27日に大坂に到着し、そこから同船で神戸へ戻ったのか、
陸路を採ったのか分かりませんが、翌28日に神戸へ着いたのだと思えます。
たと云います。約1時間ほど遅れて土方らのグループが合流したとは云え、
近藤ら5名(近藤勇、沖田総司、永倉新八、藤堂平助、近藤周平)のうち、
沖田は持病の肺結核のため酸欠となって昏倒、藤堂は頭の鉢金に斬り込まれ
て額から流血の重傷、永倉も親指の付け根を削がれるといった有様でした。
30数名も相手にしての大立ち回りですから当然と云えば当然のことです。
「今宵の虎徹はよく切れる」と近藤勇が云ったかどうか知りませんが、バッタ
バッタと斬り捲くったのでしょう。勤王志士側は7人が即死、23人が負傷の
上、捕縛されたと云います。即死でなくとも逃れる途中で討ち取られたり自刃
して果てたものもいますので被害甚大です。中でも長州の吉田稔麿、土佐の
北添佶摩、肥後の宮部鼎蔵といった大物が殺されたのは勤王志士達にとって
大きな痛手となりました。
さらに池田屋の主人惣兵衛以下、その関係者(婦女子までを含む)までもが連行
されて何らかの刑に処されたと云います。(惣兵衛は獄中で病死。)
新撰組でも、後から合流した中から奥沢栄助が即死、安藤早太郎と新田革左
衛門が重傷であり、後にこの傷が元で死亡、といった被害が出ています。
土佐の参加者は7名でしたが、北添佶摩、石川潤次郎、伊藤弘長、越智正之
の4名が即死、望月亀弥太、野老山吾吉郎の2名が負傷して逃げる途中で死亡、
藤崎八郎が負傷して捕えられた後に死亡、と全員が亡くなっています。
浪とか云われていたのが、前年(文久3)の8月18日の政変で活躍した褒美
として朝廷からその名を賜ったのです。そのときの一同52人の出で立ちが、
後にトレードマークとなる袖口を白く山形に抜いた浅黄麻のダンダラ羽織で
した。(龍馬伝ではどういうわけか、白っぽい無地の羽織を着ていますが。)
当日の新撰組の出動は、それと気付かれないように行われています。正午に
なると、白の単衣で普段と変わらない様子で壬生の屯所を三々五々出ていま
す。このときにダンダラ羽織を纏っていたかどうかまでは分からないのです
が、単衣の下には防具の竹胴を付けていました。
夏至の頃ですから日没まで長いのですが、それを待っていたかのように午後
7時過ぎ、八坂神社の石段下近くにある祇園町会所に集合します。その人数
30名。
そして局長近藤勇以下5名が四条通を真っ直ぐに進んで四条大橋を渡って、
右に折れて先斗町通を三条通に向かって行くルートを採り、副長土方歳三率
いる25名は三手(大和大路通、花見小路通、花見小路通と東大路通に挟まれ
た間道)に分かれて、それぞれ祇園方面に向かって進み、三条通に突き当たっ
て左折して三条大橋を渡るというルートを採ります。
その間、虱潰しに御用改めをして廻って、やがて池田屋へ到ることになるの
ですが、桂小五郎が後に語る(『木戸孝允長藩勤王始末覚書』)ところによると、
「夜五ツ(午後9時)頃に池田屋を訪れますが未だ同志が来ていなかったので、
近くにある対馬藩別邸に立寄ってからまた来ようと一旦立ち去った、それから
数刻も経たない内に新撰組が池田屋を襲った」(意訳)とあります。
近藤ら5名が池田屋へ踏み込んだのは夜四ツ頃と云いますから午後の10時
半頃です。その間1時間30分ほどですから、二刻(80分)ちよっとを話し
込んでいて命拾いしたことになります。
土佐勤王党の獄については、次に回すことにして、今回は池田屋騒動につい
て。
池田屋事変は、元治元年6月5日の夜に起きました。当日は晴れでしたが、
昼過ぎに小雨が降ったものの、梅雨の長雨も丁度この日に上がったそうです。
新暦だと7月8日に当たりますので、盆地特有の炒る様な京の夏が始まった
ことになります。5日は祇園祭の鉾の曳き初めの日で、翌日の宵山、翌々日
の巡行を控えて、京の町はお祭り気分。
池田屋は、三条大橋から高瀬川に架かる三条小橋を渡って北側の五軒目にあ
りましたので、四条室町辺りを中心とする祇園祭の喧騒の外にありました。
そもそも何故この騒動が起こったか、ですが、
肥後の宮部鼎蔵(ていぞう)の下僕が捕えられて、その口から古高俊太郎の名
が出て、木屋町通り四条上ル桝屋喜右衛門となって薪炭商を営んでいた古高
の正体が露見して捕えられたことが端緒とされています。6月4日夜半のこ
とです。
捕えられた古高の家からは武器弾薬や会津藩の印の付いた提灯までもが発見
されます。さらに長州藩士らとの往復書簡も見つかります。
これだけの証拠を突き付けられても口を割らなかったのですが、新撰組の土
方歳三による過酷な拷問に耐え切れず、到頭「風の烈しい夜を待って、禁闕
に火を放ち、その騒動に紛れて中川宮と会津侯の参内の途中を要撃して、昨
年8月18日の復讐をする、そしてその混乱に乗じて天皇を長州へ動座する」
と白状してしまいます。
共謀者の名や潜伏先も自白したので、翌日には会津藩士、所司代、町奉行、
新撰組による大捜査網が敷かれることになります。
家に帰ってみると、今度は末の妹の君江が居ない。どうしたのか母に
聞くと、昨日中根のおつぎが来て今度の舞の会に貸してくれというの
で貸したが、(今日になっても)まだ帰って来ないと言う。
お龍はまたまた吃驚して、あの人は娘を騙して連れていっては芸娼妓
に売り飛ばす悪人、お母さん、待っていて、私が連れ戻してくるから、
と云うや直ぐに中根の家へ行って、アレコレ談判の末、無事連れ帰った」
そしてこのままで置いたら、また同じ様なことが起きると心配して、人に
頼んで光枝を公卿の伏原家へ奉公させ、君江は大仏の加藤という本陣へ
預けたとあります。
大仏騒動のとき、光枝はやはり奉公に出ていたことが分かりましたね。
君江が預けられた大仏の加藤と云う本陣とは、大仏の河原屋五兵衛の隠
居所(勤王浪士の隠れ家)のことで、「水口加藤下陣」と表札を出していた
のです。琵琶湖の南側に位置する近江の水口(みなくち)藩の加藤の屋敷
と称して潜伏していたのです。
聞書ですので、書き手の誇張なども入ってくるので、その通りに受け取る
ことはできないのですが、おおよそのところ(雰囲気)は伝わってきます。
気になるのは、慶応元年9月9日付の龍馬が姉乙女(と姪春猪)に宛てた手紙
では、君江は殊の外美人なので島原の里へ舞妓に売ったが、未だ年端も行か
ないので(12歳)、気遣いないだろうとそのままにして置いた、とあること
です。お龍の回顧談とちょっと違うでしょ。
と云うことは、龍馬がお龍から詳しく聞いたのでは無いと云うことになり、
(前回、母貞が、お龍に気がある龍馬に、そのようなことを語る筈が無い、と
書きましたが)回顧談による限りは、無防備な母貞が語ったのだろうと思い
ます、それも未だ龍馬と会って間もない頃(文久2年末?)に。
おい、お前さん方は何だって妹をこんな処へ連れてきたんです、母に
聞けば大家へ小間使いにやるとか、いうそうですが、妾(わたし)の眼
の黒い内は、めったに、妹を他処へは遣りませんよ、さあ、妾が妹を
連れて帰りますから、其積りで居て下さいと、立上って妹の手を執る
と、一人の男が、矢庭にお良(お龍)の腕を捉えて、やい阿魔、何でい、
此女を如何(どう)するというんでいと、眼を怒らせて今にも飛かから
ん勢い、お良は平気で、何だとい、此女を如何する、フン自分の妹を
自分が連れてゆくに、何が如何したとお言いだい、ふざけた事を言い
なさんな、手前達は何だい気の毒だが、真白昼(まっぴるま)往来を両手
振って歩ける身分じゃあるまい、いけずうずうしい畜生だっと、最早
怒り心頭に発して居るものですから、思い切って男の横面を、火の出る
程撲りました。おやっと外の二人が立上ろうとする奴を、傍にあった
火鉢を執って、投げつけますと、ぱっと上る灰神楽、即意即妙の目つ
ぶしに、三人とも、目をやられて、言い合したように台所へ馳せゆく
隙を窺い、光枝の手を執って表へ出ますと、お吉婆が背後から、帯を
捉えて引戻そうとするやつを、エイッと蹴飛ばして、逃げ出し、八軒
屋の京屋という船宿に飛び込んで、三十石船に乗り、京都へ帰って我
家へ着きました。
本編に入る前に前回「(64-3)」の訂正を。イツモノコトナガラ、スミマセン
お龍の逸話、迂闊にも龍馬の手紙だけを頼ったのが間違いのもと。
見落としていた史料があったのです。お龍自身が語っているのです。
「続反魂香」(安岡秀峰聞書)の第4回「お良の憤怒」です。
ちなみに反魂香(はんごんこう)とは、焚くと死者の姿が煙の中に
現れる香のことで、お龍からアレコレ聞き出すことで龍馬のこと
を炙り出すといった意味合いから名付けたものと思われます。
では、その要約を。
「(安政の大獄に連座し捕えられて禁錮刑に処せられて、翌安政6年
夏に釈放されたものの、3年後の文久2年1月20日、京都柳馬場
三条下ルの自宅で)父楢崎将作に死に別れてから一家は落魄し、京都
の木屋町(借家)に居た頃、お龍が留守のときに下河原の芸者屋玉家の
女将お吉が訪ねてきて、将作に散々世話になったことを語り、その恩
返しにと、大坂で小間使を求めている大家に光枝を遣る話を始めます。
その猫撫で声に乗せられて母貞は承知してしまいます。
お龍が戻ってくると光枝の姿が見えないので、母に聞くと、これこれ
との話。お龍は吃驚して、相手がとんでもない女であることを話して
聞かせると、母はもうオロオロして涙ぐんでさえいる。お龍は、お母
さん心配しないで、私が行って取り返してきますと云って、金子を調
えると、先ずお吉の家へ行きます。その亭主と言い争いになったもの
の、何とか大坂の居所が分かって、お龍は大坂へ。
大坂のドブ池という処に行くと、お吉と三人のゴロツキが光枝を取り
囲むようにして何かを云っている。そこへ割って入っていって座り込
んで彼らを睨み回してから、お龍が啖呵を切ります。
勤王浪士たちの隠れ家として使用されていたと考えるべきなのでしょう。
僕は文久3年の比較的早い時期に貞らが遣って来たように思います。
そしてその時期にお龍と顔見知りになり、半平太が帰国する直前に龍馬を訪ねて
遣って来たとき(龍馬が京都藩邸での謹慎を終えて、3月6日に藩から正式に航海
術修行を命じられた直後?)に、お龍が仲居として働く扇岩へ誘って別れの杯を交
わしたのではないでしょうか。
扇岩は名前からしても割烹旅館だったのでは。ですから飲み食いもできたよう
に思うのですが。
それに上記9月9日付の手紙に「(一家は)もとは十分裕福に暮らしていたので、
花を活けたり、香を聞いたり、茶の湯をしたりなどはしても、炊ぎ奉公などを
することはできず」(要約)とあるように、龍馬伝のようにお龍が扇岩で飯炊き
といった下働きをしていたとは思えません。お龍の容貌からしても、料理店の
仲居であった筈です。
そして、そのときにお龍を紹介したのか、それとも後になって、あのときに連れ
てきた立派な身形(「アゴ」と云ったかも)をした大男(半平太は六尺近くあったと
云いますから龍馬よりちょっと背が高い)が半平太であると説明したのかも知れま
せんが、そのときのことをお龍が回想して「武市さんには一度逢いました」と云
ったように思えてなりません。
つまり文久3年3月頃、二人はそれなりに親密な仲だったのかも知れません。
付の長い長い手紙ですが、そこでは、お龍の年齢を23歳としているので、話
は文久3年(1863)のことなんですね。
その逸話は次のようなものです。
悪者が母貞を騙して、12歳の君江を島原へ舞妓に売り(年端も行かないので
差し当たりは問題ないだろうと後回しにするのですが)、16歳の光枝を大坂
へ女郎に売ってしまいます。それを知ったお龍が自分の着物を売るなどして金
を作り、大坂へ下ってその悪者相手に啖呵を切って妹を連れ帰ったというもの
です。
龍馬伝のように、5両の身請けに1両しか調達できず、龍馬が立て替えて
あげた、というようなことは、どこにも書かれてありません。
事情を聞いた上でとあれば、龍馬が金だけ出して知らん振りということは
有り得ません。一緒に大坂まで付いて行った筈です。もしお龍が口の堅い
女で、事情を話さなかったのだとしたら、上記のような経緯だって教えて
もらえなかったでしょうし。
龍馬、見てきたように書いているのです。お龍にしても他人に自慢できるよう
な話ではないので、本人が後(翌年)に龍馬に話して聞かせたとは思えません。
母貞だって、お龍に気がある龍馬にそのようなことを語る筈がありません。
と云うことは、その一件があったときに龍馬はお龍の身近に居て、(当然事後の
ことでしょうが)聞き知ったとしか思えません。
多分、龍馬が扇岩にお龍を訪ねたときに居合わせなかったので、店のもの
に訊いて、お龍が戻ってきたときに更に詳しいことを訊き出したのだと思
います。
であれば、文久2年冬から翌3年にかけて龍馬が京都の隠れ家として利用して
いたのは、この大仏の隠居所であった可能性が高いことになります。
前述したような関係から、貞らが移ってきた時期を元治元年5月頃と考えてし
まい勝ちですが、時間軸が不明確なのは回顧談の常、そしてそれをしっかり確
かめられない聞き手の問題ということもあります。
ごんこう)」(安岡秀峰聞書)の第2回「大仏騒動及び内祝言」で、次のよう
に語っているからです(要約)。
天誅組の残党が京都大仏南門(方広寺南門のことで、現在の三十三間堂南門)
の今熊野道のところにある河原屋五兵衛の隠居所を借りて隠れ棲んでいたの
ですが、男所帯では不便ということで、(その当時お龍の一家は四条の裏通り
の借家に住んでいたのですが、)大仏に出入りしている米屋からお龍の母貞に
住み込みの話が舞い込んできたのです。
それで母貞の大仏への引越しに合わせて、三人の子の始末として、長女の
お龍を大仏からそんなに離れていない七条新地にある扇岩という旅館で働
けるようにし、12歳の三女君江は貞が連れて行き、5歳の次男次郎は粟田
の金蔵寺という親戚(父将作の知友知足院)に預けた(そうです)。
長女光枝と長男太一郎はどうしたのか分かりませんが、光枝は16歳にな
っていたので既に働きに出ていたのかも知れませんし、太一郎は7歳です
が、龍馬が「すこしさしきれなり」と褒め言葉とは思えない表現(マリアス・
ジャンセンはその著書『坂本龍馬と明治維新』の中で、これを「たいへん
利発な」としていますが、「少し」という副詞は「いささか」とか「やや」
と云うように、どちらかというと否定的な表現に使用されます)をしている
ことから、やはり貞が連れていったように思います。なぜなら龍馬の留守
に池田屋事件関係で大仏にも手入れがあって、貞も引っ立てられて取調べ
を受けたりしたものですから、江戸から戻ってきてそのことを知った龍馬
が心配して、金蔵寺の住職を仲人にしてお龍と内祝言を済ませ、お龍を寺
田屋へ預け、貞は杉坂の尼寺へ預け、君江は神戸の海舟の許へ預け、そし
て太一郎は、(弟二郎と同じ)金蔵寺へ預けたとあるからです。
そして貞が大仏へ引き移ってきたときに、その隠れ家に出入りしていた龍馬
が貞から一家の窮状を聞いて気の毒に思って、そしてお龍にも一二度会って
もいて気を引かれていたことから、お龍を私にくれ、そうしてくれれば及ば
ずながら力になろうと云って、お龍を娶ることになった云々と書かれてあり
ます。
つまり、天誅組が敗走したのが前年(文久3年)9月末で、大仏騒動があったの
が元治元年6月5日のこと。そして龍馬が、6月1日に扇岩にお龍を訪ねて別
れ盃を交わし、翌2日朝に江戸へ向けて出立したことから、大仏騒動の起こる
少し前に知り合ったのだろうとして、(漠然と)5月頃とされているのです。
愈々お龍の登場。(でも真木よう子、なんかしっくりこないなー。
本編に入る前に、ちょっと前回の補足。
8月18日の政変で長州藩士の殆どが京を後にして国へ引き上げたのは、
長州藩に対して「留守居ならびに添役一両人は滞京、その余は御用無く
候間帰国これ有るべき事」の御沙汰書が下されたからです。
では、「龍という女」について。
龍馬伝では、「団塊の世代雑感(11-13)」に書いた、元治元年5月
頃に龍馬と出会ったことにしていましたね。
でもね、前回の団塊の世代雑感(63-7)のお仕舞いの方に以下のお龍
の回顧談(川田雪山聞書「千里駒後日譚」第5回)を載せましたが、
「武市さんには一度逢いました。江戸から国へ帰る時京都へ立寄って
龍馬に一緒に帰らぬかと云うから、今お国では誰でも彼でも捕えて斬
って居るから、帰ったら必ずヤラれると留めたけれども、武市さんは
無理に帰って、果してあの通り割腹する様になりました。龍馬が、お
れも武市と一緒に帰って居たもんなら命は無いじゃった。武市は正直
過ぎるからヤられた惜しい事をした、と云って歎息をして話しました。」
最初の「武市さんには一度逢いました」がずっと気になって気になって。
元治元年5月頃だと思ったから、主語(一度逢ったというの)は龍馬だろう
と思ったのですが・・・。
ましたが、土佐でも尊攘派への弾圧が強まり、9月21日には半平太ら
土佐勤王党の者が投獄されます。
半平太は一連の活躍で白札から上士格に取り立てられていましたので、
南会所の獄舎に繋がれますが、下士はことごとく山田町の獄舎に入牢
となります。
江戸や京などに出ている土佐勤王党の者に対しても帰国命令が出されます。
12月6日付で海舟は自分の塾にいる土佐人数名についての帰国命令の猶
予を願い出ています。
その願書を江戸の土佐藩邸の目付まで持参したのは龍馬と云いますから、
このときには又江戸に出ていたことが分かります。
しかし、この願いは拒絶されてしまいます。そして龍馬、惣之丞は再脱藩、
他の者は脱藩の身となります。
でも海舟の庇護(自分の家来とするなど)があって、土佐藩でも海舟門下の
者に対してはお目こぼしがあったのでしょう、海舟に翌年10月22日に
帰府命令(11月10日御役御免)が出るまでの間は大坂、神戸の海軍塾で
然程の不自由さを感じることも無く学ぶことが出来たように思います。
お龍の回顧談(川田雪山聞書「千里駒後日譚」第5回)に「武市さんには一度
逢いました。江戸から国へ帰る時京都へ立寄って龍馬に一緒に帰らぬかと云
うから、今お国では誰でも彼でも捕えて斬って居るから、帰ったら必ずヤラ
れると留めたけれども、武市さんは無理に帰って、果してあの通り割腹する
様になりました。龍馬が、おれも武市と一緒に帰って居たもんなら命は無い
じゃった。武市は正直過ぎるからヤられた惜しい事をした、と云って歎息を
して話しました。」とあります。
聞書きですから主語があやふやであったり、時間軸もハッキリしないので、
しっかり読み解く必要があるのですが、「半平太が江戸への勅使下向の使命
を終えて京に立寄って、それから国へ帰ろうとしているまさにそのときに、
おれ(龍馬)は半平太と一度逢った。半平太はおれに一緒に帰るよう勧めたが、
既に収二郎らが令旨事件に関わったことが判明していることだし(後に捕縛
されて、国許に送られて切腹)、帰ったら必ず捕まるからと留めたのだが、
半平太はそれを押し切って帰ったので、後に切腹するようなことになってし
まった。おれもあのときに帰っていたら命は無かったことだろう。半平太は
バカ正直だから日本のために、そして土佐のために正しかろうと思って(令旨
事件も)やったことだから、必ず分かってもらえる筈だと意を決して帰ったの
だろうが、果してあのような結末となった。真に惜しい人物だった」と歎息
してお龍に話して聞かせたのが慶応元年閏5月11日(半平太切腹)以降のこと
であることだけは確かです。
そんな厄介なことが無かったとしても龍馬に帰国する意思が無かったことは、
これまで見てきた通りです。
13日に出航し、16日に江戸に到着しています。次に海舟が順動丸で
(老中酒井雅楽頭忠績<だだしげ>を運ぶため)江戸を発って大坂天保山沖に到る
のは9月9日のことで、それまでの間は江戸に居ます。
龍馬が8月9日に大坂を発って、19日に江戸へ到着したことは先述し
ましたが、何時頃まで在府したかですが、大久保一翁が海舟に宛てた9月
20日付の手紙に「昨夕も坂龍(坂本龍馬)、沢愛(沢村愛之助、すなわち
沢村惣之丞)両子罷り越し、相伺い候」とありますので、この時点でもまだ
在府であることが分かります。
さらに大久保一翁が春嶽に宛てた10月15日付の手紙にも「坂下龍馬
も不日登り候積りに候」とありますので、まだまだ江戸です。
龍馬の姿を京に見出すのは、11月7日のことで、京都の越前藩藩邸で
春獄に謁見しています。
ここでの会見内容、記録が遺されていないのですが、龍馬が江戸へ遣っ
て来たのは、おそらく千葉重太郎からの手紙で、北添佶摩が蝦夷地の現
地調査を終えて江戸へ着いたことを知らされてのことだと思えます。
そして大久保一翁の許には何度か足を運んで相談しています。
大久保一翁は春嶽に宛てた9月9日の手紙の中で「先頃も一寸申し上げ
候、北広地新店御開の義に付いては御自身御任希度く候、鎖を是非と談
じ候と北広地と対(対馬)とは速に彼(外国)の有に相成べく、これは後世
までの大害と存じ奉り候」(以前にもちょっと申し上げたように北海道
に新たに交易場を開こうとする件は、春嶽公ご自身が取り組まれること
を願っています。鎖港を是非ともと談じることは北海道と対馬とを外国
に直ぐに盗られることを意味しており、そうなっては後世までの大きな
禍となると思っています。)と述べているようにロシアが蝦夷地(英仏は
対馬・壱岐・佐渡、アメリカは南七島)を占領することを危惧しています。
この後に述べることになると思いますが、龍馬は蝦夷地での交易とその
防衛とを宿志として考えていますので、そのための軍艦として越前藩所
有の黒龍丸を狙っているのです。11月7日に京都の越前藩藩邸で話し
合われたことがこの一件であることはまず間違いないと思います。
文久3年8月19日付の龍馬が川原塚茂太郎(兄権平の妻千野の弟)に
宛てた手紙(龍馬を養子とする兄権平の意向、しかし龍馬にはその気が
無いので誰かを世話して欲しいという内容)の中に「猶龍馬事も要々こ
れ有り候て、江戸よりの書状八月二十八日(七月二十八日の誤りと思える)
来り、同九日すでに大坂を発足致す事に相成り候」とありますように、
8月9日に大坂を発っています。
そしてこの手紙を出した8月19日は江戸に居たことは、以下の乙女と
春猪に宛てた手紙(日付が無いので文久3年秋頃のものとされていますが、
後に述べるような理由から茂太郎に宛てた手紙と同じ8月19日に書かれ
たものと思えます)に「私事は急用これあり、今日江戸へ参り申し候」と
あることから分かります。つまり8月19日に江戸到着です。
この日に書かれたと思えるのは、文末に、春猪に対して(おそらく養子の
こと)「(龍馬の)思惑一杯の所は川らづか(川原塚)まで申しやり候。其文
御らん御らん」と云っているからです。
この手紙では更に「先日大和国にてすこしゆくさ(戦)のようなる事これあり。
其中に池蔵太(池内蔵太)、吉村虎太郎、平井のあいだがら(親類)の池田
のをとをと(平井収二郎の従兄弟に当たる池田虎之進の弟土井佐之助)、
水道のをさとのぼうず(龍馬の実家から直ぐの水道町を里とする茶道家上田
宗児<そうこ>)など、先日皆々うちまけ候よし」とありますが、この戦のようなものと
いうのは、大和で挙兵した天誅組のことです。
8月13日に攘夷親征大和行幸の詔勅が発布されたことから、先駆けと
なって14日に前侍従中山忠光を旗頭として挙兵したのですが、18日に
政変が起こると忽ち逆賊となり、9月27日に吉村虎太郎が戦死(享年27)
するなど、天誅組は敗走します。
先に挙げた那須信吾も戦死(享年35)、北添佶摩らと蝦夷地へ現地調査に
赴いた森下幾馬も戦死(享年30)、同じく蝦夷地へ赴いた安岡斧太郎は捕
らえられて翌元治元年2月に京都六角牢で斬刑(享年26)、那須信吾と同
じく東洋暗殺犯の一人安岡嘉助も捕らえられて翌元治元年7月に禁門の変
のとばっちりから六角牢内で斬殺(享年29)。
池内蔵太と上田宗児は中山忠光を護って長州三田尻に逃れました。
近衛忠煕、右大臣二条斉敬ら公卿が続き、その後から京都守護職松平
容保、京都所司代稲葉正邦らが参内し、同時に議奏加勢(三条実美が
議奏であったため、代理として仮の役職を設けた)の葉室長順によって、
ことごとく九門を閉ざし、召命のない者は一切通させない旨の勅命が伝
えられます。
九門(清和院門、蛤門、乾門、今出川門、堺町門、寺町門、下立売門、
中立売門、石薬師門)の警衛は京都守護職会津、京都所司代淀、薩摩、
因幡、備前、越前、米沢といった公武合体派の諸藩が当たることにな
りました。すでに会津藩二千の藩兵を九隊に分けて九門を固めていま
したが、寅ノ刻(午前四時)に九門の警衛配備完了を示す合図の号砲が
鳴るのを待っていたかのように中川宮が「長州の暴論に従った違勅を
議奏や国事掛の輩が多く発している。御親征行事は延期する。三条中
納言を始めとする議奏、国事掛のものは、おって取調べがあるのでそ
れまでは外出禁止、他人との面会も禁止する」旨の勅旨を読み上げて
クーデターは成功します。
三条実美ら急進的攘夷派の公卿らは諸藩の攘夷浪士二千ほどとともに
鷹司関白邸に立て籠もったのですが、宰相清水谷公正使が勅使として
派遣され、勅下に退散しなければ違勅となる旨を告げます。
鷹司関白邸の門前に南北に並んで集まっていた長州藩の人数に対して、
薩摩藩と会津藩の兵が大砲6門を長州勢に向けていたのですが、戦闘
に入るのを懼れた朝廷が勅使を派遣して、大砲の筒口を転じさせるの
を条件に長州勢の退去を命じたので、やがて移動を起こし、大仏の妙
法院殿へ向けて立ち去ります。
そして官位を剥奪された三条実美、三条西季知、東久世通禧、壬生基
修、四条隆謌、錦小路頼徳、沢宣嘉の七卿は、8月19日の巳ノ刻(午前
10時)頃、在京の長州藩士ならびに尊攘派浪士に護られるようにして
長州へ落ちていきます。世に言う七卿落ちです。
意趣返しも多少はあったかも知れませんが、直接の切っ掛けは文久
3年8月13日に攘夷親征大和行幸の詔勅が発布されたことにあり
ます。
詔勅は三条実美以下尊攘派の公卿が強引に引き出したもので、「天皇
はまず攘夷祈願として大和国に行幸、神武帝以下の諸陵に参拝。大和
で攘夷親征の軍略を定めてから伊勢に行き、伊勢神宮から関東へ向け
て軍を発する」というもので、内容が内容だけに孝明天皇は気が進み
ません。この機をとらえたのが公武合体派の中川宮(青蓮院宮)、前関白
近衛忠煕(先の姉小路暗殺事件で失脚)、右大臣二条斉敬でした。そして
薩摩藩へ密かにこの旨を通じます。
島津久光に宛てた宸翰(5月29日付)から天皇の苦衷を承知していた
薩摩藩はもっと早い時期に考えていたようで、越前藩の率兵上京を当
てにしていた節があります。しかしそれが中止となって、手を組む相手
を京都守護職の会津藩に絞ることになります。
会津藩は丁度その時期、在京と国許の兵士交代が行われることになって
いたことから、京都に通常の倍にあたる兵力(約二千名)を抱えることに
なりますので、そういったことも勘定に入れてのことだと思いますが、
薩摩藩はそのタイミングを見計らって会津藩に働きかけます。
諸藩周旋方の高崎佐太郎を黒谷金戒光明寺に陣を張る会津藩の公用方
秋月悌次郎のもとへ、しかも彼の旅宿へ遣わして隠密裏に事を運びます。
秋月は話を聞くや直ちに本陣へ高崎を伴い、容保へ報告し、ここに薩摩
と会津の同盟が成立します。
ですし、現場に残された刀が新兵衛の差料に間違いないと証言し
たのが、土佐脱藩浪士那須信吾(龍馬の脱藩を手助けした、その
10日余り後に吉田東洋を暗殺し脱藩)と云うのも如何にも怪しい
話なのです。
なぜなら、脱藩後長州藩に身を寄せていた那須信吾が、この事件
当時は薩摩藩に匿われていて、そして新兵衛のことをよく知って
いたというのですから。
しかも新兵衛は、差料奥和泉守忠重を事件の数日前に三本木の
料亭ですりかえられたことを友人に語ってもいますし、陰謀の臭い
がプンプンします。
事件の翌21日の朝、三条の屋敷門に「転法輪三条中納言、右の者、
姉小路と同腹にて、公武御一和を名として、実は天下の争議を好み
候者につき、急速に辞職して隠居致さざるにおいては、旬日を出で
ずして天誅に代わりて殺戮すべきものなり」の貼り紙がしてあるのが
発見されます。
三条と暗殺された姉小路とは長州系公卿の頭目ですから、この貼り
紙で「犯行は長州ではありませんよ」とカモフラージュしているとも
とれるわけです。(だって三条実美は辞職も隠居もしませんし、そう
しなかったからと殺されてもいません。)
以前にも述べましたように、姉小路は幕府や越前藩とともにクーデ
ターを企てていたようですから、長州にとって姉小路は最早邪魔者
でしか無かったわけで、暗殺することで、公武合体派公卿への見せ
しめにもなったのですが、狙いは公武合体を推進する薩摩藩の排斥
にもあったのです。
当時、朝廷警固のため御所の九門を各藩が守っていたのですが、こ
の事件により、薩摩藩は担当していた乾門の警衛を解任されただけ
でなく、薩摩藩関係者の九門内への出入りを禁じられてしまいます。
つまり、薩摩藩は京都政界から締め出された形になるのです。
7月27日には越前藩の率兵上京時に旅寓にしようとしていた京都
高台寺が放火されます。加えて京都市中のみならず大津辺りまで
貼り紙をして、春嶽を朝敵、国賊呼ばわりしています。
要するに、一気呵成に攘夷を推し進めるために、邪魔な公武合体
派の大名が京都政局に乗り出せないように、尊王攘夷派はアレコレ
工作をしているのです。
文久3年8月18日の政変は、薩摩藩が会津藩と示し合わせて、
京都政界から尊攘激派と称される公家を一掃した事件ですが、
その伏線となったのが5月20日に起きた姉小路公知の暗殺で
した。
評定を終えて姉小路が三条実美とともに御所を後にしたのは亥
の刻(午後11時)頃でした。
三条と公家門で南北別々の方向に別れた姉小路が朔平門の前を
通り過ぎて巽の角、猿ヶ辻に差し掛かった所で、突然数名の賊
が斬り付けてきて、頭部に深手を負ってしまいます。
姉小路は万が一に備えて、雑掌(武家の用人に当たる)として一刀
流の剣客吉村右京、そして太刀持ちとして今弁慶の渾名を持つ
大男の剣客金輪勇、この二人を用心棒として常に従えていたの
ですが、賊が襲ってきたときに姉小路が太刀を求めたにも係らず、
金輪勇が太刀を抱えたまま逃げ出してしまったのです。
これに気付いた吉村右京が取って返してその賊へ斬りかかると、
賊は持っていた刀を吉村目掛けて投げ付け、そのまま脱兎の如く
暗闇に消え失せてしまいます。
姉小路は吉村の肩にすがりながら五町ほど先にある屋敷に帰り
着いたのですが、出血がひどく、翌21日の丑の刻(午前2時)頃に
絶命します。
わざと投げ付けたとしか思えない刀が証拠になって、薩摩藩の
田中新兵衛が捕縛されます。
しかし田中新兵衛は、京都町奉行永井尚志(なおゆき)による取調
べ中に、一言も釈明することなく自害してしまいます。
広瀬 健太
平井収次郎
間崎 哲馬
右三人之者、於京師、御令旨等拝戴致候仕業、奉欺上不届至極之儀、
御隠居様委細、青蓮院宮様より御直聴被遊候。従て御三殿様 御不快に
被思召、吃度可被仰付筈之処、御含之筋被為在、御慈恵を以て、於牢屋
切腹申付候様御意に付、其旨可被及作配候。 以上
亥六月
(健太、収二郎、哲馬の3人の者が京都において令旨を賜ったことは、
上を欺いた不届き千万のことであり、容堂が青蓮院宮から直に詳しく
聴いて分かっている。このことは容堂の他、豊資、豊範も不快に思って
いることであり、厳しい処置があってしかるべきだが、思し召しもあり、
慈恵を以て、牢屋においての切腹を申し付けることになった云々)
本来なら、打ち首なんでしょうね。それが武士にとっては名誉の切腹に
なったのは、まだ土佐勤王党を刺激したくないとの思惑も働いていたか
らなのでしょう。
この責任を取らされたのだと思いますが、勤王攘夷派の上士である大目
付の小南五郎右衛門や平井善之丞などがお役御免となります。が、土佐
勤王党の獄が始まるのはもう少し先のことになります。
この切腹の模様を当時まだ17歳であった中江兆民が逐一見ていたよう
で、加尾の求めに応じて明治25年に「平井収二郎君切腹の現状」と題
した文章を書いています。それによると収二郎の切腹は見事であったそ
うです。
健太は常々、見事に腹を切ることで男の値打ちが決まると口にしてい
ただけのことはあって、切っ先を左腹に突き立てて右へ割き、そのま
ま刃先を心臓に向かってはね上げ、衣服も汚さず、介錯の必要もない
見事なものであったそうです。
哲馬は、「55-1」に龍馬と会って飲んだことを書きましたが、かなりの
酒好きであったらしく(酒の力も必要としていたのでしょうか)、切腹の
当日も牢番を通じて酒を取り寄せて、この世の飲み収めとがぶ飲み
したそうで、「酔態歔欷(すいたいきょき)」(酔っ払ってすすり泣いて)
で切腹したとあります。
間崎哲馬、享年30。平井収二郎、享年28。弘瀬健太、享年28。
龍馬は収二郎の切腹を乙女から知らされたのだと思いますが、文久3年
6月29日付の乙女宛の返信(有名な「日本を今一度せんたくいたし申候」
の手紙)の中で「そして平井の収次郎は誠にむごいむごい。」と書いたその
上に「じうもんじ(十文字)」と小さく書き添えてあります。収二郎も十文字に
腹を切ったのでしょうか。
この文に続いて「いもふと(妹)おかを(加尾)がなげき(嘆き)いか斗か、
ひとふで(一筆)私のよふす(様子)など咄してきかしたい。まだに少し
はきづかい(気遣い)もする」とあります。
を半平太らの意の如くしようとしたのが青蓮院宮令旨事件です。
文久2年12月17日のこと、土佐勤王党の間崎哲馬、平井収二
郎、弘瀬健太の求めに応じて、青蓮院宮が一封の令旨を下します。
その内容は、大御所的存在である豊資に宛てたもので、藩政への
干渉を望む意向を伝えたもので、文末には「委細は哲馬、健太に
聞いてほしい」とあります。
この令旨も江戸東京博物館の龍馬展に展示されています。
要するに、藩主豊範では正面切って容堂に楯突くことは難しいだ
ろうから、容堂の養父に当たる豊資を前面に押し出せば、容堂も
面と向かって半平太らの目指す(尊王攘夷へ土佐一藩を投ずる)こと
に反対は出来ないだろうと踏んだのです。
しかし容堂がこのことに勘付いたと思った哲馬と収二郎は自白書
を提出してしまいます。(おそらく累が半平太に及ぶことを懼れ
たのでしょう。)
3月26日に容堂は京を出足し帰国の途に付きますが、親王の力
を借りて藩政を左右しようとする越権行為が赦される筈もなく、
28日に哲馬と収二郎は逮捕されます。そして4月1日、二人は
国許へ檻送されます。健太は、令旨を哲馬とともに国許へ持ち帰
って、そのまま土佐に留まったため、そこで捕縛されます。
それから色々と取調べがあったものと思いますが、また半平太は
手を尽くして助命に駆けずり回ったことと思いますが、6月7日
に切腹の申渡しがあり、翌8日ついに3人は切腹となります。
これも現物が江戸東京博物館の龍馬展に展示されていますが、
山田町の獄に収監されていた収二郎が切腹を知らされて、自ら
の爪で引っ掻きながら書いた漢詩の辞世の句、矯めつ眇めつし
ても何が書かれてあるのか分かりません。
でも、妹の加尾が兄のために建てた墓碑にそれが刻み付けられて
あります。
嗚呼悲哉兮綱常不張 洋夷陸梁兮辺城無防 狼臣強倔兮憂在薺牆
憂世患國兮忠臣先傷 月諸日居兮奈我神皇
と云うものものですが、「悲しいことに綱領を張ることもせず、
外国の跋扈を防ぐこともできない。悪賢いやつらの勢いは強く、
世を憂い国を思う忠臣が先ず傷付く。云々」と云った内容なの
だと思うのですが、難しい漢字が多くてよく分かりません。
最初は、収二郎の墓石に刻まれていたのですが、藩吏に削り取ら
れて(平井家自身が削り取ったとも云われていますが)、墓も倒さ
れたそうです。そして明治の代になって、加尾が石碑を建て復刻
したと云います。なお、辞世の句が削り取られた墓石も最近見つ
かったそうです。
親王のことで、文政7年(1824)に伏見宮邦家親王の第四王
子として誕生し、いくつかの寺院を経て、嘉永5年(1852)
に青蓮院門跡となります。青蓮院は京都粟田にありましたので、
粟田宮と呼ばれたりもしますが、正しくは尊融法親王と云いま
す。
法親王というのは、既に剃髪していて法名を持っているとき
に親王宣下があった場合を云います。親王宣下が先で、その
後に寺に入り、得度の上法名をつけると入道親王となります。
宮家は、伏見、有栖川、桂、閑院の四宮(文久3年1月に中川
宮、元治元年1月に朝彦親王の兄の晃親王が山階宮に取立ら
れるので、幕末には六宮家が存在)で、宮家を相続する者は時
の天皇の猶子(ゆうし)として親王宣下があり、門跡寺院に入っ
ている者は、時の天皇の養子として親王宣下があります。
(青蓮院宮は、尊融入道親王という説もありますが、どちらだ
か僕には判断ができません。)
青蓮院宮は、嘉永7年4月に御所が火災を起こしたとき、禁裏
御修法(みしほ)を機縁として孝明天皇の信頼を得るようになり
ます。
青蓮院宮が孝明天皇の父仁孝天皇の養子として親王宣下されて
いることから身近に感じていたでしょうし、天保2年(1831)
6月14日誕生の孝明天皇よりも7歳年長ですから頼り甲斐も
あったのでしょう。
そして嘉永6年のペリー来航以来、宮廷にあって孤立感を強めて
いた孝明天皇が縋りたい人物を求めていたときに眼前に現れた
ことも手伝って、その絆は孝明天皇が崩御するまで続きます。
しかし将軍継嗣問題で(それでは親王を罪に問えないため、出家
の身でありながら女性との間に子を成したことを咎めて)安政6
年2月17日に隠居・永蟄居となります。
しかし、文久2年4月、公武合体論に幕府が転じたことから、
永蟄居が赦され、その年の12月に国事御用掛が新設されると
その職に就いて朝廷での発言力を増します。
はちゃめちゃの内容はいつものことなので無視するとして、
今回は収二郎が関わって命取りになった青蓮院宮令旨事件
について。
長州の殿様が、家臣の進言がなんであろうと「そうせい」と
云ってくれるのに対して、土佐藩の場合はそうはいかないの
で、半平太ら尊攘派はあせります。
そもそも土佐藩の殿様、事情が複雑なのです。
第12代藩主山内豊資(とよすけ)には倅が三人いるのですが、
嘉永元年に第13代豊熙(とよてる)、第14代豊惇(とよあつ)
とその内の二人が相次いで逝去します。末弟の豊範は三歳であ
ったことから、急遽中継ぎとして分家の豊信(容堂)が第15代
藩主となり、豊範を養継嗣とします。
豊信は、将軍継嗣問題で一橋慶喜側に就いていたため、安政の
大獄に連座することを懼れ隠居となって逃れようとしたのです
が、そうはさせじと処分を受けて鮫洲藩邸で蟄居謹慎の身とな
ります。
半平太らは、井伊直弼=幕府=開国と看做していましたから、
その対極にある一橋派を尊王(攘夷)派と捉えて、土佐勤王党
を結成したのですが。
文久2年、島津久光の率兵上京により、勅使下向で幕政改革が
行われて、将軍後見職に一橋慶喜が、政事総裁職に松平慶永(春
嶽)がそれぞれ就任するなど、一橋派が復活します。豊信(容堂)
も幕政顧問となり政治的な発言力を増すことになります。
一方の第16代藩主豊範はこのとき未だ17歳ですから、容堂
が赦免される以前には吉田東洋を頼っていたのですが、それが
暗殺されると、半平太の画策した勤王党と保守派との連合政権
のなすがままといった状態になります。
そして率兵上京し、三条実美、姉小路公知を勅使として下向し、
幕府に攘夷を督促したのです。
でも慶喜、春嶽、容堂のいずれもが尊王であっても開国派とい
うか攘夷反対派なんですね、それを半平太らが知ったことから
青蓮院宮令旨事件が起こります。
ありません。
暮六ッ半頃といいますから午後六時半過ぎになりますが、菊屋という
本屋の倅峯吉が慎太郎の使いを終えて復命に近江屋へ遣って来たとき
に槐堂が居たという証言はしていません。(大正十五年『坂本龍馬関係
文書二』の中の岩崎鏡川著「坂本と中岡の死」より。)
ですから誕生日に近江屋の龍馬を訪ねた日は別の日ということになり
ます。
ではそれが十一月十日なのでしょうか。
龍馬が近江屋を寓居としたのは、福井から戻ってきた十一月五日です。
その移転先を聞き知って十日に槐堂が龍馬を訪ねたときが、偶々龍馬
の誕生日だったのでしょう。槐堂が転居祝いとして持参した掛軸を見
ながら、龍馬は西洋の誕生祝を知っていたでしょうから、「ハッピー
バースデーじゃきに、まっこと有り難いプレゼントぜよ」とかなんと
か云ったのでしょう。それを槐堂が覚えていたというのが真相のよう
に思えます。
ます。
板倉槐堂の弟江馬天江(えまてんこう)が著した『淡海槐堂先生略伝』
に「丁卯十一月十六日、坂本竜馬、石川清之助(中岡慎太郎の変名)と
を先生は河原町四条上ル醤油屋ヤ(「乃」の誤りか)旅寓を訪いて雑談、
深夜にて帰る。瞬時ならずして刺客来りて両氏および力士藤吉殺害さ
る。先生、幸いにして難を逃る」とあります。
槐堂は元々は下坂姓で、京都へ出て醍醐家に仕えたときに板倉姓を
賜りました。そして明治元年三月、新政府から徴士を拝命した際に
(醍醐家を退出したことから)新たに淡海(たんかい)を名乗るように
なります。槐堂は明治十二年六月十九日に亡くなっています(享年58)。
『淡海槐堂先生略伝』が何時のものか分からないのですが、槐堂の
没後であるように思います。
龍馬の没年が十一月十六日となっているのは、慶応四年七月十九日に
建立された霊山の墓碑にも、明治十二年に作成された「霊山招魂社并
(ならびに)墳墓明細帳」にもそうなっているからです。しかしこの
ことは槐堂が江馬天江に日付までを語り伝えていないことを示してい
ることになります。であるならば、槐堂は龍馬が暗殺された日を龍馬
の誕生日と知らされて、それならば自分が龍馬の寓居(近江屋の名前も
忘れていたのかもしれませんが)の醤油屋へ絵を持って訪ねた日である、
と弟に語ったとも考えることができます。
ということは、明治十二年以前にもそういったことが関係者の間には
漏れ伝わっている可能性があるということになります。
であれば、お龍の耳に達していることも考えられますし、そうでなか
ったとしても川田雪山には達していたことは十分考えられることです。
そしてその真偽を確かめるために川田雪山がお龍に質したという成行
も考えられるわけです。
登場となります。
明治三十二年十一月に土陽新聞に連載された『千里駒後日譚』の
最後の回(第六回、十日)の中で「龍馬の生まれた日ですか、天保
六年の十一月十五日で丁度斬られた月日と一緒だと聞いて居るの
ですが書物には十月とあります、どちらが真だか分かりませぬ」
と著者の川田雪山の問に答えています。
これをその通りに捉えるならば、十一月十五日が龍馬の誕生日と
なります。
しかし誰から聞いたのかハッキリしない上に曖昧な答えです。
龍馬から直接聞いたのであれば、上記に続く「龍馬の名乗りの直
柔(なおなり)と云うのは後に換えた名で初は直陰(なおかげ)と云
ったのです。伏見に居た時分に、直陰は何日迄も日陰者の様でイ
ケないから直柔と換えると云って換えました」のようにハッキリ
した表現を取ったと思うのです。
それにインタビューに答えた一言半句がそのまま活字になったと
は限りません。
例えば「龍馬の生まれた日ですか、天保六年の丁度龍馬が斬られ
たのと一緒だと聞いて居るのですが」とお龍がおぼろげな記憶の
中から月だけを答えたのを川田雪山が月日のことだと捉えて補っ
たことも考えられるのです。
明治十六年の最初の龍馬伝『汗血千里駒』では、龍馬の誕生日は
十月十五日となっています。それが同じ坂崎紫瀾の手になる大正
元年の『維新土佐勤王史』では十一月十日に改められています。
そして大正三年の千頭清臣の『坂本龍馬』で十一月十五日となり、
以降はこの日が当たり前のようにして通用しています。
以前、龍馬ブームが三度あって、最初が『汗血千里駒』を切っ掛
けにして、二度目は明治三十七年の日露戦争開戦前夜に美子皇后
の夢枕に現れてから、といったことを書きましたが、その二度目
のときのことですが、まだ新聞に発表される前に皇后の求めに応
じて、未だ原稿レベルであった『維新土佐勤王史』をご覧に供し
ています。このことから二度目のブームになる以前、そして最初
のブーム以降に坂崎紫瀾は誤りを指摘されて十月十五日を十一月
十日に変えたことが推定できます。