
この写真は、慶応三年十一月十五日夜に龍馬が刺客に襲われた近江屋二階
の奥座敷の床の間に掛けられていた掛軸です。この小さな写真では判り難いと
思いますが、その下部の向かって左から右へ飛散した数滴の血痕が付着して
います。
現在、江戸東京博物館で開催中の龍馬展に実物は展示されていませんが、複
製品が展示されています。それも原寸大で再現された奥座敷の床の間に掛け
られてあります。
僕がこの再現された奥座敷に一入興味を抱いたのは、龍馬・慎太郎と刺客たち
の動き(僕が想定したもので間違い無いか)を確かめることにあったからですが、
その一環としてこの掛軸の血痕もそれがどの辺りからとばしったのか確かめる
必要がありました。
この血痕、それまでは慎太郎のものである可能性もあると思っていたのですが、
今は龍馬のものに間違いないと思っています。
先日(5/8)、フジテレビの土曜プレミアムという番組で「暗殺の4秒間、5滴の
血痕」ということで、龍馬が斬り殪されるまでの再現フィルムを流していました
が、大小合わせて三十四ヶ所もの刀傷を受けている上に、龍馬が斃れてい
たのは 奥座敷の隣の六畳間ですから、あのような単純な立廻りでなかっ
たことは確かです。
この血染掛軸、梅と椿が描かれているので「梅椿図(ばいちんず)」とか「椿花白
梅図」とか称されていますが、龍馬に贈られたときにそのような名が付いていた
わけではありません。
この絵を描いたのは板倉槐堂(かいどう)で、その本人が龍馬に贈ったのです。
龍馬の私物ですから龍馬の家系を継いだものが相続し、やがて京都国立博物
館に寄贈されて現在に至ります。重要文化財です。
画幅の上に書いてある漢文は、海援隊文司長岡謙吉の手になるもので、
「龍馬と慎太郎が灯下のもとで炬燵を囲んで閑談しているときに三人の
刺客が襲って二人を斬った。私(謙吉)の僕雲井龍藤吉もまた殺された。
私は当時大坂にいてこの変を聞き近江屋へ至ったが、辺り一面の狼藉で、
迸った血がこの絵や壁に及んでいた。当時の状況を想うことができる。
それは慶応三年十一月十五日のことであった」(意訳)といったことが記
されています。
この項で述べたいのは、暗殺の模様云々ではなくて、この画幅が龍馬の誕生
日を知る手掛かりとなるということです。
(文字数制限があるので続きはコメント欄で。)



















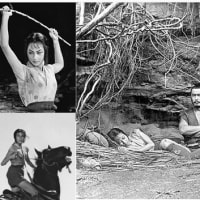
明治十六年の最初の龍馬伝『汗血千里駒』では、龍馬の誕生日は
十月十五日となっています。それが同じ坂崎紫瀾の手になる大正
元年の『維新土佐勤王史』では十一月十日に改められています。
そして大正三年の千頭清臣の『坂本龍馬』で十一月十五日となり、
以降はこの日が当たり前のようにして通用しています。
以前、龍馬ブームが三度あって、最初が『汗血千里駒』を切っ掛
けにして、二度目は明治三十七年の日露戦争開戦前夜に美子皇后
の夢枕に現れてから、といったことを書きましたが、その二度目
のときのことですが、まだ新聞に発表される前に皇后の求めに応
じて、未だ原稿レベルであった『維新土佐勤王史』をご覧に供し
ています。このことから二度目のブームになる以前、そして最初
のブーム以降に坂崎紫瀾は誤りを指摘されて十月十五日を十一月
十日に変えたことが推定できます。
登場となります。
明治三十二年十一月に土陽新聞に連載された『千里駒後日譚』の
最後の回(第六回、十日)の中で「龍馬の生まれた日ですか、天保
六年の十一月十五日で丁度斬られた月日と一緒だと聞いて居るの
ですが書物には十月とあります、どちらが真だか分かりませぬ」
と著者の川田雪山の問に答えています。
これをその通りに捉えるならば、十一月十五日が龍馬の誕生日と
なります。
しかし誰から聞いたのかハッキリしない上に曖昧な答えです。
龍馬から直接聞いたのであれば、上記に続く「龍馬の名乗りの直
柔(なおなり)と云うのは後に換えた名で初は直陰(なおかげ)と云
ったのです。伏見に居た時分に、直陰は何日迄も日陰者の様でイ
ケないから直柔と換えると云って換えました」のようにハッキリ
した表現を取ったと思うのです。
それにインタビューに答えた一言半句がそのまま活字になったと
は限りません。
例えば「龍馬の生まれた日ですか、天保六年の丁度龍馬が斬られ
たのと一緒だと聞いて居るのですが」とお龍がおぼろげな記憶の
中から月だけを答えたのを川田雪山が月日のことだと捉えて補っ
たことも考えられるのです。
ます。
板倉槐堂の弟江馬天江(えまてんこう)が著した『淡海槐堂先生略伝』
に「丁卯十一月十六日、坂本竜馬、石川清之助(中岡慎太郎の変名)と
を先生は河原町四条上ル醤油屋ヤ(「乃」の誤りか)旅寓を訪いて雑談、
深夜にて帰る。瞬時ならずして刺客来りて両氏および力士藤吉殺害さ
る。先生、幸いにして難を逃る」とあります。
槐堂は元々は下坂姓で、京都へ出て醍醐家に仕えたときに板倉姓を
賜りました。そして明治元年三月、新政府から徴士を拝命した際に
(醍醐家を退出したことから)新たに淡海(たんかい)を名乗るように
なります。槐堂は明治十二年六月十九日に亡くなっています(享年58)。
『淡海槐堂先生略伝』が何時のものか分からないのですが、槐堂の
没後であるように思います。
龍馬の没年が十一月十六日となっているのは、慶応四年七月十九日に
建立された霊山の墓碑にも、明治十二年に作成された「霊山招魂社并
(ならびに)墳墓明細帳」にもそうなっているからです。しかしこの
ことは槐堂が江馬天江に日付までを語り伝えていないことを示してい
ることになります。であるならば、槐堂は龍馬が暗殺された日を龍馬
の誕生日と知らされて、それならば自分が龍馬の寓居(近江屋の名前も
忘れていたのかもしれませんが)の醤油屋へ絵を持って訪ねた日である、
と弟に語ったとも考えることができます。
ということは、明治十二年以前にもそういったことが関係者の間には
漏れ伝わっている可能性があるということになります。
であれば、お龍の耳に達していることも考えられますし、そうでなか
ったとしても川田雪山には達していたことは十分考えられることです。
そしてその真偽を確かめるために川田雪山がお龍に質したという成行
も考えられるわけです。
ありません。
暮六ッ半頃といいますから午後六時半過ぎになりますが、菊屋という
本屋の倅峯吉が慎太郎の使いを終えて復命に近江屋へ遣って来たとき
に槐堂が居たという証言はしていません。(大正十五年『坂本龍馬関係
文書二』の中の岩崎鏡川著「坂本と中岡の死」より。)
ですから誕生日に近江屋の龍馬を訪ねた日は別の日ということになり
ます。
ではそれが十一月十日なのでしょうか。
龍馬が近江屋を寓居としたのは、福井から戻ってきた十一月五日です。
その移転先を聞き知って十日に槐堂が龍馬を訪ねたときが、偶々龍馬
の誕生日だったのでしょう。槐堂が転居祝いとして持参した掛軸を見
ながら、龍馬は西洋の誕生祝を知っていたでしょうから、「ハッピー
バースデーじゃきに、まっこと有り難いプレゼントぜよ」とかなんと
か云ったのでしょう。それを槐堂が覚えていたというのが真相のよう
に思えます。
はちゃめちゃの内容はいつものことなので無視するとして、
今回は収二郎が関わって命取りになった青蓮院宮令旨事件
について。
長州の殿様が、家臣の進言がなんであろうと「そうせい」と
云ってくれるのに対して、土佐藩の場合はそうはいかないの
で、半平太ら尊攘派はあせります。
そもそも土佐藩の殿様、事情が複雑なのです。
第12代藩主山内豊資(とよすけ)には倅が三人いるのですが、
嘉永元年に第13代豊熙(とよてる)、第14代豊惇(とよあつ)
とその内の二人が相次いで逝去します。末弟の豊範は三歳であ
ったことから、急遽中継ぎとして分家の豊信(容堂)が第15代
藩主となり、豊範を養継嗣とします。
豊信は、将軍継嗣問題で一橋慶喜側に就いていたため、安政の
大獄に連座することを懼れ隠居となって逃れようとしたのです
が、そうはさせじと処分を受けて鮫洲藩邸で蟄居謹慎の身とな
ります。
半平太らは、井伊直弼=幕府=開国と看做していましたから、
その対極にある一橋派を尊王(攘夷)派と捉えて、土佐勤王党
を結成したのですが。
文久2年、島津久光の率兵上京により、勅使下向で幕政改革が
行われて、将軍後見職に一橋慶喜が、政事総裁職に松平慶永(春
嶽)がそれぞれ就任するなど、一橋派が復活します。豊信(容堂)
も幕政顧問となり政治的な発言力を増すことになります。
一方の第16代藩主豊範はこのとき未だ17歳ですから、容堂
が赦免される以前には吉田東洋を頼っていたのですが、それが
暗殺されると、半平太の画策した勤王党と保守派との連合政権
のなすがままといった状態になります。
そして率兵上京し、三条実美、姉小路公知を勅使として下向し、
幕府に攘夷を督促したのです。
でも慶喜、春嶽、容堂のいずれもが尊王であっても開国派とい
うか攘夷反対派なんですね、それを半平太らが知ったことから
青蓮院宮令旨事件が起こります。
親王のことで、文政7年(1824)に伏見宮邦家親王の第四王
子として誕生し、いくつかの寺院を経て、嘉永5年(1852)
に青蓮院門跡となります。青蓮院は京都粟田にありましたので、
粟田宮と呼ばれたりもしますが、正しくは尊融法親王と云いま
す。
法親王というのは、既に剃髪していて法名を持っているとき
に親王宣下があった場合を云います。親王宣下が先で、その
後に寺に入り、得度の上法名をつけると入道親王となります。
宮家は、伏見、有栖川、桂、閑院の四宮(文久3年1月に中川
宮、元治元年1月に朝彦親王の兄の晃親王が山階宮に取立ら
れるので、幕末には六宮家が存在)で、宮家を相続する者は時
の天皇の猶子(ゆうし)として親王宣下があり、門跡寺院に入っ
ている者は、時の天皇の養子として親王宣下があります。
(青蓮院宮は、尊融入道親王という説もありますが、どちらだ
か僕には判断ができません。)
青蓮院宮は、嘉永7年4月に御所が火災を起こしたとき、禁裏
御修法(みしほ)を機縁として孝明天皇の信頼を得るようになり
ます。
青蓮院宮が孝明天皇の父仁孝天皇の養子として親王宣下されて
いることから身近に感じていたでしょうし、天保2年(1831)
6月14日誕生の孝明天皇よりも7歳年長ですから頼り甲斐も
あったのでしょう。
そして嘉永6年のペリー来航以来、宮廷にあって孤立感を強めて
いた孝明天皇が縋りたい人物を求めていたときに眼前に現れた
ことも手伝って、その絆は孝明天皇が崩御するまで続きます。
しかし将軍継嗣問題で(それでは親王を罪に問えないため、出家
の身でありながら女性との間に子を成したことを咎めて)安政6
年2月17日に隠居・永蟄居となります。
しかし、文久2年4月、公武合体論に幕府が転じたことから、
永蟄居が赦され、その年の12月に国事御用掛が新設されると
その職に就いて朝廷での発言力を増します。
を半平太らの意の如くしようとしたのが青蓮院宮令旨事件です。
文久2年12月17日のこと、土佐勤王党の間崎哲馬、平井収二
郎、弘瀬健太の求めに応じて、青蓮院宮が一封の令旨を下します。
その内容は、大御所的存在である豊資に宛てたもので、藩政への
干渉を望む意向を伝えたもので、文末には「委細は哲馬、健太に
聞いてほしい」とあります。
この令旨も江戸東京博物館の龍馬展に展示されています。
要するに、藩主豊範では正面切って容堂に楯突くことは難しいだ
ろうから、容堂の養父に当たる豊資を前面に押し出せば、容堂も
面と向かって半平太らの目指す(尊王攘夷へ土佐一藩を投ずる)こと
に反対は出来ないだろうと踏んだのです。
しかし容堂がこのことに勘付いたと思った哲馬と収二郎は自白書
を提出してしまいます。(おそらく累が半平太に及ぶことを懼れ
たのでしょう。)
3月26日に容堂は京を出足し帰国の途に付きますが、親王の力
を借りて藩政を左右しようとする越権行為が赦される筈もなく、
28日に哲馬と収二郎は逮捕されます。そして4月1日、二人は
国許へ檻送されます。健太は、令旨を哲馬とともに国許へ持ち帰
って、そのまま土佐に留まったため、そこで捕縛されます。
それから色々と取調べがあったものと思いますが、また半平太は
手を尽くして助命に駆けずり回ったことと思いますが、6月7日
に切腹の申渡しがあり、翌8日ついに3人は切腹となります。
これも現物が江戸東京博物館の龍馬展に展示されていますが、
山田町の獄に収監されていた収二郎が切腹を知らされて、自ら
の爪で引っ掻きながら書いた漢詩の辞世の句、矯めつ眇めつし
ても何が書かれてあるのか分かりません。
でも、妹の加尾が兄のために建てた墓碑にそれが刻み付けられて
あります。
嗚呼悲哉兮綱常不張 洋夷陸梁兮辺城無防 狼臣強倔兮憂在薺牆
憂世患國兮忠臣先傷 月諸日居兮奈我神皇
と云うものものですが、「悲しいことに綱領を張ることもせず、
外国の跋扈を防ぐこともできない。悪賢いやつらの勢いは強く、
世を憂い国を思う忠臣が先ず傷付く。云々」と云った内容なの
だと思うのですが、難しい漢字が多くてよく分かりません。
最初は、収二郎の墓石に刻まれていたのですが、藩吏に削り取ら
れて(平井家自身が削り取ったとも云われていますが)、墓も倒さ
れたそうです。そして明治の代になって、加尾が石碑を建て復刻
したと云います。なお、辞世の句が削り取られた墓石も最近見つ
かったそうです。
広瀬 健太
平井収次郎
間崎 哲馬
右三人之者、於京師、御令旨等拝戴致候仕業、奉欺上不届至極之儀、
御隠居様委細、青蓮院宮様より御直聴被遊候。従て御三殿様 御不快に
被思召、吃度可被仰付筈之処、御含之筋被為在、御慈恵を以て、於牢屋
切腹申付候様御意に付、其旨可被及作配候。 以上
亥六月
(健太、収二郎、哲馬の3人の者が京都において令旨を賜ったことは、
上を欺いた不届き千万のことであり、容堂が青蓮院宮から直に詳しく
聴いて分かっている。このことは容堂の他、豊資、豊範も不快に思って
いることであり、厳しい処置があってしかるべきだが、思し召しもあり、
慈恵を以て、牢屋においての切腹を申し付けることになった云々)
本来なら、打ち首なんでしょうね。それが武士にとっては名誉の切腹に
なったのは、まだ土佐勤王党を刺激したくないとの思惑も働いていたか
らなのでしょう。
この責任を取らされたのだと思いますが、勤王攘夷派の上士である大目
付の小南五郎右衛門や平井善之丞などがお役御免となります。が、土佐
勤王党の獄が始まるのはもう少し先のことになります。
この切腹の模様を当時まだ17歳であった中江兆民が逐一見ていたよう
で、加尾の求めに応じて明治25年に「平井収二郎君切腹の現状」と題
した文章を書いています。それによると収二郎の切腹は見事であったそ
うです。
健太は常々、見事に腹を切ることで男の値打ちが決まると口にしてい
ただけのことはあって、切っ先を左腹に突き立てて右へ割き、そのま
ま刃先を心臓に向かってはね上げ、衣服も汚さず、介錯の必要もない
見事なものであったそうです。
哲馬は、「55-1」に龍馬と会って飲んだことを書きましたが、かなりの
酒好きであったらしく(酒の力も必要としていたのでしょうか)、切腹の
当日も牢番を通じて酒を取り寄せて、この世の飲み収めとがぶ飲み
したそうで、「酔態歔欷(すいたいきょき)」(酔っ払ってすすり泣いて)
で切腹したとあります。
間崎哲馬、享年30。平井収二郎、享年28。弘瀬健太、享年28。
龍馬は収二郎の切腹を乙女から知らされたのだと思いますが、文久3年
6月29日付の乙女宛の返信(有名な「日本を今一度せんたくいたし申候」
の手紙)の中で「そして平井の収次郎は誠にむごいむごい。」と書いたその
上に「じうもんじ(十文字)」と小さく書き添えてあります。収二郎も十文字に
腹を切ったのでしょうか。
この文に続いて「いもふと(妹)おかを(加尾)がなげき(嘆き)いか斗か、
ひとふで(一筆)私のよふす(様子)など咄してきかしたい。まだに少し
はきづかい(気遣い)もする」とあります。
文久3年8月18日の政変は、薩摩藩が会津藩と示し合わせて、
京都政界から尊攘激派と称される公家を一掃した事件ですが、
その伏線となったのが5月20日に起きた姉小路公知の暗殺で
した。
評定を終えて姉小路が三条実美とともに御所を後にしたのは亥
の刻(午後11時)頃でした。
三条と公家門で南北別々の方向に別れた姉小路が朔平門の前を
通り過ぎて巽の角、猿ヶ辻に差し掛かった所で、突然数名の賊
が斬り付けてきて、頭部に深手を負ってしまいます。
姉小路は万が一に備えて、雑掌(武家の用人に当たる)として一刀
流の剣客吉村右京、そして太刀持ちとして今弁慶の渾名を持つ
大男の剣客金輪勇、この二人を用心棒として常に従えていたの
ですが、賊が襲ってきたときに姉小路が太刀を求めたにも係らず、
金輪勇が太刀を抱えたまま逃げ出してしまったのです。
これに気付いた吉村右京が取って返してその賊へ斬りかかると、
賊は持っていた刀を吉村目掛けて投げ付け、そのまま脱兎の如く
暗闇に消え失せてしまいます。
姉小路は吉村の肩にすがりながら五町ほど先にある屋敷に帰り
着いたのですが、出血がひどく、翌21日の丑の刻(午前2時)頃に
絶命します。
わざと投げ付けたとしか思えない刀が証拠になって、薩摩藩の
田中新兵衛が捕縛されます。
しかし田中新兵衛は、京都町奉行永井尚志(なおゆき)による取調
べ中に、一言も釈明することなく自害してしまいます。
ですし、現場に残された刀が新兵衛の差料に間違いないと証言し
たのが、土佐脱藩浪士那須信吾(龍馬の脱藩を手助けした、その
10日余り後に吉田東洋を暗殺し脱藩)と云うのも如何にも怪しい
話なのです。
なぜなら、脱藩後長州藩に身を寄せていた那須信吾が、この事件
当時は薩摩藩に匿われていて、そして新兵衛のことをよく知って
いたというのですから。
しかも新兵衛は、差料奥和泉守忠重を事件の数日前に三本木の
料亭ですりかえられたことを友人に語ってもいますし、陰謀の臭い
がプンプンします。
事件の翌21日の朝、三条の屋敷門に「転法輪三条中納言、右の者、
姉小路と同腹にて、公武御一和を名として、実は天下の争議を好み
候者につき、急速に辞職して隠居致さざるにおいては、旬日を出で
ずして天誅に代わりて殺戮すべきものなり」の貼り紙がしてあるのが
発見されます。
三条と暗殺された姉小路とは長州系公卿の頭目ですから、この貼り
紙で「犯行は長州ではありませんよ」とカモフラージュしているとも
とれるわけです。(だって三条実美は辞職も隠居もしませんし、そう
しなかったからと殺されてもいません。)
以前にも述べましたように、姉小路は幕府や越前藩とともにクーデ
ターを企てていたようですから、長州にとって姉小路は最早邪魔者
でしか無かったわけで、暗殺することで、公武合体派公卿への見せ
しめにもなったのですが、狙いは公武合体を推進する薩摩藩の排斥
にもあったのです。
当時、朝廷警固のため御所の九門を各藩が守っていたのですが、こ
の事件により、薩摩藩は担当していた乾門の警衛を解任されただけ
でなく、薩摩藩関係者の九門内への出入りを禁じられてしまいます。
つまり、薩摩藩は京都政界から締め出された形になるのです。
7月27日には越前藩の率兵上京時に旅寓にしようとしていた京都
高台寺が放火されます。加えて京都市中のみならず大津辺りまで
貼り紙をして、春嶽を朝敵、国賊呼ばわりしています。
要するに、一気呵成に攘夷を推し進めるために、邪魔な公武合体
派の大名が京都政局に乗り出せないように、尊王攘夷派はアレコレ
工作をしているのです。