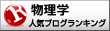粒子と反粒子の質量の不均衡を、左巻きに右巻きが混ざった粒子と、右巻きに左巻きが混ざった反粒子とで解消しようというのでしょう?
ですが、そんなことでは、致命的な困難が解消されませんよ。左巻きニュートリノが右巻きニュートリノに変化する、その瞬間が問題なのです。シーソー機構が正しいとしたならば、その瞬間に粒子は粒子と反粒子とが半々になるだけでなく、はっきりと二つの質量を物理定数として持つことになってしまいます。そんなこと、矛盾してるではありませんか。ということはmにしてもMにしても可変なのではないかと疑ったのですよ、そこから来るm₀=m²/Mというのもね、シーソー機構というのは質量可変機構なのではないかと思い至ったのです。
mもMも速度に関する変数ではないのかということですね・・。
v=0になったらm=M=m₀だというのはいかにもあり得そうに思ったのです!
むしろ、そうあって初めて納得できるというかね、なんかそんな感じの感覚に打たれたのですw
だって左巻きに右巻きが混ざる度合いというのは速度によって変化する変数ではないですか、そうしたらその混ざりによって決まってくる質量というのも変化してしかるべきでしょう、そしてニュートリノを止めてしまったらm₀=m=Mになるのも自然の成り行きではありませんか。このようにしてニュートリノは静止質量は有限だけれども、光速度質量が無限大ではなくて0になる可能性が示されました。つまり、ニュートリノ振動を以てして標準模型を否定していくというのはできない相談だということになるわけですよ、残念ながら。
それでもユニバーサルフロンティア理論は別の切り口から成立することが示される、ニュートリノ質量に頼った世界ではないということですw
ですが、そんなことでは、致命的な困難が解消されませんよ。左巻きニュートリノが右巻きニュートリノに変化する、その瞬間が問題なのです。シーソー機構が正しいとしたならば、その瞬間に粒子は粒子と反粒子とが半々になるだけでなく、はっきりと二つの質量を物理定数として持つことになってしまいます。そんなこと、矛盾してるではありませんか。ということはmにしてもMにしても可変なのではないかと疑ったのですよ、そこから来るm₀=m²/Mというのもね、シーソー機構というのは質量可変機構なのではないかと思い至ったのです。
mもMも速度に関する変数ではないのかということですね・・。
v=0になったらm=M=m₀だというのはいかにもあり得そうに思ったのです!
むしろ、そうあって初めて納得できるというかね、なんかそんな感じの感覚に打たれたのですw
だって左巻きに右巻きが混ざる度合いというのは速度によって変化する変数ではないですか、そうしたらその混ざりによって決まってくる質量というのも変化してしかるべきでしょう、そしてニュートリノを止めてしまったらm₀=m=Mになるのも自然の成り行きではありませんか。このようにしてニュートリノは静止質量は有限だけれども、光速度質量が無限大ではなくて0になる可能性が示されました。つまり、ニュートリノ振動を以てして標準模型を否定していくというのはできない相談だということになるわけですよ、残念ながら。
それでもユニバーサルフロンティア理論は別の切り口から成立することが示される、ニュートリノ質量に頼った世界ではないということですw