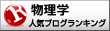湯川はπ中間子によって陽子と中性子が区別つかなくなると言った。
二つの素粒子(当時は陽子などは素粒子だと思われていた)が区別つかなくなる以上に強い力はないと考えられていたのであった。それで電弱統一のストーリーを「宇宙の歴史には電子とニュートリノが区別つかなかった一時期があった」にして、さらなる大統一のストーリーは「宇宙の始まりにはクォークとレプトンが区別つかなかった」とした。
これはこれでシンプルな良い指導原理のようだが彼らは自分自身の研究方針を自ら洗い直して考える必要があったのではなかったか。彼らにとって宇宙初期とは高温度と高密度でしかなく、彼らが考えている環境は中性子星よりももっとハードな環境であり、ようするに中性子星の中身はすべてが中性子からできているというよりはもっと複雑な環境であるのと同じだということである。
中性子星の密度では核外電子のすべてを捕獲することはできない。
そして中性子星の限界を超える密度になればブラックホールにまで収縮してしまうから、結局のところ陽子と中性子とが区別できない世界というのは訪れないことになる。これらのことから区別つかない力ということ自体が幻想だということが疑われてよい。π中間子に陽子と中性子を変換する力は存在しないということでもある。
電弱統一も大統一も似たような過ちは無かっただろうか?
区別できなくなる力などでなくても核力も電弱統一も成立していると考えてはどうだろうか、ところが大統一はそれなしでは必然性が無くなる、事情と言ったらそんなところではなかっただろうか・・。
二つの素粒子(当時は陽子などは素粒子だと思われていた)が区別つかなくなる以上に強い力はないと考えられていたのであった。それで電弱統一のストーリーを「宇宙の歴史には電子とニュートリノが区別つかなかった一時期があった」にして、さらなる大統一のストーリーは「宇宙の始まりにはクォークとレプトンが区別つかなかった」とした。
これはこれでシンプルな良い指導原理のようだが彼らは自分自身の研究方針を自ら洗い直して考える必要があったのではなかったか。彼らにとって宇宙初期とは高温度と高密度でしかなく、彼らが考えている環境は中性子星よりももっとハードな環境であり、ようするに中性子星の中身はすべてが中性子からできているというよりはもっと複雑な環境であるのと同じだということである。
中性子星の密度では核外電子のすべてを捕獲することはできない。
そして中性子星の限界を超える密度になればブラックホールにまで収縮してしまうから、結局のところ陽子と中性子とが区別できない世界というのは訪れないことになる。これらのことから区別つかない力ということ自体が幻想だということが疑われてよい。π中間子に陽子と中性子を変換する力は存在しないということでもある。
電弱統一も大統一も似たような過ちは無かっただろうか?
区別できなくなる力などでなくても核力も電弱統一も成立していると考えてはどうだろうか、ところが大統一はそれなしでは必然性が無くなる、事情と言ったらそんなところではなかっただろうか・・。