二月の花といえばなんといっても梅です。月次屏風和歌でも四季折々の木草や、鳥獣が各月に配置されていますが、鎌倉期の屏風歌では、二月の花には梅が描かれています。花札の二月が梅の拠りどころもこの辺りにあるのでしょう。
万葉人の梅への愛着は並ではないようです。物の本に拠れば、万葉集中梅を詠んだ歌は百十二首。桜は三十五首だそうですから、三倍もの数です。
梅の花夢に語らくみやびたる花と我思ふ酒に浮かべこそ 巻五
我が宿の梅の下枝に遊びつつうぐいす鳴くも散らまく惜しみ 巻五
雪の色を奪ひて咲ける梅の花今盛りなり見む人もがな 巻五
梅の花香をかぐはしみ遠けども心もしのに君をしぞ思ふ 巻二十
福岡県人としては、旅人邸での梅花宴もさることながら、飛梅伝説の道真公遺愛の梅を落すわけにはいきません。天満宮の梅は紅梅です。清少納言が「木の花は、濃きも薄きも紅梅。と断言し、源氏物語でも春の御殿のあるじ紫の上の紅梅への愛着を語っていますから、王朝の女房達に愛されたのは紅梅のようです。
そして、梅に似合う鳥は、雉よりも鴬。「うぐいすの縫ふてふ笠は梅の花笠」―古今集―であり、紅梅襲をまとう女房達が、梅花の名のある薫物を合せ、催馬楽「梅が枝」を詠う公達。まさに梅の花盛りです。
ところで、近世の舞台では、なぜか恋人達の別れの場面で梅がとりあわされることが多いように思います。「新版歌祭文」野崎村の段で、お染久松が舟と堤に引き分けられての別れに添えられる早咲きの梅をあしらった幕切れ。そして、湯島の白梅。お蔦と早瀬の切ない別れの舞台背景も。
弟のところに出かけて、直ぐ裏の山すその梅を堪能して来ました。日当たりのよい斜面の梅は満開でした。すっかり市街化した周辺では耕作を継ぐ人のいない田畑は荒れて「人はいさ。花ぞ昔の香ににほひける。」でした。
画像は5枚です。
万葉人の梅への愛着は並ではないようです。物の本に拠れば、万葉集中梅を詠んだ歌は百十二首。桜は三十五首だそうですから、三倍もの数です。
梅の花夢に語らくみやびたる花と我思ふ酒に浮かべこそ 巻五
我が宿の梅の下枝に遊びつつうぐいす鳴くも散らまく惜しみ 巻五
雪の色を奪ひて咲ける梅の花今盛りなり見む人もがな 巻五
梅の花香をかぐはしみ遠けども心もしのに君をしぞ思ふ 巻二十
福岡県人としては、旅人邸での梅花宴もさることながら、飛梅伝説の道真公遺愛の梅を落すわけにはいきません。天満宮の梅は紅梅です。清少納言が「木の花は、濃きも薄きも紅梅。と断言し、源氏物語でも春の御殿のあるじ紫の上の紅梅への愛着を語っていますから、王朝の女房達に愛されたのは紅梅のようです。
そして、梅に似合う鳥は、雉よりも鴬。「うぐいすの縫ふてふ笠は梅の花笠」―古今集―であり、紅梅襲をまとう女房達が、梅花の名のある薫物を合せ、催馬楽「梅が枝」を詠う公達。まさに梅の花盛りです。
ところで、近世の舞台では、なぜか恋人達の別れの場面で梅がとりあわされることが多いように思います。「新版歌祭文」野崎村の段で、お染久松が舟と堤に引き分けられての別れに添えられる早咲きの梅をあしらった幕切れ。そして、湯島の白梅。お蔦と早瀬の切ない別れの舞台背景も。
弟のところに出かけて、直ぐ裏の山すその梅を堪能して来ました。日当たりのよい斜面の梅は満開でした。すっかり市街化した周辺では耕作を継ぐ人のいない田畑は荒れて「人はいさ。花ぞ昔の香ににほひける。」でした。
画像は5枚です。
<< > > |
| <紅白梅図> |










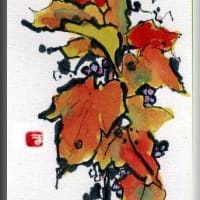





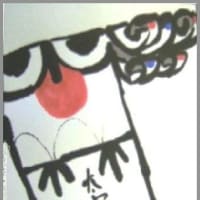

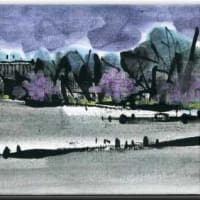
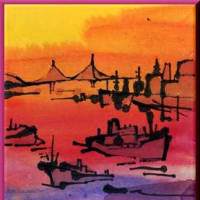
先ずは解説後記を眺める。
ありました、梅の故事が。
紀貫之のお嬢さん紀内侍の和歌、
”勅なれば いともかしこし うぐいすの 宿はと問はば いかに答へん”
これを読んで梅ノ木を返した村上天皇の器量も素晴らしい。
平安時代の中でも最も平安な時期だったのかな?
なんと、”業平東下りの図”尾形光琳作のオマケが記載ありましたよ。
某琳派サポーターを思い出してブログにアクセスした次第。
大阪の梅の名所・大阪城公園は咲き始めとの
”梅だより”。何処とも女性が主流派でしょうね?
かの定家も後鳥羽院から柳を取り上げられています。草木ならばと目を瞑ったのでしょうか。
村上天皇の梅への愛着は有名です。(拾遺集より)
天暦の御時、台盤所の前に鶯の巣を紅梅 の枝に付けて立てられたるを見て
一条摂政
花の色はあかず見るとも鶯のねぐらの枝に手なな触れそも
おなじ御時、梅花のもとに御椅子たてさせたまひて花の宴せさせたまふに、殿上のをのこども歌つかうまつりけるに
源寛信朝臣
折りて見るかひもあるかな梅の花けふここのへににほひまさりて
村上天皇の孫、花山院もご出家の後も紅梅に執着を寄せ、いさめられる話が古今著聞集に出ています。
色香をば思ひも入れず梅の花つねならね世によそへてぞ見る
長文の英語と違って古典なら、すらすらと思い出せます。
”業平東下りの図”は、富士を見る見返り美男でしたか。それとも杜若に”妻をしぞおもふ”姿でしたか。
琳派サポーターを思い出していただけて「ありがとうございます。」
みやびな花をお酒に浮かべて、今宵もboa!邸の宴は盛んでしょう。
梅の花ふりおほふ雪をつつみ持ち君に見せむと取れば消につつ
やはり紅梅… 紅と雪の白さが目にしみて。「大空は梅のにほひに霞みつつ」boa!さんのお作から、こちらまでよい香りが漂いました。
画像のUPも昨日はできませんでした。
「君に見せんと取れば消につつ」暗示的でした。
わが家の紅梅は貰われて嫁入りしたので、今は若木の成長を待っているところです。
ここ2,3日は鶯の訪問もしきりです。声のほうは???未熟者です。
梅花の宴は強風が邪魔をしてまだ見合わせています。ひらひらとかぐわしく花びらが風にあおられて舞う風情を楽しんでいます。