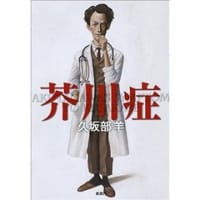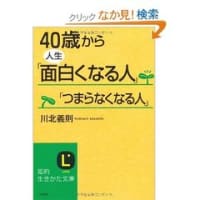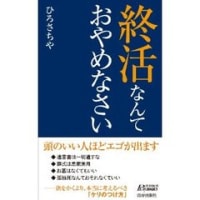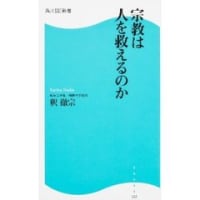本書を「映画好きのお坊さんたちのおしゃべり本」だと
思ったら間違いです。
これは映画論のかたちを借りた宗教書、
それもかなりレベルの高い宗教書です。
(内田樹氏解説より)
↑
今読んでいる本、「仏教シネマ」の解説に、こう書かれている。
───映画が始まる直前、ブザーが鳴って、映画館内が一瞬
真っ暗になる。ドキドキする。
この瞬間、このときだけは、いくつになっても変わらない
至福の瞬間である。
↑
「はじめに」の中で、釈徹宗さんは、こう言っている。
私たち、団塊の世代のみなさんは、
こんな瞬間を、幾度となく経験されたことだろう。
今、この本を手にして、なつかしいあのころに、想いを
馳せている。
“場末の溜まり場”としての映画館、
“悪所”としての映画館で、私たちは、
「悪所の連帯」感というか、とても、居心地のいい場所だった。
映画の途中で、拍手が起こる。
“男はつらいよ”の最初には、必ず、寅さんが夢を見るシーンで
始まる。この映画では、
どんな、シーンで始まるんだろう。
いつも、ワクワクしていた。
健さんの任侠道に、体育会系の連中が、涙を流している。
この本は、2011年の秋に出版されている。
今回は、それを若干、リメイクと新しいテーマを加えて、
二人の法力あるお坊さんが、映画の中にある“生老病死”と
“葬る”ということについて、
仏教の深い知恵を、みごとに輝かせている本である。
その中で、私の想いの中に、見事にはまってみせた、
お二人のお話を少し、書かせていただきます。
我々は大きな物語が機能しない社会へと突入しています。
さまざまな世代が共有できるストーリーや価値というものが
次々と解体されてきました。
異なる価値をお互いに認め合って尊重する方向を
志向すれば、当然の帰結です。成熟した、あるいは
先鋭化近代社会の形態ですね。そして、我々はそこで
行き詰まってしまいました。気がつくと、それぞれが
自分の物語ばかりを語るような状況になりました。
(本書 P52・53)
私たち戦後生まれの団塊として育ってきた世代は、
戦争は知らないけど、戦争のしでかした、重たい罪みたいな
ものをなんとなく、身に背負いながら生きてきました。
戦後の復興というシナリオに書かれた、大きな物語が
そこにあったと思います。
戦争で亡くなられた人たちのためにも、日本の復興を
果たさなければならない。
ある意味、「平和」と「民主主義」とか「生きる権利」とか、
そんな言葉を呪文のように唱えながら、
生きてきたように思います。
それが、私たちの、人生物語・青春ストーリーでした。
それが、今。。。
家族は崩壊し、横の連帯意識も薄れて、
孤立死とか孤独死とか、ささやかれる時代なりました。
高度に成長した日本経済も陰りが見え始め、
消費生活になじみすぎた日本社会は、物づくりを忘れ、
肝心な“人づくり”もできなくなりました。
その結果は、釈さんがおっしゃっているとおり、
自分の物語の“読み聞かせ”しか、“聞き取り”しか、
できなくなった社会のようです。
この20年は、まさに、連帯とか、大きな夢ストーリーの
喪失の“とき”でした。
これからの、日本の大きなストーリーとは、いったい何でしょうか。
やはり、歴史は繰り返すというのか、今からは、
震災後の復興が、大きな“物語”になるのでしょう。
10年前の“小泉劇場”には、みんな注目しました。
戦後の50年体制が崩壊しました。
次の、民主党政権では、政権交代という、夢物語を
見せてもらうはずでした。でも。。。
こんどこそ、震災で失ったものや、物づくり、人づくりの
復興復活に向けて、大ストーリーを展開しなければなりません。
そんな、シナリオを描いてくれるリーダーは、
今の日本に、早く現われて欲しい。そんな想いです。
ええっ、橋下さん?
65歳以上の高齢者も、4分の3は健康な人たちです。
そんな年寄りが頑張らなければ、日本の出口は見えてこない、とか、
どなたかが、おっしゃっていました。
そんな場末の私たちですが、微力ながら、社会の力になるよう、
微力でも、尽力したいと思います。
ご静聴、ありがとうございました。(笑
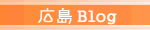

きょうも来てくださって、ありがとうございます

2011年11月に発行された単行本
思ったら間違いです。
これは映画論のかたちを借りた宗教書、
それもかなりレベルの高い宗教書です。
(内田樹氏解説より)
↑
今読んでいる本、「仏教シネマ」の解説に、こう書かれている。
───映画が始まる直前、ブザーが鳴って、映画館内が一瞬
真っ暗になる。ドキドキする。
この瞬間、このときだけは、いくつになっても変わらない
至福の瞬間である。
↑
「はじめに」の中で、釈徹宗さんは、こう言っている。
私たち、団塊の世代のみなさんは、
こんな瞬間を、幾度となく経験されたことだろう。
今、この本を手にして、なつかしいあのころに、想いを
馳せている。
“場末の溜まり場”としての映画館、
“悪所”としての映画館で、私たちは、
「悪所の連帯」感というか、とても、居心地のいい場所だった。
映画の途中で、拍手が起こる。
“男はつらいよ”の最初には、必ず、寅さんが夢を見るシーンで
始まる。この映画では、
どんな、シーンで始まるんだろう。
いつも、ワクワクしていた。
健さんの任侠道に、体育会系の連中が、涙を流している。
この本は、2011年の秋に出版されている。
今回は、それを若干、リメイクと新しいテーマを加えて、
二人の法力あるお坊さんが、映画の中にある“生老病死”と
“葬る”ということについて、
仏教の深い知恵を、みごとに輝かせている本である。
その中で、私の想いの中に、見事にはまってみせた、
お二人のお話を少し、書かせていただきます。
我々は大きな物語が機能しない社会へと突入しています。
さまざまな世代が共有できるストーリーや価値というものが
次々と解体されてきました。
異なる価値をお互いに認め合って尊重する方向を
志向すれば、当然の帰結です。成熟した、あるいは
先鋭化近代社会の形態ですね。そして、我々はそこで
行き詰まってしまいました。気がつくと、それぞれが
自分の物語ばかりを語るような状況になりました。
(本書 P52・53)
私たち戦後生まれの団塊として育ってきた世代は、
戦争は知らないけど、戦争のしでかした、重たい罪みたいな
ものをなんとなく、身に背負いながら生きてきました。
戦後の復興というシナリオに書かれた、大きな物語が
そこにあったと思います。
戦争で亡くなられた人たちのためにも、日本の復興を
果たさなければならない。
ある意味、「平和」と「民主主義」とか「生きる権利」とか、
そんな言葉を呪文のように唱えながら、
生きてきたように思います。
それが、私たちの、人生物語・青春ストーリーでした。
それが、今。。。
家族は崩壊し、横の連帯意識も薄れて、
孤立死とか孤独死とか、ささやかれる時代なりました。
高度に成長した日本経済も陰りが見え始め、
消費生活になじみすぎた日本社会は、物づくりを忘れ、
肝心な“人づくり”もできなくなりました。
その結果は、釈さんがおっしゃっているとおり、
自分の物語の“読み聞かせ”しか、“聞き取り”しか、
できなくなった社会のようです。
この20年は、まさに、連帯とか、大きな夢ストーリーの
喪失の“とき”でした。
これからの、日本の大きなストーリーとは、いったい何でしょうか。
やはり、歴史は繰り返すというのか、今からは、
震災後の復興が、大きな“物語”になるのでしょう。
10年前の“小泉劇場”には、みんな注目しました。
戦後の50年体制が崩壊しました。
次の、民主党政権では、政権交代という、夢物語を
見せてもらうはずでした。でも。。。
こんどこそ、震災で失ったものや、物づくり、人づくりの
復興復活に向けて、大ストーリーを展開しなければなりません。
そんな、シナリオを描いてくれるリーダーは、
今の日本に、早く現われて欲しい。そんな想いです。
ええっ、橋下さん?
65歳以上の高齢者も、4分の3は健康な人たちです。
そんな年寄りが頑張らなければ、日本の出口は見えてこない、とか、
どなたかが、おっしゃっていました。
そんな場末の私たちですが、微力ながら、社会の力になるよう、
微力でも、尽力したいと思います。
ご静聴、ありがとうございました。(笑
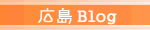

きょうも来てくださって、ありがとうございます

2011年11月に発行された単行本