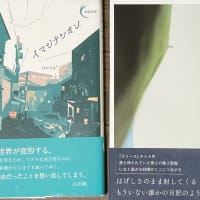三枝昂之『遅速あり』が、第54回迢空賞を受賞されたとのこと。
おめでとうございます。
この歌集について、ある会で話すつもりが、コロナウイルスのために中止になってしまいました。
その資料に、短いコメントをつけて掲載します。
くぬぎは深くコナラは浅く身を鎧い樹の肌に樹の温かみあり
木肌の特徴をよく見ています。クヌギの木肌は特に襞(ひだ)が深いです。冬の雑木林でしょう。自然に対する親近感がよく表れている歌です。
里山に木の葉すくいて挙がる声おのこごの声その父の声
下の句がシンプルな対句で、落葉で遊んでいる男の子と父親の楽しそうな様子が伝わってきます。素朴な作りの良さがあります。
ここが故郷であるかのように如月の樹々の高さを風が響(な)りたり
故郷から離れて生活している人の歌。ここは故郷ではないが、暮らしているうちに故郷のような懐かしさを感じるようになってきた、という思いが詠まれています。「樹々の高さを風が響りたり」がいい表現。「高さを」の「を」という助詞もいいですね。「高さに」ではない。「を」のほうが空間の広がりが生まれる感じがします。
いちはやき春の河口が見えるはず父と息子の肩車あり
これも、(他人の)父と子の歌ですね。自分の息子は、もう子育ての時期を過ぎてしまい、他人の父子関係が懐かしく、うらやましく見えてしまう、という思いも背後にあるのかもしれません。肩車の視線の高さだと、遠くの早春の河口が見えるだろう、という想像が、さわやかな一首。
二十日月の明るさを言うメールありいつの世も人は人に告げたき
月の美しさを他人に告げたい思いは、古典和歌のころから変わらない。今は、それをメールでやっているだけなのだ、という思想が歌われています。はるかなものへの思いが、ときどきこの歌集にはあらわれますね。「二十日月」という選択もいいし、下の句の愛誦性のあるリズムもいい。
岸に待つ暮らしがあればひと筋の水脈(みお)を広げて帰りくる船
漁をして暮らしている人でしょう。家族が岸に待っているんですね。昔ながらの生活を営んでいる人々へのあこがれがこうした歌にあります。下の句が美しい。
寒林に枝打つ音が響きたり一人の男の一つの戦後
これは林業をしている男。この歌も、質朴な暮らしをしている人々への親近感があらわれた歌といえるでしょう。「寒林」から、決して楽ではない暮らしがイメージできます。自分とは全く別の世界に、ともに戦後の時間を過ごしてきた男がいる。共感と、距離感がないまぜになったような思いがあるのだと思います。
遠くにてかなかなの声湧きあがりわれのみが聴くあかつき方を
これはリズムが柔らかくて、美しい一首ですね。こういう歌は、あまり解釈をしなくてもよくて、快い調べを味わえばいいのだと思います。
落葉松の針をつまみて手に載せるわれの肩からかたわらの手に
隣りに誰かいるんです(たぶん妻でしょう)。自分の肩に落ちてきた落葉松のとがった葉を、かたわらの人の手に載せてあげる。行為だけを詠んでいますが、ほどよいロマンティシズムがある感じがします。
ひとり来て花を捧げる 永遠はないがしばしの陽だまりはある
墓に献花している場面でしょう。箴言的な下の句が印象的です。「陽だまり」だから、冬の日なたのイメージ。日なたといっても、とてもはかない。でも、そんな冬の日なたに、永遠的なものを感じることは、ときどきあるのではないでしょうか。そんな感覚を掬い取っている歌だと思います。
翳りなきあかるさとして素枯れたる一樹一樹も甲斐のみほとけ
これも冬の林の歌。寒林の歌が多いですね。枯れた木の一本一本を、仏像のように感じている。とてもおもしろく、すごくスケールの大きなイメージです。甲斐は、三枝さんの故郷でもあります。
うつしみを抱く蒼穹よ胸中に農鳥岳があれば帰らず
農鳥岳は、山梨と静岡の境界にある山だそうです。故郷の山なんですね。自分は今、農鳥岳が見えない地に暮らしている。しかし、自分の心の中に農鳥岳があるから、故郷には帰らないんだと歌っている。啄木みたいで、ちょっと古風でしょうか。でも、私はこの気持ちがよく分かるので、好きな一首です。
水張田となりてととのう出羽の国かなたに雪の月山を置き
五月くらいの東北に行くと、水田が見渡すかぎり広がる風景に驚かされます。田に水が入って風景が「ととのう」感じはよく分かる。一面に広がる水田の端のほうに、月山(がっさん)がちょこんと見えている。「ととのう」「置き」という動詞の選びがおもしろい。
冬枯れのこの国原に薪を割る音がひびきて年あらたなり
これも日本の風土に対する心寄せ、というべき歌でしょう。「国原(くにはら)」ですから、古代的な、土地に対する敬意があります。現代では、こうした「くに」への思いは、実感しにくくなっているし、抑圧されてもいます。でも、新しい年を迎えるとき、「薪を割る音」が響いて、古代から連綿と続いてきた時間と空間の中に、自分も存在しているのだ、という思いを抱くこともある。この歌はいかにも短歌的な歌かもしれない。様式的、といってもいいでしょう。でも、こうした歌も、とても大切なんじゃないかと私は思いますし、「薪を割る音」が確かに響いてくる感じがします。
読んで、来て、訊いて、語って、泡盛を飲んで、沖縄はいまなお見えず
これは沖縄で短歌のシンポジウムをしたときの歌で、私もいっしょだったので、共感する歌です。沖縄に来る前にいろいろな本を読んで、現場の人の話を聞いて、シンポジウムで語り、その後の打ち上げで泡盛を飲んで、濃厚な時間を過ごしたのですが、それでもまだやはり、沖縄の人間ではない自分には、見えないものがある。しかし、見えないからこそ、また読んで、また来て、また泡盛を飲もう、という思いになるのではないでしょうか。
今年も沖縄に行きたかったのですが、コロナウイルスの影響で難しいかな……
枇杷釉のぐいのみに呼び止められて二、三歩戻る菊屋横町
「菊屋横町」は萩市にある古い町らしいです。萩焼なんでしょう。枇杷色のぐいのみ、というのが、色彩感があっていいですね。通り過ぎたんだけど、欲しくなってまた店の前に戻ってきた。「呼び止められて」という擬人化が、この歌では効いています。楽しい旅の歌です。
もうニュースは消しておのれに戻りたり非力な非力な言葉のために
これは、東日本大震災のときの歌ですが、現在のコロナウイルスの蔓延の状況でも、通じる一首だと思います。テレビのニュースで報道される圧倒的な現実を前にすると、もう何も言葉が出てこない。けれども、「非力な非力な」自分の言葉に戻っていって、そこから表現を立ち上げていくしかない。非力であっても、自分自身の言葉を拠点にするしかないんだ、という決意です。これはとても重要な歌だと思います。
(二〇一九年四月二〇日・砂子屋書房)