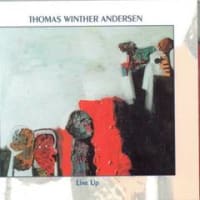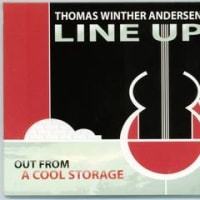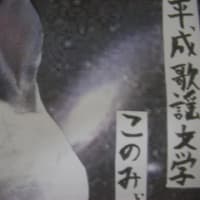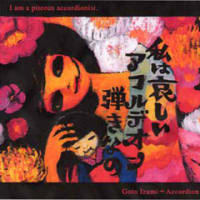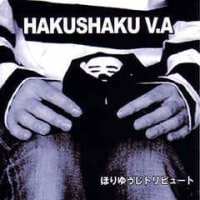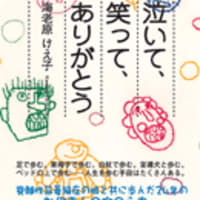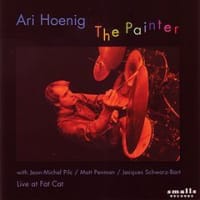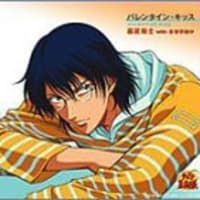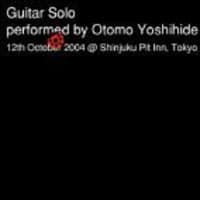生活扶助基準切り下げが見送りになるのではないかという報道が複数出ている。
読売新聞
産経新聞
しかしいずれも「地域間の基準額の差を実態に合わせ」る作業はやるのだという。
これが曲者になりそうである。
つまり生活扶助基準の地域格差(現在は6段階にわかれていて都市部‐1級地の1と地方‐3級地の2)は22.5パーセントであるのに対して、実際の生活費の差はそんなに開いていないのだから見直しが必要という議論である。
もし仮に生活扶助基準の地域格差を見直す必要それ自体は認めたとしよう。
その場合、
(1)都市部の扶助基準を妥当として残りをすべて引き上げる
(2)地方の扶助基準を妥当として残りをすべて切り下げる
(3)どこかに基準‐中央値を定めてそこより都市部は引き上げそこより地方は切り下げる
の3つの選択肢が考えられる(さらに区分を見直す可能性もある)。
そして、いずれにしろその妥当性を判断するためには結局のところどの水準が妥当であるのかという判断が求められるということになる。
そしてそして、その判断基準に見送ったはずの「低所得世帯との均衡」理論がすべりこむ危険性があるのである。
第3回「生活扶助基準に関する検討会」で厚労省は2級地の1あたりで「一般世帯の生活扶助相当支出額」と「生活扶助基準額」がクロスする図を示している。
第3回資料5ページ
しかしこれはあくまでもこの基準点を100とした場合の差の開き具合であり、2級地の1の扶助基準が妥当なラインであるという検証が行われているものではない。
従って、これだけでは2級地の1あたりには影響は及ばないがそれより都市部は保護費が上がりそれより田舎は上がるというハナシになるというものではない。
ところが、標準3人世帯の生活扶助費は2級地の1で150770円、今回の見直しの根拠となっている「第1十分位」の「夫婦子一人世帯」「生活扶助相当支出額」は148781円と近似の値が出ている。
これを考え合わせると2級地の1でクロスさせてそこを中央値に上げ下げしていいんじゃない?ということになってしまうかもしれないということになる。
見送ったはずの価値判断の基準がここで生かされることになってしまいはしないかという心配をどうしてもしてしまう。
2003年から2004年にかけて開催された「生活保護制度の在り方に関する専門委員会」では第14回目にこのポイントが論議されている。
そしてそこでは根本委員(今回の「検討会」の委員でもある)が「今の中間値くらいのところに標準値を定めて、プラスマイナス10%であるとか、厳密に言えば11コンマ何がしということになるのでしょうが、そういうような形で県などと協議していき、決定をしていくのはどうか」という意見を出しているがそれが採り入れられることはなく、この点については「保護基準委員会のようなものが常設あるいは一定の間隔で招集され、そこでいろんなデータをきちんと比較して、」「同じ地域格差を設けているほかの制度も比較検討しながら、何が一番適切かを検討する場を設けてはどうかという提案を、この委員会ではしておく形ではいかがでしょうか」(岩田委員長)というところに落ち着いている。
そして今回岩田正美元在り方専門委員会委員長は「生活扶助基準に関する検討会」にもとづく見直しついて「審議会のもとで専門部会を設け、必要な調査がおこなわれると期待していた。国民全体の最低生活ラインをどのように考えるのかというのは、厚労省内の研究会を数回開いてすむような話ではない」という手厳しいコメントを出されているとおり(12月1日「朝日」)、「在り方」で求められていたレベルの検討機関としては今回の「検討会」は不適格であるといわざるをえない。
わずか40日、わずか5人の検討委員が、厚労省お手盛りの資料のみで検討していいような課題ではもともとなかったのである。
にもかかわらず、そして「低所得世帯との均衡」理論は見送られようとしているにもかかわらず(まだそうと決まったわけでもない)、級地見直しにかこつけてその判断基準が潜り込んでしまうのであるとすれば、これは姑息というよりほかにない(ちなみに2級地の1を基準に見直しを行うと1級地の1では8929円減という試算もある)。
もちろん、大体真中であわせればいいんじゃない?という根本委員のような非科学的な議論も行われるべきではない。
もしどうしても見直すというのであれば、保護利用者・低所得者に影響の出ないように都市部を据え置いてその他の部分を全て引き上げるべきである。
それ以外の結論は容認しがたい。
この問題について生活保護問題対策全国会議の緊急声明はこちら。
読売新聞
産経新聞
しかしいずれも「地域間の基準額の差を実態に合わせ」る作業はやるのだという。
これが曲者になりそうである。
つまり生活扶助基準の地域格差(現在は6段階にわかれていて都市部‐1級地の1と地方‐3級地の2)は22.5パーセントであるのに対して、実際の生活費の差はそんなに開いていないのだから見直しが必要という議論である。
もし仮に生活扶助基準の地域格差を見直す必要それ自体は認めたとしよう。
その場合、
(1)都市部の扶助基準を妥当として残りをすべて引き上げる
(2)地方の扶助基準を妥当として残りをすべて切り下げる
(3)どこかに基準‐中央値を定めてそこより都市部は引き上げそこより地方は切り下げる
の3つの選択肢が考えられる(さらに区分を見直す可能性もある)。
そして、いずれにしろその妥当性を判断するためには結局のところどの水準が妥当であるのかという判断が求められるということになる。
そしてそして、その判断基準に見送ったはずの「低所得世帯との均衡」理論がすべりこむ危険性があるのである。
第3回「生活扶助基準に関する検討会」で厚労省は2級地の1あたりで「一般世帯の生活扶助相当支出額」と「生活扶助基準額」がクロスする図を示している。
第3回資料5ページ
しかしこれはあくまでもこの基準点を100とした場合の差の開き具合であり、2級地の1の扶助基準が妥当なラインであるという検証が行われているものではない。
従って、これだけでは2級地の1あたりには影響は及ばないがそれより都市部は保護費が上がりそれより田舎は上がるというハナシになるというものではない。
ところが、標準3人世帯の生活扶助費は2級地の1で150770円、今回の見直しの根拠となっている「第1十分位」の「夫婦子一人世帯」「生活扶助相当支出額」は148781円と近似の値が出ている。
これを考え合わせると2級地の1でクロスさせてそこを中央値に上げ下げしていいんじゃない?ということになってしまうかもしれないということになる。
見送ったはずの価値判断の基準がここで生かされることになってしまいはしないかという心配をどうしてもしてしまう。
2003年から2004年にかけて開催された「生活保護制度の在り方に関する専門委員会」では第14回目にこのポイントが論議されている。
そしてそこでは根本委員(今回の「検討会」の委員でもある)が「今の中間値くらいのところに標準値を定めて、プラスマイナス10%であるとか、厳密に言えば11コンマ何がしということになるのでしょうが、そういうような形で県などと協議していき、決定をしていくのはどうか」という意見を出しているがそれが採り入れられることはなく、この点については「保護基準委員会のようなものが常設あるいは一定の間隔で招集され、そこでいろんなデータをきちんと比較して、」「同じ地域格差を設けているほかの制度も比較検討しながら、何が一番適切かを検討する場を設けてはどうかという提案を、この委員会ではしておく形ではいかがでしょうか」(岩田委員長)というところに落ち着いている。
そして今回岩田正美元在り方専門委員会委員長は「生活扶助基準に関する検討会」にもとづく見直しついて「審議会のもとで専門部会を設け、必要な調査がおこなわれると期待していた。国民全体の最低生活ラインをどのように考えるのかというのは、厚労省内の研究会を数回開いてすむような話ではない」という手厳しいコメントを出されているとおり(12月1日「朝日」)、「在り方」で求められていたレベルの検討機関としては今回の「検討会」は不適格であるといわざるをえない。
わずか40日、わずか5人の検討委員が、厚労省お手盛りの資料のみで検討していいような課題ではもともとなかったのである。
にもかかわらず、そして「低所得世帯との均衡」理論は見送られようとしているにもかかわらず(まだそうと決まったわけでもない)、級地見直しにかこつけてその判断基準が潜り込んでしまうのであるとすれば、これは姑息というよりほかにない(ちなみに2級地の1を基準に見直しを行うと1級地の1では8929円減という試算もある)。
もちろん、大体真中であわせればいいんじゃない?という根本委員のような非科学的な議論も行われるべきではない。
もしどうしても見直すというのであれば、保護利用者・低所得者に影響の出ないように都市部を据え置いてその他の部分を全て引き上げるべきである。
それ以外の結論は容認しがたい。
この問題について生活保護問題対策全国会議の緊急声明はこちら。