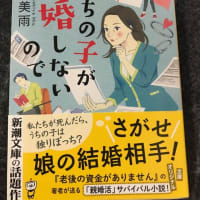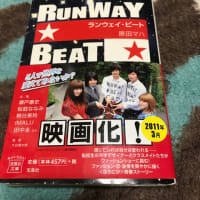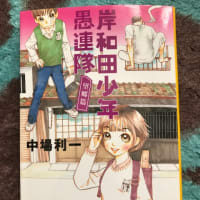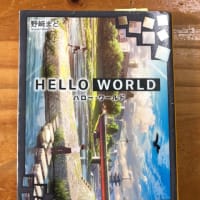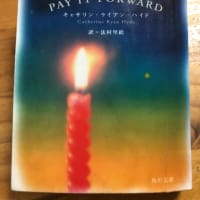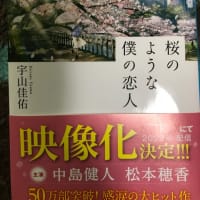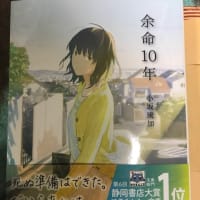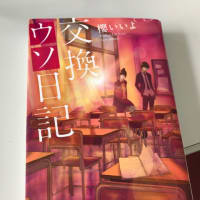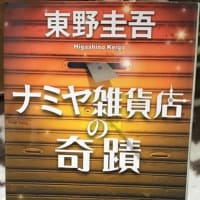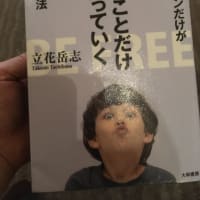脳が認める最強の集中力 林成之著 2018.3.15
《読む目的》集中力を最強にする
《お勧め度》★★★★★
《質問》無心レベルを作り出すには
《発見》自分の弱点を前向きにとらえ、明るく開示(オープン)するほうが脳の力を高めていける
《ポイント》
プロローグ
◼︎トップ1%の人だけが知っている集中力とのつきあい方
◼︎集中力の正体① 結果を残す人たちの真の強さは、集中力の発揮にある
第1章
◼︎集中力が続かない!それは「脳」仕業だった
◼︎脳と集中力① 飽きる、やる気がでない。
・イヤだ!は集中力は働かない。
・やらされ感、損得勘定はダメ。
◼︎脳と集中力② 「集中力がない」は脳が拒否するための言い訳
・脳は無意識に自分を守る
★集中力とは、自ら「こうやる」と考え、そこに向かって「やってやる!」と強い気持ちをもち、全力投球で一心に取り組む。このような力です。
◼︎脳と集中力③ 脳の仕組みを知れば130%発揮
・脳の中の2つの情報ルート
・「ダイナミック・センターコア」の働きを高めていくことが重要
★入ってきた情報に前向きなレッテルを貼る
◼︎脳と集中力④ 集中力は脳力の総結集
・集中力が生まれる場所「自己報酬神経群」
・「脳機能」と「脳本能」のリンク
・「自分からやってやる」「認めてほしい」
・「生きたい」「知りたい」「仲間になりたい」「伝えたい」
★気持ちを入れて!脳細胞の同期発火を起こす
◼︎脳と集中力⑤ 「年を取ると集中力が落ちる」は大ウソ
・集中力低下は脳細胞ではなく、脳の使い方
・集中力が高まると記憶力も高まる
★目標を作り達成レベルを確認する。目標を達成するごとに喜びを感じ、自己報酬神経群を刺激してくれますから、その積み重ねで集中力・記憶力ともに向上していきやすくなる。
★忘れないようにしたいなら3日以内に復習する
◼︎脳と集中力⑥ 脳の悪いクセ「否定」
第2章
◼︎日頃からの絶対習慣
・集中力を生み出す源
◼︎集中力の準備① 「好きになる力」を意識
・「好き」「おもしろい」が出発点
・スポーツ選手は明るい性格でないと一流になれない
★笑顔を鍛える。A10神経群の「尾状核」は顔の表情筋とつながっている。笑顔を増やすだけで前向きになれる。
◼︎集中力の準備② 何事も否定から入らない
◼︎集中力の準備③ 人や物事をバカにするな
・「人を尊敬する力」が集中力につながる
・「好かれる力」がチームの集中力を高める
✖︎教え育てる「教育」
◯共に育つ「共育」の考え方が必要
★人間の脳は、相手がいることで機能するようになっている。人を尊敬し、好きになる力を鍛えて、周りの人の存在も借りながら、脳力をアップしていく。
◼︎集中力の準備④ 人の話をきちんと聴く
・目を見て話す
・「なるほど」「そうだね」を多用することで、同期発火の仕組みは機能しだす。
・相手の発した言葉を極力使って会話をする
★強い気持ちが込もっているほど、伝わる情報が多くなり、人と人の間に同期発火が生じやすい。
普段から気持ちを込めて話す、伝えるができていないと、相手の脳に入って考える力もついていかない。
◼︎集中力の準備⑥ 「今やる!」習慣づけ
◼︎集中力の準備⑦ 手を抜かない
・練習でも手を抜かない
◼︎集中力の準備⑧ ダメではなく、次につながる点に着目する
★成績が上がらないチームや選手ほど反省会が多い。反省すればするほど勝負に弱くなる。
振り返りであれば「うまくいったところ」だけを見つけて、そこをどうやったら次にもっと生かせるか考えていくようにする。
・相手の優れているところに目を向けて、どうやったらそれを超えられるか。
★自分の弱点を前向きにとらえ、明るく開示(オープン)するほうが脳の力を高めていける
◼︎集中力の準備⑨ ひとつを成し遂げてから
・最後までやり切るクセをつけていく。
「統一・一貫性の本能」が働き定着していく。
◼︎集中力の準備⑩ 正しい姿勢「空間認知能」
★正しい姿勢でいると体が疲れないため、脳も疲労を覚えず、集中力を発揮しやすいことに加えて維持することができる。
・目線を水平にする
・背筋を伸ばす
・左右の肩甲骨の高さを地面と水平にする
・目をつぶって同じ位置でジャンプする
第3章
◼︎瞬時に集中モードに切り替える絶対習慣
◼︎日常の集中力① 頭をすぐに切り替える
・デスクの上を片付ける
・簡単なことから手を付ける
◼︎日常の集中力② 本場の緊張対策
・ゆっくり深呼吸で副交換神経を働かせる
・下見と予行演習。一度離れる。
・「1.2.ィ-.3.4.ィ-」「1.2.3.4.ィ-」シータリズム
◼︎日常の集中力③ 期限との戦い
★最終ゴールは決まっていても、そこに向かうまでのプロセスが具体的になってないと脳は機能しません。
・脳を働かせるためにマイルストーンをあえて小さくしておく
◼︎日常の集中力④ 長時間作業との向き合い方
・「楽しい・おもしろい」時は脳は疲れない
・長時間作業、時折り「目線を移す」だけで思考を止めずに休息をとれる
・仕事の質を上げるのであれば、朝の時間帯がベスト
★寝ている間に脳の中の悪い記憶はすべて排除される。新しい発想が必要なときほど、朝の時間帯を活用したほうがよい
◼︎日常の集中力⑤ 同時作業は優先順位をつける「トリアージ」。ひとつに絞ってやる。
・日常の小さな事でも「即断即決」
◼︎日常の集中力⑥ 時間的に「もう後がない」
・「勝負脳の集中力」すべてを出し切りやり遂げる。自分がやることに関して他の追随をゆるさない。といった気持ち。
第4章
◼︎無意識のうちに最高の結果を出す絶対習慣
・無意識へと落とし込む集中力
◼︎無意識の集中力① 最後までやり抜く
◼︎無意識の集中力② 今は無理でも最後はかなえる
◼︎無意識の集中力③ 小さな成功体験
◼︎無意識の集中力④ 反復やルーティンを大切にする
・本当の判断力とは、微妙な違いを瞬時に見極められる力
・「統一・一貫性の本能」は、同じことを何度も何度も繰り返すことで鍛えられる。
◼︎無意識の集中力⑤ 半分の時間でやる
◼︎無意識の集中力⑥ 否定の否定
第5章
◼︎想定外の好結果を生み自分を変える絶対習慣
・無心レベルにまで高める集中力
◼︎予想外の集中力①「自分のゾーン」をもつ
・北島選手Kゾーン最後の10m
・フリースペースにもマイゾーンをつくる
◼︎予想外の集中力②「勝負の場はチャンス」
・勝負は闘いではなく「自分を高めるチャンス」「自分の力量を試すチャンス」ととらえる
・ライバルは自分を成長させてくれる仲間だと思え
◼︎予想外の集中力③「誰にも負けない技」をもつ
・脳科学から「心技体」を語るとするなら、まず鍛えるべきは「技」。なぜなら脳は技術=テクニックが最初にあってこそ機能する仕組み。
◼︎予想外の集中力④「自分の常識」を打ち破る
・一般的に常識と思われていることでも、常識ではない可能性はある
◼︎予想外の集中力⑤「集中力の高いチーム」
・反対意見を述べるときは、必ず理由と代替案を添えることをルールとする
・互いをカバーし合って集中力を高める
◼︎予想外の集中力⑥「無心レベル」
・素直に目の前のことに全力投球すること
・ルーティンをつくり、何も考えずに体が動くようになるまでそれを繰り返すこと

《読む目的》集中力を最強にする
《お勧め度》★★★★★
《質問》無心レベルを作り出すには
《発見》自分の弱点を前向きにとらえ、明るく開示(オープン)するほうが脳の力を高めていける
《ポイント》
プロローグ
◼︎トップ1%の人だけが知っている集中力とのつきあい方
◼︎集中力の正体① 結果を残す人たちの真の強さは、集中力の発揮にある
第1章
◼︎集中力が続かない!それは「脳」仕業だった
◼︎脳と集中力① 飽きる、やる気がでない。
・イヤだ!は集中力は働かない。
・やらされ感、損得勘定はダメ。
◼︎脳と集中力② 「集中力がない」は脳が拒否するための言い訳
・脳は無意識に自分を守る
★集中力とは、自ら「こうやる」と考え、そこに向かって「やってやる!」と強い気持ちをもち、全力投球で一心に取り組む。このような力です。
◼︎脳と集中力③ 脳の仕組みを知れば130%発揮
・脳の中の2つの情報ルート
・「ダイナミック・センターコア」の働きを高めていくことが重要
★入ってきた情報に前向きなレッテルを貼る
◼︎脳と集中力④ 集中力は脳力の総結集
・集中力が生まれる場所「自己報酬神経群」
・「脳機能」と「脳本能」のリンク
・「自分からやってやる」「認めてほしい」
・「生きたい」「知りたい」「仲間になりたい」「伝えたい」
★気持ちを入れて!脳細胞の同期発火を起こす
◼︎脳と集中力⑤ 「年を取ると集中力が落ちる」は大ウソ
・集中力低下は脳細胞ではなく、脳の使い方
・集中力が高まると記憶力も高まる
★目標を作り達成レベルを確認する。目標を達成するごとに喜びを感じ、自己報酬神経群を刺激してくれますから、その積み重ねで集中力・記憶力ともに向上していきやすくなる。
★忘れないようにしたいなら3日以内に復習する
◼︎脳と集中力⑥ 脳の悪いクセ「否定」
第2章
◼︎日頃からの絶対習慣
・集中力を生み出す源
◼︎集中力の準備① 「好きになる力」を意識
・「好き」「おもしろい」が出発点
・スポーツ選手は明るい性格でないと一流になれない
★笑顔を鍛える。A10神経群の「尾状核」は顔の表情筋とつながっている。笑顔を増やすだけで前向きになれる。
◼︎集中力の準備② 何事も否定から入らない
◼︎集中力の準備③ 人や物事をバカにするな
・「人を尊敬する力」が集中力につながる
・「好かれる力」がチームの集中力を高める
✖︎教え育てる「教育」
◯共に育つ「共育」の考え方が必要
★人間の脳は、相手がいることで機能するようになっている。人を尊敬し、好きになる力を鍛えて、周りの人の存在も借りながら、脳力をアップしていく。
◼︎集中力の準備④ 人の話をきちんと聴く
・目を見て話す
・「なるほど」「そうだね」を多用することで、同期発火の仕組みは機能しだす。
・相手の発した言葉を極力使って会話をする
★強い気持ちが込もっているほど、伝わる情報が多くなり、人と人の間に同期発火が生じやすい。
普段から気持ちを込めて話す、伝えるができていないと、相手の脳に入って考える力もついていかない。
◼︎集中力の準備⑥ 「今やる!」習慣づけ
◼︎集中力の準備⑦ 手を抜かない
・練習でも手を抜かない
◼︎集中力の準備⑧ ダメではなく、次につながる点に着目する
★成績が上がらないチームや選手ほど反省会が多い。反省すればするほど勝負に弱くなる。
振り返りであれば「うまくいったところ」だけを見つけて、そこをどうやったら次にもっと生かせるか考えていくようにする。
・相手の優れているところに目を向けて、どうやったらそれを超えられるか。
★自分の弱点を前向きにとらえ、明るく開示(オープン)するほうが脳の力を高めていける
◼︎集中力の準備⑨ ひとつを成し遂げてから
・最後までやり切るクセをつけていく。
「統一・一貫性の本能」が働き定着していく。
◼︎集中力の準備⑩ 正しい姿勢「空間認知能」
★正しい姿勢でいると体が疲れないため、脳も疲労を覚えず、集中力を発揮しやすいことに加えて維持することができる。
・目線を水平にする
・背筋を伸ばす
・左右の肩甲骨の高さを地面と水平にする
・目をつぶって同じ位置でジャンプする
第3章
◼︎瞬時に集中モードに切り替える絶対習慣
◼︎日常の集中力① 頭をすぐに切り替える
・デスクの上を片付ける
・簡単なことから手を付ける
◼︎日常の集中力② 本場の緊張対策
・ゆっくり深呼吸で副交換神経を働かせる
・下見と予行演習。一度離れる。
・「1.2.ィ-.3.4.ィ-」「1.2.3.4.ィ-」シータリズム
◼︎日常の集中力③ 期限との戦い
★最終ゴールは決まっていても、そこに向かうまでのプロセスが具体的になってないと脳は機能しません。
・脳を働かせるためにマイルストーンをあえて小さくしておく
◼︎日常の集中力④ 長時間作業との向き合い方
・「楽しい・おもしろい」時は脳は疲れない
・長時間作業、時折り「目線を移す」だけで思考を止めずに休息をとれる
・仕事の質を上げるのであれば、朝の時間帯がベスト
★寝ている間に脳の中の悪い記憶はすべて排除される。新しい発想が必要なときほど、朝の時間帯を活用したほうがよい
◼︎日常の集中力⑤ 同時作業は優先順位をつける「トリアージ」。ひとつに絞ってやる。
・日常の小さな事でも「即断即決」
◼︎日常の集中力⑥ 時間的に「もう後がない」
・「勝負脳の集中力」すべてを出し切りやり遂げる。自分がやることに関して他の追随をゆるさない。といった気持ち。
第4章
◼︎無意識のうちに最高の結果を出す絶対習慣
・無意識へと落とし込む集中力
◼︎無意識の集中力① 最後までやり抜く
◼︎無意識の集中力② 今は無理でも最後はかなえる
◼︎無意識の集中力③ 小さな成功体験
◼︎無意識の集中力④ 反復やルーティンを大切にする
・本当の判断力とは、微妙な違いを瞬時に見極められる力
・「統一・一貫性の本能」は、同じことを何度も何度も繰り返すことで鍛えられる。
◼︎無意識の集中力⑤ 半分の時間でやる
◼︎無意識の集中力⑥ 否定の否定
第5章
◼︎想定外の好結果を生み自分を変える絶対習慣
・無心レベルにまで高める集中力
◼︎予想外の集中力①「自分のゾーン」をもつ
・北島選手Kゾーン最後の10m
・フリースペースにもマイゾーンをつくる
◼︎予想外の集中力②「勝負の場はチャンス」
・勝負は闘いではなく「自分を高めるチャンス」「自分の力量を試すチャンス」ととらえる
・ライバルは自分を成長させてくれる仲間だと思え
◼︎予想外の集中力③「誰にも負けない技」をもつ
・脳科学から「心技体」を語るとするなら、まず鍛えるべきは「技」。なぜなら脳は技術=テクニックが最初にあってこそ機能する仕組み。
◼︎予想外の集中力④「自分の常識」を打ち破る
・一般的に常識と思われていることでも、常識ではない可能性はある
◼︎予想外の集中力⑤「集中力の高いチーム」
・反対意見を述べるときは、必ず理由と代替案を添えることをルールとする
・互いをカバーし合って集中力を高める
◼︎予想外の集中力⑥「無心レベル」
・素直に目の前のことに全力投球すること
・ルーティンをつくり、何も考えずに体が動くようになるまでそれを繰り返すこと