弁慶岬(べんけいみさき)
源義経北行伝説の1つに数えられる場所であり、岬の入り口には約5mの高さの弁慶の銅像が立っている。
平泉を脱出し、さらに三厩から蝦夷地(北海道)へと渡った義経主従であるが、その地でアイヌの人々交流しつつ再起を図ろうとしたとされる。
伝説では、この岬のあたりに義経主従がしばらく滞在し、毎日のように弁慶が岬から海を見ていたという。弁慶の舎弟となる常陸坊海尊が、義経再起のための兵を集め、蝦夷地へ船でやって来る手筈となっており、その船が来るのを待っていたのである。しかしその船が訪れることはなく、結局義経主従はこの地を離れ、さらに北の雷電岬を目指して去ったという。
なおこの岬一帯は、その地形からアイヌの言葉で“破れたところ”を意味する“ペル・ケイ”と呼ばれており、その名を和人が“べんけい”と発音したことから、義経伝説と繋がったのではと言われている。

源義経北行伝説の1つに数えられる場所であり、岬の入り口には約5mの高さの弁慶の銅像が立っている。
平泉を脱出し、さらに三厩から蝦夷地(北海道)へと渡った義経主従であるが、その地でアイヌの人々交流しつつ再起を図ろうとしたとされる。
伝説では、この岬のあたりに義経主従がしばらく滞在し、毎日のように弁慶が岬から海を見ていたという。弁慶の舎弟となる常陸坊海尊が、義経再起のための兵を集め、蝦夷地へ船でやって来る手筈となっており、その船が来るのを待っていたのである。しかしその船が訪れることはなく、結局義経主従はこの地を離れ、さらに北の雷電岬を目指して去ったという。
なおこの岬一帯は、その地形からアイヌの言葉で“破れたところ”を意味する“ペル・ケイ”と呼ばれており、その名を和人が“べんけい”と発音したことから、義経伝説と繋がったのではと言われている。












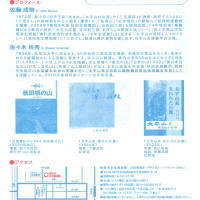
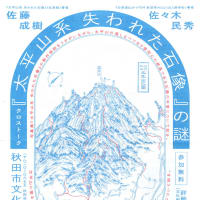




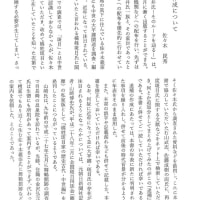







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます