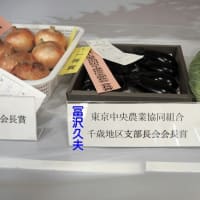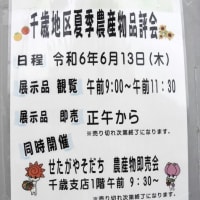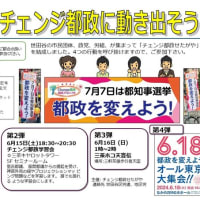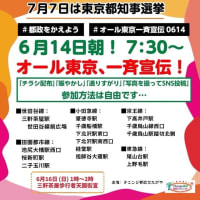「江戸城かわら版」NPO法人江戸城天守を再建する会(秋号)が配達されました。その中で、河村たかし名古屋市長がすすめている「名古屋城」についての論考は、「江戸城天守再建」にも参考になりますので転載します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第二回名古屋城
城郭建築の頂点を実体験できることが復元の意義
名古屋城天守は、規模といい様式といい、戦災焼失する前は城郭建築の頂点として存在していました。日本の木造建築技術として見れば、法隆寺から始まった進歩の到達点であったといえます。
名古屋城は慶長一七年(一六一二年)に建てられてから、天守の自重のために徐々に傾いてしまったといいます。そこで宝暦期(着工期間一七五二~一七五五年)に、木造建築技術の粋を集めた大修理が行われます。このとき行った様々な修理が絵付きで詳細に記録されています(宝暦大修理関係資料)。先人はこれだけの技術を磨いて、名古屋城を保存してきたのです。
従って焼失前の名古屋城天守は宝暦の大修理を施した後の姿であり、創建時の慶長期の天守ではありません。宝暦修理で追加された窓がありますし、天守台の北側と西側の石垣を積み直しています。ですから、木造復元においては、宝暦期の修理後の姿に戻すことになります。
復元に必要な資料として、古写真(名古屋城総合事務所に七〇〇枚以上保存)と各階の実測図(平面図及び見上図)などが豊富に残っています。昭和七年から五か年計画で実測図(昭和実測図、全二七九枚)を作成しました。
戦後の復興で、SCR(鉄骨鉄筋コンクリー卜)として、外観だけを再現した天守が建てられました。
もし、木造で焼失前の姿に戻すことができたら、内部に入って、当時の最高の天守の有様を実体験できます。それが復元の意義といえます。
史実に忠実な復元を追求するときの課題とは
復元に伴う課題として、資料(史実)に基づいた忠実な復元そのものが課題である一方、竣工後の建物を維持?活用するための現代的な諸問題に対する課題が加わりました。
史実に忠実な復元においては、意匠だけでなく材料や工法も再現したいといいます。とはいえ、現代工法の適切な導入も必要とのことです。
一方、竣工後の建物を維持、活用するために、建築基準法、消防法など法規の遵守や耐震対策、防火消化対策、バリアフリー対策、維持管理に対する配慮などが必要です。史実に忠実な復元とバリアフリー対策は、どちらにも配慮するバランスをとりながらの決定が求められます。
最後に視聴者から名古屋城天守の復元工事の着工見通しを問われました。着工のための準備は着々と進んでいる一方で、文化庁の許可をめぐるやりとりが続いているそうです。石垣などそこにあるすベての史跡の「本質的価値の保存」の対策が必要になるという、特別史跡内における復元ゆえの難しさがあるそうです。とはいえ、その許可を得る見通しが立ちつつあるとのことです。文/近藤一郎
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(了)