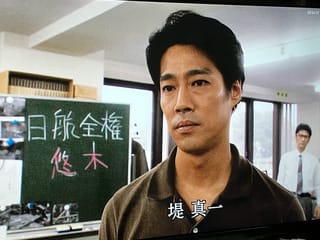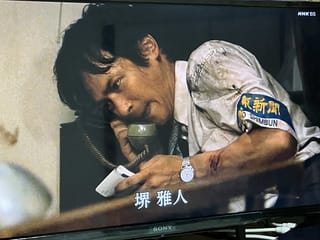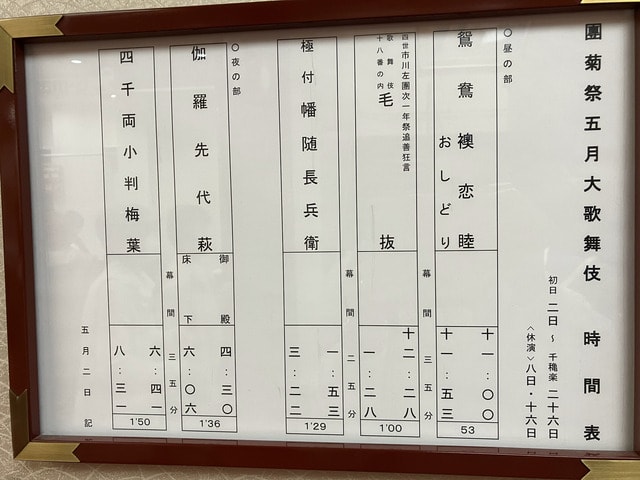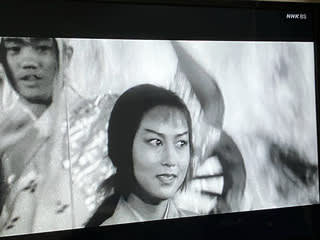さて、今日は最終日、天気は晴れ。まず朝食だがノダコーヒ本店に、朝7時開店のため、少し早めに到着。ここは開店前だが客が店先に並ぶと店の中に入れてくれるので好きな席に座って備え付けの新聞を読みながら7時を待つ。

もう結構先客が入っていたが、奥の広い庭園が見える席が空いていたので、そこに座る。今朝の注文は、昨日食べ過ぎたので、トーストとコーヒーのみとした、二人合計で2,000円くらいか。
ここはコーヒーにクリームと砂糖をあらかじめ入れて提供する方式、私はブラックを飲むのでそう言えば対応してくれる。ここは、1940年に猪田七郎氏が海外産コーヒーの卸売を始め、1947年にコーヒーショップを開いたのが創業である。この時、客が会話に夢中になってコーヒーが冷め、砂糖とミルクがうまく混ざらなかった事がきっかけとなり、初めから砂糖とミルクを入れた状態でのコーヒーの提供が始められた

イノダコーヒも京都府内に何店舗があり、東京の大丸にも出店しているが拡大主義ではない。近くに三条店もあり、そこも大変しゃれているが現在改装中。私はこの本店が好きだ、庭が見えて、天井も高く、開放感があって上品な感じがして落ち着くのだ。

2022年9月に後継者不在を理由に事業承継を目的とした投資ファンド「アント・キャピタル・パートナーズ」が運営するファンドへの株式譲渡を発表し、ショックを受けた。





朝食後、今日は車で貴船(きぶね)に行くことにした。30分で到着する、市内よりは高地にあるため涼しい、9時前に到着して、運よく駐車場が空いていたのでそこに駐車し、貴船川沿いに歩いて貴船(きふね)神社本宮に向かう、地名の貴船は濁るが、神社の貴船は濁らない、これは、貴船神社は水の神様のため濁ってはいけないため。

貴船神社の入口の鳥居をくぐると本宮に続く階段があり、そこが写真の名所なっている。階段を昇って本殿に到着すると、本殿から上の山には木々のほかに水草、シダやツタのような水源の地によく生えている草ゝが鬱蒼と茂っていた、そして上のほうから水がしたたり落ちてきていた。

貴船神社は、全国に約500社ある貴船神社の総本宮、本宮の横に「由緒」が掲示されており、神社の始まりは不詳だが、第18代天皇の御代に奥宮の社殿を建てた記録があるので、日本でも指折りの古社に数えられる、とある。すごいところだ。

さらに、そこから奥に500メートルくらい歩くと奥宮があるので行ってみた。この本宮から奥宮までの川沿いには川床料理の料理屋がびっしりと並んでおり、もうすでに営業していた、道路沿いにはメニューが出ている店も多く、料理の値段はピンキリだが、5,000円くらいから利用できるようだ。

奥宮に参拝し、同じ道を歩いてまた駐車場のところまで戻った、奥宮にも駐車場があったが、ここは本宮の入口近くの駐車場に入れて、奥宮まで歩いたほうが新緑の景色をゆっくり楽しめるので良かったと感じた。


この後、すぐ近くの鞍馬に行ってみた、鞍馬駅前に駐車して駅の大きな天狗や駅舎内や叡山電車が到着するのを見た、この鞍馬が終点だ。電車から多くの観光客が降りてきた。



そのあと、鞍馬寺がすぐ横なので行ってみた、寺の山門を見上げる階段の入口がやはり観光ガイドブックによく出てくる景色である、何枚か写真を撮ったが、あとの予定も控えているので、それ以上は中に入らなかった







さて、貴船と鞍馬で午前の予定は終わり、次は昼食の予約を取ってある旧三井家下賀茂別邸に向かう、場所は下賀茂神社の一番南側、出町柳駅のすぐそばだ、そこに市営駐車場があるので車を停めて、別邸に向かう。

この別邸には誰でも入れる、もとは隣接する家庭裁判所も含めて三井家の財産だったが財閥解体で国の所有になり、家庭裁判所とその裁判所長の宿舎として利用されることになった、ただ、その宿舎は利用勝手が悪く、宿舎だけは何年か前から観光用の施設として民間に運営委託されていると説明してくれた。したがって、家庭裁判所は今でもあるし、財産は国の所有物だ。

この別邸では見学だけでなく、抹茶プランやランチプランがあり、お屋敷内の部屋で楽しめる。今回は初夏のランチプランを予約しておいた、見学だけの人は入れない2階のお座敷で京都の有名な仕出し料理屋「三友居」のお弁当を楽しむプランだ。


(庭園がよく見える大きなガラス窓が特徴)
時間が来ると2階に案内され、若干の説明の後、ゆっくりと庭園を見下ろしながら三友居のお弁当をいただいた、ビールなどお酒もオプションである


食後には、ガイドの男性と3階の望楼に昇った、この日の参加者は7名、望楼に入り景色を楽しみガイドの方のいろんな説明を聞き、写真を撮って楽しんだ。望楼からは大文字焼きの山や比叡山、別邸の庭園などが眺められ、天気も良かったので楽しめた。このガイドの方から、昨日行った真如寺は三井家の菩提寺だと教えてもらってびっくりした。

さて、また2階の部屋に戻り、今度は食後の茶菓が用意されていた、茶道のお茶碗に入れられた薄茶と鶴屋吉信のきれいでかわいらしい和菓子だ。

このランチプランは7,500円と少し高めだが、なかなか来られるところでもないので、払う価値は十分あると思った、観光客や外人さんが殺到しないことを祈りたい

別邸を後にしたのが午後2時過ぎ、飛行機の時間を考慮すると京都出発は4時少し前、そうすると観光できるのはあと1か所、出町柳の駅前で阿闍梨餅を買って、あとは車を停めたまま、バスで三条のカフェ、Tribute Coffee、に行くことにした。ここは比較的新しい店だと思う。

三条の交差点からすぐだが、ビルの3階にあるので少し不便だ、しかしテレビなどに出たため結構客が来ている、すぐに座れたので、アイスオレとプリンをたのんだ、若者が多いが、中高年の客も来ている。店はそれほど広くなく、店主と奥さんの二人でやっている感じで、忙しそうだ。

コーヒーを飲みながらこれから出町柳に戻り、車で伊丹空港までにどのくらい時間がかかるかGoogleマップで確認し、そのあと店を出た。

これで今回の京都の旅は終わりだが、計画したけど行けないところもあった、それは次回以降のお楽しみに取っておこう、京都は年に1回は訪問したい





(完)