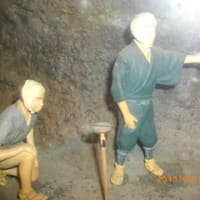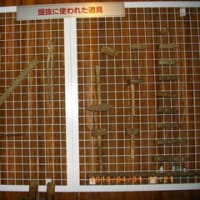前回(昨日)は、庄司の言語教育「体系化への構想おぼえがき」を、庄司自身に語らせて、「おぼえがき」の奥にある内容を展開してみました。「展開」というよりは、短いコトバで書かれているそれを、もっと具体的にときほぐすといったほうが的確なので、前回ブログのタイトルを修正しておきました。なぜこんな試みをしたのかを書いてみますと、「おぼえがき」は、庄司の学問づくりにとっては重要な機転になっていると感じてきたことが一つあります。これはメモ調の単語・短句・短文が箇条書きになったものですが、私が庄司の著書を理解しようとするとき、たびたび示唆をもらってきたという経験があったからです。ここには「なにかある」と感じてきたのです。このナゾを解いてみるために、箇条書きのおぼえがきの趣旨と繋がりを解釈し文章化してみようと思い立ったのです。二つめの理由は、「おぼえがき」もコトワザも、あるいは俳句なども、これを文章によって詳しく展開(ときほぐし)できるのはなぜなのか、を考える材料にしてみたかったのです。この疑問は、庄司のコトワザ「論理(学)」説を異なった側面から掘り下げることができるのではないかという直観と結びついています。この疑問を探る道も用意しておく必要がありました。ともあれ、今回は昨日の続き。庄司の「おぼえがき」の続きを綴ってみます。もちろん庄司口調を思い出しつつ、話題は、言語教育構想においてはどんな目標を設定するか、というものでした。
④言語の記憶技術能力を高める
今日は爽やかな天気ですな。・・・では、昨日の続き。われわれは日常の暮しでよく目にするモノ・大事なこと・忘れてはならないことをコトバよって記憶しようとしています。どうすればこの能力を高めることができるか。この目標にも原理があります。方法ノ工面ニヨッテ、語彙の習得がデキルという原理です。えーと、これは何でしたかな。五十年以上も前に書き記したことで、ハテ、・・・単に記憶術の工夫によって語彙をふやすことはここで考える、と書いたものだったのか。今となっては当時の趣意が思い出せませんナ。
記憶の技術(方法の開拓)の歴史を調べれば、思い出すかもしれませんが、ハッキリしているのは、ナゾナゾやコトワザなどには、前代からの記憶術がその表現の仕方に込められている事実です。まずナゾナゾ。(このフィクションでは掟破りになるけれど)これは後に「コトワザの論理と教育」(本書『コトワザの論理と認識理論』の第二部 二一頁)で整理した「ナゾナゾのもつ論理の周辺」を読み返してみて思い出しました。ナゾナゾというのは一種の「問題法」という教育方法なんです。単に教えたい事柄をストレートに子供に話すのではなく、問題を提示して答えを考えさせるというものです。今では、何かを教えようとするときには、教師でなくても「問題法」は民間に広く普及していますが、これは明治以後に西欧から移入されて、大正期に、子供みずからが考え問題を解いて進むという学習法として定着したと考えられるんです。ある事柄をただ知ることと比べ問題法はまず自分で考えるという点で答えの印象がまるで違いますね。これは一つの記憶法としてとらえていいわけですが、また考える技術としても見逃せないね。考える技術は仮説実験授業や予想実験授業において成功をみているといってよいです。
でもね、「問題法」は日本にもあったんですよ。子供のナゾナゾ遊びです。たとえば、「ヒトツ目小僧二足一本ナアニ?」なんてナゾナゾがありますね。子供からこういうナゾかけコトバを投げられると、ふつうの大人でもふと目の前が一瞬マックラになるでしょう。すでに知っているなら別ですが、答えが思いつかないからです。答えは「ぬい針」です、と聞くとナーンだとガッカリします。もう一つ出すと、「山でコイコイ畑でイヤイヤナアニ?」。これはどうでしょう。風に吹かれると、山ではススキの穂がオイデオイデしているように見え、畑ではサトイモの葉っぱが横揺れしてイヤイヤしているように見えます。この風景を思い起こすには山里の風景を見た経験がないとまず答えられません。これもまったく見当がつかいないマックラ状態です。反対に、ナゾナゾをつくるときというのは、非常に明快かつ楽しいものです。答えとなるモノを何かに似せて比喩をつくるのはそれほど難しくないし、そのモノを見たままを形容する仕方は観察しながらだからいくらでも考えつくし、どのような形容をすれば、相手が困るだろうとか、この程度ならば正答してくれるだろうか、など考えるのも楽しいものです。以前に子供に尋ねてみたところ、子供のナゾナゾつくりは、ナゾナゾ遊びと同時期に始まっていますナ。つくりやすいし楽しいんだね。
ナゾナゾに答える側でも、つくって問いかける側でも、そのモノを形容した感覚的な手がかりをもとにして問答をしているわけです。こういう遊びを繰り返していきますと、モノは別の見方ができるということが自然理に身につくだけではなく、モノは感覚的なコトバを結びつけて記憶しておけるという技術もこれまた自然理に身につけることできるのではないでしょうか。かくて、ナゾナゾ遊びは記憶術を養っているということができましょう。
コトワザのほうには、口拍子のよいおぼやすいものがたくさんありますね。特にボクが「知識コトワザ」よぶ種類のコトワザには、天気・生産関係など便利な知識がたくさんコトワザに込められ各地に伝承されています。「朝雨ニ傘イラズ」、「桃栗三年柿八年」、「尾﨑谷口淵の上」などがあります。最後など漢字熟語が三つ並んでいますが、これは苗字ではなく、地形名です。こういう場所は水害にあう可能性が多いから住むなという前代からのメッセージなんです。ほかに思惟(モノの見方考え方)をこめたコトワザも多数存しますから、これらも、大切な知識を保存する記憶術に含めていいのです。いわゆるの『記憶術』もいろいろ出ているようだけど、その積極面をすくいあげることが大切ですナ。人は、記憶術を使ってどのような問題解決をはかろうとしてきたのか。そこにはそれぞれの人生観が表われます。だから人生観教育にひとつでもあるんです。
⑤言語以前の感覚能力も高める
この目標の原理はね、われわれが人間以外の動物の心をどうつかむか、かれらの発する信号というものをどうつかむか、と考えることなんです。ただ考えるだけでなく、具体的に人間の身振り・素ぶりの示すものを手がかりに、人間のコトバ以前という世界を知ることなんです。これは、われわれの使っているコトバの内意を広くとらえることに繋がっていきます。たとえば、コトバにはならないけど、人間は目で感情を表現することができるし、身振りで自分の意志を相手に伝えることができますね。「せんせい、オシッコ」なんていわなくても、からだをモジモジさせていれば、トイレに行きたいと直ぐに分かるし、悪戯をした子供に説教しようと思っても、目をみれば素直に反省しようとしているか、反抗的になろうとしているか、すぐ分かりますね。後者の場合など、子供がそうせざるを得なかった「わけあり」だな、と予想できます。
一方で、犬に対して「シッシ、あっち行け」なんて言っても、犬はわからんでしょう。人間以外の動物を相手にすることは、人間のコトバの限界というものを教えてくれるわけです。しかし、先の例のように、人間同士でもコトバなしで何かを伝え合うことができるという経験は、これを手がかりに、人間以外の動物に対してその心を知る手がかりにすることができるんです。たとえば、聞いた話ですが、家で飼っている子犬が、オシッコしたいときには、閉まっているドアの前で行ったり来たりするそうです。また、その目をみれば、機嫌がいいのか悪いのかも直ぐに分かるそうです。こんなふうに考えると、犬のあいだにも通じる、意志や感情を伝える合図・信号というものが浮かびあがってきますね。このようにコトバというものをもっと広く合図・信号を含めたものとしてとらえると、コトバという存在、人間という存在を絶対視せずに済むでしょう。このような例は、言語以前の感受性と行動の問題として、どこかで子供たちに伝えたいものだと思います。長くなりました。もう一つ残っていますね。コトワザの世界です。
今回も晩年の庄司先生の面影をアタマに御浮かべながら綴ってみましたが、テンションが高くなるところをいささか忘れていたようです。語りが単調になってしまったことは否めません。さて、言語教育の「体系化への構想おぼえがき」における「(A)目標にしていきたいもの」をこれで二回ときほぐしてきました。「教育」のことですから、子供たちの「認識の発展」をいかに準備しいかに実現するかという研究の方向性がはじめからこの「おぼえがき」に込められているのは当然です。とすると、私が「三浦つとむからの学び、その核心」で整理したことの一つである「認識の発展」という問題意識は、どこの時点で、コトワザを考える場合にも再発見されるのだろうか。こういう疑問が毎日綴る自分の背中を押しています。