第二章の構成を紹介しておきましょう。「一 村の香 祭の香」、「二 小鍋立と鍋料理」、「三 米大切」、「四 魚調理法の変遷」、「五 野菜と塩」、「六 菓子と砂糖」、「七 肉食の新日本式」、「八 外で飯食う事」の計八つの節から構成されています。表題を眺めていると内容が幾つも浮んで来ますが、論理として統一された筋道はよみがえってはきません。これを可能にしたいものです。それはともかく柳田の表題の付け方は内容の論理を自覚すればするほど秀逸に感じます。いつもほれぼれします。こんなことを感じつつ読んでいけたらと思います。
「一村の香 祭の香」
柳田の「実験の歴史」という提案からみれば、誰でもが時代に変化を確認しやすい史料として感覚を取りあげるのはもっともなことです。我々の感覚は近代に入ってからどのような変化を見せるのか。「第一章 眼に映ずる世相」において、まず視覚(一部触覚)そして聴覚の変化を見てきました。その中から我々の「(時代は)もう、そうなってしまっている」といういささか没歴史的な生き方が浮彫りになってきたことを確かめてきました。「第二章 食物の個人自由」の冒頭を飾るこの節では、嗅覚を導入として触覚と味覚が史料として採用されていきます。ここでは五つの話から構成されています。
(1)まず現代(昭和)の世相から「物の香」を取りあげ、おいおいと整理される傾向にあることを指摘します。それは嗅ぐ能力の衰えという事実です。なぜ現代になって嗅覚は衰えたのか。その疑問が提示されます。「問題の共同」の成立です。ここで「問題」とは疑問に含まれるテーマのことです。とはいえ、このような疑問は逐一記述されるわけではないので補って読んでいくしかありません。
(2)そこで最初の疑問(問題)を小分けして考えていきます。最初に考えるべきは、我々の以前の嗅覚はどうであったかです。前代の嗅覚のありようを我々の問題として調べていくのです。柳田は我々は以前この鼻の感覚によって大切な人生を学び味わっていたと述べます。この歴史的事実はどこから得られるのか。柳田は田舎を歩けばわかると述べ、日本アルプスの案内人のエピソードをとりあげていきます。
≪おねの曲り目に立ってこの沢には人が入っている。この沢には誰もいないということを、一言で言い当てる者がいくらもいる。わずかな小屋の煙が谷底から昇って、澄み切った大気の中に交じっているのを、容易く嗅ぎつけることができるからである。≫
このような鼻の感覚経験をなにか機械や推理や計算によって補充するのは不可能に近いと柳田は述べ、この点から言えば近代文明人は愚かになったと言います。これは一つの文明批評ですが、これと似た事例は他にもあると仄めかしています。では鼻の能力を衰えさせた原因はどこのあるか。その一つは煙草だと言います。近世になると煙草の香はきつくなり、分量も増えました。我々はそのほとんどが、鼻から煙草の煙を吹き出すことに興味をもっている。人の嗅覚はこれによって絶えず刺戟され、ついに他のいろいろな微々たる雑臭を嗅ぎ逃している。つまり最初はこの一種の強烈な香気の統一の急迫から逃れようとしたが、後にはかえって全体の嗅覚を支配され、衰えることになったというわけです。ここに一つの回答が記されますが、疑問はさらに展開してゆきます。
(3)煙草が周囲の嗅覚に与えた影響が小さくなかったことは、「村の香」についても影響を与えました。嗅覚の衰えは、人をして「祖先以来の生活に、深い由緒ももつ数々の物の香」から、なんの思い出もなく別れることを可能にしました。たまたま忘れがたき愛着を抱く離郷者がいても、都会ではこれを語り合う方便を持たなかったのです。しかし、村に育った者ならば思い出すことができる、そう柳田は言い切ります。ただ忘れているだけなのです。村の香とは、どのような香だったのでしょうか。こう記しています。
≪たとえば盆と春秋の彼岸の頃に、里にも野山にも充ち渡る線香の煙は、幼ない者にまで眼に見えぬあの世を感じさせた。休みや人寄(ひとよせ)の日の朝の庭を掃き清めた土の香というものは、妙に我々の心を晴れがましゅうしたものであった。作業の方面においても、碓場・俵場の穀類の軽い埃には、口では現わせない数々の慰安があり、厩の戸口で萎れて行く朝草のにおいには、甘い昼寝の夢の聯想があったが、やはり何と言っても雄弁なのは火と食物の香であった。≫
非常に印象深い一節です。線香の香に結びついたあの世の消息、朝の掃き清めた土の香から感じた晴れがましさ、穀物の埃から感じた慰安など、どれもこれも自分の過去を思い出させてくれる文章です。村に育った者には心あたりがあるのです。しかし、何と言っても雄弁なのが「火と食物の香」。この香はどんな思い出に結びついていたのでしょうか。柳田はその香は「無始の昔以来人類をその産土に繋いでいた力」だったと述べます。つまり火と食物の香は、産土(うぶすな)すなわち生まれた土地の思い出に繋がっていたのです。
(4)柳田は、鼻は要するに産土に繋がる力を嗅ぐために備わったものだ、そこまで言います。それには根拠があるのです。村ではいろいろの火と食物の香を統一する技術が、無意識のうちに養われてきたと記し、以下のように村の暮らしを説いていきます。
≪食物はもとは季節のもので、時を過ぐればどこにもないと同様に、隣で食う晩はまたわが家でも食っていた。これはひとり沢に採り、畠に掘り起こすものが一つだというばかりでなかった。遠く商人の売りに来る海の物でも、買うて食おうという日には申し合わせて買い入れる。臨時の獲物は豊かなるがゆえに頒たれたのみではなく、どれほどわずかであっても、こっそりとは食わぬことが人情と言うよりはむしろ作法であった。人を仲間とよその者に区別する、最初の標準はここにあった。≫
つまり、火と食物に関するさまざまな香を統一して産土に結びつける技術が述べられていますが、要諦は「こっそりとは食わぬ」という作法にあったことです。私などにもこの感覚が残っています。それは「尾骶骨的心情」(庄司和晃)とよんでいいもので、遠くの知り合いから名産を送って貰ったときなど、わが家だけで食べてしまうのはふだんから親しい付き合いのある隣近所に対して、いささか後ろめたさがともないます。又、滅多に口に入らないお菓子などを購入したときにも、家で一人で食べるのは家の者に対して後ろめたさを感じます。しかし、ふだんから付き合いのない隣近所やまったくの他人に対しては、同じ場所にいてさえ後ろめたさなど感じることはありません。不思議なものです。「こっそりとは食わぬ」作法は確かによそ者と仲間に分ける基準に相違ありません。現在でも納得できる指摘です。このような作法は近代になるにつれて崩れていきます。柳田の言葉を使えば、「竈が小さく別れる」時代になるのです。こういう時代になっても残っていたのは「祭の香」です、これについても統一する技術の養われ方を説いています。
≪竈が小さく別れてから後も、村の香はまだ久しく一つであった。ことに大小の節(せち)の日は、土地によっては一年に五十度もあって、その日にこしらえる食品は軒並みに同じであった。三月節供の乾貝や蒜膾(ひるなます)、秋は新米の香に鮓(すし)を漬け、甘酒を仕込んで祭の客の来るのを待っている。特に香気の高く揚がるものを選んで用意するということもなかったろうが、ちょうど瓶(かめ)を開け鮓桶をこれへという時限までが、どの家もほぼ一致していたために、すなわち祭礼の気分は村の内に漾(ただよ)い溢れたのであった。≫
竈(かまど)が小さく別れてから後も、「同じ食品をおおよそ同じ時刻に作る」という作法によって、祭の香は統一されていたのですが、さらに時代が変わっていきます。どう変わっていったのでしょうか。
(5)祭の香は地方によって少しずつ差異があったけれども、これを互いに比べてみる機会がありません。比べない故に、祭の香の記憶は固有のものとして顕著だけれども、祭の香といえば普通こういうものだ、という感覚しか残りません。それぞれの香自体に色の場合のように名前でもあったら、香の記憶が保存されたかもしれません。だから、思い出すときはただ「○○の香」と呼ぶだけです。
そのうちに時代が「少しずつその内容を更(か)え、かつ混乱をもってその印象を幽かならしめた」ために、多様だった祭の香は、「だいたいにおいては空漠たるただ一つの台所の香」になってしまったのです。柳田は「一 村の香 祭の香」をこう締め括っています。
≪そうして、家々の空気は、互いに相異なるものと化して、いたずらに我々の好奇心だけを刺戟する。これが鼻によって実験せられたる日本の新たなる世相であった。≫
こう締め括っているわけですが、最後の一文にもあるように、この節の目的は、世相の史的解説にありました。現代の世相の一面から、誰にも身に覚えのある嗅覚の衰えを問題化(疑問の設定)して、我々(仲間)の問題としてその由来を説くのです。その説き方は全体の輪郭を与えるものといってよく、この節は概論的位置づけになり、各論は次節以降ということになり、焦点化されるのは、「竈が小さく別れて」いく時代,すなわち近代化の時代です。
さて、ここで少し考えておきたいのは「問題の共同」における前代と近代の区別に関することです。前代社会とは近世を指しますが、これが近代社会と決定的に異なるのは個人の自由が社会理念の主柱に置かれているかどうかです。もちろんこの自由がどの程度実現されているかは捨象しています。とすると、「問題の共同」の要件である他人と自分(社会と自分)の関係を、二つの社会について見た場合どういう違いがあるかという問いになります。
まず前代社会における構成員は、その実存様式がそのまま家や一族・・・社会の構成員になるという特徴を持っています。たとえば結婚。前代社会では婚姻の自由はないといっていいでしょう。自分の好きなひとと結婚する自由はなく、それは家同士の問題、姻戚によって一族の構成員たりうるかという問題でした。つまり個人は家(社会)と重なっていたのです。いいかえれば前代社会においては、個人はさまざまな規範によって拘束されていたわけです。一方、近代社会では階層によって違うでしょうが、その初期でさえ一般に婚姻の自由はある程度認められていたといってよいでしょう。つまり結婚は個人間の問題であり、家(社会)とは分離しているのです。言い換えれば、個人はさまざまな拘束から解かれた自由な存在なのです。ほかに職業選択や移動の問題についても同じように区別することができます。
以上の区別を踏まえたとき、同じく「問題の共同」といっても扱いが異なってきます。前代社会を前提にする場合には、個人は他(他人・家・・・社会)の問題に重なっている自分を発見すればよく、近代社会を前提にすれば、個人は他(他人・家・・・社会)の問題にどう繋がっていけるか、つまり公民としての生き方を考えることが必要になってくるはずです。第一節の記述は前代における問題の共同が語られています。次節からは近代における問題の共同が中心になっていきます。近代社会における他人はどう仲間に繋がっていくのか、ここを逃さないように読んでいこうと思います。(続く)














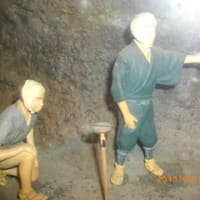




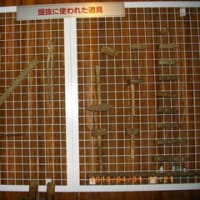
A.日本人の嗅覚の変遷
1.前代まで
ア.大きく言うと
① 嗅覚は情報入手の重要手段であった。
② 日本人は嗅覚によって大切な人生を味わっていた。
イ.詳しく見ると
① 匂いを元に、それに付随する生活や心持ちを連想することができた(特に火と食物の匂い)。
② 食物は季節やその土地と結びついていた。つまり得難いものであった。
③ 得難い食物は分かち合うという「作法」が共同体にはあった。
2.近代以降
ア.大きく言うと
① 嗅覚が現代になって衰えた。それは共同の問題である。
イ.詳しく見ると
① 強い匂い(煙草など)の導入が嗅覚を衰えさせた(柳田のこの説は疑問:いざわ君の感想)。
② 各戸の「竈が別れる」と共に食物を分かち合う「作法」は弱まり、共同の匂いも衰退していった。
③ しかし祭という共同体行事においてのみ、食物を分かち合う「作法」が存続した。
④ 物資の流通や祭の衰退、共同体の衰退によって祭りの「個別性」が失われていったのだろう(いざわ君の意見)。
⑤ 共同体の香りは失われ匂いは個々人の好奇心と結びつくだけのものになった。
B.嗅覚の変遷から考えられる現代の共同の問題の見方
ア.前代:個人は社会構成員としての個人でしかなかった。つまり個人は1つだけ。
近代:社会構成員としての個人と、社会構成員ではない自由な個人の2つの個人となった。
イ.「社会構成員としての個人」としての社会との関わり方、そこに共同の問題が発生する。