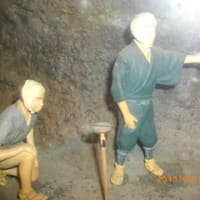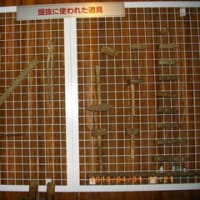前二回(10/10、10/17)は、朝鮮通信使中官・崔天宗を殺害した対馬藩通詞・鈴木伝蔵の二つの言い分を紹介しました。一つは崔天宗と「日本の恥辱」をめぐって争論があり衆人環視のなかで打擲されたこと、二つはそのような場合はどうすればいいか「対馬藩の掟」があり、それを熟知している人々の面前で打擲されたのでやむを得ず殺害したこと。幕府の取り調べでは、衆人環視のなかで打擲されたという事実は認定されず、「対馬藩の掟」の存在も藩自身によって否定されました。この中途半端な取り調べからわかるのは、幕府は初めから処刑ありきであって伝蔵が殺害に及んだ正当性などは問題外だったということです。つまり、10/3のブログで紹介したように幕府の狙いは対馬藩の不手際・管理責任だったのです。これに対して対馬藩側はどのように対処したのでしょうか。
≪これに対して対馬藩の対馬藩の側は、崔天宗殺害事件は起るべくして起きた事件であると捉えている。鈴木伝蔵と崔天宗とのあいだには争論があり、しかも事件を引き起こした要因は朝鮮側にあるのであって、対馬藩側に越度があるとされるのは承伏しがたいとの立場である。
たとえば八月六日、対馬藩国元家老小野典膳が以酊庵(イテイアン)僧に対して次のように述べる。朝鮮通信使来日の度ごとに日朝双方ともに国法を守り礼儀を正し、非法の無いようにして紛争発生を回避するように申合せを取り交わしている。にもかかわらず。今回の事件に至ったのは、崔天宗が打擲するなどという過ちをおかしたからなのであって、申し合わせ破った朝鮮側が誤っていると主張する。またこの間対馬藩国元にあった御隠居様(前藩主宗義蕃)は、八月十九日付で江戸家老へ宛てて書簡を送り、この間の幕府の態度は朝鮮の動向を配慮しすぎであって、対馬藩の越度であるとする大坂一件ついての幕府の処理を批判している[慶応119](第二章)。こうした点からも崔天宗殺害事件の処理をめぐっては、幕府と対馬藩との間に懸隔があったといえよう。
ところでそうした懸隔は、実はこの八月に発覚する問題によって増幅されていく。それは、鈴木伝蔵一件に関する最終的な裁許内容を朝鮮側に伝達するという問題である。この「伝達問題」は、すべての裁許が済まないうちに帰国せねばならなかった通信使側の要望に基づくものであった。そして五月はじめの段階では、そうした通信使側の要望にもかかわらず、大阪城代は伝達しないことを明言しており(第一節(2))、その旨は対馬藩にも伝えられていた。ところが対馬藩には一切知らせないままに、幕府はおそくとも七月初めまでには先の方針を転換し、裁許結果を朝鮮へ伝えることに決する。老中松平右近将監武元らが以酊庵僧に「伝達」を依頼するのが、江戸の日付で七月一一日のことである[慶応119]。崔天宗殺害事件後の朝鮮政府での動静を気遣っていた幕府は、裁許結果の伝達が幕府と朝鮮との間の友好関係の維持に資すると判断したもののようである。
この「伝達問題」について対馬以酊庵僧から対馬藩国元家老小野典膳にうちあけられるのが八月六日のことである。その後小野典膳と以酊庵僧との間で度々会談が繰り返され、しかも藩側からの一方的かつ激烈な意見表明がなされる。対馬藩の国元と江戸藩邸とはその対応に追われる。八月一六日には今回の「伝達」一件に関しての対馬藩側の意向を幕府に伝えるために、使者俵忠右衛門が国元を発って江戸家老古川大炊のもとへ赴く。次に示すのはその時に携えた老中に対する意見書の草案であり、ここには藩の意見が集約されている[慶応119]。≫(池内敏『「唐人殺し」の世界──近世民衆の朝鮮認識』臨川選書 一九九九 三五、四〇~一頁)
朝鮮に気兼する幕府の起した「伝達問題」に対する対馬藩の対応は、対朝鮮外交を一手に担ってきた矜恃と、実際交渉の豊富な経験に裏づけられたまっとうな反論だったことが知れます。また、朝鮮とのふだんの交渉はどうなのか。そこにおける互いの民族観はどうだったのかを知りたいところです。次回は対馬藩の「意見書の草案」を読んでいきます。