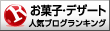京都の金剛能楽堂さんで野村萬斎さんのござる乃座の公演を観てきました。
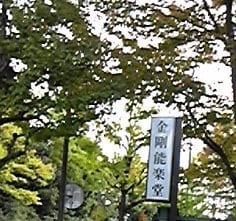
名古屋のござるは毎年観劇させていただいているんですが、京都での公演は今回初めてです。
今年のござるは「花子」の連続上演という事で、名古屋とは違う形での上演だったのと、京都の非公開文化財の特別公開時期が重なり、京都が満喫できそうだったので、チケット購入しました。
久しぶりの金剛さん、やはり、茂山家の時とは雰囲気が違う気が。
でも、京都で萬斎さんの狂言会を観るなんてなんだか不思議。
さて、公演です。
「花子」は能の「班女」のパロディと言われる事から「花子」上演の前に金剛龍謹さんの舞囃子「班女」が上演されました。

能楽師の方の舞囃子を拝見するのは多分初めて。
足拍子は力強いのにその動きには重量感が全く感じられないのに存在感がある・・・。
そのたたづまいが何とも美しくてかなりガン見状態に。
おかげでかなり疲れたのですが、能の装束を付けた状態での舞とはまた違う美しさがあり感動しました。
そして、草の形の萬斎さんの「花子」。
私的にはこの草の形が一番好きかも。
プログラムに近年、真、行、草のすべてを演じた狂言師はいないとありましたが、以前にも書いた通りこの「花子」は萬斎さんに似合う曲だと思うので、又、機会があったら、連続上演でなくてもかまわないので上演していただきたいです。
万作さんがシテをされた「福の神」では地謡に萬斎さんが参加されていました。
萬斎さんの狂言会で、萬斎さんが地謡をされる姿を観るのは珍しいのではと思いました。
ちょっと貴重な光景だったかも。
狂言会前に京都の街を歩いていたので開演ギリギリに能楽堂に到着したり、休憩時間もトイレの回転が悪くてあまりゆっくり能楽堂の雰囲気を味わえなかったのがちょっと残念でしたが、最前列という良席で、大満足の狂言会となりました。
来年も演目によっては京都にも来ようかな。
そんな京都から家に帰ったら、来年の名古屋での「万作を観る会」のチケット確保通知が届いてました。
メインは万作さんによる「木六駄」です。
「木六駄」を初めて拝見したのは萬斎さんの披きの時だったと思いますが、その後、上演回数も少ないですし、もしかすると万作さんの「木六駄」を拝見するのは初めてかもしれません。
かなり長い曲ですが、久しぶりの牛追いを楽しみにしています。

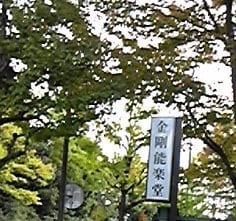
名古屋のござるは毎年観劇させていただいているんですが、京都での公演は今回初めてです。
今年のござるは「花子」の連続上演という事で、名古屋とは違う形での上演だったのと、京都の非公開文化財の特別公開時期が重なり、京都が満喫できそうだったので、チケット購入しました。

久しぶりの金剛さん、やはり、茂山家の時とは雰囲気が違う気が。
でも、京都で萬斎さんの狂言会を観るなんてなんだか不思議。

さて、公演です。
「花子」は能の「班女」のパロディと言われる事から「花子」上演の前に金剛龍謹さんの舞囃子「班女」が上演されました。

能楽師の方の舞囃子を拝見するのは多分初めて。

足拍子は力強いのにその動きには重量感が全く感じられないのに存在感がある・・・。
そのたたづまいが何とも美しくてかなりガン見状態に。

おかげでかなり疲れたのですが、能の装束を付けた状態での舞とはまた違う美しさがあり感動しました。

そして、草の形の萬斎さんの「花子」。
私的にはこの草の形が一番好きかも。

プログラムに近年、真、行、草のすべてを演じた狂言師はいないとありましたが、以前にも書いた通りこの「花子」は萬斎さんに似合う曲だと思うので、又、機会があったら、連続上演でなくてもかまわないので上演していただきたいです。

万作さんがシテをされた「福の神」では地謡に萬斎さんが参加されていました。
萬斎さんの狂言会で、萬斎さんが地謡をされる姿を観るのは珍しいのではと思いました。
ちょっと貴重な光景だったかも。

狂言会前に京都の街を歩いていたので開演ギリギリに能楽堂に到着したり、休憩時間もトイレの回転が悪くてあまりゆっくり能楽堂の雰囲気を味わえなかったのがちょっと残念でしたが、最前列という良席で、大満足の狂言会となりました。

来年も演目によっては京都にも来ようかな。

そんな京都から家に帰ったら、来年の名古屋での「万作を観る会」のチケット確保通知が届いてました。

メインは万作さんによる「木六駄」です。
「木六駄」を初めて拝見したのは萬斎さんの披きの時だったと思いますが、その後、上演回数も少ないですし、もしかすると万作さんの「木六駄」を拝見するのは初めてかもしれません。
かなり長い曲ですが、久しぶりの牛追いを楽しみにしています。