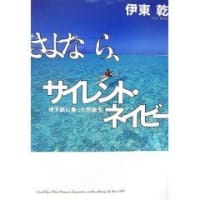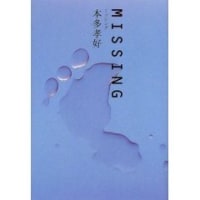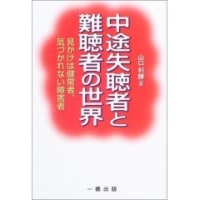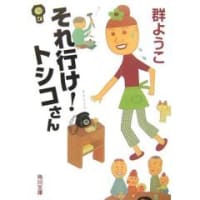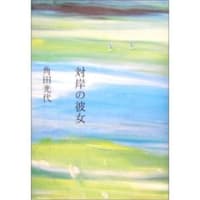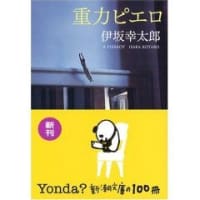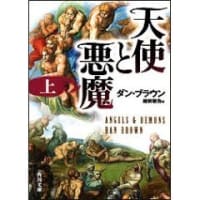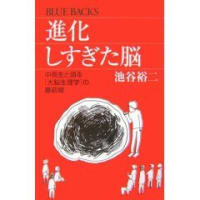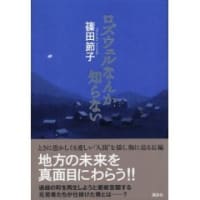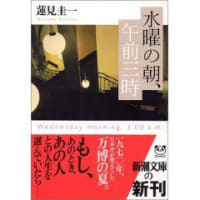これを第二十三師団にかぎっていえば、師団軍医部の調査によると事件の全期間をとおして、出動人員1万5975人中の損耗(戦死傷病)は1万2230人、実に76パーセントに達したという、実質の損耗率はもっと大きいともいわれる。ちなみに日露戦争の遼陽会戦の師匠率が17パーセント、太平洋戦争中もっとも悲惨といわれるガダルカナル会戦の死傷率が34パーセント。この草原での戦闘の過酷さがこれによってもよく偲ばれる。
 |
ノモンハンの夏 (文春文庫) |
| 半藤 一利 | |
| 文藝春秋 |
以前、自分では注文した(記録はあるが)記憶がないのに、Amazonから届いた一冊で、間違って押しちゃったかなぁとそのまま放置して忘れていたました。先月、図書館通いがちょっと途切れてしまい読む本がなくなったときに、本棚をゴソゴソ探していて見つけて読みました。
半藤一利氏の「昭和史」は以前読みましたが、記憶力の悪い私には、はっきりいって「ノモンハン」ってなんだっけ???というレベル。
とりあえず、ノモンハン事件とは、(Wikipediaから抜粋です)
1939年(昭和14年)5月から同年9月にかけて、満州国とモンゴル人民共和国の間の国境線をめぐって発生した日ソ両軍の国境紛争事件。
私が内容を知らないのも当然、と胸を張れる訳ではないのですが、土門修周平の解説によると、戦中から戦後にかけて、きちんと研究されたものは少ないとのこと。
司馬遼太郎氏が書こうとされていたものの、急逝により果たせず、当時文芸春秋の編集者であった半藤氏が一緒に調査されたという経緯もあって、引き継いだということのようです。
本書中、陸軍は参謀本部も、関東軍もまぁボロクソに書かれております。
当時は、天津事件のあと国民の対英感情は悪化の一途、ドイツとの同盟に向けて陸軍は賛成、海軍は反対の立場で、政治家は決断できずおろおろするばかり。しびれをきらしたドイツはソ連と不可侵条約を成立させたため、スターリンは極東に力を入れ始める。
というような世界の情勢があるにもかかわらず、現地の関東軍は、そういった情報に驚くほど無頓着で、目の前の何もない草原にあるようなないような国境線をめぐって暴走を始める。東京の参謀本部では紛争を起こすな、拡げるなと指示は出すものの、結局は止められず、起こってしまったことを、追認するような格好で、ずるずると日本軍だけでも一万人近い戦死者をだしてしまったのです。
軍人はだれしも、将兵が血を流した地をむざむざ敵には渡せない、という論理の前にはひたすら頭を下げざるを得ない。理非曲直は抜きで、その言葉は直截に彼らの精神にせまってくるからである。これに反対することはできない。
ということなんですね。
しかし、著者があまりにもボロクソに書くもので、もしかしてかなり偏ってる???と心配になりますが、上記の通り自分には知識がありませんのでなんとも言えません。
ただ、本書を読みながら感じたのは、日本人って実はちっとも変っていないんだなってこと。
首相は調整役でしかなく、政治家は何も決められない・・・。
国民はメディアがつくる世論の一翼を担わされるだけ。
自分たちが国を背負って立っているんだという軍人の危機感が、良い方に働けばいいんでしょうが、真のリーダが不在で、暴走したら止められない。
そして、”情報戦”に弱い。
軍人を官僚に置き換えれば、または、ある種の”経済人”に置き換えて見れば現代と何も変わらないような。
本書の中で、本当に興味深い一節がありました。
日露戦争後、参謀本部で戦死が編纂されることになったとき、高級指揮官の少なからぬものがあるまじき指摘をしたという。
「日本兵は戦争においてあまり精神力が強くない特性を持っている。しかし、このことを戦死に書き残すことは弊害がある。ゆえに戦史はきれい事のみを書きしるし、精神力の強かった面を強調し、その事を将来軍隊教育にあって強く要求することが肝心である。」
なんということか。日露戦史には、こうして真実は記載されなかった。つまり戦争をなんとか勝利で終えたとき、日本人は不思議なくらいリアリズムをうしなってしまったのである。そして夢想した。それからはいらざる精神主義の謳歌と強要となる。
私はこれを読んで、やっぱりフクシマのことを思い出してしまいました。(連日で申し訳ありません。)
フクシマは、これまでの原子力ムラの、そしてそれを信じてついてきた日本国民の敗戦だったのではなかったのでしょうか。戦後、それまで信じていた軍隊への信頼を失った日本国民は、技術や科学に希望と信頼を寄せるようになった。確かにそれらは日本に平和と経済的繁栄をもたらした。
けれど、70年後その戦にも負けたのでは・・・。緒戦かもしれませんが、象徴的であったと、将来振り返ることになるような気がします。
だからこそ、ここから学ばないといけないのに、”原子力ムラ”のエリートたちは、自分たちの価値観を変えず、これまでに得た地をむざむざと敵(って誰?)に明け渡せないと必死になっているように見えるのです。
フクシマを敗戦ととらえると、国民には、二度と戦争をしないため軍隊を持たないという選択肢もある一方、反省の上に立って、もう一度一から立て直すという選択肢ももちろんあります。
でも、真実から目を背けて、反省という視点に立たず、過去の勝利の栄光を忘れられずに(安全という)神話を信じ続けて、敵(?)の変容から目を背けているとしか思えない状況・・・。
とにかく、歴史から、そして目の前で繰り広げられている歴史から学ばないと、手遅れになる・・・そんなことを思った一冊でした。