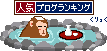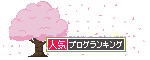私が古書の中でも特に好きなのは、前に持っていた方が一番愛読なさったページのところが自然にパラっと開くような本なのです。
へレーン・ハンフ 編著 江藤淳 訳
副題、”書物を愛する人のための本” です。
この本に出てくる、イギリス文学はひとつも読んだ事の無い私ですが、とても楽しく読むことが出来ました。
ニューヨーク在住の脚本家ヘレーン・ハンフ女史と、ロンドンのチャリングクロス街の古書店で働くフランク・ドエル氏の間に1949年から20年にわたってやり取りされた手紙が集められているのです。
まずイギリス文学に造詣が深いアメリカ人の著者は、ニューヨークで彼女の望む本が見つからないため、雑誌の広告で見たロンドンのマークス社から本を買い始めます。
彼女のマニアックな希望をきちんと叶えてくれるフランクとの間には、手紙を通じて、友情が芽生えていきます。そして、ロンドンでは1949年当時食料が配給制だったようで、そのことを知った、ヘレーンが何かにつけて、店に食料を送るようになります。
そして、マークス社の他の従業員やフランクの妻とも手紙のやりとりが始まります。
何が面白いの?と言われたら、よくわからないのですが、もう、ただ読んでいるだけでワクワクするのです。この気持ちをどうしても書き留めたくて、放置しているこのブログに記事をアップしてしまいます。
読みながら、本の装丁や、紙の手触り、そして古書店独特の匂いが感じられるようでした。
読後、映画も見ました。
本を読んで映画をみると、だいたいがっかりするのですが、この作品は、本の世界をそのまま映像にしたような感じで、世界観を損ねるどころか、見終わった時の幸福感をどうやって伝えればよいのかしら・・・。
そして、江藤淳氏による解説が、また読んでいて楽しい。
「チャリングクロス街84番地」を読む人々は、書物と言うものの本来あるべき姿を思い、真に書物を愛する人々がどのような人々であるかを思い、そういう人々の心が奏でた善意の音楽を聴くであろう。世の中が荒れ果て、悪意と敵意に占領され、人と人とのあいだの信頼が軽んじられるような風潮がさかんな現代にあってこそ、このようなささやかな本の存在意義は大きいように思われる。
1972年3月 江藤 淳
もう、この時の”現代”ですら、半世紀近く前になるのです。
ロンドンに観光に行くなら、あらかじめ計画を立てて行けば、見たいと思うものが必ずみられるのですって。私、イギリス文学のイギリスが見てみたいと言いましたら、彼、「だったら、必ず見られる」って言ってましたわ。(1950年4月)
ヘレーンがフランクの秘書のセシリーに送った手紙の中の一文ですが、今のロンドンもまだそうなのでしょうか。
ロンドンに行ってみたくなりました。(でもちょっと怖い)
追記:
実はこの本は旦那(豪州人)から教えてもらったのです。(旦那は本ではなく映画を見ただけなんですが、)
さほど本好きでもない彼にとって、この映画のどこがよかったのかと思い、聞いてみたところ、”昔のイギリス映画にある、古風な趣(quaintness)”がよかったらしいのです。
それってどういう意味??と考えて、思い出したのがスティングの「イングリッシュマン イン ニューヨーク」
I'm an alien I'm a legal alien
I'm an Englishman in New York
というフレーズ♪は、聞けば、皆さん聞いたことある~って思うはずの名曲ですよね。
alien(エーリアン)には単純に外国人と言う意味もありますが、やはり異分子というか、宇宙人につながるようなベクトルをもった言葉なんでしょうね。
確かに、フランクがニューヨークを歩けば、まさにそんな気持ちになるかもしれません。
フランクの博識なのに、それを見せびらかさず、控えめで、律儀な人柄。そしてヘレーンは自分でもガサツと言っているこれぞアメリカ人ぽい女性。
けれども、文学と文通を通じてこの二人の間に友情が生まれたというところが、アメリカ人、イギリス人共に受けたのかもしれません。
長年好きだった、スティングの名曲もより深く理解できた気がして、益々読書って楽しいと思えました。