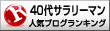結婚式にはタブーと言われる言葉がたくさんあります。
「別れる」「死」「切る」「破れる」などです。
主に、離別や不幸を連想させるような言葉は忌み嫌われます。
「ケーキをナイフで切る」ではなく、「ケーキにナイフを入れる」あるいは「ケーキ入刀」というくらいです。
この感覚は、英語の世界にはあまりありません。
たとえば「死」は結婚式でタブーの言葉ではありません。
結婚の時に、新郎新婦の誓いの言葉の中にすら「死」は登場します。
in sickness and in health,
till death do us part
病める時も健やかなる時も
死するまでともに過ごす
日本の感覚をあてはめると、わざわざ「死するまで」という不吉な言い方をするのではなく、「一生」とか「いつまでも」とか「永遠に」とか、前向きな表現にすればいいではないか、と突っ込まれそうな表現です。
しかし、主にキリスト教文化圏である英語の世界では、死は神様に召されるステップであり、受け入れるべき現実であり、特にそれを結婚式で口にすることが不吉であったり失礼であったりするものではないようです。
古来日本では、言霊(ことだま)という言葉がありました。
言葉には霊力が宿っていて、言葉を口にするとそれが現実のものとなったり、現実の世界に影響を与えるという考え方です。
そういう考え方がある社会では、不用意な言葉を発すると、不吉なことが起きかねない、だから縁起の悪い言葉は慎むべきだ、と考えられるようになるのです。
もちろん、現代の日本人は、結婚式で誰かが「死」という言葉を使ったから、すぐに誰かが死ぬなんて思っていませんが、それでも忌み言葉として「死」や「別れる」を結婚式などで避ける背景には、日本人の言葉に対するデリケートなセンスがあるのでしょう。
「別れる」「死」「切る」「破れる」などです。
主に、離別や不幸を連想させるような言葉は忌み嫌われます。
「ケーキをナイフで切る」ではなく、「ケーキにナイフを入れる」あるいは「ケーキ入刀」というくらいです。
この感覚は、英語の世界にはあまりありません。
たとえば「死」は結婚式でタブーの言葉ではありません。
結婚の時に、新郎新婦の誓いの言葉の中にすら「死」は登場します。
in sickness and in health,
till death do us part
病める時も健やかなる時も
死するまでともに過ごす
日本の感覚をあてはめると、わざわざ「死するまで」という不吉な言い方をするのではなく、「一生」とか「いつまでも」とか「永遠に」とか、前向きな表現にすればいいではないか、と突っ込まれそうな表現です。
しかし、主にキリスト教文化圏である英語の世界では、死は神様に召されるステップであり、受け入れるべき現実であり、特にそれを結婚式で口にすることが不吉であったり失礼であったりするものではないようです。
古来日本では、言霊(ことだま)という言葉がありました。
言葉には霊力が宿っていて、言葉を口にするとそれが現実のものとなったり、現実の世界に影響を与えるという考え方です。
そういう考え方がある社会では、不用意な言葉を発すると、不吉なことが起きかねない、だから縁起の悪い言葉は慎むべきだ、と考えられるようになるのです。
もちろん、現代の日本人は、結婚式で誰かが「死」という言葉を使ったから、すぐに誰かが死ぬなんて思っていませんが、それでも忌み言葉として「死」や「別れる」を結婚式などで避ける背景には、日本人の言葉に対するデリケートなセンスがあるのでしょう。