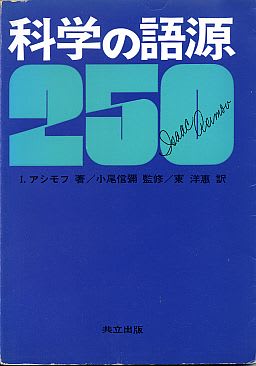
大栗博司さん言うところの「物理学界の曲芸師」ファインマンさんの『ファインマンさん、力学を語る』を読んでいて、ふつふつと疑問が沸き上がって来ました。「楕円の「楕」ってなあに?」ということ。この本では惑星の軌道が楕円をなす事を微分方程式ではなく初等幾何学の方法で示す事を目的としています。英語ならば楕円はellipseで語源はアイザック・アシモフの『科学の語源250』には以下のように記されています。
この扁平な円というのは、紀元前250年頃にアッポロニウスによって説かれた。三つの関連ある幾何学図形のうちの一つである。それぞれについて彼は数学上の記述を行なっているが、三つの中で記述の価値がもっとも少ないのが、この扁平な円に関してであった。この場合には他とくらべて不十分である。"不十分な"の意をギリシャ語で"elleipsis"ということから、この曲線はellipse<楕円>と呼ばれた。
アシモフさんの説明をそのまま信じるほど私はお人よしではありません。「記述の価値がもっとも少ない」と思うのは『円錐曲線論』のある読者であって著者がそう思ったからではないでしょう。やはり『円錐曲線論』を参照する必要があります。手持ちの「現代ギリシア語辞典」も参照しましたが、英語での初出はOEDで調べることになるでしょう。
当初の疑問に立ち返ると、漢字文化圏では楕円の「楕」とはどんな意味を持っていたのでしょうか?まず木偏である理由です。次いで、この様な数学用語は和製漢語である可能性が高いと予想しました。ある人から聞いた話では「中華人民共和国」のうちメイド・イン・チャイナは中華だけで、人民も共和国もメイド・イン・ジャパンだそうです。
Web上の漢和辞典は非力なので、手持ちの『大字典』(上田萬年編集)を見ると「車中におく一の器、小判形をなす故に長円形の義とす 木は義を示し隋(ダ)は音符。」とありました。木製の器なので木偏であると分かりますが、車中で使う器とは何でしょうか?疑問は深まるばかりです。
電車の外側に付いているボタンを押してドアを開ける湘南新宿ラインに乗って東京に出かけた折りに、某出版社の社長にこの疑問をぶつけると、「楕円は堕落した円だよ」と鋭い冗談を飛ばしながら小学館の日本国語大辞典(通称にっこく)の当該個所のコピーをとってくれました。OEDを目標とした辞書だけあって楕円と言う言葉の用例が載っていました。
※暦象新書─大陰も楕円を画するとも、殊に種々の変動あるは、時々に地の離日と同じことによりて生ず
貴重な情報でした。『暦象新書』は日本で最初にニュートン力学を理解して紹介した志筑忠雄(しづき ただお、宝暦10年(1760年) - 文化3年7月3日(1806年8月16日))の著作である事だけは知っていましたので楕円は和製漢語との確信を深めたのでした。因みに志筑を発掘して紹介したのは狩野亨吉です。狩野は安藤昌益の発見者として有名ですが、志筑の業績も後に伝えた業績は知りませんでした。

ここまで調べて楕円が和製漢語と決定かと思ったのですが、念のために大修館の「大漢和辞典」に当たってみることにしました。向ったのは群馬県立図書館です。係りの女性に用件を告げると親切に対応してくれました。大きな分冊の「木」の部に詳細な説明があります。
橢
1、車中にそなえへておくほそ長い器。
2、小さいをけ。
3、圓く細長い。又、細長くする。
4、細長い器。
図版が無いので視覚的に理解できませんが、「橢」は古代から存在していたようです。驚いたことに「橢圓」の用例は董仲舒の著作を編集した『春秋繁露』にありました。私の予想は見事に外れました。従って結論としては、楕円は和製漢語ではありませんでしたが、この言葉を数学用語として定着させたのは志筑忠雄の功績だったと言えるでしょう。
↓ポチッと応援お願いします!

(3/6追記)Wikipediaの志筑忠雄の記事には以下のような記述があります。
『暦象新書(上中下)』1798年から1802年 - 原著はジョン・ケイル(John Keill, 1671年-1721年)の『真正なる自然学および天文学への入門書(Introductiones ad Veram Physicam et veram Astronomiam)』(1725年)のオランダ語版(1741年)。アイザック・ニュートンやヨハネス・ケプラーの生んだ法則や概念、+、-、÷、√といった記号を日本に紹介し、「遠心力」、「求心力」、「重力」、「加速」、「楕円」という語を生んだ書。
この記述の典拠とされているのが吉田光邦著『江戸の科学者たち』です。アマゾンで調べると古書が200円(送料250円)だったので直ちに注文しました。
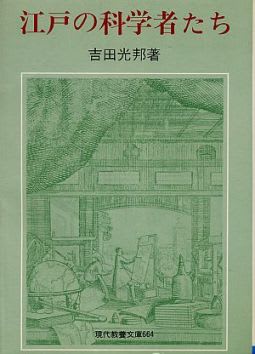
到着した『江戸の科学者たち』の156ページには一般的な記述しか書いてありません。著者には責任はありませんが、Wikipediaの編集者の早とちりでしょう。良くあることなので腹も立ちません。
それで『暦象新書』の原典がWebに公開されているか確認すると、早稲田大学の古典籍総合データベースにあることが分かりましたが、昔の写本がすらすら読めるほどの教養を持ち合わせていません。やはり活字化されたものをどこかの図書館で見せてもらうしかありません。
そして一昨日、アマゾンに注文した『円錐曲線論』が到着しました。
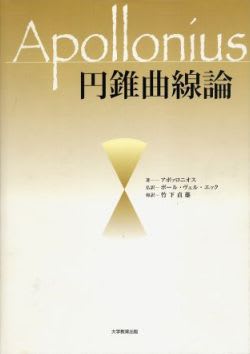
重要な本を入手してまず最初の作業、表紙をスキャナに乗せて表紙の画像を電子化して、ぱらぱらと中身を覗いただけです。本書の存在は前から知っていましたが、アマゾンのレビューが極端に悪かったので購入を躊躇していました。匿名の評者は仏訳者も邦訳者も工学者であることが気に入らないらしい。
この扁平な円というのは、紀元前250年頃にアッポロニウスによって説かれた。三つの関連ある幾何学図形のうちの一つである。それぞれについて彼は数学上の記述を行なっているが、三つの中で記述の価値がもっとも少ないのが、この扁平な円に関してであった。この場合には他とくらべて不十分である。"不十分な"の意をギリシャ語で"elleipsis"ということから、この曲線はellipse<楕円>と呼ばれた。
アシモフさんの説明をそのまま信じるほど私はお人よしではありません。「記述の価値がもっとも少ない」と思うのは『円錐曲線論』のある読者であって著者がそう思ったからではないでしょう。やはり『円錐曲線論』を参照する必要があります。手持ちの「現代ギリシア語辞典」も参照しましたが、英語での初出はOEDで調べることになるでしょう。
当初の疑問に立ち返ると、漢字文化圏では楕円の「楕」とはどんな意味を持っていたのでしょうか?まず木偏である理由です。次いで、この様な数学用語は和製漢語である可能性が高いと予想しました。ある人から聞いた話では「中華人民共和国」のうちメイド・イン・チャイナは中華だけで、人民も共和国もメイド・イン・ジャパンだそうです。
Web上の漢和辞典は非力なので、手持ちの『大字典』(上田萬年編集)を見ると「車中におく一の器、小判形をなす故に長円形の義とす 木は義を示し隋(ダ)は音符。」とありました。木製の器なので木偏であると分かりますが、車中で使う器とは何でしょうか?疑問は深まるばかりです。
電車の外側に付いているボタンを押してドアを開ける湘南新宿ラインに乗って東京に出かけた折りに、某出版社の社長にこの疑問をぶつけると、「楕円は堕落した円だよ」と鋭い冗談を飛ばしながら小学館の日本国語大辞典(通称にっこく)の当該個所のコピーをとってくれました。OEDを目標とした辞書だけあって楕円と言う言葉の用例が載っていました。
※暦象新書─大陰も楕円を画するとも、殊に種々の変動あるは、時々に地の離日と同じことによりて生ず
貴重な情報でした。『暦象新書』は日本で最初にニュートン力学を理解して紹介した志筑忠雄(しづき ただお、宝暦10年(1760年) - 文化3年7月3日(1806年8月16日))の著作である事だけは知っていましたので楕円は和製漢語との確信を深めたのでした。因みに志筑を発掘して紹介したのは狩野亨吉です。狩野は安藤昌益の発見者として有名ですが、志筑の業績も後に伝えた業績は知りませんでした。

ここまで調べて楕円が和製漢語と決定かと思ったのですが、念のために大修館の「大漢和辞典」に当たってみることにしました。向ったのは群馬県立図書館です。係りの女性に用件を告げると親切に対応してくれました。大きな分冊の「木」の部に詳細な説明があります。
橢
1、車中にそなえへておくほそ長い器。
2、小さいをけ。
3、圓く細長い。又、細長くする。
4、細長い器。
図版が無いので視覚的に理解できませんが、「橢」は古代から存在していたようです。驚いたことに「橢圓」の用例は董仲舒の著作を編集した『春秋繁露』にありました。私の予想は見事に外れました。従って結論としては、楕円は和製漢語ではありませんでしたが、この言葉を数学用語として定着させたのは志筑忠雄の功績だったと言えるでしょう。
↓ポチッと応援お願いします!
(3/6追記)Wikipediaの志筑忠雄の記事には以下のような記述があります。
『暦象新書(上中下)』1798年から1802年 - 原著はジョン・ケイル(John Keill, 1671年-1721年)の『真正なる自然学および天文学への入門書(Introductiones ad Veram Physicam et veram Astronomiam)』(1725年)のオランダ語版(1741年)。アイザック・ニュートンやヨハネス・ケプラーの生んだ法則や概念、+、-、÷、√といった記号を日本に紹介し、「遠心力」、「求心力」、「重力」、「加速」、「楕円」という語を生んだ書。
この記述の典拠とされているのが吉田光邦著『江戸の科学者たち』です。アマゾンで調べると古書が200円(送料250円)だったので直ちに注文しました。
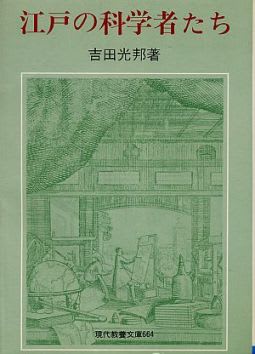
到着した『江戸の科学者たち』の156ページには一般的な記述しか書いてありません。著者には責任はありませんが、Wikipediaの編集者の早とちりでしょう。良くあることなので腹も立ちません。
それで『暦象新書』の原典がWebに公開されているか確認すると、早稲田大学の古典籍総合データベースにあることが分かりましたが、昔の写本がすらすら読めるほどの教養を持ち合わせていません。やはり活字化されたものをどこかの図書館で見せてもらうしかありません。
そして一昨日、アマゾンに注文した『円錐曲線論』が到着しました。
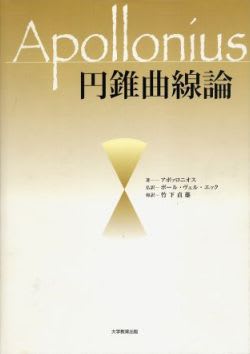
重要な本を入手してまず最初の作業、表紙をスキャナに乗せて表紙の画像を電子化して、ぱらぱらと中身を覗いただけです。本書の存在は前から知っていましたが、アマゾンのレビューが極端に悪かったので購入を躊躇していました。匿名の評者は仏訳者も邦訳者も工学者であることが気に入らないらしい。


























OED電子版で ellipseを調べてみました。
ギリシヤ語で「~より小さい」というような意味で、楕円を円錘の断面として定義した場合に、母線よりも小さい角度で切ると楕円になることから来ているとのこと。hyperbora[双曲線]の語源は「~より大きい」で、逆に大きい角度で切った場合、だそうです。たぶん。
以下が語源部分のOED原文です。
----
[ad. Gr. ἔλλειψις, n. of action f. ἐλλείπειν to come short. (In the case of the ellipse regarded as a conic section the inclination of the cutting plane to the base ‘comes short of’, as in the case of the hyperbola it exceeds, the inclination of the side of the cone.)
Not in Johnson, Todd, or Richardson (1836); for early examples of the pl. ellipses see ellipsis.]
1753年のようです。
1.1 A plane closed curve (in popular language a regular oval), which may be defined in various ways: a.1.a Considered as a conic section; the figure produced when a cone is cut obliquely by a plane making a smaller angle with the base than the side of the cone makes with the base. b.1.b A curve in which the sum of the distances of any point from the two foci is a constant quantity. c.1.c A curve in which the focal distance of any point bears to its distance from the directrix a constant ratio smaller than unity.
The planetary orbits being (approximately) elliptical, ellipse is sometimes used for ‘orbit’ (of a planet).
1753 Chambers Cycl. Supp. s.v. Ellipsis, [The form ellipse is used throughout; the Cycl. 1751 has only ellipsis]. 1815 Hutton Math. Dict., Ellipse or Ellipsis. 1842 Tennyson Golden Year 24 The dark Earth follows wheel'd in her ellipse. 1868 Lockyer Heavens (ed. 3) 120 A circle seen obliquely or perspectively shows the form of an ellipse. 1880 C. & F. Darwin Movem. Pl. 1 Other irregular ellipses‥are successively described.
2.2 transf. An object or figure bounded by an ellipse. Also fig.
1857 Bullock tr. Cazeaux's Midwif. 29 The abdominal strait has been‥compared to an ellipse. 1869 Dunkin Midn. Sky 163 An ellipse of small stars.
3.3 Gram. = ellipsis 2. Somewhat rare.
1843–83 Liddell & Scott Gr. Lex. s.v. Ἔλλειψις. 1886 Roby Lat. Gram. II (ed. 5) 511 (Index).
y^2 = px; y^2 = px ± (p/d)x^2
こうなって、±のプラスの時がhyperbola、マイナスの時がellipseになるので、数式の値が小さくなる方、という意味だったのではないでしょうか。アポロニウスが数式に「価値」を見出すというのは変だし、楕円の価値が他より低いというのも変ですよね。
矢継ぎ早に3つのコメントをありがとうございます。
大変助かります。
ケプラーが第一・第二法則を定式化して出版したのが1609年、プリンキピアの初版が1687年なので英語でellipseの初出が1753年とは随分遅いなと思いました。でもプリンキピアに名前が残っているピープスの学力を思い出して納得しました。
アシモフの本の原題は"WORDS OF SCIENCE"です。こちらも確認して頂きありがとうございます。邦訳の後に監修者と訳者の略歴がありました。訳者の数学の能力の足りないところを監修者がきちんとサポートしなかったのです。語学力だけでは翻訳出来ない。内容の理解が前提ですね。