

「三人吉三」の通し上演は、まず福助×橋之助×勘三郎の2007年コクーン歌舞伎が初見。2009年11月に菊之助×愛之助×松緑の花形歌舞伎も観たが、歌舞伎座での上演は未見。話題の玉三郎主演の公演はまだ歌舞伎の本格観劇前だった。
菊五郎のお嬢吉三は10年前の通し上演以来ということで、大川端の名場面だけでもその時の三人が揃って歌舞伎座さよなら公演の最後に出してくれたのが心憎い。
【三人吉三巴白浪(さんにんきちさともえのしらなみ)】
大川端庚申塚の場
今回の配役は以下の通り。
お嬢吉三=菊五郎 お坊吉三=吉右衛門
和尚吉三=團十郎 夜鷹おとせ=梅枝
金貸し太郎右衛門=菊十郎 研師与九兵衛=松太郎
駕籠かき=吉六、辰巳
冒頭に金貸し太郎右衛門と研師与九兵衛が名刀「庚申丸」をめぐって争う場面があるが、ここと駕籠かきには長年のお弟子さんを配役していると思う。敬意を払って上記に全員書いておく。





夜鷹おとせの梅枝がいい。梅枝の進境著しさは今年の国立劇場初春歌舞伎で目の当たりにしたが、今回の大顔合わせに抜擢されても遜色がない。台詞回しにも所作にも存在感が出てきたし、夜鷹の儚げな風情がある。
梅枝の綺麗な声に対抗してか、菊五郎のお嬢さまに化けている時の声が3月の弁天の時よりも可愛らしい。
菊之助で観た時と同様、人魂に怖がってから財布に手を伸ばして本性をあらわすまでに手順が少ないのは音羽屋の型ではないかと推測。
おとせを大川に蹴込み、通りかかった与九兵衛から庚申丸をとりあげて白刃をきらめかせていると、通り過ぎようとした駕籠かきも駕籠を残して逃げてしまう。大川端の杭に片足をかけて客席側を見込んでの名台詞の場面には「待ってました!」の大向こうがかかる。
「月も朧に白魚の~」、黙阿弥の有名な七五調を菊五郎が節をつけながらもあっさりと聞かせてくれるのを聴くのが至福。肩の力が抜けて身についたものが流れ出るような芝居ができるようになるのが「至芸」ということなのだろう。
Wikipediaの「三人吉三」の項に名台詞あり
駕籠で全てを聞いていて姿を現すお坊吉三。吉右衛門のお坊吉三がすっくと立ち上がり、これから二人のやりとりがあると思うだけでゾクゾクする。
武家のお坊ちゃまがぐれたという屈折感が強く漂う吉右衛門のお坊吉三の名乗りにクラクラする。お嬢さま姿の生意気な年下格の吉三から百両を巻き上げようとするのだが、蛇のようにからみつく暗い粘っこさを感じる。二人は白刃を交し合うのだがその後の二人の男色関係につながる官能の予感がここにある。
團十郎の和尚吉三が喧嘩の仲裁に割って入る。実に堂々とした兄貴分の貫禄だ。それが命を捨てずにすんだ代わりに争いの元の百両を半分ずつ俺にくんなというちゃっかりした申し出をするのが笑えるが、和尚に義侠を感じた二人は執着をさっぱり捨てる。その上で義兄弟になってほしいと頼みに応えた和尚の主導で血杯を交わすのだが、ワルたちであっても江戸の「粋」の美学を貫く名場面。

「寺子屋」の重苦しさをふっとばし、短いながらも気分すっきりの名場面。江戸歌舞伎の大御所三人の舞台にしびれまくり恍惚に浸った一幕だった。

写真は当月の筋書の表紙の鏑木清方の「さじき」という絵。今の歌舞伎座では1階の桟敷席デビューができないで終ったけど・・・(^^ゞ
さて次からは、いよいよ千穐楽の第三部の感想へ突入する。

4/24御名残四月大歌舞伎(1)「御名残木挽闇爭」
4/24御名残四月大歌舞伎(2)初めて堪能できた「熊谷陣屋」
4/24御名残四月大歌舞伎(3)菅原伝授手習鑑「寺子屋」
4/24御名残四月大歌舞伎(4)中村屋の「三人連獅子」、藤十郎の「藤娘」













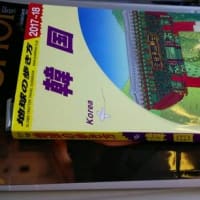
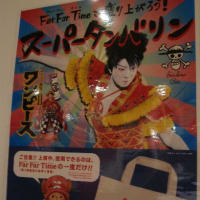

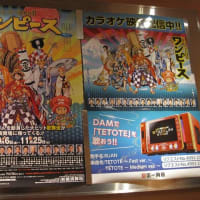
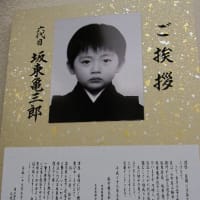
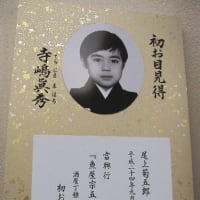

第二部の「三人吉三」は4/24に玲小姐さんと並んで観ていました。やはり音羽屋+播磨屋+成田屋という風に加わっていき、最後に三人揃いぶみになるという大顔合わせの大ご馳走の演目に大満足でした。
杮落し公演に入るかもしれないと、ちょっと楽しみにしておきましょうか!