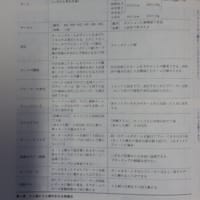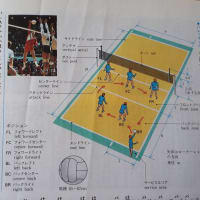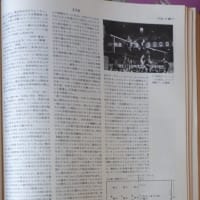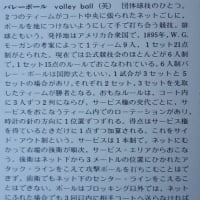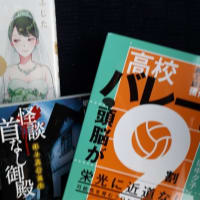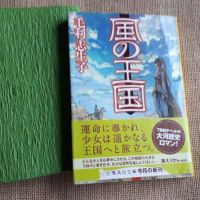「三省堂国語辞典のひみつ」の方なのですね! 飯間浩明「小説の言葉尻をとらえてみた」(光文社新書)。
「桐島、部活やめるってよ」「風が強く吹いている」「残穢」「オレたちバブル入行組」「チッチと子」「桜ほうさら」「横道世之介」「猫を抱いて象と泳ぐ」「マチネの終わりに」「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」「八日目の蝉」「阪急電車」「グラスホッパー」「ギケイキ 千年の流転」「チョコレートコスモス」の十五作を、辞書にはない言葉を中心に語る一冊です。
例えば、伊坂幸太郎は「ささめく」という古語を愛用し、朝井リョウは高校生に方言混じりの若者言葉をしゃべらせるけど、「ら抜き言葉」は使わない。
平野啓一郎は「割り込み感動詞」を使うというのもおもしろい。
「え、洋子さんって……」ではなく、「洋子さんって、え、……」という語順で、驚きを示す。言葉遣いがリアルな感じがしますね。
飯間さんの書き方がまた独創的で、彼自身が本の中に入り込んで登場人物に話しかけたり、地の文がどこからともなく聞こえてきたり、紛らわしい読み仮名は聞こえにくかったりします。
そして、「言葉尻をとらえ」といいながらも、決してその言葉を否定しない。
わたしは言葉に関する本が好きであれこれ読んできましたが、否定する系統のものが多かったので、なんだかこの本は懐が深いような気がします。
辞書編集は例語収集が重要ですから、普段は古典といえるような作品を読まれているそうです。
三浦哲郎さんの作品も、二作引き合いに出されていました。
「忍ぶ川」に、「T字路」という表現がある。これは、「俺妹」がラノベなのに意外と古風な言葉遣いだという例。「丁字路」とこちらでは言っていたそうですよ。
また、「海の道」では、「容易ならない」という表現(本来なら「容易ならぬ」「容易ではない」)の例として引かれています。(恩田陸が「穏やかならない」という使い方をしていたため)
表現の特徴には、作家自身も気づいていないものがあるのかもしれません。朝井リョウの「体操座り」や有川浩の「お幼稚」は、本人の生育歴で獲得した語が自然に出てきた感じですね。おそらくわたしは、自分の馴染み言葉に置き換えて読んだと思われます。
それに対して小川洋子は、「綿菓子」圏内で育っているのに「綿飴」と書く。
三浦しをんが、マイクテストで使った「メーデーメーデー」は、飯間さんにとっても知らなかった言葉だそうです。
うーん、わたしもここに紹介されたものの半分は読んだはずなのですが……。あんまり言葉に着目しないですね。かなり飛ばし読みしている気がしてきました。
「ギケイキ」読もうかな。確かに「姉歯の松」あたりを彼は通りそう。近くに住んでいても、どこにあるのかよくわからないわたし。同じものを見てひっかかることって、それぞれ違うのかもしれませんね。
「桐島、部活やめるってよ」「風が強く吹いている」「残穢」「オレたちバブル入行組」「チッチと子」「桜ほうさら」「横道世之介」「猫を抱いて象と泳ぐ」「マチネの終わりに」「俺の妹がこんなに可愛いわけがない」「八日目の蝉」「阪急電車」「グラスホッパー」「ギケイキ 千年の流転」「チョコレートコスモス」の十五作を、辞書にはない言葉を中心に語る一冊です。
例えば、伊坂幸太郎は「ささめく」という古語を愛用し、朝井リョウは高校生に方言混じりの若者言葉をしゃべらせるけど、「ら抜き言葉」は使わない。
平野啓一郎は「割り込み感動詞」を使うというのもおもしろい。
「え、洋子さんって……」ではなく、「洋子さんって、え、……」という語順で、驚きを示す。言葉遣いがリアルな感じがしますね。
飯間さんの書き方がまた独創的で、彼自身が本の中に入り込んで登場人物に話しかけたり、地の文がどこからともなく聞こえてきたり、紛らわしい読み仮名は聞こえにくかったりします。
そして、「言葉尻をとらえ」といいながらも、決してその言葉を否定しない。
わたしは言葉に関する本が好きであれこれ読んできましたが、否定する系統のものが多かったので、なんだかこの本は懐が深いような気がします。
辞書編集は例語収集が重要ですから、普段は古典といえるような作品を読まれているそうです。
三浦哲郎さんの作品も、二作引き合いに出されていました。
「忍ぶ川」に、「T字路」という表現がある。これは、「俺妹」がラノベなのに意外と古風な言葉遣いだという例。「丁字路」とこちらでは言っていたそうですよ。
また、「海の道」では、「容易ならない」という表現(本来なら「容易ならぬ」「容易ではない」)の例として引かれています。(恩田陸が「穏やかならない」という使い方をしていたため)
表現の特徴には、作家自身も気づいていないものがあるのかもしれません。朝井リョウの「体操座り」や有川浩の「お幼稚」は、本人の生育歴で獲得した語が自然に出てきた感じですね。おそらくわたしは、自分の馴染み言葉に置き換えて読んだと思われます。
それに対して小川洋子は、「綿菓子」圏内で育っているのに「綿飴」と書く。
三浦しをんが、マイクテストで使った「メーデーメーデー」は、飯間さんにとっても知らなかった言葉だそうです。
うーん、わたしもここに紹介されたものの半分は読んだはずなのですが……。あんまり言葉に着目しないですね。かなり飛ばし読みしている気がしてきました。
「ギケイキ」読もうかな。確かに「姉歯の松」あたりを彼は通りそう。近くに住んでいても、どこにあるのかよくわからないわたし。同じものを見てひっかかることって、それぞれ違うのかもしれませんね。