
夏目家には、四人の女子の後に二人の男子が生まれ、その次に女児が生まれた。この子は、桃の節句の前の晩に生まれたので、雛子(ひなこ)と名づけられた。
〔知恵も早く、非常なおしゃまっ子でございました。一年半もたったこの年の秋ごろには、よちよち遊んでいては、自分も見よう見まねで猫の墓にお水を上げにいって、ついでに自分もその水を飲んでしまうという按配でちっとも目が離せません。それがまたなかなかの癇癪持ちの意地悪でございました。〕
(夏目鏡子述『漱石の思い出』)
ところが、この雛子は、生まれて一年半ほどで急死してしまう。ある日、御飯を食べているときに、急にキャッと言ってあおむけに倒れた。
ただ、そのころの子供というのは、よくこういうことはあったらしい。ひきつけなどは日常的なことで、顔に水をかけて息をふきかえさせるというようなことに皆なれっこになっていて、あわてることもしなかった。ところが揺すっても水をかけても雛子には反応がなく、そのまま死んでしまった。
〔子供の死因はとうとうわからずにしまいました。その時私は解剖でもしみたらとふと思いましたが、それも残酷なような気がしてそのまま黙っておりました。ほどへて何もかもすんだ後でその話をしますと、ほんとうに解剖すればよかった。そうすれば死因もよくわかっただろうに、ちっとも残酷なことなんかないよ。自分はまるでそんなことに気がつかなかったと惜しそうに申しておりました。夏目が亡くなりました時に、私が進んで解剖していただくように申し出ましたのは、その時のことを思い出したからでございます。〕
〔口に出してこそ何も申しませんでしたが、これは相当にこたえた様子で、ずいぶんと心のうちでは悲しんでもいたようでした。子供に逝かれるというのはいやなもんだなあと、何かの拍子につくづく思いつめたように言っていたこともありました。〕 (『漱石の思い出』)
その夏目漱石が死んだのは、1916年12月9日である。
上にあるような夏目家の体験から、鏡子夫人は漱石の遺体の解剖を申し出たという。それで、翌10日、遺体は東大病理学教室にて解剖に附された。
さらに、
〔脳と胃とはおすすめにより大学のほうへ寄付いたしました。〕とある。すると今も東大のどこかに「漱石の脳と胃」は保存してあるのだろうか。(たぶん、あるのだろう。)
じつは僕は若い時に、東大病院であるバイトをしたことがある。雇い主は大学病院ではなく、葬儀屋である。
1ヶ月のバイトだった。夕方の5時から、翌日の朝7時までだから、拘束時間は長い。なんの仕事をするかというと、病棟のベッドで亡くなった遺体を、1F(半地下)の霊安室へ運ぶのを手伝うのである。それだけである。つまり、だれも亡くならない日は、仕事がない。その間は自由である。寝ていてもよい。仕事が入ると、つまり死人がでると、となりの部屋で同じく待機していた葬儀屋の社員が呼び出しブザーで起こしてくれる。その社員と二人で病室へ行く。その時の実働は長くみても2時間くらいのもので、むつかしいことは何もない。死者のでない日の方がほとんどで、そういう日は、なにもせず、寝て、朝になって、簡単に掃除をして終了である。もちろんそれで1日分のバイト代は出る。バイト後、東大の食堂へ行って朝食を食べたこともあった。
ほんとうは、死んだ人の遺体を霊安室に運ぶのは病院のしごとなのだが、それを葬儀屋が「やらせてください」と割りこんで手伝うのは、場合によっては、葬儀屋に「ほんらいの仕事」が回ってくる可能性があるからである。亡くなった方の家族の側にいて、「ところで葬儀屋はもうお決まりでしょうか。もしまだお決まりでなかったら…」と話かけるのである。ただしそれは葬儀屋の社員の仕事で、僕は遺体運び要員として雇われたバイトなので、そこまではしないでよい。
葬儀屋としては、病院で寝て待っているだけで「仕事」がやってくるわけだから、こんな良いポジションはない。だからこの役目を一社が独占するわけにはいかず、葬儀屋同士で取り決めがあって、1ヶ月ごとに順番でまわしているとのこと。それで、その手伝いとして雇われた僕のバイトも、1ヶ月の短期契約なのだった。
遺体を運ぶといっても、車つきのベッドに載せてエレベーターを使うのだし、カンタンなものだ。ラクなバイトではあったが、これを長期続けるのは、やはり精神的には健康によくない気がする。1ヶ月でよかったと思う。夜、犬が吼える声が聞こえていたが、あれは多分大学病院の実験用の動物だろう。
1ヶ月の間に、実際に「しごと」は5件くらいだったと思う。(あまりよく憶えていないのだが。) そのうちの2件は、遺族の理解を得て、「解剖」へ回された。そのケースの場合、朝になって、冷房の効いた霊安室から、「解剖室」へと遺体を運ぶ(車で移動)のも我々のしごととなっていた。服を脱がせて、解剖台へ横たわらせるまでがお役目だ。そんなわけで僕は、東大病院の解剖室にも2度入室しているのである。
待機しているのは、葬儀屋の社員1名(ずっと同じ人ではなかった)とバイト1名(僕)。 社員とは別の6畳ほどの広さの部屋があって、そこで僕は一人で待機。ということで気楽だったが、拘束時間が14時間もあると、いくら自由に寝てもいいといっても、そんなには眠れない。TVもなかった。それで僕は図書館で本を借りてきて読んだ。
その時に読んだ本が、司馬遼太郎の『坂の上の雲』である。
長い長い小説である。 だから、ちょうどよかった。 9月だった。
『坂の上の雲』は、日露戦争を中心に据えて、司馬遼太郎が、「明治時代の人間」というものを描こうと構想した物語である。この物語の主人公として、司馬さんが選んだのが、正岡子規、秋山好古(よしふる)、秋山真之(さねゆき、好古の弟)の三人。かれらは三人とも、伊予松山の出身なのである。
正岡子規と秋山真之は同い年であり、親友であり、東大予備門へともに通った。ということは、実は、夏目漱石と秋山真之も同級生なのである。ただ、秋山真之は、家の経済的事情から、予備門をやめ海軍への道を進むことになる。 それで、子規が漱石との会話中に、秋山真之の話をしたときに、漱石が真之のことを憶えていないというので、「写生能力の不足じゃな」と漱石をからかった__という場面が『坂の上の雲』に描かれており、僕はそれを切り取って前回記事に入れた。
日露戦争は1904年2月にはじまった。ロシア軍が「旅順」を占拠したことに反発した日本が、とうとう戦争に踏み切ったのである。(子規が死んで1年半後のこと)
夏目漱石の家に例の「福猫」が現われるのは、この戦争のさなかであった。
日本陸軍は「旅順」を奪うのに苦労をした。沢山の犠牲の上に、1905年1月、ついに「旅順」陥落。といってもこれで「勝ち」というわけではない。
漱石の『吾輩は猫である』の第1回が発表されたはその時期である。これが好評だったので、漱石はどんどん『猫』の続きを書いた。生活が苦しくそれまで借金をしていた夏目家だが、東大の講師の給料のほかに、原稿料が入るようになって徐々にラクになった。つらかった漱石の神経症症状もやわらいでいった。
その『吾輩は猫である』のその第5話の中では、猫がこんなことを言っている。
〔先達中(せんだってじゅう)から日本は露西亜(ロシア)と大戦争をしているそうだ。吾輩は日本の猫だから無論日本贔屓(びいき)である。出来得べくんば混成猫旅団を組織して露西亜兵を引っ掻いてやりたいと思う位である。〕(『吾輩は猫である』)
「混成猫旅団」というのが、可笑しい。
日本海軍連合艦隊の司令長官は東郷平八郎である。参謀長は加藤某であるが、その作戦を実質的に担当していたのは、秋山真之であった。正岡子規の友人の、秋山真之である。
日本の陸軍は「旅順」を獲った。海軍は、ロシアの太平洋艦隊を壊滅させた。しかし、ロシアには、まだ、バルチック艦隊があった。バルチック艦隊が日本海にやってきて、これに日本海軍が敗れることになれば、日本の陸軍の補給路も分断され、これまでの頑張りもすべて水泡に帰す。さいごの決戦だ。世界の列強もこの海戦を前にさあ始まるぞと注目して待っていた。
秋山真之は、もてる限りの知恵をしぼって対策を考えていた。敵=バルチック艦隊は、インド洋を渡り、南からやってくる…。
司馬遼太郎の少年時に、家には、徳冨蘆花全集と正岡子規全集があったそうだ。司馬さんはそれらを読み、どちらも好きだけれども、しかし、蘆花の小説の「重苦しさ」にはつらくてやりきれないところもあったという。それに対して子規は「あかるい」という。この「あかるさ」に魅かれて、司馬さんは、こつこつと正岡子規の資料を集めていた。そのうちに、子規と秋山真之とが、同郷であり同じ塾に学び、東京では大学予備門へともに通っていたことを知り、彼らを描きたくなったという。日露戦争の勝利も、明治時代の、子規のような、「素朴な人々のあかるさ」に支えられた上での勝利だったということを、描きたかったのではないかと思う。
僕はこの物語を、あの東大病院の半地下で読みながら、その時には、戦争に関わらない正岡子規がどうしてこの小説に出てくる(しかも主人公として)のか不思議だったが、いまは、わかる気がする。ああいう「あかるさ」が、いいのだ、ということが。戦争が主題ではなく、子規の「あかるさ」が主題なのだと。
そして今、東大と漱石と『坂の上の雲』と僕とが、ふしぎな形でつながった。司馬さんの描いた正岡子規の「あかるさ」は、子猫を通して、漱石の『猫』の中にも受け継がれたと考えるいうのはちょっと強引すぎるか。(混成猫旅団…)
「坂の上の雲」というタイトルは、明治時代の、坂をゆっくり登って行く人の前方に、ぽっかりと浮かんだ雲のことのようである。
この小説のエンディングには、戦争後、秋山真之が、東京根岸の正岡子規の住んでいた家(子規庵)を訪ねるシーンが描かれている。途中、その根岸の「芋坂(いもざか)」とよばれるあたりの茶屋(藤の木茶屋)でひとやすみし、真之は団子を食う。 …
漱石の『猫』の中にも、僕はいま、「芋坂」を見つけて喜んでいる。
多々良という男が苦沙弥先生(猫の主人)をたずねてきて話をするのだが、しばらく話して先生は「多々良、散歩をしようか」という。
多々良「行きましょう。上野にしますか。芋坂へ行って団子を食いましょうか。先生あすこの団子を食った事がありますか。奥さん、一返行って食って御覧。柔らかくてやすいです。酒も飲ませます」…
これも第5話中にある。 漱石はこれを書く時に、あるいは子規庵を意識していたかもしれない。いや逆か? 司馬遼太郎が漱石の『猫』を意識して、芋坂の団子屋を書いたのか。
〔知恵も早く、非常なおしゃまっ子でございました。一年半もたったこの年の秋ごろには、よちよち遊んでいては、自分も見よう見まねで猫の墓にお水を上げにいって、ついでに自分もその水を飲んでしまうという按配でちっとも目が離せません。それがまたなかなかの癇癪持ちの意地悪でございました。〕
(夏目鏡子述『漱石の思い出』)
ところが、この雛子は、生まれて一年半ほどで急死してしまう。ある日、御飯を食べているときに、急にキャッと言ってあおむけに倒れた。
ただ、そのころの子供というのは、よくこういうことはあったらしい。ひきつけなどは日常的なことで、顔に水をかけて息をふきかえさせるというようなことに皆なれっこになっていて、あわてることもしなかった。ところが揺すっても水をかけても雛子には反応がなく、そのまま死んでしまった。
〔子供の死因はとうとうわからずにしまいました。その時私は解剖でもしみたらとふと思いましたが、それも残酷なような気がしてそのまま黙っておりました。ほどへて何もかもすんだ後でその話をしますと、ほんとうに解剖すればよかった。そうすれば死因もよくわかっただろうに、ちっとも残酷なことなんかないよ。自分はまるでそんなことに気がつかなかったと惜しそうに申しておりました。夏目が亡くなりました時に、私が進んで解剖していただくように申し出ましたのは、その時のことを思い出したからでございます。〕
〔口に出してこそ何も申しませんでしたが、これは相当にこたえた様子で、ずいぶんと心のうちでは悲しんでもいたようでした。子供に逝かれるというのはいやなもんだなあと、何かの拍子につくづく思いつめたように言っていたこともありました。〕 (『漱石の思い出』)
その夏目漱石が死んだのは、1916年12月9日である。
上にあるような夏目家の体験から、鏡子夫人は漱石の遺体の解剖を申し出たという。それで、翌10日、遺体は東大病理学教室にて解剖に附された。
さらに、
〔脳と胃とはおすすめにより大学のほうへ寄付いたしました。〕とある。すると今も東大のどこかに「漱石の脳と胃」は保存してあるのだろうか。(たぶん、あるのだろう。)
じつは僕は若い時に、東大病院であるバイトをしたことがある。雇い主は大学病院ではなく、葬儀屋である。
1ヶ月のバイトだった。夕方の5時から、翌日の朝7時までだから、拘束時間は長い。なんの仕事をするかというと、病棟のベッドで亡くなった遺体を、1F(半地下)の霊安室へ運ぶのを手伝うのである。それだけである。つまり、だれも亡くならない日は、仕事がない。その間は自由である。寝ていてもよい。仕事が入ると、つまり死人がでると、となりの部屋で同じく待機していた葬儀屋の社員が呼び出しブザーで起こしてくれる。その社員と二人で病室へ行く。その時の実働は長くみても2時間くらいのもので、むつかしいことは何もない。死者のでない日の方がほとんどで、そういう日は、なにもせず、寝て、朝になって、簡単に掃除をして終了である。もちろんそれで1日分のバイト代は出る。バイト後、東大の食堂へ行って朝食を食べたこともあった。
ほんとうは、死んだ人の遺体を霊安室に運ぶのは病院のしごとなのだが、それを葬儀屋が「やらせてください」と割りこんで手伝うのは、場合によっては、葬儀屋に「ほんらいの仕事」が回ってくる可能性があるからである。亡くなった方の家族の側にいて、「ところで葬儀屋はもうお決まりでしょうか。もしまだお決まりでなかったら…」と話かけるのである。ただしそれは葬儀屋の社員の仕事で、僕は遺体運び要員として雇われたバイトなので、そこまではしないでよい。
葬儀屋としては、病院で寝て待っているだけで「仕事」がやってくるわけだから、こんな良いポジションはない。だからこの役目を一社が独占するわけにはいかず、葬儀屋同士で取り決めがあって、1ヶ月ごとに順番でまわしているとのこと。それで、その手伝いとして雇われた僕のバイトも、1ヶ月の短期契約なのだった。
遺体を運ぶといっても、車つきのベッドに載せてエレベーターを使うのだし、カンタンなものだ。ラクなバイトではあったが、これを長期続けるのは、やはり精神的には健康によくない気がする。1ヶ月でよかったと思う。夜、犬が吼える声が聞こえていたが、あれは多分大学病院の実験用の動物だろう。
1ヶ月の間に、実際に「しごと」は5件くらいだったと思う。(あまりよく憶えていないのだが。) そのうちの2件は、遺族の理解を得て、「解剖」へ回された。そのケースの場合、朝になって、冷房の効いた霊安室から、「解剖室」へと遺体を運ぶ(車で移動)のも我々のしごととなっていた。服を脱がせて、解剖台へ横たわらせるまでがお役目だ。そんなわけで僕は、東大病院の解剖室にも2度入室しているのである。
待機しているのは、葬儀屋の社員1名(ずっと同じ人ではなかった)とバイト1名(僕)。 社員とは別の6畳ほどの広さの部屋があって、そこで僕は一人で待機。ということで気楽だったが、拘束時間が14時間もあると、いくら自由に寝てもいいといっても、そんなには眠れない。TVもなかった。それで僕は図書館で本を借りてきて読んだ。
その時に読んだ本が、司馬遼太郎の『坂の上の雲』である。
長い長い小説である。 だから、ちょうどよかった。 9月だった。
『坂の上の雲』は、日露戦争を中心に据えて、司馬遼太郎が、「明治時代の人間」というものを描こうと構想した物語である。この物語の主人公として、司馬さんが選んだのが、正岡子規、秋山好古(よしふる)、秋山真之(さねゆき、好古の弟)の三人。かれらは三人とも、伊予松山の出身なのである。
正岡子規と秋山真之は同い年であり、親友であり、東大予備門へともに通った。ということは、実は、夏目漱石と秋山真之も同級生なのである。ただ、秋山真之は、家の経済的事情から、予備門をやめ海軍への道を進むことになる。 それで、子規が漱石との会話中に、秋山真之の話をしたときに、漱石が真之のことを憶えていないというので、「写生能力の不足じゃな」と漱石をからかった__という場面が『坂の上の雲』に描かれており、僕はそれを切り取って前回記事に入れた。
日露戦争は1904年2月にはじまった。ロシア軍が「旅順」を占拠したことに反発した日本が、とうとう戦争に踏み切ったのである。(子規が死んで1年半後のこと)
夏目漱石の家に例の「福猫」が現われるのは、この戦争のさなかであった。
日本陸軍は「旅順」を奪うのに苦労をした。沢山の犠牲の上に、1905年1月、ついに「旅順」陥落。といってもこれで「勝ち」というわけではない。
漱石の『吾輩は猫である』の第1回が発表されたはその時期である。これが好評だったので、漱石はどんどん『猫』の続きを書いた。生活が苦しくそれまで借金をしていた夏目家だが、東大の講師の給料のほかに、原稿料が入るようになって徐々にラクになった。つらかった漱石の神経症症状もやわらいでいった。
その『吾輩は猫である』のその第5話の中では、猫がこんなことを言っている。
〔先達中(せんだってじゅう)から日本は露西亜(ロシア)と大戦争をしているそうだ。吾輩は日本の猫だから無論日本贔屓(びいき)である。出来得べくんば混成猫旅団を組織して露西亜兵を引っ掻いてやりたいと思う位である。〕(『吾輩は猫である』)
「混成猫旅団」というのが、可笑しい。
日本海軍連合艦隊の司令長官は東郷平八郎である。参謀長は加藤某であるが、その作戦を実質的に担当していたのは、秋山真之であった。正岡子規の友人の、秋山真之である。
日本の陸軍は「旅順」を獲った。海軍は、ロシアの太平洋艦隊を壊滅させた。しかし、ロシアには、まだ、バルチック艦隊があった。バルチック艦隊が日本海にやってきて、これに日本海軍が敗れることになれば、日本の陸軍の補給路も分断され、これまでの頑張りもすべて水泡に帰す。さいごの決戦だ。世界の列強もこの海戦を前にさあ始まるぞと注目して待っていた。
秋山真之は、もてる限りの知恵をしぼって対策を考えていた。敵=バルチック艦隊は、インド洋を渡り、南からやってくる…。
司馬遼太郎の少年時に、家には、徳冨蘆花全集と正岡子規全集があったそうだ。司馬さんはそれらを読み、どちらも好きだけれども、しかし、蘆花の小説の「重苦しさ」にはつらくてやりきれないところもあったという。それに対して子規は「あかるい」という。この「あかるさ」に魅かれて、司馬さんは、こつこつと正岡子規の資料を集めていた。そのうちに、子規と秋山真之とが、同郷であり同じ塾に学び、東京では大学予備門へともに通っていたことを知り、彼らを描きたくなったという。日露戦争の勝利も、明治時代の、子規のような、「素朴な人々のあかるさ」に支えられた上での勝利だったということを、描きたかったのではないかと思う。
僕はこの物語を、あの東大病院の半地下で読みながら、その時には、戦争に関わらない正岡子規がどうしてこの小説に出てくる(しかも主人公として)のか不思議だったが、いまは、わかる気がする。ああいう「あかるさ」が、いいのだ、ということが。戦争が主題ではなく、子規の「あかるさ」が主題なのだと。
そして今、東大と漱石と『坂の上の雲』と僕とが、ふしぎな形でつながった。司馬さんの描いた正岡子規の「あかるさ」は、子猫を通して、漱石の『猫』の中にも受け継がれたと考えるいうのはちょっと強引すぎるか。(混成猫旅団…)
「坂の上の雲」というタイトルは、明治時代の、坂をゆっくり登って行く人の前方に、ぽっかりと浮かんだ雲のことのようである。
この小説のエンディングには、戦争後、秋山真之が、東京根岸の正岡子規の住んでいた家(子規庵)を訪ねるシーンが描かれている。途中、その根岸の「芋坂(いもざか)」とよばれるあたりの茶屋(藤の木茶屋)でひとやすみし、真之は団子を食う。 …
漱石の『猫』の中にも、僕はいま、「芋坂」を見つけて喜んでいる。
多々良という男が苦沙弥先生(猫の主人)をたずねてきて話をするのだが、しばらく話して先生は「多々良、散歩をしようか」という。
多々良「行きましょう。上野にしますか。芋坂へ行って団子を食いましょうか。先生あすこの団子を食った事がありますか。奥さん、一返行って食って御覧。柔らかくてやすいです。酒も飲ませます」…
これも第5話中にある。 漱石はこれを書く時に、あるいは子規庵を意識していたかもしれない。いや逆か? 司馬遼太郎が漱石の『猫』を意識して、芋坂の団子屋を書いたのか。










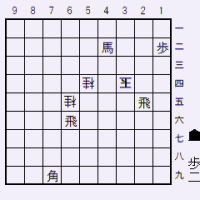
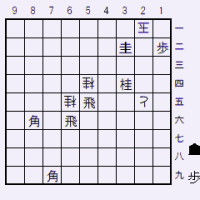
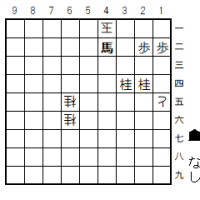
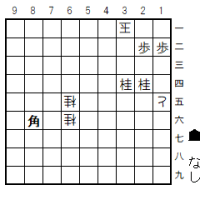
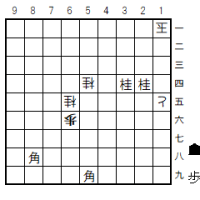
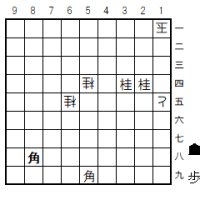
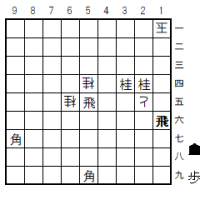
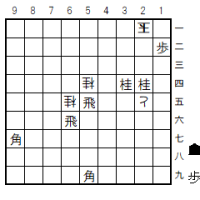
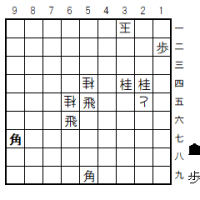
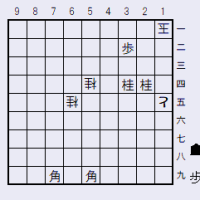






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます