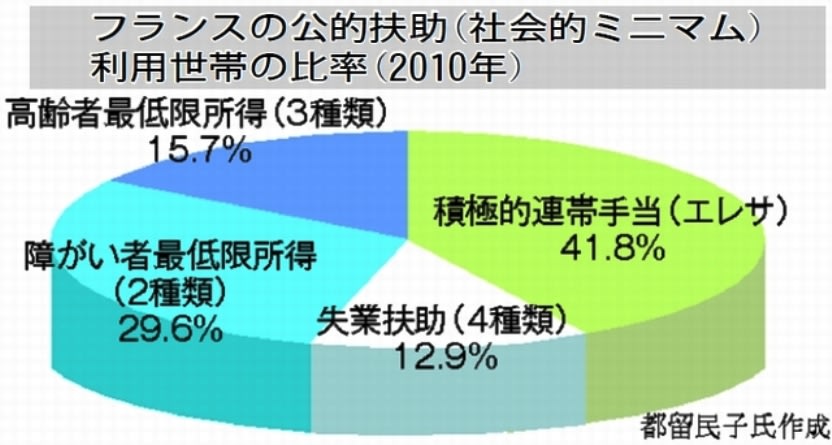しんぶん赤旗 2013年5月4日(土)
改憲派の三つの矛盾と憲法9条の生命力 5・3憲法集会 志位委員長のスピーチ
東京・日比谷公会堂で3日に開かれた「5・3憲法集会2013」での、日本共産党委員長の志位和夫氏のスピーチを紹介します。
________________________________________

(写真)スピーチする志位和夫委員長=3日、東京・日比谷公会堂
みなさん、こんにちは。ご紹介いただきました日本共産党の志位和夫です。(拍手)
今日は、会場あふれるたくさんのみなさんがおこしくださいまして、私からもお礼を申し上げさせていただきます。ありがとうございました。(拍手)
昨年の総選挙では、自民党や維新の会など、むき出しの改憲派が多数を占めるにいたりました。彼らの一番の狙いは、憲法9条を改定して、日本をアメリカとともに海外で戦争をできる国につくりかえるところにあります。
しかし、昨日(2日)発表された朝日新聞の世論調査をみても、「9条は変えない方がよい」という方が、52%と国民の過半数ではありませんか。(拍手)
私は、憲法施行66周年の憲法記念日にあたって、憲法を守り、憲法を生かした日本をつくるために、政治的立場の違いをこえてスクラムをくみ、知恵と力をつくして頑張り抜く決意をまず申し上げるものです。(大きな拍手)
改憲派が衆議院で多数をしめたことの危険はもとより重大です。同時に、私は、改憲派が次の三つの矛盾を自らつくりだしていることに注目し、その弱点を攻めに攻めるたたかいが大切だと考えています。
第一の矛盾 96条改定を突破口としたことが、多くの人々の批判を広げる

(写真)第2会場の日比谷公園で大型スクリーンで視聴する憲法集会の参加者=3日、東京都千代田区
第一の矛盾は、改憲派が、憲法96条改定――憲法改定手続きの緩和――を、憲法9条改定の突破口として押し出したことです。このことが、逆に、憲法9条改定の是非をこえて、多くの人々の批判を広げる結果となっているのではないでしょうか。
権力を縛るのが憲法――憲法が憲法でなくなる「禁じ手」は許せない
みなさん。この問題は、単なる「手続き論」や「形式論」の問題ではありません。近代の立憲主義は、主権者である国民が、その人権を保障するために、憲法によって国家権力を縛るという考え方にたっています。国民を縛るのが憲法ではありません。権力を縛るのが憲法なのであります。(「そうだ」の声、大きな拍手)
そのために憲法改定の要件も、時の権力者に都合のいいように、憲法をコロコロと改変することが難しくされております。このことは、世界の多くの国々でも当たり前の大原則になっています。
国会による憲法改定の発議要件を、両院の3分の2以上から、過半数にする。すなわち一般の法律並みにする。これは、憲法が憲法でなくなる「禁じ手」であって、絶対に許すわけにはいきません。(大きな拍手)
9条改憲派からも批判の声――96条改定反対の一点で力をあわせよう
自民党や維新の会などは、“96条改定ならばハードルが低い”と見込んでことをはじめました。しかし、これは浅知恵だったと思います(笑い)。これはとんでもない見込み違いになっていると思います。
日本の弁護士がすべて加入する日本弁護士連合会(日弁連)も、96条改定は断固反対という声明を出しました。(拍手)
憲法9条改憲派で有名な慶応大学教授の小林節さんは、ラジオ番組のインタビューでこのようにおっしゃいました。
「本来、権力者を制限する、権力者を不自由にするのが憲法ですから、こんなことが許されたら憲法は要らないということになる。良心的な法律家、憲法学者はみな反対するでしょう。体を張って反対する。だって憲法が憲法でなくなっちゃうんですから。裏口入学みたいな改憲は、やったらダメです」(拍手)
私は、憲法96条改定反対の一点で、一致するすべての政党、団体、個人が協力し、国民的共同を広げ、改憲派の出はなを徹底的にくじくために、力をあわせることを心からよびかけるものです。(大きな拍手)
第二の矛盾 自民党「改憲案」の時代逆行の内容に、不安と批判が広がる
第二の矛盾は、自民党が、昨年4月に発表した「改憲案」そのものです。ここにもってまいりましたが、そのあまりの時代錯誤、時代逆行の内容にたいして、多くの人々から不安と批判の声が広がっております。
基本的人権を“不可侵の永久の権利”とした条文(97条)を全文削除
多くの人々の不安と批判の矛先は、自民党「改憲案」が、憲法9条2項を削除し「国防軍」を書き込んでいることとともに、基本的人権を「侵すことのできない永久の権利として信託されたもの」とした憲法97条を全文削除し、基本的人権を根底から否定するものとなっていることにむけられています。
憲法21条に保障された表現・結社の自由も、自民党「改憲案」では、「公益及び公の秩序」に反しない範囲のものしか認めないとされています。しかし「公益及び公の秩序」を決めるのはいったい誰でしょうか。時の権力者でしょう。そういうことになりましたら、あれこれの「人権」を掲げながら、それを「法律の範囲内」に押し縮めて、国民を無権利状態においやった大日本帝国憲法と少しも変わらなくなってしまうではありませんか。(拍手)
雑誌『アエラ』が、この問題について特集をして、「もしも自民党草案が憲法になったら」どうなるか、というシミュレーションを行っています。シミュレーションによると、このようなことになるという。
「先日は、皇室のあり方をテーマにした集会が中止になった。憲法が禁じる『公益及び公の秩序に反する行為』にあたる恐れがあると国が指摘し、市民会館が会場の利用を断ったとか。最近、同じ理由で原発反対デモも警官隊に解散させられていたけど、改憲以来、国が市民活動を制限するケースが目立つ」
こういう日本にすることを、いったい誰が望むでしょうか。
米紙も“世界中の人権擁護グループは反対世論の喚起を”とよびかけ
アメリカの新聞ロサンゼルス・タイムズは、自民党「改憲案」を痛烈に批判する論説を書きました。こう言っております。
「自民党は、権威主義日本、軍国日本に向けた基礎を築くための提案をしているのである。…世界中の人権擁護グループは、自民党による憲法に関する革命に反対する世論を喚起すべきである」(拍手)
よく自民党は、「日米は価値観を共有している」といいますね。しかし、「すべての人間は生まれながらにして不可侵の基本的人権を与えられている」という思想の世界史的源流はどこか。1776年のアメリカの「独立宣言」ではありませんか(拍手)。その条項を丸ごと削ってしまったら、アメリカから見ても「独立宣言」の精神の否定になるのではないでしょうか。(拍手)
私は、この自民党「改憲案」を読むことをお勧めしたいと思います。「とにかく読んでみてください」ということをいいたいと思います。一読すれば、誰でも必ず背筋がぞっとします(笑い)。これに丸ごと賛成する人は、ほとんどいないと確信するものであります。(拍手)
このような人類普遍の基本的人権すら否定して恥じない勢力が、憲法9条改定をもちだしている危険性を広い国民に明らかにしていこうではありませんか。(大きな拍手)
第三の矛盾 侵略戦争肯定・美化の本性をむき出しにしたこと
第三の矛盾は、9条改憲をめざす安倍政権が、この間、過去の侵略戦争と植民地支配を肯定・美化する歴史逆行の本性をむきだしにしたことであります。
靖国問題、「村山談話」見直し――侵略戦争肯定の立場は許せない
麻生副総理ら4閣僚が靖国神社に参拝し、安倍首相は真榊(まさかき)を奉納しました。靖国神社はA級戦犯を合祀(ごうし)していることだけが問題なのではありません。過去の日本軍国主義による侵略戦争を「自存自衛の正義のたたかい」「アジア解放のたたかい」と丸ごと美化し、宣伝することを、その存在意義とする特殊な施設であることこそ、最大の問題であります。ここへの参拝や奉納は、侵略戦争を肯定する立場に自らの身を置くことを宣言するものにほかなりません。
安倍首相は、韓国や中国などからの批判にたいして、「わが閣僚においては、どんな脅かしにも屈しない」と言い放ちました。この傲慢(ごうまん)きわまる姿勢、この居直りの姿勢を許すわけにはいかないではありませんか。(大きな拍手)
さらに安倍首相が、「村山談話」の見直しに言及し、「侵略の定義は定まっていない。国と国との関係でどちらから見るかで違う」とのべたことも重大です。あの戦争を侵略といわないつもりでしょうか。ポツダム宣言を認めないつもりでしょうか。首相が、過去の侵略と植民地支配を「国策の誤り」と認めた「村山談話」の到達点を、大幅に後退させようという歴史逆行の意図をもっていることは明らかです。これは絶対に許してはならないということを、私は訴えたいのです。(拍手)
戦争の善悪の区別もつかない勢力が、武力で海外にのりだす危険
米国の主要紙もそろって社説で安倍首相の恥知らずな言動を厳しく批判しました。
過去の侵略戦争を肯定・美化する勢力――戦争の善悪の区別もつかない勢力が、憲法9条を変えて海外に武力でのりだすことほど危険なものはありません。
みなさん。国会の中だけみれば、改憲派は数が多いように見えます。しかし国民の中では理性をもって憲法問題を考えようという人々が多数であります。
そして、安倍内閣の改憲への暴走は、みずから矛盾と破たんをつくりだしています。その弱点を徹底的に突き、この暴走を世論と運動で孤立させるために、力をつくそうではありませんか。(大きな拍手)
9条の生命力を生かし、アジアと世界の平和に貢献する日本を
改憲派は、「北朝鮮や中国との関係を考えても憲法改定が必要」との宣伝を行っています。維新の会の石原共同代表などは、党首討論で、北朝鮮問題は「改憲の好機」だとまで言って、憲法改定をけしかけました。
北朝鮮、中国――道理にたった外交交渉による解決に徹することこそ
しかしみなさん。北朝鮮問題にしても、中国との紛争問題にしても、何よりも大切なことは、道理にたった外交交渉による解決に徹するということではないでしょうか(拍手)。この点で、安倍首相はそういう努力をやっていますか。どちらの問題についても、対話による解決の外交戦略をもっていないではありませんか。
もっぱら「力対力」の立場にたって、これらの問題を、軍事力強化、憲法9条改定に利用しようという態度をとっていることこそ、思慮も分別もない最悪の党略的態度だということを、私は言いたいと思います。(大きな拍手)
ASEAN方式(紛争の対話による解決)を北東アジアに広げよう
みなさん。人類社会で紛争――もめ事をなくすことは難しいかもしれません。しかし紛争を戦争にしないことはできます。人類の英知によってそれは可能です。
現に東南アジアの国々――ASEAN(東南アジア諸国連合)は、TAC(東南アジア友好協力条約)やARF(アセアン地域フォーラム)など、多国間の対話の枠組みをつくり、それを域外にも広げていますが、その合言葉は、「紛争を戦争にしない」「紛争の対話による解決」であります。
こうしたASEAN方式――アセアン・ウェイを、北東アジアに広げるという構想こそ大切ではないでしょうか。(拍手)
そして「紛争を戦争にしない」という点では、その最も先駆的な財産を私たち日本国民はもっているではありませんか。それが憲法第9条です。(大きな拍手)
みなさん。憲法9条を守りぬくとともに、その生命力を存分に生かして、アジアの平和、世界の平和に貢献する日本をつくろうではありませんか。そのことを訴えまして、私のあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。(大きな拍手)