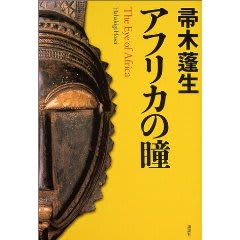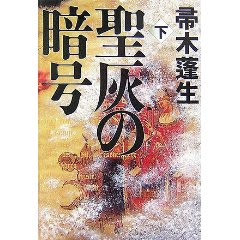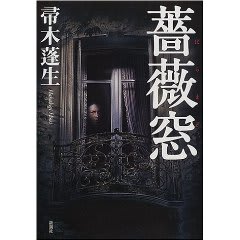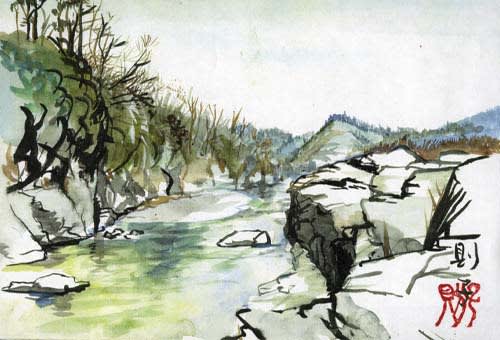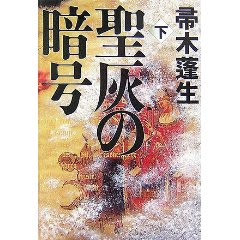
やっと読み終わった
ミステリー仕立てだかれど
私の関心は
ローマ教会とカタリ派の論争
私にはキリスト教の知識がないので
分かりにくいけれど
九州の人はキリシタンが迫害を受けても
信仰を守ったことを
関東に住む私たちよりも
身近な歴史と感じているのだろうか?
人にとって
自分のモラルは
何処から来てるか考えてみると
面白い
・高校の修学旅行中に
夜映画を見に行った
教師が黙認した
というこれはナツさんの話
一方
・ゆすらうめさんの話では映画は保護者同伴でないと駄目だったそうだ!
・映画といえば
私も高校生のとき辛気臭い試験勉強に飽きて
試験前はぱーっと映画でも見て
脳みそリフレッシュしたほうが
結果オーライだわ
と
職員室に新聞を見に行って
映画欄を見漁っていたら(新聞には何処で何の映画をやってるか書いてあった)
担任の先生
あらあらまあまあ
とあきれながらも叱りはしなかったのを思い出した
どういう風に
自分の中のモラルを築いてきたか
それは
本当に色々
道徳心の足りない私が
一番チリチリ守るのが時間
って
考えたら本当に変
ここ田舎の人は
どうやら
人様に後ろ指を刺されない
というのが基準のような気がする
人目をはばからない私には
違和感がある
いったい何を大事だと思って暮らしていくのか
しみじみ考えてる
とはいえ
道徳的な遊工房になるわけではないが
宗教というのとも縁がなく暮らしてる
と思い込んではいるけれど
多分血肉となっているものの考え方というものがあって
自力で何もかも分かるわけにも判断できるわけでもないとは
分かってはいる
それでも
教育とか子育てとか考えるときは
子の自律的な成長をうんと大事にしたいという思いは強く
それも
自分が育ってきたことと深く結びついてる
考え方だなと思った
私が育ったころは
戦後の民主主義教育が盛んな時期で
どの段階でも
かなり自由に教育を受けてきた
小学校ではクラスで犬を飼ってたし
中学では学校で飴をなめるのも早弁も
悪ではなく学校帰りに渋谷や自由が丘で映画も見た
高校では
空き時間に銀座まで出て行ったり
制服のまま新宿の風月堂でお茶しながら先輩たちの芸術論を聞いてたりした
後に
東京東部の学校には坊主頭を強制する学校
スカートの膝下何センチと測る物差しがあるような教育が
まかり通っていたのに仰天したし
一方では
中学生が
遠足の目的地決めから行程まで
生徒の手で運営させる教育も行われてたり
日本中が
千差万別の教育理念で教育が施されてきたことに
これが日本らしいのかもしれないと思った
わが子の通う学校には日本全国から子供が集まるので
中学校時代にどんな校則
隠れ校則があるか出し合っては
自分たちのおかれてた環境を相対化して見直すような授業があった
子供たちは
笑い転げながら概念砕きというのをやっていたわけだ
もうじきクリスマス
サンタなんか作って楽しむし
正月が来れば初詣に行くし
墓参り命の高齢者にはついていくし
宗教的には寛容極まりない
というか
信仰と縁がないだけかもしれないけれど
この小説に出てくる
カタリ派はなぜか九州で迫害を受け焼き殺されたキリシタンを思わせる
宗教戦争って こういう私には理解するのが難しい
さて
今日はKINU洋画会
もう一枚
紬の人を描くのです
ルンルン











 でしょうね
でしょうね