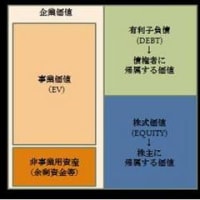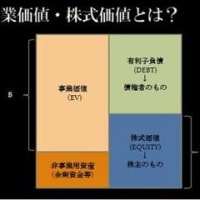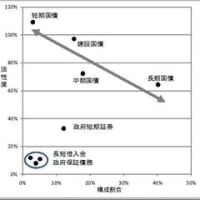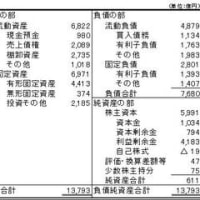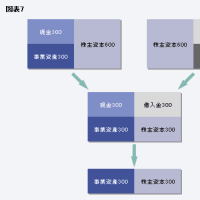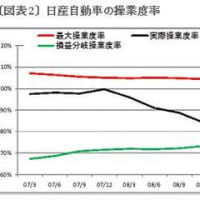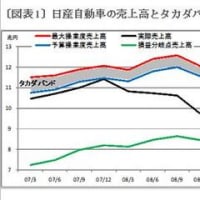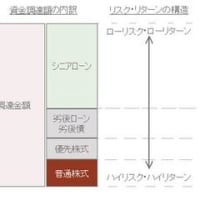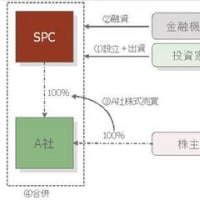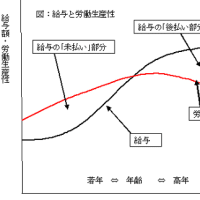Gross profit = 売上総利益
EBITDA =キャッシュ創出力= Gross profit - SGA → P/Lには出てこない(単独でキャッシュベース)
EBIT =営業利益
EBT =税前利益
EBI =長期リスク提供者への分配前の収益性 = NOPLAT → P/Lには出てこない(単独ではキャッシュベースではない)
E =純利益 = 株主の取り分
EBITDA=経常利益+支払利息-受取利息+DP費
EBITDAは「税引き前償却前金融収支前利益」で、AはAmortizationのことであり、無形固定資産(のれん代)の償却費を表します。
金利支払前の税引き後利益に、DP費をプラスした指標は、「営業活動によって得られたCF」に近い意味を持ちます。そこからさらに税金を足し戻したのがEBITDAということになります。
DP費と税金を足し戻したEBITDAは、DPの方法、金利、税率などの会計基準が利益に与える影響を最小限にしているので
「海外の同業他社との収益力の比較に有効」
というメリットがあります。
また、投資を積極的に行っているため赤字になっている企業でも、金利の支払が除かれ、結果として数値がプラスになる可能性があります。よって
「投資の効果が本業の業績(企業が年間に創出するCF)にどのように反映されるかがわかりやすい」
というメリットもあります。
①
EBITDA =アンレバー + CF化 + 無税
EBIT =アンレバー + 無税
EBT =レバー + 無税
→レバー・アンレバーのポイントは支払利息を控除しているか否か。
EBIが出てくれば利息は払っていないのでアンレバー、EBIがなければ利息を払っているのでレバー
→アンレバーとはレバレッジを効かせていないわけではなく、無負債だと暫定的に仮定しているだけ。
→CF化のポインとはDP前(EBDAがある)で見ているかどうか。
→EBTがあれば無税、Tがなければ有税
・EBITDA=キャッシュ創出力= EBIT + DP費 = Gross profit - SGA
・EBITとは金融収支前経常利益です。EBITは企業が経常利益のうち金融的な収支を差し引いたものです。
・EBIT=(経常利益+支払利息-受取利息)
・EBI = EBITDA - 税金(T) - DP費 = NOPLAT
→ EBIがあるからアンレパーの世界を見ている。だがTが無いので「有税」だ、NOPLATは無負債であるが、税金を払ったケースだと考えてよいだろう。
→ NOPLATは債権者への分配前なので、債権者・株主比率が可変とする分析によく用いられる。
→ NOPLATはキャッシュではなく企業の資産サイドの収益性(利益獲得能力)を見る指標だ。
②
FCF と NOPLAT と EBITDA の関係
EBITDA=NOPLAT + 税金 + DP費
NOPLAT(EBI)=EBITDA -税金 -DP費
FCF = EBITDA -税金 -運転資本の増減-設備投資額
FCF = NOPLAT +DP費-運転資本の増減-設備投資額
(※ ここで純投資 =運転資本の増減 + 設備投資額 - DP費)
FCF = NOPLAT - 純投資
(※ ここで 投資比率 =純投資/NOPLAT)
FCF = NOPLAT - (NOPLAT × 投資比率)
FCF = NOPLAT(1-投資比率)
(※ ここで 投資比率 = g/ROIC or g = ROIC×投資比率)
FCF = NOPLAT(1-g/ROIC) ← バリュー・ドライバーの分子
ちなみに・・・FCF = NOPLAT(FCF/NOPLAT)
※
EVA = NOPLAT -(投下資本×WACC)
※バリュードライバー式
V = FCF/(WACC-g) = NOPLAT(1-[g/ROIC])/(WACC-g)
EBITDA =キャッシュ創出力= Gross profit - SGA → P/Lには出てこない(単独でキャッシュベース)
EBIT =営業利益
EBT =税前利益
EBI =長期リスク提供者への分配前の収益性 = NOPLAT → P/Lには出てこない(単独ではキャッシュベースではない)
E =純利益 = 株主の取り分
EBITDA=経常利益+支払利息-受取利息+DP費
EBITDAは「税引き前償却前金融収支前利益」で、AはAmortizationのことであり、無形固定資産(のれん代)の償却費を表します。
金利支払前の税引き後利益に、DP費をプラスした指標は、「営業活動によって得られたCF」に近い意味を持ちます。そこからさらに税金を足し戻したのがEBITDAということになります。
DP費と税金を足し戻したEBITDAは、DPの方法、金利、税率などの会計基準が利益に与える影響を最小限にしているので
「海外の同業他社との収益力の比較に有効」
というメリットがあります。
また、投資を積極的に行っているため赤字になっている企業でも、金利の支払が除かれ、結果として数値がプラスになる可能性があります。よって
「投資の効果が本業の業績(企業が年間に創出するCF)にどのように反映されるかがわかりやすい」
というメリットもあります。
①
EBITDA =アンレバー + CF化 + 無税
EBIT =アンレバー + 無税
EBT =レバー + 無税
→レバー・アンレバーのポイントは支払利息を控除しているか否か。
EBIが出てくれば利息は払っていないのでアンレバー、EBIがなければ利息を払っているのでレバー
→アンレバーとはレバレッジを効かせていないわけではなく、無負債だと暫定的に仮定しているだけ。
→CF化のポインとはDP前(EBDAがある)で見ているかどうか。
→EBTがあれば無税、Tがなければ有税
・EBITDA=キャッシュ創出力= EBIT + DP費 = Gross profit - SGA
・EBITとは金融収支前経常利益です。EBITは企業が経常利益のうち金融的な収支を差し引いたものです。
・EBIT=(経常利益+支払利息-受取利息)
・EBI = EBITDA - 税金(T) - DP費 = NOPLAT
→ EBIがあるからアンレパーの世界を見ている。だがTが無いので「有税」だ、NOPLATは無負債であるが、税金を払ったケースだと考えてよいだろう。
→ NOPLATは債権者への分配前なので、債権者・株主比率が可変とする分析によく用いられる。
→ NOPLATはキャッシュではなく企業の資産サイドの収益性(利益獲得能力)を見る指標だ。
②
FCF と NOPLAT と EBITDA の関係
EBITDA=NOPLAT + 税金 + DP費
NOPLAT(EBI)=EBITDA -税金 -DP費
FCF = EBITDA -税金 -運転資本の増減-設備投資額
FCF = NOPLAT +DP費-運転資本の増減-設備投資額
(※ ここで純投資 =運転資本の増減 + 設備投資額 - DP費)
FCF = NOPLAT - 純投資
(※ ここで 投資比率 =純投資/NOPLAT)
FCF = NOPLAT - (NOPLAT × 投資比率)
FCF = NOPLAT(1-投資比率)
(※ ここで 投資比率 = g/ROIC or g = ROIC×投資比率)
FCF = NOPLAT(1-g/ROIC) ← バリュー・ドライバーの分子
ちなみに・・・FCF = NOPLAT(FCF/NOPLAT)
※
EVA = NOPLAT -(投下資本×WACC)
※バリュードライバー式
V = FCF/(WACC-g) = NOPLAT(1-[g/ROIC])/(WACC-g)