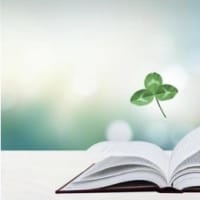2025年1月18日土曜日。
この日も最高気温が前日よりも数度低め。正直、畑に出たくない気分ですが…。2日前の第二弾コマツナ畑(11月10日種まき分)の生育が気がかりで。
1月12日は土が湿り気味だったため、酢酸カルシウム液(卵の殻粉末を酢で溶かし、100倍希釈したもの。以後、「卵酢」と呼ぶ)だけをスプレー。
ところが、1月16日はカラカラに乾いていて、危ない!
通常通り、米汁をうすめた水やりをジョウロでおこなったあとで、石灰+卵の殻粉末を追肥のうえ、卵酢スプレーを念入りに。
本日1月18日も、他の種まき後と発芽中などの畝と同様、基本の水やりをしたあとで、卵酢スプレーを。
その効果を今回は画像で検証してみるものです。
トップ画像は畝の第5列目、西側からの撮影。この箇所は極端に黄化はないのですが、けっこう隠れた場所に変色が多いところ。黄色くなった葉はカットした部分もあるので、卵酢で戻ったわけではなく。2回目までは曇天模様だったのだけれども、3回目あたりから晴れの日が続いたため、旺盛に光合成ができたのでしょう。葉っぱがかなり濃いめ。
左ふたつの撮影時は15時ぐらい。
撮影の時間帯や角度で陰影が変わるので色合いが違うこともあるのですが、肉眼で観察しても、卵酢をかける前はとにかく葉が黄緑いろで。本日のように肉厚でもありませんでしたね。
ただ卵酢をかけたあとに虫に食われたあとがちらほら。
虫害を減らす効果は薄いのかも…。

こちらはお隣の畝第6列目。
やはり葉が肉厚で色も松に近く。ピンと立ってきた感じです。4回目のときは前回カルシウム追肥をしたあとなので、すこし葉が大きくなっていました。
畑の規模が大きくなり、卵の殻が足りなくなってきたので、卵酢で溶かす場合はすこし多めに。
教本では、卵の殻1個あたり酢100ミリリットルとあったのですが、私は先に粉末状にすりつぶしてしまうので、スプーンでけっこう多めに投入、酢は最初少なめ(20ミリリットル)にしていました。そしたら、酢がカルシウムと融合して液体が減ってしまったので、1回で100ミリリットルぐらい作り置きするようにしています。この原液は陽のあたらない場所で2箇月ぐらい保存できるらしい。希釈したら、早めに使い切ったほうがよさそうです。

ただし、卵酢でも助けられなかった株も。
第4列目の間引き菜植え替え世代はもはや絶望的。第5列目以降でも場所によっては傷みがはげしいものも。
これは卵酢のせいだけではなくて。
間引きしたあとに株もとの土寄せがもろく、根が浮き上がっていたりしたもの。冬間の生育が悪いので間引きを延ばしのばしにしていたら、密集しがちで陽あたりのよくない葉もあったのでしょう。

こちらは2日前まではわりと青めだったのに、急激に黄化が進んでしまった株。東端にあるのですが、ここは隣の建物の日陰に入りやすい。さらに卵酢スプレーを根もとにかけすぎて、土がゆるみ、根が浮き上がってしまった可能性もあります。噴射口の勢いが強すぎるので、すこし離してスプレーしたほうがいいのかも。
黄ばんだり、紅くなったり、紫がかったり。
変色している葉がありますが、食べてみるとけっこう甘い! ホウレンソウは冬の寒さにあてると糖度アップといいますが、コマツナでもそうなのかも。
卵酢をかけたとしても元気になるのは変色前のものだけ。
なので、すこしでも色の異変があったものや虫食い葉はまだ食べれそうなうちに摘むことにしました。葉の間引きとりは第一弾のとき、収穫前のぞんぶんに大きくなったものを行っていたのですが。今回は手遅れになる前にどんどん葉だけとっていくほうがいい気がしました。お味は悪くはないので。

本日の間引きとりでの収穫分は、お椀一杯なり。
やはり冬なので、秋口ほど巨大化するのは望めないのでしょう。
冬もの葉物野菜はあまり欲張らずに収穫したほうがよさそうですね…。
とりあえず、卵酢+カルシウム追肥でストップしていた生育がまた復活してきたので、土壌障害や病気ではなく、肥料が足りない栄養不足と日照不足が原因だったようです。これで駄目ならばチッソ豊富な化成肥料の購入を覚悟していましたが、もうすこしお手製の卵酢で様子見してみましょう。
この日はホウレンソウ畑(2025年1月2日種まき分)の新聞マルチはりの作業も途中までしました。
これについては、また別の記事で。
(2025.01.05~18撮影分、01.18記録)