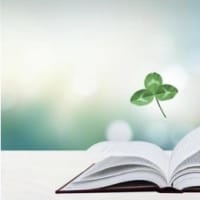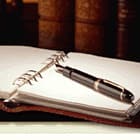
皆さんは本のどこから読みますか?
私はまず目次を読み、最初の数頁をあらまし目通ししてから、後書きがあれば読みます。よほど最初から引き込まれた本なら別ですが。
そして最後に著者紹介欄をチェック。
ここで経歴をやたらと盛っていそうな気配がしたり、一定年数以上の会社員もしくはある分野のプロフェッショナルとしての実績がありそうと判断した場合に限って、定価で買います。
つまり、うさんくさい、フリーターまがいの遍歴でなりあがりライターになった方のは購入しません。近年はSNSで有名になると、すぐに雑誌で連載をもったり、マスコミに顔出ししたりするケースが増えています。しかし、そういう方の発言を聞くと、コメンテーターとしてやや眉をひそめたくなるようないい加減な言葉も多いからです。露出が多くなって、いつのまにか本業が疎かになっていく。いったい、なんの専門家なのか。特に芸能人上がりの人の本はほとんど買いません。
お仕事小説のように、私たちの身近にありそうな業界人の職場事情を扱った創作も増えていますよね。入念は取材を重ねたうえで人物造形や背景の設定がされているものですが、その小説家自体がある程度のビジネス経験がないと書けないであろうというものの見方が、その著作には表れています。
最近読んだ本では、『92歳総務課長の教え』(玉置泰子著:ダイヤモンド社)という本がオススメ。
大阪の中小企業メーカーで勤続66年、世界最高齢の総務事務員としてギネスブック認定されたという女性の書いたエッセイ本です。戦後すぐ商業高校を卒業し、父を亡くしたため一家の大黒柱として勤めに出た女性の、お仕事にかける情熱や意気込みが分かる本です。
しかも、この女性は定年退職したうえに、年下の上司に仕えています。
女性として社内では生き字引ような存在でありながら、けっして若手には説教や自慢話を施してはならない、時には若手の知恵を借りて協力することが大事だとも語っています。これは中高年や管理職がやりがちな悪手をいさめているわけですよね。私の勤め先にも会長職を務めたのち、一介の平社員として現場の監督指揮を任されている方がいます。
現在は、生涯現役で働く時代、過去の実績や習熟度が薄らいでしまうのも早いものです。
変化についていくには、古いやりかたにしがみつかず、新しいものをむやみに信奉せず、各世代が協力して会社運営をし、働くことで個々人の幸せを追求する時代なのです。
ビジネスエッセイの類はいくらでも読みましたが、その多くが経営者やリクルートなどの有名企業を経由して脱サラしたエリート層の手によるもの。
『プレジデント』誌などのビジネス雑誌に連載をもっているような高所得者のご意見は、我々しがない一般庶民の労働者の考えとは隔離しています。こうした管理者側が説くビジネスのお説教本は、精神的パワハラに近いものも多く、生まじめな人間が読み過ぎると劣等感にさいなまれノイローゼになります。
その点、この女性のように、地道に働く側、雇われる側からの視点で描かれたお仕事論は、わかりやすく、親しみやすく、これからの世代の模範ともなります。何ごとにも挑戦する姿勢、改善点を見出すこと、整理整頓の重要性、話の聞き方、上役との付き合い方などなど。どのビジネス本にも書かれてはいることですが、実地で場数を踏んだ方の声はよく胸に響きます。
私が特に胸に刺さった言葉は、「悪口は自分の運を落とす」というもので。
これは、日頃、辞めてしまった職場の悪口をブログに書き連ねて憂さ晴らしをしている自分にとっては反省すべきところです。
行きつけの郊外の大型書店に行くと、雑貨もののコーナーが増えて、文芸書のスペースがかなり削られていました。
漫画やラノベ、文庫本はそのままですが、定価2000円以上はする単行本の、とくに純文学はとにかく売れないのでしょう。私も小説やエッセイは厚みのあるものは不便で、文庫本発売まで待つ方なので。
会社員として、あるいは事業主として、地味ながらしっかりとは働いてきた人の話には傾聴に値するものがあります。仕事の合間に旺盛な読書家であった方も多く、教養深く、読んでいてためになることも多いもの。
逆にうさんくさいと思うのは、社会人経験もないのに東大だの学歴ばかりを売りして本を出す書き手のものですね。先行書物のいいとこどりをしたツギハギ本で内容がかなり薄いので買うには値しません。高学歴でも、仕事の上手くいく習慣を身につけているとは限らないもの。文章が美しくとも、中身が空疎な言葉は誰かの人生を変えたりはしません。文章の巧拙さでいえば、昔の文豪や古典の名作にはかなわないのですから。
この世の中は、一部の思想家や芸術家肌、学者先生、政治家、経営者などのお偉方ばかりで成り立っているわけではありません。
そうした仕事は、たいがい自由で、クリエイティブで、ひとりで完結できるけれども、多くの人間にとってかならず同じ価値があるとは限らないのです。
いま、本に求められているのは、私たち労働者に近い目線の、苦労をわかちあえるような方々の経験値や未来へのビジョンなのでしょう。
私はそうした方の、ほぼ無名に近いながらも、伝えるべき言葉と行動力のある本が大好きです。この世界は一部のいまを時めく、輝けるひとのためにだけあるのではないのですから。
(2022/06/19)
読書の秋だからといって、本が好きだと思うなよ(目次)
本が売れないという叫びがある。しかし、本は買いたくないという抵抗勢力もある。
読者と著者とは、いつも平行線です。悲しいですね。