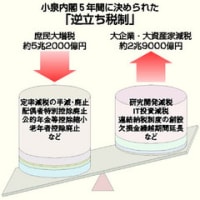④ロシア革命とシベリア出兵
ロシア革命について本書は以下のように書いています。「武装蜂起したレーニンの一派は、労働者と兵士を中心に組織された代表者会議(ソビエト)を拠点とする政府をつくった。その後、他の党派を武力で排除し、みずから率いる共産党の一党独裁体制を築いた。ソビエト政府はドイツとの戦争をやめ、革命に反対する国内勢力との内戦に没頭した。ロマノフ王朝の皇帝一族と、共産党が敵とみなす貴族、地主、資本家、聖職者、知識人らが多数、処刑された。」革命に行き過ぎたテロ行為が伴ったことは事実だとしても、ロシア帝政の国内支配体制がどんなに苛烈なものであったか、農奴制社会の無権利状態に触れないのでは片手落ちです。ソビエト政府への敵視は、シベリア出兵(1918~22年)についての記述からも、他国への干渉戦争という認識を欠落させています。そして本書は、これ以後、共産主義国をそれ自体として仮想敵国視して行きます。
⑤排日運動を口実にした中国侵略の正当化
清朝滅亡後の国民党や共産党による中国統一の動きが大きくなると日本は中国への干渉を強めたのですが、本書はその責任を排日運動に帰しています。「中国の国内統一が進行する中で、不平等条約によって中国に権益をもつ外国勢力を排撃する動きが高まった。それは列強の支配に対する中国人の民族的反発だったが、暴力によって革命を実現したソ連の共産主義思想の影響も受け、過激な性格を帯びるようになった。勢力を拡大してくる日本に対しても、日本商品をボイコットし、日本人を襲撃する排日運動が活発になった。」ここでは、共産主義思想への犯罪視も干渉の正当化に利用されています。そもそも、民族の尊厳を踏みにじる、不当な占領支配や内政干渉が行われていたから排日運動が起こったのです。排日運動を理由にした侵攻は逆立ちした論理です。
本書は更に日本の政治が軍部独裁へ移行した原因をも排日運動に求めています。「(幣原外相による協調外交にもかかわらず、)中国の排日運動はおさまらなかった。日本では軍部を中心に、中国に対する内政不干渉主義で対処するのはむずかしいと考える人もあらわれ、幣原の外交を軟弱外交として批判する声が強くなった。…軍人のあいだには、排日運動にさらされていた満州在住の日本人の窮状と、満州権益への脅威に対処できない政党政治に対する強い不満が生まれていた。…国民も、…政党政治に失望し、しだいに軍部に期待を寄せるようになった。」資料としても、排日運動を非難するものが並べられ、抗日運動側の発言はありません。
こうして1931年、満州事変が起こることになりましたが、本書はこれを軍部の専行として批判的視点に立つのでなく、「国民的支援」を送っています。「満州で日本人が受けていた不法行為の被害を解決できない政府の外交方針に不満をつのらしていた国民の中には、関東軍の行動を支持する者が多く、陸軍には多額の支援金が寄せられた。」
⑥大東亜戦争=アジア解放戦争論
以後、日中戦争から太平洋戦争に至る記述が始まりますが、ブロック経済圏を巡る列強間の利害対立から、日本が経済封鎖で追いつめられ、開戦を決意したという説明になっています。そこには、中国、アジア諸国への侵略戦争という認識はありません。『自存自衛』のための戦争、さらには、「アジアに独立の希望を広げる」戦争だったというのです。本書の「大東亜会議とアジア諸国」という二ページは、7割がアジア独立に寄与したという記述、3割がアジアの人々に損害を与えたという記述に当てられ、まとまりのない説明になっています。
⑦ナチズムとスターリン粛清の強調による日本の戦争責任の中和化
戦争の犠牲者についてのコラムも、「20世紀の戦争と全体主義の犠牲者」と題し、日本が侵略戦争で各国にもたらした被害と犠牲者への責任を曖昧にしています。「日本軍も、戦争中に侵攻した地域で、捕虜となった敵国の兵士や民間人に対して、不当な殺害や虐待を行った」と記しつつも、その直前に、「実際には、戦争で非武装の人々に対する殺害や虐待をいっさいおかさなかった国はなかった」と問題を相対化し、米軍による空襲と原爆投下、ソ連によるシベリア抑留を強調しています。そしてナチスによるユダヤ人や障害者の虐殺、ソ連でのスターリン粛清について述べた後、コラムをこう締めくくっています。「二つの世界大戦は各国に大きな被害をもたらしたが、その一方で、ファシズムと共産主義が、戦争とは異なる国家の犯罪として、膨大な数の犠牲者を出したことも忘れてはならない。」ナチスとソ連をスケープゴートにして、日本軍による毒ガス戦、細菌戦、そのための生体実験を初めとする非人道的犯罪行為、アジアでの抗日運動、国内での反戦運動への残酷な弾圧には目隠しで通しています。本書では、「二つの全体主義」が特殊な思想的妖怪のように描かれ、日本もまたファシズム国家になっていたという認識に欠けるものとなっています。そして、戦前の日本にファッショ体制を敷く道具となった治安維持法を、共産主義の脅威の名の下に正当化するということまで容認しています。本書は注で以下のように説明しています。「日本でも、日本共産党がコミンテルン日本支部としてひそかに設立された。1925年、日本政府はソ連と国交を結んだが、それによって国内に破壊活動がおよぶことを警戒し、同年、私有財産制度の否認などの活動を取りしまる治安維持法を制定した。」ここには同法の下で行われた反戦運動や社会運動の弾圧への批判はありません。
こうした記述は、東京裁判を戦勝国による一方的裁判ととらえる記述につなげようとするものです。コラム「東京裁判について考える」では、結論こそ「東京裁判については、国際法上の正当性を疑う見解や、逆に世界平和に向けた国際法の新しい発展を示したとして肯定する意見があり、今日でもその評価は定まっていない」と、両論併記ですが、それ以外の部分は否定論ばかりです。奇妙なのは、ここでマスメディア批判をしていることです。「GHQは、占領直後から、新聞、雑誌、ラジオ、映画のすべてにわたって、言論に対するきびしい検閲を行った。また、日本の戦争がいかに不当なものであったかを,マスメディアを通じて宣伝した。こうした宣伝は、東京裁判と並んで、日本人の自国の戦争に対する罪悪感をつちかい、戦後の日本人の歴史に対する見方に影響を与えた。」侵略戦争に対する反省や、戦前の軍国主義に対する批判をGHQによる宣伝としかとらえられない本書の執筆者の時代錯誤に驚かされます。そして、戦前の政府による検閲や、大本営発表による報道操作にほとんど触れてこなかった本書が、ここでは、検閲された新聞と墨で消された教科書の写真を載せているのです。本書執筆者たちの「被害者意識」の強さを見ることができます。
⑧「国際社会における日本の役割」としての軍事的貢献の示唆
本書は、冷戦下での独立の回復と警察予備隊(自衛隊)の発足、日本経済の発展、ソ連崩壊による冷戦構造の終結についてのべ、「国際社会における日本の役割」という項で本書を締めくくります。「一部に共産主義の国家が残り、また民族や宗教の対立をもとにした地域紛争もなくなりそうにない。こうした中で、独自の文化と伝統をもつ日本が自国の安全をしっかり確保しつつ、今後、世界の平和と繁栄にいかに貢献していくかが問われている。」他国、とりわけ共産主義国からの侵略と異文化民族からのテロの脅威への安全保障策の強化が示唆されています。というのも、その前段には、「この(湾岸)戦争では、日本は憲法を理由にして軍事行動には参加しなかせず、巨額の財政援助によって大きな貢献をしたが、国際社会はそれを評価しなかった。国内では日本の国際貢献のあり方について深刻な議論がおきた。」という文章が記されているのです。こうした口実からイラクに自衛隊の「人的支援」が成されたのであり、憲法改正も検討されてきているのです。
⑨敗戦へのこだわり
本書は、後書きにあたる「歴史を学んで」で、ここ半世紀にわたって、日本人が方向を見失っている理由を二つあげています。一つは、欧米諸国に追いつくという目標を達成したことによる目標の喪失であり、もう一つは、まだ癒えない敗戦の傷跡です。「日本は長い歴史を通して、外国の軍隊に国土を荒らされたことのない国だった。ところが、大東亜戦争敗北して以来、この点が変わった。全土で50万人もの市民の命をうばう無差別爆撃を受け、原子爆弾を落とされた。その後の占領によって、国の制度は大幅に変更させられた。戦後、日本人は、努力して経済復興を成しとげ、世界有数の経済大国の地位を築いたが、いまだにどこか自信をもてないでいる。戦争に敗北した傷がまだ癒えない。」米軍による無差別攻撃を責めて、国民にそうした事態をもたらした政府への批判はありません。象徴天皇制や戦後民主主義は、敗戦により押しつけられた、「国体」の変更であったとでもいっているようです。また、敗戦の傷を癒し、自信を持ち直すために、どこかの国との戦争に勝たなければならないとでも思っているのでしょうか。本書の怖さを象徴する文章です。
(3) 世界史の中での日本史
以上、二つの視点から本書の記述をみてきました。そこには、日本の歴史を、日本国民の人権・主権の発展史としてとらえるのでなく、天皇の国史としてとらえる日本史が描かれていました。本書が「独自の文化と伝統をもつ日本」というとき、そこには、「万世一系の天皇」を戴く日本がイメージされていることは、本書を通読してみれば明らかです。
また、日本の独立を重視する視点は、それ自体としては大切なものですが、それは同時に、他国の主権をも尊重するものでなければなりません。日本史を外交・戦争史としてみるとき、私たちは、単なる「チーム日本」の勝ち負けの歴史としてではなく、近隣諸国との友好と、国際平和の発展史としてとらえていく必要があります。本書は他国の主権や他国民の人権に対する目配りが欠けています。本書が語る日本国民の独立への熱い情熱と同様に、朝鮮、中国の人々もそれぞれの独立への熱い願いをもって、歴史を歩んできたのです。「各国には各国の歴史がある」というとき、「だから、各国は各国の歴史を教えればよい」ということであってはなりません。相互の歴史観から一面性を克服し、相互理解を広げて行くことにこそ、これからの各国史を、国際平和の発展史にしていく鍵があるからです。
さて、お読み頂いた感想はいかがでしょう。他の教科書と読み比べたわけではありませんが、本書で子供たちが日本史を学ぶことを思うとやはり怖くなります。私は杉並区の和泉に住んでいることから、この通信を和泉通信と称しているのですが、その杉並区が本書を教科書に採用してしまいました。結果的に本書を採用した自治体は限られたものとなりましたが、単にアジア諸国から批判があるからということではなく、日本国民自体の問題として、歴史教科書問題への関心が求められると思います。
私は、今回、本書と一緒に、日中韓3国歴史教材委員会編「未来をひらく歴史、東アジア3国の近現代史」(高文研刊)を読みました。そして、朝鮮の人が書いた朝鮮史、中国の人が書いた中国史を日本人が読むことの大切さを実感しました。もちろん、これは、お互いにいえることですが、国際的相互依存がますます強まっている今日、お互いの人と社会の成り立ちを知っておくことは、相互発展のために不可欠です。
今回は詳細な紹介は致しませんが、日中韓三国の近現代史を見直すための好著としてお奨めします。
森 史朗


ロシア革命について本書は以下のように書いています。「武装蜂起したレーニンの一派は、労働者と兵士を中心に組織された代表者会議(ソビエト)を拠点とする政府をつくった。その後、他の党派を武力で排除し、みずから率いる共産党の一党独裁体制を築いた。ソビエト政府はドイツとの戦争をやめ、革命に反対する国内勢力との内戦に没頭した。ロマノフ王朝の皇帝一族と、共産党が敵とみなす貴族、地主、資本家、聖職者、知識人らが多数、処刑された。」革命に行き過ぎたテロ行為が伴ったことは事実だとしても、ロシア帝政の国内支配体制がどんなに苛烈なものであったか、農奴制社会の無権利状態に触れないのでは片手落ちです。ソビエト政府への敵視は、シベリア出兵(1918~22年)についての記述からも、他国への干渉戦争という認識を欠落させています。そして本書は、これ以後、共産主義国をそれ自体として仮想敵国視して行きます。
⑤排日運動を口実にした中国侵略の正当化
清朝滅亡後の国民党や共産党による中国統一の動きが大きくなると日本は中国への干渉を強めたのですが、本書はその責任を排日運動に帰しています。「中国の国内統一が進行する中で、不平等条約によって中国に権益をもつ外国勢力を排撃する動きが高まった。それは列強の支配に対する中国人の民族的反発だったが、暴力によって革命を実現したソ連の共産主義思想の影響も受け、過激な性格を帯びるようになった。勢力を拡大してくる日本に対しても、日本商品をボイコットし、日本人を襲撃する排日運動が活発になった。」ここでは、共産主義思想への犯罪視も干渉の正当化に利用されています。そもそも、民族の尊厳を踏みにじる、不当な占領支配や内政干渉が行われていたから排日運動が起こったのです。排日運動を理由にした侵攻は逆立ちした論理です。
本書は更に日本の政治が軍部独裁へ移行した原因をも排日運動に求めています。「(幣原外相による協調外交にもかかわらず、)中国の排日運動はおさまらなかった。日本では軍部を中心に、中国に対する内政不干渉主義で対処するのはむずかしいと考える人もあらわれ、幣原の外交を軟弱外交として批判する声が強くなった。…軍人のあいだには、排日運動にさらされていた満州在住の日本人の窮状と、満州権益への脅威に対処できない政党政治に対する強い不満が生まれていた。…国民も、…政党政治に失望し、しだいに軍部に期待を寄せるようになった。」資料としても、排日運動を非難するものが並べられ、抗日運動側の発言はありません。
こうして1931年、満州事変が起こることになりましたが、本書はこれを軍部の専行として批判的視点に立つのでなく、「国民的支援」を送っています。「満州で日本人が受けていた不法行為の被害を解決できない政府の外交方針に不満をつのらしていた国民の中には、関東軍の行動を支持する者が多く、陸軍には多額の支援金が寄せられた。」
⑥大東亜戦争=アジア解放戦争論
以後、日中戦争から太平洋戦争に至る記述が始まりますが、ブロック経済圏を巡る列強間の利害対立から、日本が経済封鎖で追いつめられ、開戦を決意したという説明になっています。そこには、中国、アジア諸国への侵略戦争という認識はありません。『自存自衛』のための戦争、さらには、「アジアに独立の希望を広げる」戦争だったというのです。本書の「大東亜会議とアジア諸国」という二ページは、7割がアジア独立に寄与したという記述、3割がアジアの人々に損害を与えたという記述に当てられ、まとまりのない説明になっています。
⑦ナチズムとスターリン粛清の強調による日本の戦争責任の中和化
戦争の犠牲者についてのコラムも、「20世紀の戦争と全体主義の犠牲者」と題し、日本が侵略戦争で各国にもたらした被害と犠牲者への責任を曖昧にしています。「日本軍も、戦争中に侵攻した地域で、捕虜となった敵国の兵士や民間人に対して、不当な殺害や虐待を行った」と記しつつも、その直前に、「実際には、戦争で非武装の人々に対する殺害や虐待をいっさいおかさなかった国はなかった」と問題を相対化し、米軍による空襲と原爆投下、ソ連によるシベリア抑留を強調しています。そしてナチスによるユダヤ人や障害者の虐殺、ソ連でのスターリン粛清について述べた後、コラムをこう締めくくっています。「二つの世界大戦は各国に大きな被害をもたらしたが、その一方で、ファシズムと共産主義が、戦争とは異なる国家の犯罪として、膨大な数の犠牲者を出したことも忘れてはならない。」ナチスとソ連をスケープゴートにして、日本軍による毒ガス戦、細菌戦、そのための生体実験を初めとする非人道的犯罪行為、アジアでの抗日運動、国内での反戦運動への残酷な弾圧には目隠しで通しています。本書では、「二つの全体主義」が特殊な思想的妖怪のように描かれ、日本もまたファシズム国家になっていたという認識に欠けるものとなっています。そして、戦前の日本にファッショ体制を敷く道具となった治安維持法を、共産主義の脅威の名の下に正当化するということまで容認しています。本書は注で以下のように説明しています。「日本でも、日本共産党がコミンテルン日本支部としてひそかに設立された。1925年、日本政府はソ連と国交を結んだが、それによって国内に破壊活動がおよぶことを警戒し、同年、私有財産制度の否認などの活動を取りしまる治安維持法を制定した。」ここには同法の下で行われた反戦運動や社会運動の弾圧への批判はありません。
こうした記述は、東京裁判を戦勝国による一方的裁判ととらえる記述につなげようとするものです。コラム「東京裁判について考える」では、結論こそ「東京裁判については、国際法上の正当性を疑う見解や、逆に世界平和に向けた国際法の新しい発展を示したとして肯定する意見があり、今日でもその評価は定まっていない」と、両論併記ですが、それ以外の部分は否定論ばかりです。奇妙なのは、ここでマスメディア批判をしていることです。「GHQは、占領直後から、新聞、雑誌、ラジオ、映画のすべてにわたって、言論に対するきびしい検閲を行った。また、日本の戦争がいかに不当なものであったかを,マスメディアを通じて宣伝した。こうした宣伝は、東京裁判と並んで、日本人の自国の戦争に対する罪悪感をつちかい、戦後の日本人の歴史に対する見方に影響を与えた。」侵略戦争に対する反省や、戦前の軍国主義に対する批判をGHQによる宣伝としかとらえられない本書の執筆者の時代錯誤に驚かされます。そして、戦前の政府による検閲や、大本営発表による報道操作にほとんど触れてこなかった本書が、ここでは、検閲された新聞と墨で消された教科書の写真を載せているのです。本書執筆者たちの「被害者意識」の強さを見ることができます。
⑧「国際社会における日本の役割」としての軍事的貢献の示唆
本書は、冷戦下での独立の回復と警察予備隊(自衛隊)の発足、日本経済の発展、ソ連崩壊による冷戦構造の終結についてのべ、「国際社会における日本の役割」という項で本書を締めくくります。「一部に共産主義の国家が残り、また民族や宗教の対立をもとにした地域紛争もなくなりそうにない。こうした中で、独自の文化と伝統をもつ日本が自国の安全をしっかり確保しつつ、今後、世界の平和と繁栄にいかに貢献していくかが問われている。」他国、とりわけ共産主義国からの侵略と異文化民族からのテロの脅威への安全保障策の強化が示唆されています。というのも、その前段には、「この(湾岸)戦争では、日本は憲法を理由にして軍事行動には参加しなかせず、巨額の財政援助によって大きな貢献をしたが、国際社会はそれを評価しなかった。国内では日本の国際貢献のあり方について深刻な議論がおきた。」という文章が記されているのです。こうした口実からイラクに自衛隊の「人的支援」が成されたのであり、憲法改正も検討されてきているのです。
⑨敗戦へのこだわり
本書は、後書きにあたる「歴史を学んで」で、ここ半世紀にわたって、日本人が方向を見失っている理由を二つあげています。一つは、欧米諸国に追いつくという目標を達成したことによる目標の喪失であり、もう一つは、まだ癒えない敗戦の傷跡です。「日本は長い歴史を通して、外国の軍隊に国土を荒らされたことのない国だった。ところが、大東亜戦争敗北して以来、この点が変わった。全土で50万人もの市民の命をうばう無差別爆撃を受け、原子爆弾を落とされた。その後の占領によって、国の制度は大幅に変更させられた。戦後、日本人は、努力して経済復興を成しとげ、世界有数の経済大国の地位を築いたが、いまだにどこか自信をもてないでいる。戦争に敗北した傷がまだ癒えない。」米軍による無差別攻撃を責めて、国民にそうした事態をもたらした政府への批判はありません。象徴天皇制や戦後民主主義は、敗戦により押しつけられた、「国体」の変更であったとでもいっているようです。また、敗戦の傷を癒し、自信を持ち直すために、どこかの国との戦争に勝たなければならないとでも思っているのでしょうか。本書の怖さを象徴する文章です。
(3) 世界史の中での日本史
以上、二つの視点から本書の記述をみてきました。そこには、日本の歴史を、日本国民の人権・主権の発展史としてとらえるのでなく、天皇の国史としてとらえる日本史が描かれていました。本書が「独自の文化と伝統をもつ日本」というとき、そこには、「万世一系の天皇」を戴く日本がイメージされていることは、本書を通読してみれば明らかです。
また、日本の独立を重視する視点は、それ自体としては大切なものですが、それは同時に、他国の主権をも尊重するものでなければなりません。日本史を外交・戦争史としてみるとき、私たちは、単なる「チーム日本」の勝ち負けの歴史としてではなく、近隣諸国との友好と、国際平和の発展史としてとらえていく必要があります。本書は他国の主権や他国民の人権に対する目配りが欠けています。本書が語る日本国民の独立への熱い情熱と同様に、朝鮮、中国の人々もそれぞれの独立への熱い願いをもって、歴史を歩んできたのです。「各国には各国の歴史がある」というとき、「だから、各国は各国の歴史を教えればよい」ということであってはなりません。相互の歴史観から一面性を克服し、相互理解を広げて行くことにこそ、これからの各国史を、国際平和の発展史にしていく鍵があるからです。
さて、お読み頂いた感想はいかがでしょう。他の教科書と読み比べたわけではありませんが、本書で子供たちが日本史を学ぶことを思うとやはり怖くなります。私は杉並区の和泉に住んでいることから、この通信を和泉通信と称しているのですが、その杉並区が本書を教科書に採用してしまいました。結果的に本書を採用した自治体は限られたものとなりましたが、単にアジア諸国から批判があるからということではなく、日本国民自体の問題として、歴史教科書問題への関心が求められると思います。
私は、今回、本書と一緒に、日中韓3国歴史教材委員会編「未来をひらく歴史、東アジア3国の近現代史」(高文研刊)を読みました。そして、朝鮮の人が書いた朝鮮史、中国の人が書いた中国史を日本人が読むことの大切さを実感しました。もちろん、これは、お互いにいえることですが、国際的相互依存がますます強まっている今日、お互いの人と社会の成り立ちを知っておくことは、相互発展のために不可欠です。
今回は詳細な紹介は致しませんが、日中韓三国の近現代史を見直すための好著としてお奨めします。
森 史朗