高橋 透
DJバカ一代
リットーミュージック, 2007
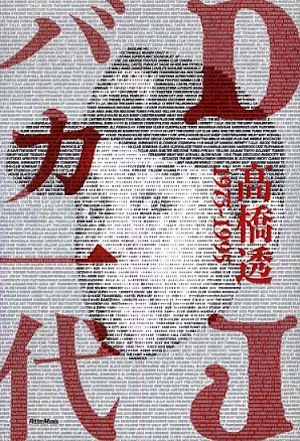
DJバカ一代
リットーミュージック, 2007
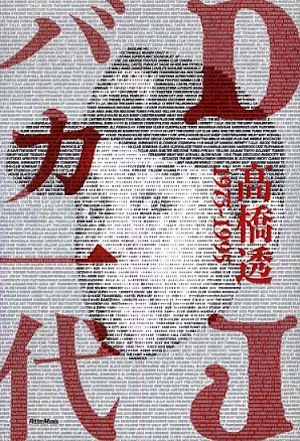
九十年代初頭、<ゴールド>のフロアに漂っていたド変態ヴァイヴが、現在のクラブ空間には果たして存在し続けているのか?あのディープ&ド変態な血を絶やしてはいけない!失われたヤバいヴァイヴをフロアに取り戻したい
ー 宇川直宏
これは50歳で今も現役のスーパーDJ・高橋透さんが半生をふりかえる自伝だ。
世にDJ論やDJ文化論は数あれど、では当のDJがいったい何を考え、どのように暮らしたり働いたりしているのかという現場レベルの「一次資料」となると意外に少ない。
そんな中、本書は臨床記録のような克明さで「人はいかにしてDJになるのか?」を活写した、貴重な証言資料と言って良いだろう。
その資料価値を支えているのは、無数の詳細な記録=記憶だ。
写真、地図、図面、人名や固有名詞、様々な事件とその年代、果ては当時のDJのギャラ金額だの、月に何枚いくらぐらいレコードを買ってたかだの「しかしまあ、よくおぼえているなぁ…」と感心させられるほど細かく積み上げられた「証拠」が、時代の空気を実にリアルに感じさせてくれる。
地方の若者が上京して修行し、海外でさらに修行し、やがてビッグなプロジェクトに関わっていく……という著者の半生は、いかにも高度経済成長時代ならではのサクセス・ストーリー。しかもそれは、日本の若者文化=夜遊びカルチャー全体の「右肩上がりな成長」というストーリーと完全にシンクロしていた。
「アメリカ」に対する若者たちの渇望。
輸入文化としてのソウルやファンク。
「ディスコ」の全盛時代。
ディスコから「ハウス」へのパラダイム・シフト。
巨大化していくクラブカルチャーとバブル経済。
本書は、こういった「時代」とその「空気」の変遷をDJの現場から定点観測した、一種のドキュメンタリーとして読む事もできるだろう。
とは言え物語の真の主役は、実は著者が深く愛した2つの伝説的な「ハコ」かもしれない。その一つはオーディエンスとして彼が通いつめたNYの伝説のクラブ<パラダイス・ガレージ>。
「今考えれば<パラダイス・ガレージ>はダンスクラブの学校のような場所だった。<略> 同じ時期に、マスターズ・アット・ワークのルイ・ヴェガや、ケニー・カーペンターなど、ありとあらゆるDJが生徒として踊っていたのだ。<略>いわばラリーが先生で、みんなその授業を楽しみにして行っていたわけである」
と著者が熱く語るように、この店のレジデントDJのラリー・レヴァンはハウスDJスタイルのオリジネイターとして、亡くなった今もなお世界中のDJにリスペクトされる存在である。
ここでは当時のパラダイス・ガレージについて、これまでしばしば語られてきたような客層や雰囲気といった面からだけでなく、ラリーのDJスタイルの技術的な分析や、それによってどのような感動が創出されたかという音楽的側面からも語られていて、興味深い。
とりわけ著者が2度遭遇したという、先が読めない強烈な音の暴力でフロアを凍りつかせる「狂気の日」の描写は、単に快楽的なミックスで聴衆を盛り上げ楽しませるだけではないDJの暗黒面(宇川直宏ふうに言えば『ヤバいド変態ヴァイヴ』)をリアルに伝えてくれる。
さらにもう一つの「場」、すなわち著者が立ち上げから参加した伝説のクラブ<ゴールド>に関する様々なエピソードが、もう一つの読みどころだ。
バブル頂点の1989年12月、東京芝浦に生まれた巨大クラブ<ゴールド>。
NY直輸入のスーパー・サウンドシステム。
直径1mの巨大ミラーボール。
地上7階建ての倉庫を丸ごと改造し、総工費15億円!
全てが空前絶後の規模であったが、その理想は著者が<パラダイス・ガレージ>から受け継いだものであった。それは、それまでの日本にはなかった「サウンドの快楽」こそをとことん追求するクラブというコンセプトだ。
ここからは当方の当時の経験談になるが、一足先に「ゴールド詣で」した友人に「どうだった?」と尋ねると、異口同音に「とにかく音が良かった!」と熱く語っていたものだ。
あわてて当方も駆けつけたところ、音量・音圧はかつてないほど大きいのに不思議と疲れない、ファットで温かな音に感動した記憶がある。
もちろん、巨大なスケール感や倉庫むき出しな内装のクールさ、そして「何でもあり」「何かが起こりそう」と感じさせる猥雑さ、妖しさにも、麻薬的な魅力があった。
中でも記憶に残っているのが、本書でも触れられている「エコ・ナイト」だ。
アメリカ西海岸のアンビエント/チルアウト系カルチャーと連動して「サイバー美学」を提唱してた武邑光裕氏がオーガナイズする、クラブのアンダーグラウンドな「カルチャー」性を強調したパーティだった。
ハウスともインダストリアル・ビートともつかない冷徹な音響空間の中、ピアッシングやボンデージのパフォーマンスが行われた『ボディ・アポカリプス』には、サイキックTVなどいわゆるノイズ系ミュージシャンが来日出演していた。
当時はまだまだ現在のようなダンスミュージックのジャンル細分化が進む前のことでもあり、ここではハウス、テクノ、ニューウェイヴやボディビートからノイズまで、分けへだてなくアンダーグラウンドな音楽に出会うことができた。
<パラダイス・ガレージ>が著者にとって「学校」だったのと同様に、著者がつくった<ゴールド>も、当方を含む多くのオーディエンスにとって、確かに「学校」だったんだ。
そのことを、本書は思い出させてくれた。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます