下村 なにが起きてるんですか……?
田所 なんというか……家庭争議のようなものです。
『バロック(再演)』台本より
2022年6月17日、下北沢のザ・スズナリで演劇ユニット鵺的の『バロック(再演版)』を見た。
作者の高木登の、ひとつの集大成ではないかと思った。
まだ公演は2日あり、当日券も出るようなので、あまり内容に踏み入らないように気を付けつつ、感想を書いておこうと思う。

あの、悲鳴と機械の摩擦音を混ぜあわせたような、猛烈に不快な効果音はどうやって作ったのだろう。
それは舞台となる洋館にいる霊の叫び、あるいは警告として劇中で何度も響き、そのつど壁や天井から下がったシャンデリアが揺れる。洋館を取り壊して、代々続いた背徳の歴史を断ってしまおうとする当主や家族達と、怨みを果たさずにはおれない霊との攻防戦が始まる。
『バロック』の初演は同じザ・スズナリで、2020年のまだ粉雪の降る、寒い春だった。
その時は面白かったけれど、戸惑いのほうが大きかった。
鵺的の高木登は、ドメスティックな家族や小さな共同体の愛憎劇をねっちり描くリアリズム現代劇を軸にしつつ、『奇想の前提』(17)では江戸川乱歩『パノラマ島綺譚』の後日譚を描いたり、『死旗』(18)ではフランケンシュタインの怪物のような存在の娘を登場させたりと、幼少期からの幻想・怪奇小説、ホラー映画などに耽溺した記憶を定期的に奔出させてきた。自分が主宰しているんだから、自分が描きたくなった物語をつくる、という優先順位はハッキリしていた。
だから一昨年の『バロック』が霊の棲む館でのスペクタクル劇であっても、決して急なイメージチェンジではなかったはずなのだが、予想とは違う方向のものを見せられて、適切な言葉が出てこなかったのだ。
おはなし自体は面白かったし、ケレンたっぷりの舞台の各種の効果と集中力の高い演技、それらを統合する演出に圧倒される思いではあったのだが、「面白かった」「圧倒された」以上の言葉が必要になるものがあるのに、僕はそれを掴めていなかった。
今回の再演版は、台本も加筆・修正されており、ほぼ初演版と同じ展開でありつつ、けっこう違うものになっているという。
あいにくその違いの具体までは特定できなかったが、少なくとも僕は今回の再演版がすごく良かったし、前回の戸惑いの理由もわかった気がした。
『バロック』には、どこかそれまでの鵺的とは違う明るさがあるのだ。しかもその明るさは、再演版のほうが強くなっている。
それについて考える前に、鵺的の、あんまり明るくなかった面をおさらい。
憎しむなら徹底的に憎しめ、と登場人物を追い立てるところがもともと高木にはあった。特に『悪魔を汚せ』(16)で。
反吐が出そうになるほど卑劣な、心の壊れた男を舞台に出してやる。だから、客席にいる女達よ、今まで出会った不愉快な男達を彼らに投映させて存分に憎め。それ相応の惨めな末期を見せてやるから、と観客を追い立てるところも高木にはあった。特に『天はすべて許し給う』(18)で。
鵺的はどの舞台にしてもトーンは基本的に陰鬱で、その暗くて冷たい感触を感じてもらわなければ困る、共感とかわかり味~とかは、優しい、温かい場合だけではないんだぜ、とでも言わんばかりの態度があった。つまりは、常に確固たる倫理観に基づいた怒りがあった。
ところが『バロック』の初演版・再演版は、その怒りをどう消化・昇華させるかにまで話が進んでいた。
そうなると面白いことに、冒頭で書いた「高木登の、ひとつの集大成ではないか」という見立てとますますつながってくるのだ。
まず『バロック』は、ここまでの鵺的の代表作のひとつ『悪魔を汚せ』の精神的な続編ともいえる話だ。
『悪魔を汚せ』は、家を焼きつくす炎のなかで辛抱強い姉と冷酷な妹が決定的な敵同士となる場がクライマックスだった。一方の『バロック』は、家を焼く姉と、姉に憎まれた妹とが炎のなかで永久に対立することを示す場から話は始まる。
しかしそれは、姉を否定する生き方を選んだ妹が、家族の絆を大事にし過ぎたあまり、息子や娘の育て方がいびつになってしまい、さらに家を、人を憎む人間を作ってしまう悪循環を生んでしまう。
五人きょうだいの、お互い心から打ち解けあえないでいる姿は、鵺的のカラーを決定づけた初期の主要作(と僕は解釈している)『荒野1/7』(12)と通じている。そして、呪われた場所にバラバラになっていた家族がイヤイヤ集まる基本的なシチュエーションは、『奇想の前提』と同じ。
鵺的の構成員だった奥野亮子は、2020年に自身のツイッターで、
「鵺的『バロック』はとても繊細な刺繍のように『悪魔を汚せ』とこの『奇想の前提』の糸が縫い込まれた作品でした」
と、これまでの作品と『バロック』とのつながりを端的に説いている。集大成では、という僕の見立てはそれほど間違っていないみたい。
(ちなみに奥野さんは現在、鵺的から円満に離れ、オフィスエンネの代表。去年の、鬼の居ぬ間に『Jeanne』のジャンヌ・ダルク役では、喜びや失意を背中で表現する細やかな演技が凄くよかった)
こうして各意匠の共通点が過去作とつながることで、「集大成」の印象は強くなる。
だが、意匠は意匠である。作家がやや煮詰まり、これまでの得意な要素の棚卸しをせざるを得なかったケースまで「集大成」と讃えてしまう不幸は、演劇、映画、文学、音楽、どの分野でも繰り返されてきた。評を書く人はみんな気をつけなきゃいけないことだ。
『バロック』の再演版は、そうした〈過去作との共通点が多い=「集大成」と言ってもらいやすいし言いやすい〉の罠から、スッと一歩遠ざかり、前に進んでいる。進んでいることで、今の高木登がよりヴィヴィッドに伝わるものになっている。
ひょっとしたら初演版との一番大きな違いではないか、と僕が現時点で推測するのは、妹の夫・五人きょうだいの父であり、洋館をすぐにでも解体したい当主の、キャラクターの変化だ。
不遜で軽薄な、現世の快楽主義者。根っからの俗物。高木がこれまで執拗に描いてきた、高木が最も憎むタイプの同性者。
ところがこの当主が実は、洋館と自分の血族に対する妻の暗い執着や、子ども達への悪影響に気付いていないようでよく見ていたことがわかってくる。
洋館の霊の力によって、自分があの世に行ったのか、それともまだこの世にいるのかよく分からなくなっても、それもまあ、しかたないと飄々と事態を受け止める。そんな大きな風情を男が見せるのは今までの鵺的の劇ではあまりなかったことだ。
『バロック』の再演版は、何でも白黒つけることが果たして全て正しいのか、と問いかけるディスカッションの場面が目立つ。
間違えた育て方をした母親を、息子として娘として許せるか、というのっぴきならない問題に対してなので、そう簡単に答えは出ない。
その結果、高木登は、許せない、とするきょうだいも肯定するし、「母は完璧なひとではありません……でも間違いを認めてくれた」と、許すきょうだいも肯定するように描いた。
家庭内の愛憎は、白黒つけようとするから余計にこじれる場合が現実にも多いので、許す・許さない、どちらの意志も尊重し、互いに受け入れるようになれば、自ずとその緊張は緩んでいく。
これが、鵺的では今までなかった質の明るさになっている要因ではないかと思う。
いや、父親が実はそれなりにデキた人物だったとしたら、もっと事前に妻や家族に対して努力すべきだったのではないか? という反論も僕のなかにはあるのだが。
おそらく彼は、そういう努力はかつてしたのだろう。でも、妻は姉との直接対決の機会が訪れない限り変わらない、とどこかで悟ったのだろうし、子ども達が洋館に引き寄せられるのも止めることはできない、と気づいたのだろう。
だから、家族みんなをよく見てきたうえで、なるようにしかならないと腹をくくったのだろう。
しょせんは家族といえども個別の人生である、ということだ。
だから、高木登も人間が丸くなった……というカンタンな話でもない気がする。むしろ人を見る目がさらにドライになった結果、相対的に家族にまつわる話への重心が軽くなったのかもしれない。
急に僕の話になるが、実家には父がつくった私設博物館がある。父が並はずれた行動力で収蔵品を集めてきた。相当な施設にはなっていると身内びいきの心情抜きでも思うのだが、思い込みの強さが激しすぎて、父以外が入り込めない状態になっている。
今後の維持や運営をどうするかは、家族の間で目下かなりデリケートな話題になっているので、『バロック』を見ていて、洋館を取り壊すかどうかがストーリーの縦筋になっている点は非常に……沁みたのだった。
ここまで僕は、『バロック』にインスピレーションを与えただろうホラー映画のタイトルを挙げないできた。僕よりもっともっとそのジャンルに通じている方が多くいるし、こちらのほうが教えてほしい位だからだ。
ただ、実は根っこにあるのが家族の生産的な解体劇だという点では、『ザ・ロイヤルテネンバウムズ』(01)のような映画を並べて考えてみるのも面白いんではないか、と思っている。
もうひとつ、『バロック』初演版・再演版通じての意外な明るさの要因となっているのは、一種の狂言回しとして、空き家管理のNPO法人の代表をつとめる下村という女性と、ゼネコンの若い社員・田所が登場し、活躍するところ。ふたりの存在が、劇の展開をかなり風通しよいものにしている。
これは、高木登がやはり幼少時から小説や映画、ドラマで、エルキュール・ポワロや金田一耕助をモリモリとよく食べてきた蓄積の発露だろう。彼らは、名探偵である条件の次か同じ位に、冷静で中立的な部外者であることが肝要なのをよく理解し、わきまえている人物だった。
おそらく高木のなかでも、ふたりがもしも商業作品の主人公になっても成立するように、という遊び心の意欲はあったと思われる。ふだんはおっとりしているけど実は霊感が強過ぎて困る下村さんと田所くんのコンビが、全国のワケあり物件のトラブルを解決していくシリーズがあれば、確かに『X-ファイル』(93-02)の日本版みたいで、楽しい。
個々の俳優陣については、みんな魅力的だった、役そのものとして舞台で生きていた、と書くにとどめておく。
演技の難しさはよくわからないくせに、あの役は初演版のひとのほうが好きだった、この役は再演版のひとのほうが……などと書きたくないのです。
それでも、メインキャストを続けて演じたふたり―美貴子役の笹野鈴々音、紗貴子役の福永マリカは凄いよ、とはやっぱり書いておきたい。
『バロック』は言ってみれば、家族みんなを何十年も巻き込んだ姉妹喧嘩、とシンプルに要約できるおはなしでもあるのだが、そんなふたりがやっと正面向き合い、笑顔で対峙する場面の、刺してえぐるようなまなざし、刻々と変わる表情の絡み合いは、なんつうか、名演技というより名勝負という感じだった。










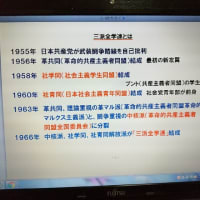
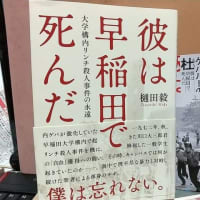






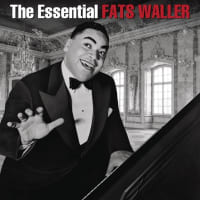

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます