「だからこういうことがあった時に信じられるの。中島は書くものにも嘘がないから……才能あるんです、中島は」
演劇ユニット鵺的の、3月の『デラシネ』に続く2023年2本目の公演『天使の群像』のなかにあるセリフだ。(以下、セリフの引用は全て劇場で販売している上演台本より)
ある高校で、不登校の生徒が家からも失踪した。はっきりした理由は不明。教職員や親のあいだで連携がとれないため、何が原因かを話し合う作業は自然と、誰の責任かを探るものになる。
お話の枠組自体は、正統派のミステリーに則っている。しかし主人公の女性・道原(堤千穂)は、金田一にもコナンくんにもなるつもりはない。
「いなくなりたいなら、好きにさせてあげたいと思う」
と考える質の人間だからだ。
それゆえお話が転がるにつれて自ずと、そもそも失踪は本当に問題のある行動なのか? 周囲の人々の視界から突然消えた人は不幸なのか? 特定の原因を探し出すのは実は不毛で、消えた人にとっては、消える前の全てが原因なのではないか? といった疑義のほうが強く炙り出されてくる。安部公房の失踪小説に印象は近い。
そんななかで、全体をミスリードさせ混乱させたい人物がいるのが分かり、それが誰かを探る必要も出てくる。
第一に疑われるのが、失踪した生徒のクラスメイトであり、同じ文芸部である女子・中島(野花紅葉)。教室と保健室を気まぐれに行き来し、言いたいことは大人にも率直に言うような子なので、男性教師達からは手に余る存在と思われている。
ところが、文芸部の顧問だった戸部(小西耕一)だけは男性教師の中で唯一、問題の攪乱を匿名でしている人物は中島ではありません、と言い切る。戸部は、生徒の不登校の原因を作った責任を感じて休職中で、話し合いの席でもひたすら恐縮しているのだが、中島を疑わないと示す時だけは、言葉に動揺がない。それが上記のセリフになる。
率直な発言をするだけでなく、「書くものにも嘘がないから」。戸部のセリフを、人が人を信用する際の絶対的な根拠として機能させている。作者・高木登の問いかけだと僕は受け止めた。自分はどうかと考えてしまった。ライター・物書きをやっている人で、このセリフにドキッとする必要のない人がいたら、それはとてもハッピーなことだ。
なんとなく触れる程度にしておきたい気持ちは山々だったのだが、このセリフを流すと、劇の把握もできないと分かってくる。なので自ずとこの感想文は、演出や俳優の演技までフォローした、しっかりした劇評ではなく、戸部のセリフに強い印象を受けたこと中心になる。
その前に、初日を見てすぐに関係者に伝えた感想をSNSであげているので、こちらにもコピペします。
「今聞きたい言葉、自分だけじゃないと思わせてくれる言葉をたくさん聞けた。なんか元気が出た」
「高木登は、根っこはモラルの作家だと前から思ってるけど、今回はそれが軸だもんね。高木さんもたくさんのことを考えてるんだな、とジンときた」
「あくまで僕の捉え方だけど、学校が舞台だけど学校の話じゃないし、ハラスメントの議論が表に出るけどそれがテーマじゃないんだよね」「人がどれだけ相手に対して自分の言葉で話せるか。本当の意味の尊重とは何かについての物語なんだと思う」
「道原先生(役名)が懸命に話すと、ブスッとしてた中島(役名)が途中で顔をあげて道原先生を見るようになる。胸にきた……。あそこは演出? 演者さんの判断?」
「でも、オネスティを持った自分の言葉を発信するようになれば、全て明るく事態が動くわけではないでしょう。かえってハレーションが強くなり、嫌われるのが日本の現実。そんなこと高木さんはよーく分かってる。でも、それでも、そこでシニカルになってはダメなんだってのが伝わるのがいいなあ」
「でさ、堤千穂さんって一体、何者? 今の話はどこまで先生としての言葉か、と聞く野花紅葉さんもすばらしかったけど、『全部です』って堤さんが答えたその時に、途中で芝居が変わってる、顔付きが変わってることに見てるこっちは初めて気付かされるんだよね。あれはよかった」
まあ、『天使の群像』のよいところは大よそ書けているんじゃないでしょうか。それに関係者からは、演出・小崎愛美理が粘ったところ、舞台美術・荒川真央香や照明・阿部将之の貢献の大きさなどをいろいろ聞かせてもらった。僕は演劇の世界にはまるっきし疎いので、こういう話はいちいち新鮮。
とはいえ、全体にぎこちないものを見たな、という印象も受けた。それで上演台本を読み、台本の指定と演出に違いがある点が幾つかあるのを確認した。
ああ、こういうところを抽象的にしているのは面白いなー。ストレートプレイらしい、そこが学校の会議室だとすぐわかる装置だと、こういう効果は生まれなかっただろうな……と感心した部分と。
うーん、もう少し、そこ(舞台)が日常の延長だという約束事を作っておいたほうが、道原が霜澤先生(ハマカワフミエ)と“同居”していることの面白みなどがもっと冴えたのでは、などと感じる部分が半々。
そのぎこちなさは、高木登の本自体の捕まえにくさから出ているのだから、当然だとは思う。
このブログでの前作『デラシネ』の感想で、僕はこんな風に書いている。
https://blog.goo.ne.jp/wakaki_1968/e/37f0113b7098b1c7cb69f1a4a2024c99
「好きで嫌いで嫌いで好きな、自分の生きている畑のことを高木は書いている。真情あふるるこなれなさである。いろいろな要素の組み立てや接着に苦労しただろうな……と察られる部分にこそ、今までの鵺的とはまた少し違う、情のある熱がこもっている」
『デラシネ』は、テレビドラマの人気脚本家と弟子の支配関係を描いてハラスメントを厳しく告発しつつ、それでも書くのはなぜか、にヘソがある話だった。
『天使の群像』も、生徒に失踪された教職員達の対応がズレていくさまをシニカルに描いて、ハラスメントや良識人の欺瞞をこっぴどく批判しているのだが、作者の意識は常にその先に向かっている。掴まえにくいというのは、そういう意味だ。
SNSのコピペ部分の冒頭で書いてある通り、『天使の群像』には「今聞きたい言葉」がたくさん散りばめられている。
「いいかげんは傷つけるけど、(中略)適当なら傷を回復できる可能性があるから」
「自分に対する誠実さは基本的に他者には関係ないものです。それを主張することは、ともすれば自分自身の押しつけになります」
「建前は理想であり原則です」
「身も蓋もない本音じゃなくて、現実と理想を嘘のない言葉で語ってみてください」
「どこまでが先生の言葉ですか」
「問題には常に解決策があるわけじゃないってことです。みんなで立ち止まってじっと考えるしかないようなことはあるんです」
など。
昨今は、ハラスメントからパレスチナまで、多くの問題について自分はどう考えているのか、何らかの立場表明を発信することが強く求められるようになった。発信しないとそれはすなわち「沈黙」ということになり、「沈黙は加害者に加担することと同じ」だなんて、ものすごいレベルの罪悪感を植え付けられるまでになった。
僕は割と冷静にこの傾向を、SNSのエコーチェンバー現象が人に及ぼす作用のひとつだと考えている。
自分や自分と価値観を共有する人達が「声をあげるべき」と思っている問題について、具体的に文字に残してつながろうとしてくれない人がいると、その人のことが実際以上に無関心・無責任・冷淡な人に見えて(そのイメージがまさに増幅されるので)、必要以上に腹立たしく感じられてしまうのだ。気持ちはよく分かるんだけど、そのモノサシは正確なものではない。リアルの場で熱心に考え、話し合っているけど、SNSはスイーツの食べ比べレポート専用と決めています、という人まで激しく叩くことになってしまうからだ。決めつけるのはあぶなっかしい。
高木登も、そういう人達にとっては、声をあげようとしない、「沈黙」を続ける文化人のひとりに含まれる。
なので僕には、「声をあげる」タイミングも場所も出かたもみんな違う。その問題が自分のなかで響いたことのほうを大事にする役割の人達もいるのだから、一律に、しかも急いで立場表明の発信を求める必要はないでしょう? と理解を求めたい気持ちがある。
自分の場合、『漫画誕生』という映画の脚本で、ある漫画家が風刺漫画に最低限必要な品性とはなにか、を説く長いセリフを書いた。しばらくしてから、もしも自分が、伊藤詩織さんが受けた中傷が裁判になった時、詩織さんの存在を苦々しく感じる人々のことばに対して「沈黙」せず、すぐにSNSで発信していたら、あのセリフは書けなかっただろうな、と考えた。溜めこんでいたからよかった、と言い切ることもできないが、いちいち発信していたら薄くなっていただろうな、という実感だけは確かだった。
高木登も、きっとそうなんだろう、だから『天使の群像』は、僕にとっての「今聞きたい言葉」がたくさんある、と思っている。
慌ててすぐ声をあげないと「加害者に加担しているのと同じ」とまで言われてしまう風潮―それは“寄り添いファシズム”という新語を作ってしまってもいいものだ。美意識や正義感の強制こそがファシズムの育ちやすい温床になるからだ―への、異議申し立ての劇でもある、とあくまで僕は勝手に受け取っている。
『天使の群像』は学校が舞台だけど学校の物語ではない、という印象は、高木が学校を社会の縮図と考えているところからもたらされる。
人間が(もっといえば日本人が)集団性を優先させる時の冷酷さも、自分さえよければいいと個人を優先させる時の醜さも、高木は学生服を着ている間にさんざん教室で見ている。見える人には、別に社会人になるのを待つ必要もなく、見えてしまうのだ。
そんな切実な、日々考え、今も考え中のことを作品のなかに込めた、アクチュアリティがある劇は、どうしても、隅々まで設計や計算が行き届かせたうえで、というわけにはいかない。
中島は書くものにも嘘がない、だから信用できる、という評価に対して、まず作者自身が向き合えるようでないといけなかったからだ。
そういうわけで『天使の群像』は、『デラシネ』に続く、高木登の〈真情あふるるこなれなさ〉シリーズの第2弾なのだ、と僕は一応、銘打っておきたい。
改めて、『天使の群像』とはどんな話かを大掴みに言うと、消えてしまった者のほうが倫理的には正しいとさえ言える世界で、それでも残ることを選んだ者は何をよすがとしていけばよいのか、をめぐる話だ。
初日の舞台を見て、上演台本を読んで、しつこいようだが僕は「中島は書くものにも嘘がないから」という戸部のセリフに、特に強く打たれた。
そして、まるでこの劇は『デラシネ』の前日譚とも言えるのだ、と思った。
世の中には、自分が書いたものをちゃんと読んでくれる人「も」いる、ということだ。
そういう大人がひとりでもいる世界ならば、消えてもいいけど、消えずに残ってがんばってもいいのだ。
最近の鵺的の舞台は、『夜会行』の頃から、女性だけで会話・対話する場面がめっきり魅力的になっている。
『デラシネ』では、酒匂(とみやまあゆみ)と吉澤(中村貴子)が、早くシナリオライターとしてデビューしたい気持ちを共有し合う場面が、しみじみと良かった。互いの才能に気付き、それを心から尊敬し、応援し合える関係のあたたかい清潔さ。
「どこかで誰かが見ててくれるのを信じてやってみる」
「わたしはずっと見てたし、これからもずっと見てるよ、吉澤さんのこと」
「……ほんと?」
「ほんと」
(『デラシネ』上演台本より)
酒匂も吉澤もきっと、ちゃんと読んでくれる人がいたことの喜びを経験しているから、こういう言葉を素直に出せるようになっている。
それは高校の時に作文を丁寧に読んでくれた先生だったかもしれないのだ。
そしてその先生が、男性であることが、『天使の群像』のとてもいいところ。少し前の鵺的なら、戸部は女性だっただろう。女性同士がフェアに、社会的な立場などを考えずに率直に話し合う場に、男性が混ざっていてもよいのだ。もしもその価値観が共有できるのならば。そんなかたちで高木登は、自分の描く世界の幅を広げている。
ただ、『デラシネ』の2人の女性は、ちゃんと読んでくれる人がいる喜びを知っている結果、誰よりも自分の才能を見抜いてくれるがゆえに支配的になる男の弟子になる、皮肉な道を行く。
『天使の群像』の道原も、自分もいつでも消えてしまっても構わない世界で、自分は残ってみる、と腹をくくった途端に、消えてしまいたいと思いながら生きていた時よりずっとずっとイヤな思いを味わうことになる。
高木登のなかに常にある、両義的な揺れだ。目の前の世界を愛したいと思っているが、こんなに醜い、自分を傷つける場所もない、と分かっている。それでも、どっちかだとは決めつけないのだ。



















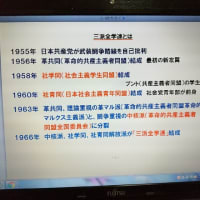
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます