まえがき
映画批評誌の映画芸術は、2007年から数年間、本誌とは別にインターネット版を立ち上げ、運営していたことがある。名前は、映画芸術DIARY。
2008年に映画芸術DIARYの管理を任された当時の編集委員・平澤竹識は、数人の無名の書き手をレギュラーに据え、彼らに順番に作品評やインタビュー原稿を作らせることにした。
レギュラーになったメンバーは定期的に集まって座談会や合評会を行うようになり、なんとなくのうちに自分達を〈映芸ダイアリーズ〉と自称するようになった。
メンバーを今の肩書で紹介すると、批評家・映画作家の金子遊、映画文筆家の千浦僚、映画宣伝・プロデューサーの加瀬修一に、現在は私立恵比寿中学(エビ中)の舞台演出やライブ映像監督などで知られる近藤キネオ(当時は近藤典行)。それに僕、若木康輔。後期には当時は若手批評家で、現在は西荻窪の書店〈本屋ロカンタン〉の店主である萩野亮も加わった。
お互いの書いたものや作ったものをかなり遠慮なく揉み合うことができる集まりで、楽しかったのだが、もともと平澤氏には「ダイアリーズは個々の活動の通過点にしてもらいたい」という意図があり、実際それぞれが違う分野で忙しくなってきたため、2012年に発展的に解散した。
みんな、今でも活躍している。僕以外はなかなかのメンツではあったと思うが、なかでも一番の出世頭となったと言っていいのが、深田晃司である。
当時から「深田くん」は、メンバーみんなに愛されるキャラクターだった。すこぶる付きで頭の回転が速いのに、つっかえつっかえの早口でやや天然ボケなので、常に愛嬌のほうが上回る独特の徳を持っていた。
その「深田くん」の映画を当時から見てきたので、2022年の新作『LOVE LIFE』の持つ、柄の大きさには素直に感動した。ここまでの映画監督としての作風、考え方などを今のタイミングでじっくり聞いておきたいと思った。
しかし、深田氏にそう持ちかけたものの、僕はあいにく売れない物書きなので、インタビュー記事を作ったところで掲載できる媒体がない。(理由は残念ながら、あくまで僕の実力の問題である)
「別に若木さんのブログでもよいですよ」と深田氏が言ってくれ、宣伝会社にも話を通してくれたので、お言葉に甘えて、公開前の各媒体の取材の合間に時間をもらい、こうして掲載させていただく。
雑談などの寄り道はかなりカットしたのだが、それでも2万8千字近くになったので、日を置いて2回に分けてアップする。
改めて、関係者の方々に感謝いたします。
(構成協力:繁田実和)

矢野顕子の曲が持つ多義性
― どうですか、取材されているみなさんのここまでの反応は。けっこういいんじゃない?
深田 まあ、いいような気がします。「今年のベストです」と言ってくれる人もいたし。前から付き合いのある人だから、多少は点を甘くしてもらっているかもしれないけど。
― でも、『LOVE LIFE』は今までの深田晃司の映画のなかでも、いいと僕も思いますよ。だから今のうちにまとまった話を聞いておきたいと欲が出て、お時間もらえるようお願いしちゃった次第です。
前に自分のブログで『海を駆ける』について書いた時にも触れたんだけど、あなたの映画にはいつも水のモチーフがある。そこに人の命も持っていかれてしまうし、鬼のようなものもやってくる。その鬼がどんな存在かは映画によって違うけれど、今回はパク(砂田アトム)という、韓国から海を渡って日本に来た男。
『歓待』以来、その存在は日常をかき回す闖入者であることが基本形でした。かき回して壊していく。パクもやはりそうで、元妻と夫の関係を揺さぶって壊すんだけど、今回はいい意味でシャッフルというのか、二人が関係をリスタートさせることにつながっていく。パク自身にそのつもりはないままにね。
つまり『LOVE LIFE』からは、これまでの深田映画とはまた違う、明るい印象を受けるんです。初期からの少しずつの変化がひとつの到達点に辿り着いている気がする。そういう実感が、本人はどこまでおありかどうか。
深田 ええと、作り手と受け手との間の認識は往々にしてズレがちなところから話したいと思うんですけど。見ているみなさんは完成・公開した時系列で作品の流れを把握してくれますよね。でも作っているほうとしては、企画・脚本開発が始まるタイミングと作品が成立するタイミングはバラバラなんです。
― 例えば、次に作りたいと考えていたものより、先に企画が決まるものがある。作品歴が常に作家の変化とシンクロしているわけではない、ということですね?
深田 はい。『LOVE LIFE』の場合はもともと22、3歳位の時、映画美学校を出た頃に書いたシノプシスが最初なんです。ただA4用紙一枚位に、妻と夫と元夫がある出来事をきっかけに三角関係になることだけを書いただけの簡単な内容でしたが。その後の展開は何も決まっていなくて、ただ最後には、主人公が出て行って誰もいなくなった部屋に矢野顕子の曲が流れて終わる。それだけは決まっていたんです。
その後で『淵に立つ』の企画、シノプシスが出来て、『本気のしるし』はさらにその前、二十歳の時に原作漫画を読んでやりたいと思ったのが最初ですから、まあ、完成する順番と比べたら本当にかなりバラバラなんです。
だから自分としては時系列は特に意識していないつもりではあるんですけど、撮影している自分、脚本と向き合っている自分は歴然とした時間の流れのなかにいるとも言えます。
― 今のお話を整理すると、企画の種が生まれたのは『本気のしるし』『LOVE LIFE』『淵に立つ』の順番。映画化が実現したのは『淵に立つ』『本気のしるし』『LOVE LIFE』の順番となります。
深田 はい。『LOVE LIFE』は確かに、ポジティブな意味合いが当初の企画の頃より高まっているかもしれません。それは多分に、矢野顕子さんの歌の力によるものなんですよ。
矢野さんの歌にはいろんな多義性がある、そういう多義性を大切にしている人だとずっと思っていて。矢野さんが「愛してる」とひとこと歌う時には、その愛は伝わらないかもしれないとか、そういった意味合いも同時に含まれています。「LOVE LIFE」という曲の「どんなに離れていても愛することはできる」というフレーズにも、近くにいても伝わらないかもしれない、という気持ちが等価に込められていると捉えてきました。
自分の今までの映画はその、近くにいても離れている、という面にフォーカスすることが多かったんですけど、さあ、そんな矢野顕子の曲をベースにして映画を作り、しかも映画のなかで響かせるぞとなったら、必然的に「離れていても愛することはできる」面を等分に描くことになった。今までよりも半歩ポジティブな意味合いが映画に生まれているとしたら、そういう理由なんです。
― 自分の中で後の作品の種になるものが自分のなかで生まれたのは、20代前半の時期が多いのかな。
深田 多くの人がそうでしょうけど、多感な時期は本当に多感で、スポンジみたいに様々なものを吸収できる。自分も10代の時に見た映画や読んだ文学、漫画などがやはり一番血肉になっていると思いますが、それをすぐには形にできなくて。30代半ば以降にやっと実現できるようになったわけです。
ただ、20代の頃から企画を温めていたものは、ほぼこれで棚卸し終了なんです。さあ、これからが大変だぞっていう(笑)。
第一作『椅子』と最新作『LOVE LIFE』
― 今日はこだわって聞いてみたいことがひとつあるんです。しばらくお会いしていない間に、あなたの最初の自主映画である『椅子』を初めて見まして。
深田 えッ、映芸ダイアリーズの時代に見てもらう機会がなかったかな。
― ないない。
深田 あの頃は本当に隠し通していたから(笑)。あんな恥ずかしいものは人に見せたくないと、黒歴史にしてしまっていて。俳優は頑張ってくれたのですが、全部監督が悪い。
― 初めてダイアリーズのメンバーに見せてくれたのは2008年の『東京人間喜劇』(2011年公開)です。その前後で、前作にあたる2006年の『ざくろ屋敷 バルザック「人間喜劇」より』。平澤竹織氏から「みなさん見ておくように」と御達しがあって。

深田 そうそう、そうでしたね。『ざくろ屋敷』『東京人間喜劇』のあたりからは、今でもそうですが、完璧な作品じゃないにしても人に見てもらおう、と思えるものが出来るようになったんだけど。それ以前の作品はずっと……。
― 「長編があるんだけど見せたくないんです」と当時あなたが言っていたのは思い出しましたよ。
その『椅子』は2001年に作って、2004年に公開。シアター・イメージフォーラムが会場の〈深田晃司映画まつり2018〉で上映されたのは、その時以来?
深田 そうです。友人達がやってくれた自分の特集上映で無理やり上映させられました。企画・プロデュースしてくれていた松本さんというプロデューサーから、新作もないとパンチが弱いから何か新作を作れと言われて短編を作って。それを2年やるうちに、『椅子』も引っ張り出されることになったんです。
その時はこんな拙い、音声もガビガビな自主制作作品で入場料をいただくのが本当に申し訳なくて。でも映画館でやる以上は無料というわけにもいかないから、せめてお詫びの粗品のつもりでボールペンを自腹で作って、来てくれた人に配りました。あれでちょっと吹っ切れたところがあるかな。
― ただね、その『椅子』を見ていると見ていないでは、ずいぶんあなたの作品歴の印象は変わってくるんです。
まず僕の場合は、『東京人間喜劇』で初めてあなたの映画を見た時、凄く人間に対してシニカルに捉えているのが印象的だった。人はどうせみんなひとりだ、と各話で念押ししていくようなオムニバスで。
深田 あの頃は「女性が嫌いなんだろう」とかたびたび言われた気がする(笑)。女性嫌いだと思われていた。
― たぶんそれはヘテロ的な、女性だけに対するものではなかったでしょう?
深田 そうそう、もちろん世の中にはジェンダーの不均衡とそこからくる差別や不公正、暴力が間違いなくありますし無視はできませんが、本質的には愚かしい人間の行為には男女の差はないと思っていて。
女性が特に嫌いというわけではなくて、人間の存在そのものへの不信であると当時よく反論していましたね。
― 「人間の8割はクズである」なんて、真顔で言ってたからさ。
深田 そこまで直接的に言ってましたっけ(笑)。それはSF作家、シオドア・スタージョンの言葉のバリエーションなんですよ。ある時、批評家から「SF小説の8割はクズだ」と言われたスタージョンは、「その通り。ただし、そもそも全ての物の8割はクズだ」と返したという。いい逸話だなあと思って。
自分自身と言えば明らかにクズの側だし、その、本当にあるかどうかも分からないクズではない2割よりも自分の日常である8割にまずは目を向けるべきだし、それらは本当にクズと言えるのかとも思ったわけです。
(注:〈スタージョンの法則〉として有名な言葉だが、正確には「9割」。それを深田晃司は「8割」として自分の法則にしていた)
(深田注:単純に私の記憶がいい加減だっただけです)
― つまりは、そういう言葉が心に刺さる青年だったわけだ(笑)。
で、僕はそれから『歓待』を見ているでしょう。ああ、深田くんは青年団に所属していたから、平田オリザさんの説く〈セミパブリックな空間〉を、作劇においても演出においても活かすようになったんだな、シニカルなものが一ひねりする形で描き込まれるようになったんだな、と素直に解釈していたわけ。以降も、そういう文脈を基本にしながら深田晃司の映画を見てきました。
ところが、日本映画専門チャンネルが2020年12月にあなたの特集を組んで『椅子』を初放送したから、そこで初めて見てみると、オイオイこれは深田映画の洗い直しが必要になるじゃないか、と驚かされたんですよ。
深田 おお。
― 『椅子』から見ておけばよかった、当時見せてくれたらよかったのにと思いましたよ。しかも今回『LOVE LIFE』を拝見して、ますます『椅子』の重要さが分かった。要はね、『椅子』はほとんど『LOVE LIFE』のプロトタイプじゃないかと思ったんです。
深田 ああ……。言われてみると、時期はけっこう近いですからねえ。『椅子』を作った時期と『LOVE LIFE』のシノプシスを書いた時期は。
― 『椅子』と『LOVE LIFE』の具体的な共通項を挙げてみます。画では、まずどちらもベランダが出てくる。2009年の短編『自転車と音楽』でも、あなたはベランダにいる子どもを撮っていますよね。深田晃司の映画にとってベランダはどんな空間なのかはまた後で伺うとして、それから、連れ子という関係がやはり両作品は共通している。
深田 そうでした。そういえば連れ子だった。
― それに『椅子』では、世捨て人のように川の傍に住む、似顔絵描きのおじさんが登場する。あの存在と『LOVE LIFE』の公園で寝ているパクさんは共通するわけ。川の傍に住むおじさんは、あれは、愛していた女性が水死したんだっけ?
深田 いや、娘ですね。絵のモデルにしていた娘が入水自殺したという設定なんです。自殺の理由は分からないけど、とにかく深いショックを受けている。
― なぜか深田晃司の映画は、水と死が近づきますよね。試写でいただいたプレス資料のプロダクションノートには、それはいつも無意識の選択で、「観た方に精神分析をしてもらうしかありません」というあなたの言葉が載っています。
深田 好きな映画に水の使われ方がうまい映画が多かったから、それで単純に、水を映画的なモチーフだと思っているところがあるんですけどね。
ただ『椅子』の時に、椅子と一緒に川辺に暮らす男を演じてくださった細原好雄さんから言われて、よく覚えていることがあります。細原さんはもともと映像関係の会社で撮影の仕事をされていて、そこを定年か何かで退職した後に事務所に入って俳優業を始めたという方で。ちょっと経歴はうろ覚えで違うかもしれませんが。
その細原さんが、川辺での撮影の時に、水というのは一瞬たりとも同じ姿にはならないから、カメラの被写体としては最適なんだと言っていたのが凄く記憶に残っていて。そういうのも積み重なった結果、とりあえず水を出しておけみたいになっているのかもしれない(笑)。
― 『椅子』と『LOVE LIFE』の共通項の話に戻ると、『LOVE LIFE』は先ほども伺った通り、矢野顕子さんの曲がモチーフであり主題歌で、これはとても新鮮でした。今まで映画監督としてはあまり音楽をドーンと前に出さない、むしろ禁欲的なほど控える人だと思っていたから。
深田 はい。そうですね。
― ところが『椅子』では、お母さんが酔って電話しながら歌うシーンがあるんですからね。あそこ、凄くいいのよ。
深田 ありがとうございます。本当は『東京人間喜劇』でも、編集でカットしたんだけど、矢野顕子さんの「ラーメンたべたい」を俳優が歌うシーンがあったんです。
― それは驚いた。矢野顕子の音楽は、ずっと深田映画の背景にあったんですね。
メロドラマを描いてから梯子を外す
― ともかく、『椅子』と『LOVE LIFE』は要素が多く重なっているんです。そうして、多くは重なっているんだけど、その意味合いが変わっている。『椅子』は登場人物達がそれぞれ川辺から立ち去っていく、関係がつながらない映画ですよね。
深田 うん、みんなバラバラになる。
― そこに若いなりのあなたの、生きていくとはおそらくこういうことなんだ、みんなひとりで生きていくしかないんだ、という人生観がストレートに表明されていた。
ところが『LOVE LIFE』は、人は一緒に生きていてもなかなか分かり合えないものだ、という人生態度は同じなんだけど、その分かり合えなさを前提としてもう一度向き合ってみよう、となっていきますよね。妙子(木村文乃)と二郎(永山絢斗)が。つまり『椅子』を踏まえて見ると、『LOVE LIFE』の明るさがより印象深くなってくると僕は思ったんです。
深田 実は、最初に書いた『LOVE LIFE』のシノプシスと今回の映画は、そこが変わっています。
妻と夫と元夫が三角関係になり、誰もいなくなった部屋に矢野顕子の曲が流れて終わるという基本構想は同じですけど、妻は、今の夫と元夫、どちらとも別れると決めて、言ってみれば『人形の家』のノラのような、独立した人間として家庭を捨てるという展開を考えていたんです。
その後、具体的な企画として脚本開発を始めて、プロデューサーと意見交換を重ねるのを経て、妙子と二郎が別れるのかやり直すのかは劇中では曖昧にしたまま部屋を出ていき、二人で歩いていくというかたちに変えました。これまでの作品を思うと、確かにそれは、自分の中では一歩の変化かもしれません。
家族と個人についてはよくインタビューで聞かれるんですけど、もともと自分にとって家族というのはあくまでサブモチーフでしかないんです。描きたいのは家族ではなく、その中の個の問題だ、そっちのほうがより普遍的だからという考えです。
普遍的というか、自分にとって強迫観念に近いほど今も昔も囚われていることは死と孤独なんです。それらの巨大なモチーフを映画できちんと捉えることができればそれで充分だし、それに対して何か答えを出したり救済したりするのは映画の役割ではない位に思っています。
(注:深田が自分の主要モチーフと考えている死と孤独については、このインタビューのⅡでさらに詳しく話してもらっている)
ただ今回の『LOVE LIFE』は、妙子が庇護するつもりだった元夫のパクが、結局はそんなに弱い存在ではないことが分かってきて、しかも韓国には韓国のコミュニティがあって、妙子だけがポーンとひとりきりになってしまう展開になりますよね。母親であり、二郎の妻であり、パクの庇護者でもありという関係性のなかで生きてきた妙子が、いろんな関係がリセットされて、ついにはゼロになったという風にしているんです。ゼロになり、ただの妙子個人になった。
それは自分なりになんとか描いたと思っています。『LOVE LIFE』は、自分が孤独だと知ったうえで、それでも隣にいる誰かとどう生きていくのか、という展開に半歩踏み込んだ、という感じですね。そこがおっしゃる通り、今までの自分の映画よりポジティブな手触りがあることに繋がっているんじゃないかな、と思います。
― 妙子と二郎についての前に、今のお話の反射で聞きたくなった。三人のやりとりの組み立てがうまいなと感心して見ていくと、韓国行きのフェリーが停泊している夜の港で、妙子が「この人は私がいないとダメなの」と二郎に告げて、パクさんを追いかける。あの一連、メロドラマの演出としては最高に近いのよ。
深田 いやもう、あそこはもう、メロドラマの気分全開でやってましたからね(笑)。
フランスのオリビエ・グワナーさんという方に音楽を作ってもらったんですけど、夜の港の場面で最初に提案してくれたのは、結構不穏な響きの音楽でした。でも、それは何か違う。ここはメロドラマであるし、妙子の恋愛、妙子の選択を全力で応援するような音楽でなければダメだ、と気づいたんです。
それでオリビエさんに聴いてもらったのが、『アルファヴィル』の音楽。
― 『アルファヴィル』? 一瞬戸惑うけど、そうか、音楽はポール・ミスラキ。
深田 そうそう、自分の中ではあれが最高のメロドラマで、高揚感のある音楽で。こんな感じにしたいとリクエストして、新たに作ってもらったんです。だから、あの一連は本当にメロドラマのつもりです。
― いやいや、『本気のしるし』の次にここまで来るかと思って。そしたら間もなく、ポコンと梯子を外されるような事態が待っている。
深田 最初の脚本の段階では、妙子とパクが韓国に渡ってからのパートはもう少し長かったんですよ。バスがエンストしたり二人で山をさまよったりするロードムービーのような展開で。でも長すぎるということで、いきなり梯子を外す展開になったんです。
― 『LOVE LIFE』で一番明るさが滲み出るところは、あそこですね。実に嫋嫋たる、どこのジャック・ドゥミかトリュフォーかと思うような場面から、スコーンと外れて、それこそ森﨑東みたいな展開になるでしょう(笑)。音楽も一転して韓国の、歌謡曲というか、ポンチャックと呼んでいいのか。
深田 あれは新しく作ってもらった映画のオリジナル曲です。「オッパ」というタイトルで。
― 夜の港の別れをたっぷりに描いた後で間の抜けた結果を用意する、あの一連はとても面白い。メロドラマ的に描きながら、同時にメロドラマ批判を行っているんだよね。「この人は私がいないとダメなの」という思い込みは一種の依存心理でもあると言えるし、主観の強調がメロドラマの基本だから。あなたは主観が強すぎる人のことは苦手でしょう?
深田 いやいや(笑)。それもその人の個性だと思っていますよ。
― それが韓国で、パクに梯子を外される事態が待っていて、妙子はさてどうしようとなる。日本に戻り、二郎と暮らした部屋に帰るけど、そこがね、二郎を一度捨てたから戻れたというんでしょうか。
妙子はともかく、違う世界で違う男と生きる決心をした時に視界を開いた。だから、それがダメになった時に、二郎さんのところに戻る選択肢もあるんだな、と改めて発見できた。人生の一波を越えたというか。その後はね、よりを戻してもいいし、離婚調停を進めてもいいし。
深田 その後どうなるかはね。ひとまずご飯を食べてからゆっくり考えようと。
― そこでまた『椅子』との対比の話に戻るんだけど、『LOVE LIFE』の、ベランダからドーンと歩いていく二人を捉えたロングショットは見事なものでした。ああいうロングショットは、あなたの映画のなかではこれまでそれほど強調されなかったと思うから、余計に印象的なんです。それにキネマ旬報だったかで、「深田晃司の映画には空間性が足りない」と書かれた評が載った時、あなたが凄く悔しがっていたのを覚えているので。
深田 『歓待』の時の評ですね。コンチキショーとなりましたね。現代演劇をほとんど見たことなさそうな映画評論家から「演劇的」とか揶揄されたりもして。青年団にいたからって勝手に「演劇映画」と決めつけるな、こっちは演劇を作ったことないわって。
― 深田映画は、個人を通して社会を描く。なんとならば、社会のことは全て個人に集約されるのだという考え方がたぶんベースにありますよね。だからなおさら、ロングの風景と人が一緒になっていくカットが良かった。これは新境地ではないかと思ったら、実は『椅子』でも、うまくいかないカップルがデートして気まずく歩いている時は、同じ位にロングショットなんだよね。
深田 確かにそうかもしれない。『椅子』は、ひたすらなんか積み重なっていく物語なだけだったけど。

苦しみは理不尽に訪れる
― しつこいようだけど、『椅子』と『LOVE LIFE』を続けて見れば、あッとなる人はけっこう多いと思います。
深田 『椅子』は本当にほぼ一人で撮った初めての自主映画で、レギュラースタッフも自分以外は友人一人しかいなかった状況で。
― 裏を返せば、誰の手も通っていない、深田晃司そのものが出ているとも言えるわけだよね。
深田 はい。『椅子』の脚本には、当時の自分の世界観みたいなものはそのまま反映されていると思います。当時、『椅子』を見た友人に「作家は処女作に向かって成熟する」という言葉を教えてもらったんですよね。初めての作品には、どんなに拙いものであろうとその作家自身の本質が現れていると。
(注:文芸評論家・亀井勝一郎の言葉)
確かに『椅子』は自分にとってそういう手ごたえ、感触のある作品なのかもしれません。
『椅子』を作る時に制作意図として文章を書いたんですけど、そこで書いたことはけっこう今でも繰り返し意識しているんです。ですから、描き方などは変わってきているだろうけど、いわゆる自分の世界観みたいなものは、『椅子』から『LOVE LIFE』までずっと通底していると思いますね。
― どんなことを書いていたんですか。
深田 それが達成できているわけではないから、言うのもあれなんだけど……。
ひとつだけ言うと、〈苦しみは理不尽に訪れるものである〉ということですね。これは自分のどの作品にも共通している点で、『LOVE LIFE』の妙子もそうです。苦しみは、突然理由もなくやってくる。自然災害もそうでしょうし、それがおそらく世界の摂理であり、私達が生きることの本質だと思うんです。でも、苦しみが理不尽に訪れるのであれば、救済だって理不尽に訪れてもいいんじゃないかなという。
だから自分は、エリック・ロメールの作品が本当に好きで。ロメールの映画って、急に救済が訪れるでしょう? たまたま緑色の光を見たり、たまたま棚の上から物が落ちてきて探し物が見つかったり、バスでばったり再会したり。主人公の努力や能力、個性などを根拠にハッピーエンドがもたらされることがほとんどないんですよね。
それは実はとてもペシミスティックでもあるんだけど、同時にある種、楽天的でもある。この感覚が凄く好きだったんです。自分はまだあまり、救済の面を描けてはいないと思うんだけど。
― なるほど。妙子が、パクさんには全く悪気はないけど結果的には騙されることになり、どうしようとなった時に天気雨が降ってくる。踊るしかない……あの場面はずいぶん、そういう域だと思いますよ。
ただ、せっかくだから聞きますけど、あそこで踊り出す妙子を背中からずっと撮っているのは、なかなか味なわけ。味なんだけど、顔も見たかったかな。
深田 いやあ、そうか……いや、うん、自分は必要ないと思いました(笑)。踊るところはもうカット割の段階で不要と考えていたので撮影していません。ご想像にお任せします、という感じで。
― 僕は、『ほとりの朔子』を見て以来、あなたの映画には日本のアイドル映画のDNAも受け継がれていると勝手に思っているからさ。澤井信一郎なら、天気雨のなかで踊るヒロインの顔を正面から撮らないわけないだろうって(笑)。
深田 まあねえ。あそこは当日の朝までカット割を考えていて、どうしようかなどうしようかなと。朝の集合前の新宿駅でパッと思いついたんですよね。そうだ、後ろだって。
カメラマンの条件は優しい人
― あなたの映画は基本お芝居中心だし、コンテを事前にしっかり作って現場に臨むわけではないんだ?
深田 字コンテみたいな形で、台本上で簡単に割ることはしますよ。全く何もないと不安なんで。ただ、決まってないところも多い。それでも、以前は事前にカット割を決めていたんだけど、『本気のしるし』以降は現場で芝居を見ながら即興的に決めるほうに傾きつつありますね。
理由として一番大きいのは、『本気のしるし』の頃から、現場で“これ”をやって段取りを見ていくのを解放したんです。それまでは封印していて。
(注:親指と人差し指を付けて四角いアングルを作り、覗くこと)
― それはまたどうして?
深田 だってなんか、恥ずかしいでしょ(笑)。10年以上前、何かの雑誌でカメラマンあるあるみたいなコラムを読んだら、プロはこんなことしねーよと書いてあって。あ、これをやるとシロウトくさいんだ……って、すっかり怯えてしまった。それに現場で監督がやったりしたら、カメラマンにも悪い気がして。
ところが、『本気のしるし』からもういいやと思ってやり始めたら、カットを決めやすい決めやすい(笑)。あれで、現場の段取りである程度いけるぞって自信が付いたんです。だから今は、事前のカット割りの決め込みは少なくなっていると言えば言えますね。
― そういえば深田映画は、カメラマンが常に同じではありませんよね?
(注:スチールのカメラマンと混同しないよう、映画の撮影スタッフはキャメラマンと表記するのが通例だが、この記事ではカメラマンで統一させていただく)
深田 別に毎回喧嘩して変えているとかではなくて、全てその時その時のタイミングの結果です。スタッフィングはプロデューサーとも話し合うので、条件に合う人を推薦してもらったりとかで。
こちらからカメラマンに求める条件というのは、そんなに。撮影の技術的なことに詳しいわけでもないし……まあ、優しい人ですよね(笑)。自分である程度はカット割りを決めたいほうなので、監督がカットを決めてもムッとしない人。現場で怒鳴らない人。スタッフを殴らない人。それが条件です。
― カメラマンと監督は現場ではバッテリーみたいなもんだから、合わなかったら大変だと思います。
前に誰かに聞いた、笑えない笑い話ですが、ある若い女性の演者さんが初日の舞台あいさつで、撮影監督への感謝を明るく話したそうです。素直に語られたその内容が、「映画の撮影はすぐ大声を出す怖いおじさんがやるものと思っていたから、今回の映画は違っていて良かったです」。それを聞いていた映画関係者は、なんとも複雑な顔になったという。
深田 それはねえ、僕も分かるんですよ。映画美学校の終わり頃、学生のスカラシップ作品の現場に手伝いに行った時の話なんですけど、監督もスタッフも学生上がりか学生ばかりだから、プロデューサーが撮影だけはプロに頼もうと、一回りキャリアが上のカメラマンを呼んでいたんです。その人がまあ、超怖い。自分は遠目に見ていただけなのですが、スタッフも監督もカメラマンに連座でめっちゃ怒鳴られていまして。それに、自主映画上がりの監督がプロの現場に行って職人達からボコボコにされるという話は、都市伝説のように聞かされていたから(笑)。カメラマンは、とにかく優しい人をとお願いしています。
そのおかげで、今まで組んだカメラマンさんとはうまくいっていると自分は思っています。今後も機会があればぜひやりたいです。
― 『LOVE LIFE』の撮影は、『HANA-BI』や『フラガール』、三池崇史、三谷幸喜作品など錚々たるキャリアの山本英夫さん。
深田 山本英夫さんとは『LOVE LIFE』が初めてです。プロデューサーから「うまいわよ」と推薦されて、「それは分かってますよ」って(笑)。山本さんと仕事をしたことがある人に聞いてみたら、誰に聞いてもめちゃめちゃ評判がいいんですよね。現場でも穏やかで優しいよと。実際に現場をご一緒したら本当にそうだったんで、それはとても良かったです。
山本さんは本当にうまかったですよね。他の方との比較論は一回抜きにして山本さんだけのことを言うと、まず技術力が素晴らしくて、ストレスが全くない。安心してお任せできるんです。カット割りはこっちからこういうアングルで、といった説明はするんですけど、自分がイメージしていたよりも二割増しでカッコいい画が上がってくる。うわー、いいなと。毎回どんな画があがって来るか楽しみでしたね。
― 今、期せずして撮影現場のパワーハラスメント問題に近い話題になりました。あなたは積極的に発言する監督のひとりで、もはやスポークスマンに近い立場も担っています。
深田 大した人間じゃないので、あまり期待されるとつらいところなんですけど……。
― 大変なことも多いでしょう。それでも発言するのは、若い頃の現場での体験や、平田オリザさんのところで学んだ経験が大きいんだろうと思います。
それに、日本映画専門チャンネルが2020年12月にあなたの特集を組んだ時に放送した番組「監督深田晃司にまつわるいくつかのこと」のなかで、Motion Gallery代表の大高健志さんが、「深田氏はおそらく映画祭出品などを通じてフランス映画界と交流するなかで、フランスの映画製作環境と同じだけの基準を日本に求めるべきだ、という思いを強くしたのではないか」といった内容をコメントされていました。
深田 そうですね。一つの良い先行事例として、真似できるところはとりあえず真似していきましょうよという気持ちはあります。
あの番組は、いろんな方が出てくださってとても有り難かったんだけど、見るのは恥ずかしくて。みなさん番組の意図を汲んで褒めちぎってくれるから、結婚式のお祝いのスピーチを聞いているような気持になる(笑)。
(Ⅱ)に続く
















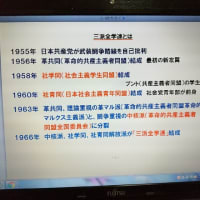
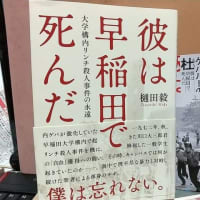

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます