それは正しい
それとも正しくはない
誰かを汚したくない
誰かにいつも汚されたくない
(「SHAME ― 君を汚したのは誰」佐野元春)
演劇ユニット鵺的の公演『デラシネ』を見た。3月7日の回。
12日までやっているので、当日券が出る日に見ようかどうしようかな、と検討中の方の参考のために、急いで感想を書いておきたい。
ざざっとアウトラインから書くと― (セリフは劇場で販売している上演台本より)
飛鳥井宏道というテレビドラマの脚本家がいる(演じるのは佐瀬弘幸。僕は近年の劇団チョコレートケーキの『一九一一年』(21)などで、この人の存在をしっかり覚えた)。プライムタイムから深夜枠まで、地上波キー局の連続ドラマの注文が次々と舞い込み、バリバリとこなす、売れっ子でベテランで、まさに大御所的な存在。自宅に何人も住み込みや通いの弟子がいるほどだ。
ところが、彼は書かない。トップクラスの弟子達が代筆している。全て女性。
彼は彼女達を、何かというと「おまえたちはここに『いる』んじゃない。おれが置かせてやってるんだ!」などと怒鳴りつけては服従させ、「もっと嫉妬しろ。悔しいと言ってみろ」と挑発し、競い合わせる。そして、さんざん罵倒しておきながら「おれは実力主義だ」「おまえは実力がある」「こんな程度のもの、おまえなら片手でいくらでも書ける」とかき立てていく。
才能のある女性達は、宏道は書かないのではなく書けないのだと見抜き、「とっくの昔に才能の涸れた張りぼての虎」と軽蔑しながら、業界の顔である宏道に無能の烙印を押されてチャンスを失うのを恐れ、毎週やってくる目の前の仕事に追われる。
そうした危うい均衡によって宏道の小さな王国は成り立っているのだが、大きな脚本賞の選考が近づいたのをきっかけに、王国の壁は次第に崩れていく。
現在のところ宏道の一番弟子は、酒匂。(さこうと読む。演じるのは、とみやまあゆみ。僕は、特に去年の青年団リンクやしゃご『きゃんと、すたんどみー、なう。』が鮮やか)
酒匂は誰もが「充分一枚看板でやっていける」と認める実力者なのだが、宏道に一本立ちを許されないでいる。それどころか宏道は、特に酒匂にきつく当たり、さまざまなかたちで彼女をいじめ抜く。彼女は無表情でそのいじめを受け止め、代筆した〈飛鳥井宏道脚本作品〉のクオリティをかえって高めてみせることで抵抗する。
二番格の弟子は、田邊。田邊は酒匂で違って温和な笑顔で従順に、宏道に従う。宏道も公然と、田邊を私的な意味も込めたアシスタントとして扱う。彼女が書く〈飛鳥井宏道脚本作品〉は、酒匂のような高い作品的評価こそ得られない代わりに視聴率がいい。(演じるのは、高橋恭子。鵺的の飛躍作『悪魔を汚せ』(17)でも、おっとりした雰囲気で作品にコントラストを持ち込んでいた)
そんな二人が、賞を争う。
酒匂は飛鳥井宏道のクレジットで書いたもので選ばれ、田邊は、宏道が久々に書く一稿を手直ししたものが自分の脚本作品になって選ばれる。
宏道が久々に書き、田邊に直しを任せた一稿は「いまひとつです。さらっとしていて、普通っていうか」なので、実力のある酒匂に分があるようで、これが意外とちゃんとした勝負になる。
田邊には、人が書いたものを引いた目で俯瞰し、適切に手を入れることができる才がある。彼女のその対応能力は、オリジナルを書く作家としての能力が際立っている酒匂とイーブンに評価される価値のあるものだ。宏道の一稿が凡庸であるため、直しを任された田邊の長所がますます活かされる条件になっている。
そうなると、横暴な宏道が実はよく弟子達の特性を見極めていることがジワジワと明らかになってくる。
酒匂に対する、主演女優にワガママな注文を出させるなどのいじめも、酒匂が書いているものが「いろんな人間の視点が入った方が面白くなるドラマ」であり、その要求に「打たれ強くて粘り強いタイプだと」人にも言っている酒匂が耐え切って、さらに成長するだろうことを見越して言っている気がしてくる。
おそらく宏道は、酒匂も田邊も、予算やスケジュール、俳優や事務所の意向、スポンサーの要望などなどあらゆるハードルをクリアすることで成立するテレビドラマの脚本において、しっかりとプロフェッショナルなのをすでによくよく分かっている。
さて、賞の行方はどうなるか。宏道と弟子達の関係はどうなるか……は、できればご自分で見届けてくださるとありがたいです。
『デラシネ』は、これまでの鵺的作品=高木登作品のなかでも突出して面白い。人物達の職業や仕事の内容が今までになく具体的だ。輪郭がハッキリしていて、引き付けかたが強い。業界物としては随所に誇張はされているが、要点はジャーナリスティックなほどにリアルだ。
(これは例えば、往年のフジテレビの恋愛ドラマが、「ふつうの若いOLが家賃を払えるはずがない」と誰もがツッこめる広い部屋にヒロインを住まわせながら、誰でもキュンと共感できる恋ごころを繊細に描いていたようなものだ。そういう誇張は、アリなのである)
と同時に、いつにない強引さを感じ、こなれていない印象も受けた。そして不思議なことに、そういうところこそが味わい深かったりする。
去年(2022年)、鵺的の前作にあたる『バロック』再演版公演についてこのブログで書いた。
https://blog.goo.ne.jp/wakaki_1968/e/9270188f619c58d53073739b67e70d9a
ここで僕は、高木登が、マチズモ的な男性性や、男性優位社会が維持されている日本だからこそのうのうと生きていけるタイプの男性を嫌悪する自身の生理を、初期からハッキリと示し続けてきたことを、確認するように書いている。
やはり昨年12月の、高木の別ユニットである動物自殺倶楽部の公演『凪の果て』でも、男と名のつくものみんな大っ嫌いと言わんばかりの作風は一貫していた。さまざまな業界ハラスメントの問題が明らかになる以前からなのは、少し強調しておきたい。
といって高木登はイコール女性の味方だ、というカンタンな話でもない。
要は、ちゃんと自分の芯があり、群れずに一人で考え一人で歩くことができる人なら高木は男女関係なく好きで(そういう人は自ずと他人を尊重できるから)、そうでない人は、男女の差なく平等に嫌いなのだ。
『デラシネ』に出てくる女性達は、それぞれがそれぞれのかたちでプライドがあり、明晰で、自分のやるべきことに対して真剣だ。高木が肯定的に書きたい女性ばかり。
にも関わらず、みんな宏道のあからさまなハラスメントに従っている。家父長的な強さを持つ男性に盲目的に従っていた女達が、自分達が心を壊されている状況に気付いた ―という明快な構造の劇であればよいのだが、そうはならない。
ここが本作の構造の、ちょっと説明が必要なところ。
彼女達が従っているのは、宏道の大声や恫喝、オスの力ではない。彼女達は、テレビドラマに従っているのだ。それゆえ宏道の暴君ぶりを大目に見て、マスコミの取材に実情は話さない申し合わせができてしまう(そこは批判されても仕方ない)という順になっている。
酒匂も田邊もほかの女性達も、何よりも書くのが、人が書いた優れたものを読むのが、それをもとにして作られたテレビドラマを見るのが好きだ。字によって世界が作られ、そこで登場人物達が生き始めることに献身するのが好きだ。
そんな場所は他にもあるでしょう、今は仲間うちでインディーズ映画も作れるし、小説だってZINEだってお芝居だって……と言われても、きっと彼女達は困る。
キー局のテレビドラマなのだ。十代の頃に見て心を奪われた、キー局のテレビドラマでなければならないのだ。全国区の俳優がどこにでもいそうな隣人の日常の機微を演じるキー局のテレビドラマを書き、いつか名前が出ることにこそ意味があるのだ。
「……でも、いいかげん自分の名前で勝負したい」
「……そうだね」
という言葉が、血が出そうなほど痛切なのは、自己顕示や功名心に必死だからではない。かつての自分のような少女に、自分の名前で届けたいからだ。大人向けのドラマを見て胸を揺さぶられるほど早熟で、だから教室でもきっと少し浮いている女の子とつながりたいからだ。そんな子に名前を覚えてもらい、ああ、この人みたいにドラマを書く人になりたい……!と大人になることの希望を持ってもらえることで、自分が受け取った感動を次代に手渡せるからだ。デビューできないというのは、そんな継承の無私のリレーに加われないということだ。真剣に憧れるものを見つけた人間には、それが何より辛いのだ。
そんな彼女達の前に立ちふさがり、大きな壁となるからには、男は、女への支配欲、放送界の大物で居続けることへの名誉欲に凝り固まった卑小な俗物では済まなくなる。
宏道はのべつひっちゃかめっちゃかに怒鳴っているようで、指導者としては「実力主義」の姿勢は一貫している。彼は、彼女達の才能を自分の名前で世に出して髙く評価されているので、その点はれっきとして卑劣だが、彼女達の才能を嫉妬してスポイルし、潰そうとする工作だけはしない。自分よりも書ける者をいち早く見抜く、その才能に恵まれた運命に対しては誠実でいる。
彼もまた、テレビドラマに従う者だからだ。
もちろん、雇うアシスタントは若い女性ばかりだったフォトジャーナリストの例があるし、ワークショップの後のふたりきりの酒に誘うのは若い女優ばかりだった映画監督の例がある。
宏道の、自分より書ける女を見つけ、育てることができる才能と、その女を愛して手元に置いたまま独占してしまいたくなる(だから自ずと弟子は女性ばかりになる)執着とは表裏一体で、その背反の苦しみが『デラシネ』の隠れた玩味どころのひとつなのだが、それがハラスメントの免罪符になる時代はもう終わっている。
『エースをねらえ!』の宗方コーチだって、指導法が岡ひろみにだけ通用した特殊なもので、男女ともに伸ばせるメソッドを確立するところまでは構築できないままだったとしたらば、名コーチとは言えないのであって。
つまり彼女達は、根っからのテレビっ子で現在多忙な脚本家の高木登自身でもある。
ハラスメントへの怒りも、テレビドラマに憧れ、傷つき殉じてきた人達への思いも、どっちも高木のなかではのっぴきならない切実なものだ。
なのでこれまでの作品で登場させてきた陰湿なビジネスマンやエリート、あるいは描写が抽象的で済んできた資産家や性犯罪者のようには、男への糾弾がスパッとはいかない。
背景のリアリティが具体的な分、宏道こそが実はどんな男よりも、そのままでは世に埋もれてしまう才能のある女性を見つけ、戦う場を与えられる男だったという、ねじくれた皮肉がより前に出てしまう。
好きで嫌いで嫌いで好きな、自分の生きている畑のことを高木は書いている。真情あふるるこなれなさである。いろいろな要素の組み立てや接着に苦労しただろうな……と察られる部分にこそ、今までの鵺的とはまた少し違う、情のある熱がこもっている。
もっと言えば、『デラシネ』は、キー局のテレビドラマがメディアの花形であることに胡坐をかく時代の終わりを描いた、テレビドラマ版の『桜の園』かもしれない。人気俳優の注文は気まぐれなものでも絶対に聞かなくてはならないし、視聴率の高さは正義である。そういうことが絶対常識として語られる会話自体が、もう数年も経てば、地主が大きな権力を持った時代が終わっている現実にピンとこないまま舞踏会の準備に忙しいラネーフスカヤ夫人とその家族のように、ものがなしく感じられるようになるかもしれない。
あるいは『デラシネ』は、高木登なりの『6羽のかもめ』なのかもしれない。
「テレビの仕事をしていたくせに、テレビを本気で愛さなかったあんた! テレビを金儲けとしか考えなかったあんた! テレビを決して懐かしんではいけない。懐かしむ資格のある者はテレビを愛し、戦ったことのあるヤツ。それから視聴者、楽しんでいた人たちだけだ」
と登場人物が叫ぶ最終回のタイトルは、「さらばテレビジョン」。そういうドラマが昔ね、あったのです。
しかし、かつての自分のような少女は今はテレビをあまり見ないことがいよいよ分かった時にこそ、彼女達は本当に自律した戦いを始められるのかもしれない。他のメディアやプラットフォームの、違う表現の開拓か。大手事務所と広告代理店が売りだしたいタレントの〈お芝居付きお披露目ショー〉ではない、作り手と視聴者がまっすぐ交換し合える、テレビドラマのありかたの更新か。
僕自身はどうかというと、まあ、いろいろと思いはある。
映画学校の脚本ゼミを出て、人の下働きをして、何を書いてもダメで怒られるので、原稿用紙に向かおうと思うだけで吐き気をもよおす時期がしばらく続いた。脚本ではなく構成台本ならなんとか書けるのに気づいて、それに縋った。
こっち一本でいこうと決めた頃にVシネマの話が来て、アクション中心の一本道でいけるものなので思い切って一気に書き、吐き気が出ないままラストまで辿りつけた時は本当に、本当に嬉しかった。
決定稿まで進んだ後で、プロダクションがマルチクリエイターとして売り出したい人が脚本も書けることにしたいと言われた時には、なぜか抵抗することもなく「ギャラさえもらえれば」とすぐにゴーストになるのを承諾した。
その後、戯曲の話があり、今度こそはと思って書いたら、スポンサーになってくれる予定だった原作者の夫が逮捕されて全部立ち消えになった。
などなどが続いて、結局、脚本のクレジットに自分の名前が出ている映画はこれまで1本きりだ。
宏道が、一線で活躍できるようになるのに必要なのは才能や実力ではなく「運だ。それだけだ」と言い切るのは、骨まで響いた。アイロニーの意味合いが大きいセリフだったかもしれないが、僕は自分ごととして、しみじみとこたえた。
もう一つだけ。
冒頭、酒匂役のとみやまあゆみが登場して机に向かう時、右手に手袋をしているのに気づいて、僕はかなり動揺した。ここまで書いておいてなんだが、冒頭でいきなり泣きそうになったので、実は今回の舞台を冷静に見られたかどうか自信はあまりない。
酒匂の手袋は、ふつうの手袋ではない。小指だけを残して、他の指の部分は全てハサミで切ってある。
鉛筆で書き、原稿用紙に芯の顔料を文字として残すうち、小指の付け根から手首にかけてのもりあがりの部位(小指球)が紙に直接当たって擦れ、汚してしまうのを防ぐためだ。小指以外の指の部分を全部切れば、手袋をしたまましっかり鉛筆が持てる。
僕の場合は、薄い白手袋だった。学校を卒業して下働きを始めた頃に教わった。ペラ(二〇〇字詰原稿用紙)を前にして、小指だけ残した白手袋をはめると、プロの脚本家に近づけた気がして引き締まった。
ただしそのまま、こども向け5分枠アニメの下書きの、ト書きの最初の1行が、一晩かけても出てこなかったけれど。
ワードプロセッサを誰だったかに譲ってもらった後も、しばらくは手書きだった。手袋は何度も洗濯してるうちに鉛筆の顔料と汗が浸み込んで取れなくなり、全体がくすんだ灰色になってから買い換えた。
書けば書くほど脚本が分からなくなる不安や恐怖。また怒られるだろうけど何を怒られるのかが分からない、「シナリオの体になっていない」はもう百回言われたとして「夫婦の会話が書けてない」なのか「緩急がない」なのかと、そっちばかりに想像が忙しくなる怯え。徹夜で書いてもまた翌朝までに書き直しを命じられるのが分かっているので、今のうちに寝ておこうか、でもそれで間に合うのかと悩む夜明け前。あの頃の僕の黒い怨念を、誰よりも知っていたのはあの手袋だった。
でも僕と酒匂では、きっと思いは似ていて違うと思う。
酒匂は怒り、憎しみを内に秘めて脚本を書き続けるが、原稿に書きつけた文字は汚さない。彼女がはめる小指だけ残した手袋は、「言葉が美しければ、残るものは残ると思うんだ」と話してくれた、尊敬する先輩の尊厳を守るためなのだ。
















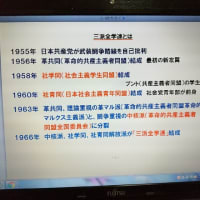
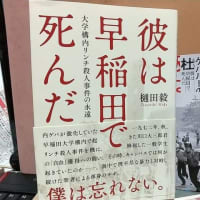

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます