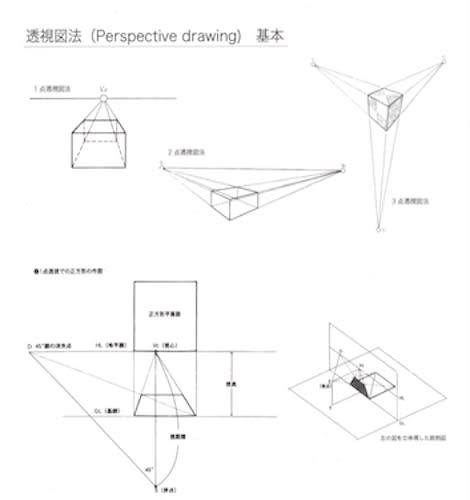第5回壁画技術講座 5月28日(土)
講師 : 米谷 和明 先生
第4回に引き続き、イラストレーションの模写を行う講義。
見本となるイラストは、佐藤邦雄さんの猫の絵です。
米谷先生に、この絵の描き方の手順を概略で教えて頂きました。

(米谷先生の作品。5時間くらいで描いて頂きました。)
手順1 ベースとなる中間調子を地塗りする。
手順2 2階調でおおまかに陰影をつける。
手順3 毛並みを描いていく。陰の焦げ茶の毛並みと、ホワイトのハイライトの毛並み。
手順4 同時に細かい描写をして仕上げていく。
手順1では、中間調子となるクリーム色を調色するのに、時間がかかりました。明るすぎず、暗すぎず、程よい調子の色を素早く調色したいものです。
手順2で、さらに苦戦してしまいました。2階調化させるのに、陰の明度を落とした、暗い色を調色する必要があるようです。暗い色を作るために、黒を混色するのですが、思い切って黒を混色して、陰の色を作るようにします。
手順3、鼻の色、耳の色、目の下の微妙な赤みを出しながら、いよいよ毛並みを描いて行きます。これが、簡単そうで難しかったです。うまく、しなやかな毛が描けません。
米谷先生のアドバイス、「毛並みを描く時は、塗料をつけた筆によく水分を含ませて描くようにする」とのこと。この水を多く含んで描く事を、「水をシャブシャブにして塗る」とか「シャブクする」といって表現しています。

(米谷先生の作品のアップ。毛並みが「ふわっ」としていて良い感じです。眼球や汗の粒も丁寧です。)
早速やってみましたが、よくわからず、途中で手が止まってしまいました。米谷先生に、「とにかく全部、毛並みを描き切ってみなさい。描ききったら、何か掴めるはずだよ」と励まされました。そこで、とにかく、ひたすら毛を描いて行きました。その間に気がついた事を挙げてみたいと思います。
1.手首をしなやかに使って、リズムよく筆を払う。
2.毛並みの生えている目を読む。
3.毛並みをハッチングすることで調子が生まれる。
4.毛足の長さの強弱で調子を出して行く。
5.基本的には、左右対称なので、左右を振り分けて、手を入れて行く。
6.筆を替える。
などなど。
米谷先生のアドバイス通り、毛並みタッチをやり切ってみると、多くの事に気がつきました。私の手順で行うと、ハイライトでホワイトの毛並みタッチが多くなってしまい、若干『粉っぽい』状態になってしまいました。地塗りのクリーム色の毛並みを増やして、調子を整えました。

(アトリエでの制作風景。みんな、いい感じに仕上がって来ました。同じものを描いても、各自、微妙なニュアンスの違いがあって、個性を感じます。)
by Amano










 (講評での球の展示)
(講評での球の展示)