 深夜、台風13号による大雨が降る。現在、ここ千葉の内陸部でも1時間あたりの降雨量は50mm近く、最終的には150mmが予想される。
深夜、台風13号による大雨が降る。現在、ここ千葉の内陸部でも1時間あたりの降雨量は50mm近く、最終的には150mmが予想される。ところでこのごろ、わたしはやたらと本を読んでいる。
わたしは、車はめったに洗わず、4つタイヤがあって前に動きゃあいいし、ゴルフなんて営業上の接待は別にしてあんなに金掛けてやる人の気がしれない。着る洋服は高級そうで(!)安物の既製品で事足りる。おいしい食べ物なんて、探す気もないし店へ行く気にもなれない、おにぎりで十分、それでわたしは飽きない。わたしにしてみれば、味はともかく腹いっぱい食べれば満足する戦後のあの時代の田舎の農家育ちのDNAが自覚されてくるこの頃だ。
そんなわたしにとって、本は唯一の道楽だ。これにしたところで突然変異なのか親譲りでもなく、身内にもこんな趣味嗜好の持ち主はいない、わたしは異人種にちがいない。たぶん、わたしの周辺、交友関係、仕事上の仲間にもいないはずだ。
千葉そごうの三省堂書店で本をまとめ買いしたのが、8月も末のことだ。「吉本隆明」総特集の月刊誌8月臨時増刊号 ‘現代思想’ は相変わらず難解な内容だが、吉本隆明氏にはいつもながら精神的な慰撫をもとめて読むことになっている。
島木健作の ‘生活の探求2’ は1の後編だが、戦前、昭和初期の埼玉の農村社会を背景にしている、随分昔のように感じるが、今でも農村の耕作の場では同じ百姓の意識が連綿と底流としてあると言える、わたしの農村出身の意識も刺激されて面白い。この長編小説は長い間食わず嫌いであったのだが、中身はまじめでまとまっており、出版当時はベストセラーになったということにうなずけるものを感じる。
以前読んだ、アララギ派の歌人長塚節の小説 ‘土’ は同じ関東の茨城県を舞台にした農村小説だが、こちらは移りゆく四季の自然の風景、農民の心情、それに情景をとらえた好編であった。
次の門田隆将の ‘なぜ君は絶望と闘えたのか’ はあの広島高裁で差し戻しの死刑判決のあった原告側本村洋の話、彼が育った北九州市にわたしもわずかながらも土地鑑がある。この本で初めて知ったのだが、これからという人生の青春の中学生のころから難病に発症し入退院を繰り返し、それが今でも続いている本村氏の厳しい現実におもわず息をのむ。ことの詳細は、なんどもブログで紹介しているので今回は省略する。
ここで注意を!、この本は感動のあまり落涙のおそれがありますので自宅でお読みください。これは今でも書店の店先で平積みされて売れ続けているそうだ。
角川文庫の斎藤充功著 ‘陸軍中野学校の真実’ は市川雷蔵主演の大映映画のDVD[陸軍中野学校]シリーズを見た際に本書の存在を知った。インテリジェンス、スパイ養成学校のその後の生き証人を精力的に追いかけたもの、戦後にもその生き延びた卒業生は一種の人材供給源となっている現実をしるす。社会に隠蔽された存在を明らかにするノンフィクション。
川端康成の ‘山の音’ は今まで敬遠していたのだが、ある意味深刻な老人の心境小説である。読後感じたのは、これは川端康成の第一級の小説だと再認識したものである。
楡周平の ‘プラチナタウン’ について、著者は以前このブログでも取り上げたが同郷出身の人でサスペンスものから中間小説に著作傾向が移ってきているらしい。内容はわがふるさと岩手県南部・藤沢町の実際のことを面白おかしくカリカチュア(戯画)したもの。わたしはそれに惹かれて一日で読み終えた(祥伝社 ¥1,890.)。だけれど、現在住んでいる町民はこれを読んでどう感じるだろうか。無表情で苦笑いし、意外とあっけらかんとするのかな。人間がおとなしいから。
この春、観光資源であるサファリパークがオープンして町の財政事情が少しでも良くなればいいのだが。
岩手藤沢 野生の王国 岩手サファリパーク
余談になるが、実は現町長はわたしにとって遠い親戚に連なる人である。
文春新書の ‘零戦と戦艦大和’ は太平洋戦争の武器生産技術がいかに平和な戦後社会の経済発展の基本になったかを論じている。
最近の本では、池谷祐二/木村俊介の 文春単行本 ‘ゆらぐ脳’ であるが、これは現代の最先端科学である難しい脳科学の研究にまつわる話だが、未知の領域を率直でわかりやすく表現していこうとする跡がほの見える、好印象の少壮学者である。この姿勢があれば、視野の狭い独りよがりな学者馬鹿にはならないだろう。
読書範囲がわたしのキャラクターのごとく散らばりとりとめがないが、日常の時間の合間を縫うようして、以上のように8冊を順に読了した。割と今回は集中して良書を読んだ気がしている。
























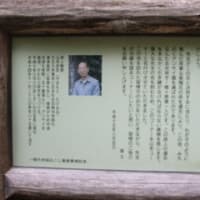









先日、きっこのブログで拝見しまして、何となく近所かな、地域問題、短歌をおつくりになる・・ということで勝手にリンクさせていただきました。
僭越ですが、流れるようなセンテンスと文意、ITずれしない記述に惹かれました。
この日のわたしの記事は、結果的には、残念ながら総花的になりましたが、実のところ、単なる内容紹介、いわゆる読書感想文にはしたくありませんでした。
ここ一ヶ月は、しばらくは植物ネタが続きますが、我慢していただくか、無視してくださるよう願います。
地域でのボランティア活動も、一度わたしのなかで
整理、総括して書き込む予定です。(生活のためにはこの無償の行為には、今までのようには時間をさけませんので)
わたしも俳句を詠みますが、いつも突発的です。その際はUPしますので、ご感想をお寄せください。
いろいろ書き込んで失礼に感じたでしょうが、PC、ITよりも日常の感覚を大事にして、物事はすべからく、まずアナログありきと思います。
これからも、内野さんのブログに再三おうかがいしますので、今後ともよろしく願います。
それでは、またまた、また。
折り返し、即、貴ブログへコメントを書き込みましたが、なんのリアクションもないままのようですので、大変恐縮ですが、“内野光子ブログ”へのリンクを削除させていただきます。
Webであれなんであれ、その内容、主義、主張がどうであれ、わたしはもともとアナログで育ってきた世代、今の世代のようにデジタル万能などと思っておりません。地域ボランティア活動、短歌、教養がどうだとか、そんなに意味を持ちません。ブログでも、日常の規範・ルールが第一といつでも考えております。
相互交信不可、貴ブログへの連絡手段がないので、あらためてここにお知らせしておきます。
以上ですが、あしからず。