日本国債の信用力、中国を下回る
こっちが戦いたくなくても向こうが戦いを挑んでくる以上、ボクはしにましぇん!とか精神論を言ってるだけというわけにはいかない。現実とは辛く苦いもののようだ。
経済なんてどうでも良いって思う反面、今すぐ経済から離れるなんて到底ムリで、だから軟着陸するまでは日本の負の歴史を少しずつ精算していかなければならないと思う俺がいる。可能性は農本主義にあるとTさんと一致。
今後、日本ではどのような教育が望ましいだろうか。妙な平等主義はおかしいと思うけど、あまりに競争主義なのも考えもの。競争とは勝ち目がある場合のみやるべきであって、勝ち目がないなら勝てるステージを作っていくのが政治だと思う。
日本の中だけで競争していれば良かった時代から、競争率が10倍にも20倍にも膨れ上がるのがグローバル時代だと思う。勝てる人は勝てる。負ける人は負ける。何百人に一人の勝者を創り上げるために何百人という敗者を作るのが教育だ。どんな教育を施そうとも、現行の経済システムではそうせざるを得ない。
しかし、敗者がそのまま人生終了で良いのか?という疑問は持っている。負けたらお終い、という社会ではなく、せめて国内ではみんなで負けても良いのかもしれないじゃんね、とも思うわけだ。
それを妙な平等主義と一緒にされては困るのだが、勝ち負けという相対的な価値観だけを頼りにする社会の在り方から、競争するステージの多様性を創出することによって、誰もがそのステージの勝者になりうる社会の在り方へと移行してゆくことを俺は望む。人間社会のコンパニオンプランツだ。
弱肉強食でいいんだよ。
でも、場所場所によって弱者と強者が入れ替わり、連続性の中では弱者も強者も無いんだよっていうことを忘れたくない。特に、自分は負けている、とか、お前は負け組だ、とか、そういう無意味な価値観の中だけに教育が存在してしまうのは好ましくない。
勝ち負けは必要だ。勝ち負けは存在する。弱肉強食は自然の摂理だ。しかし、君が戦える場所はそこだけか?そこで負けたことが君の全てか?他に勝てる場所はあるんじゃないのか?君は雑草か?害虫か?益虫って本当に勝ち組だけか?
というステージを用意していきたいものだ。紋切り型の教育は反対。それが競争主義であろうと平等主義であろうと。
ただし、狭小的な利益ではない、一定水準・国策レベルでの国益を追求する紋切り型は大切だと思う。義務教育はガチガチの型に嵌めていいだろう。そこから這い上がれる一部の勝者に対外的な国益を担ってもらい、敗者は別の勝者になることで国内の国益を担う。
能力の違いを差別的に扱うか、差異だと認めるか、能力の差異による享受可能な利益を差異と取るか差別と叫ぶか。
自由の中で活かし合う社会。新・社会主義ということで(笑)
そのためにどうするかということなんだけど、お金を食べ物に交換して生きていく生き方では、どうしてもお金=生きる、になりがちだ。なるべくお金と生きるは距離を置くべき。そうすることで心に余裕が生まれる。
10年後、中国とインドを足しただけで24億人だ。日本は1.2億人。単純計算、20倍以上の倍率で多国籍企業の中の一部勝ち組の椅子を取り合う。20人のうち19人は効率化されたシステムの部品で終わる。
こう考えるだけで俺はもう降りるわ、ってなってしまう。称え合うように1人を押し上げられるなら喜ばしいものであるが、そうなるためには余裕がなきゃね。そこで勝ち残れるかどうかで、人生の全てが決まると思ってしまったら、ある程度汚いことしてでも勝ち残ろうとしちゃうじゃん。24億人はそういう思いで挑んでくると思うんだよね。
闘士を燃やせる人が育つ環境と、そうじゃない人でも戦える環境を併設するような社会。んー。どんな社会だろうなー。
地域の特色、地域内貨幣、地域間貨幣ギャップ、その辺にヒントがありそうな気がするんだよなー。
世界に通用する貨幣で対外競争し、地域間為替ギャップで地域の特色をステージ化する。そんな感じ。
債券の信用力を表すクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、日本国債の保証料率が急ピッチで上昇している。直近では1.5%台を付け、わずかながら数字上は中国にも劣る信用力と評価された。社会保障と税の一体改革など、財政再建への取り組みが遅れれば、欧州にかかる市場の圧力が日本にも及びかねない。
CDSは債券を発行する政府や企業の資金繰りが滞った場合に損失額を補填する金融商品。発行体の信用力が低ければ低いほど、保証料率が上がる仕組みだ。
日本国債の保証料率が目立って上昇し始めたのは昨年末からだ。金融情報会社マークイットによると、昨年12月上旬には5年物国債の保証料率は1.2%台だったが、11日には1.5%台にまで上昇。東日本大震災後の1.4%を上回る水準となった。
この間、中国国債の保証料率はほぼ横ばいだった。足元では1.48%で、5カ月ぶりに日本国債の保証料率を下回っている。欧米系の格付け会社は日中の国債をほぼ同水準にしているが、CDS市場に限ってみれば、日本国債の評価は中国国債に劣る。
日本国債の保証料率が上昇したのは、一体改革を巡る与野党間の協議が難航すると予想されているからだ。「議論の行方次第では1~3月中に日本の国債格付けが見直される」(バークレイズ・キャピタル証券の江夏あかねクレジットアナリスト)とみる市場関係者も少なくない。
もちろん、欧州各国の国債と日本国債の保証料率にはかなりの開きがある。日本国債が1.5%台なのに対してスペイン国債は4%、イタリア国債は5%を超える。金融市場にほとんど流通していない中国の国債と日本国債を一律に比較するのにもやや無理がある。
ただ注意しなければならないのは、保証料率が示すのは海外の投機筋の評価という点だ。欧州各国を債務危機に追い込んだ海外の投機筋が、先進国で最悪の財政状況といわれる日本を「次の標的に据えた」(メリルリンチ日本証券の藤田昇悟チーフ債券ストラテジスト)とも映る。(平本信敬)
こっちが戦いたくなくても向こうが戦いを挑んでくる以上、ボクはしにましぇん!とか精神論を言ってるだけというわけにはいかない。現実とは辛く苦いもののようだ。
経済なんてどうでも良いって思う反面、今すぐ経済から離れるなんて到底ムリで、だから軟着陸するまでは日本の負の歴史を少しずつ精算していかなければならないと思う俺がいる。可能性は農本主義にあるとTさんと一致。
今後、日本ではどのような教育が望ましいだろうか。妙な平等主義はおかしいと思うけど、あまりに競争主義なのも考えもの。競争とは勝ち目がある場合のみやるべきであって、勝ち目がないなら勝てるステージを作っていくのが政治だと思う。
日本の中だけで競争していれば良かった時代から、競争率が10倍にも20倍にも膨れ上がるのがグローバル時代だと思う。勝てる人は勝てる。負ける人は負ける。何百人に一人の勝者を創り上げるために何百人という敗者を作るのが教育だ。どんな教育を施そうとも、現行の経済システムではそうせざるを得ない。
しかし、敗者がそのまま人生終了で良いのか?という疑問は持っている。負けたらお終い、という社会ではなく、せめて国内ではみんなで負けても良いのかもしれないじゃんね、とも思うわけだ。
それを妙な平等主義と一緒にされては困るのだが、勝ち負けという相対的な価値観だけを頼りにする社会の在り方から、競争するステージの多様性を創出することによって、誰もがそのステージの勝者になりうる社会の在り方へと移行してゆくことを俺は望む。人間社会のコンパニオンプランツだ。
弱肉強食でいいんだよ。
でも、場所場所によって弱者と強者が入れ替わり、連続性の中では弱者も強者も無いんだよっていうことを忘れたくない。特に、自分は負けている、とか、お前は負け組だ、とか、そういう無意味な価値観の中だけに教育が存在してしまうのは好ましくない。
勝ち負けは必要だ。勝ち負けは存在する。弱肉強食は自然の摂理だ。しかし、君が戦える場所はそこだけか?そこで負けたことが君の全てか?他に勝てる場所はあるんじゃないのか?君は雑草か?害虫か?益虫って本当に勝ち組だけか?
というステージを用意していきたいものだ。紋切り型の教育は反対。それが競争主義であろうと平等主義であろうと。
ただし、狭小的な利益ではない、一定水準・国策レベルでの国益を追求する紋切り型は大切だと思う。義務教育はガチガチの型に嵌めていいだろう。そこから這い上がれる一部の勝者に対外的な国益を担ってもらい、敗者は別の勝者になることで国内の国益を担う。
能力の違いを差別的に扱うか、差異だと認めるか、能力の差異による享受可能な利益を差異と取るか差別と叫ぶか。
自由の中で活かし合う社会。新・社会主義ということで(笑)
そのためにどうするかということなんだけど、お金を食べ物に交換して生きていく生き方では、どうしてもお金=生きる、になりがちだ。なるべくお金と生きるは距離を置くべき。そうすることで心に余裕が生まれる。
10年後、中国とインドを足しただけで24億人だ。日本は1.2億人。単純計算、20倍以上の倍率で多国籍企業の中の一部勝ち組の椅子を取り合う。20人のうち19人は効率化されたシステムの部品で終わる。
こう考えるだけで俺はもう降りるわ、ってなってしまう。称え合うように1人を押し上げられるなら喜ばしいものであるが、そうなるためには余裕がなきゃね。そこで勝ち残れるかどうかで、人生の全てが決まると思ってしまったら、ある程度汚いことしてでも勝ち残ろうとしちゃうじゃん。24億人はそういう思いで挑んでくると思うんだよね。
闘士を燃やせる人が育つ環境と、そうじゃない人でも戦える環境を併設するような社会。んー。どんな社会だろうなー。
地域の特色、地域内貨幣、地域間貨幣ギャップ、その辺にヒントがありそうな気がするんだよなー。
世界に通用する貨幣で対外競争し、地域間為替ギャップで地域の特色をステージ化する。そんな感じ。










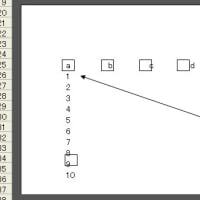
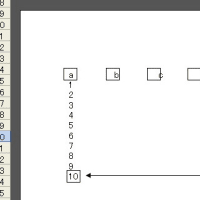
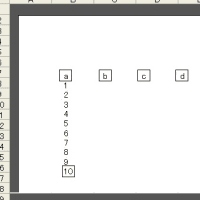





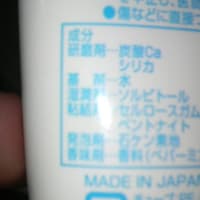
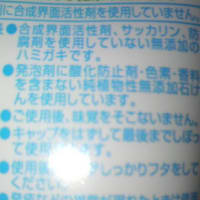
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます