相も変わらず文化の日を迎えると疑問符が湧く。なぜ春は湧かずに秋に湧くかは、察しの通りだ。より秋の方が文化意識が高いせいだろう。何を言わんかといえば、叙勲や褒章制度に対する違和感だ。お受けする方々に快くお祝いを申せばよいものを、平民たるわが心のどこかに、このシステムへの違和感が子どものころからある。このごろは等級が付されることはなくなったが、等級が付くことの違和感よりもそのものへの違和感の方がもともと強くあった。このことはずいぶん以前、2005年に「叙勲から考える」で触れた。あらためて当時の日記を読んでみて、今も思いは変わらないと確認したしだいだ。
ちかごろ義父が高齢者叙勲というものを受けた。「何それ」と思うほど家族に公に携わった人がいないとさっぱりなモノだ。逆に言えば高齢者叙勲など無意味ではないかと思う人も多い。この高齢者叙勲も誰でも受けられるものではない。「高齢者叙勲は、春秋叙勲で受章していない功労者を対象として毎月1日に発令され、年齢満88歳に達したのを機に叙勲される」。もちろん公の場で功績があった方を対象としているから高齢者叙勲は対象者が限定されてくる。ほとんど公務員であって、ケースとして学校長を勤めた方が多い。「なぜ、高齢者叙勲や死亡者叙勲に学校の校長を経験した人が多く選ばれる」という質問が知恵袋にも登場している。しかしそんなことより、「春秋叙勲で受章していない功労者を対象」にしているところに問題がある。それなら春秋叙勲で叙勲対象にするべきで、88歳になったからといって叙勲することの意味がさっぱりなのだ。いいや88歳にならなくても死亡した段階にこうした方々は死亡者叙勲にも対象になるから当たり前のように叙勲されることが約束されているようなもの。そのいっぽうで春秋に叙勲される人もいる。そしてどうみても春秋叙勲者は高齢者叙勲や死亡者叙勲よりも格が高く見える。もちろん春秋叙勲は推薦する側の意図によるもので、国民的視点よりもいかに〝著名であったか〟といったなんとも不可思議な基準が基となる。叙勲されるにも「なぜあいつが春秋叙勲なのか」などという思いが浮かぶのは必然である。
叙勲と同様に褒章も不可思議だ。とくに藍綬褒章。「公衆の利益を興し成績著明なる者又は公同の事務に勤勉し労効顕著なる者」に授与されるという。わけが解らないのが例えば国勢調査員とか農林業センサス調査員というやつ。長年そのに任に当たられて受けるというケースがあるのだろうが、そもそもこういう調査員を長年継続して行っているというのが意味不明なのだ。地域形成という面では、継続性よりも交代してその意図をみなが共有することの方が大切だ。継続されて人にはない苦労をされたということは言えるのかもしれないが、その背景になんらかの理由もある。なぜ継続してその任を受けてきたのか、むしろその背景にこそ問題を感じる。長年の蓄積といえば普通に働いている人たちにだっていくらでもいる。それが公という場にどれほど貢献しているかなどと言うことは、あくまでも表面上のことに過ぎない。それを公に公表して格付けするようなものに、どうしても納得いかないのである。たゆまなく趣味のごとく働いているわが社の社員を見ていると、彼らが百パーセントそのような立場にたどりつくことがない現実と比較して哀しい公を感じるわけだ。もう一つ。とくにこの叙勲・褒章には女性が対象になることが極端に少ない。なぜにらば女性の地位が低いからではない。女性は家庭のために人生を尽くされる方が多いからだ。きっと多くの叙勲・褒章を受けられる方たちの背景に、女性の力がなかったはずがない。そういう意味でも確かにその個人が継続や業績の原点にはあるが、埋もれる現実をより一層際立ててしまうようなひとの評価は、まったく意味がないことだとわたしは思う。



















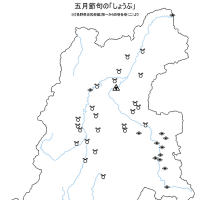







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます