「分水工を探る」なども含めて、最近は西天竜のことについてよく触れている。天竜川に対して西にある川だから西天竜と名づけられたわけだが、「川」と言えば普通はそこそこの大きさの川をイメージする。ところが国土交通省所管の河川にしても一級河川と言われる川には、ずいぶんと川幅も狭く、水量の乏しい川も少なくない。それにくらべたら西天竜もしかり、安曇野を流れる十ケ堰もしかり、ようは農業用用水路にそうした一級河川以上の規模を持つものがいくつもある。
かつては小さな農業用用水路も小川と言われて「川」というイメージが一般にあったと思う。コンクリートで覆われるようになると同じ水量を狭くても流せることもあって、川幅は狭まってくるのだが、そういう姿が「川」というイメージをこれらの水路から取り除いていったに違いない。いや「川」と呼ばれるべきものでも人目から遠ざけられていき、「○○川はどこを流れているのですか」と聞いても、その近在に住んでいながら答えられない人も多いことになる。伊那市の中央を流れる小沢川の北側には鳥谷川という小さな「川」がある。一応一級河川ではある(一級ではなく準用河川でした)ものの、山寺区に入って地上からところどころ姿を消すようになると、その行き先を探すのがやっかいなことになる。都市部に入り込んでくる川というものは、きっとかつては人々の暮らしに関わっていただろうに、いまや遠ざけられた存在で認識すら怪しくなるのだ。低位にあって水が集まってくるようなところなら川とのかかわりは大きい。いっぽう台地上とか扇状地上のような立地では川とはもともと縁遠い。そんな縁遠い地にいきなり水がやってくればそれは「川」であることに違いはないのだ。
さきごろ仕事の打ち合わせの中での話し。ある農業用用水路を整備したのだが水路の幅はせいぜい広いところでも1メートル程度。狭いところはいわゆる蓋付きの側溝で幅も50センチ程度。ここまで書いてきた捉え方でいけば「川」というよりは「用悪水路」がイメージし易い。打ち合わせの中でこの場合「川と言ってはいけないんでしょうね」と相手方の上司が言うのだが、同席した部下は盛んに「川」という言葉を使われる。なぜ「川と言ってはいけないんでしょうね」と言うかといえば、農業用用水路を整備したのに「川」を整備したと揚げ足を取られたら問題のネタにもなりかねないというわけだ。しかし、そもそもが農業用用水路も「川」であることに違いはない。「川」ではなければなんと呼ぶかといえば「水路」ということになるのだろうが、わたしは「川」と呼ぶ人にむしろ心引かれる。この時代では道が溢れるほどあってそこには側溝が当たり前のように付属する。その路面の排水専用なら「側溝」という人もいるだろうし、そこに絶えずどこからともなく水が流れてくれば「水路」という人もいる。その形態や利用方法によってそこに暮らしている人々もさまざまに捉えるだろう。きっと「川」を頻発した方も、道路側溝のようなものを「川」とは呼ばないかもしれない。
現代人は「川」と呼ばないこうした水路を「川」と呼ぶに値するようなかかわりを、かつての人々は体現していた。西天竜について最近文献をあさっている。ところが意外にも西天竜に関する記述はとても少ない。歴史的な部分では市町村誌や区誌といったものに記述をみるが、西天竜に関わる暮らし上のことはほとんど公なものには登場しない。そもそも郷土研究と言われる歴史だけではなく社会的な部分も扱っているようなものにも文献を探すのは難しいのである。この地域の郷土研究といえば上伊那郷土研究会がある。その発行雑誌『伊那路』に探してもほとんど「西天竜」というタイトルはなく、文中に記載があるかどうかという程度。西天竜よりは新しい時代に開発された三峰川総合開発に関わるものはあるものの、西天竜はほとんど対象にされてこなかったのだ。唯一タイトルにあったのが竹入弘元氏が昭和41年11月号に発表された「西天竜-その恩恵と哀話-」である。随想的なこの文の中には、とても興味深い体験談がたくさん記述されていて、こういうものが後に大きな財産になるとつくづく教えられたのである。このことは日を改めて書くことにする。
続く
かつては小さな農業用用水路も小川と言われて「川」というイメージが一般にあったと思う。コンクリートで覆われるようになると同じ水量を狭くても流せることもあって、川幅は狭まってくるのだが、そういう姿が「川」というイメージをこれらの水路から取り除いていったに違いない。いや「川」と呼ばれるべきものでも人目から遠ざけられていき、「○○川はどこを流れているのですか」と聞いても、その近在に住んでいながら答えられない人も多いことになる。伊那市の中央を流れる小沢川の北側には鳥谷川という小さな「川」がある。一応一級河川ではある(一級ではなく準用河川でした)ものの、山寺区に入って地上からところどころ姿を消すようになると、その行き先を探すのがやっかいなことになる。都市部に入り込んでくる川というものは、きっとかつては人々の暮らしに関わっていただろうに、いまや遠ざけられた存在で認識すら怪しくなるのだ。低位にあって水が集まってくるようなところなら川とのかかわりは大きい。いっぽう台地上とか扇状地上のような立地では川とはもともと縁遠い。そんな縁遠い地にいきなり水がやってくればそれは「川」であることに違いはないのだ。
さきごろ仕事の打ち合わせの中での話し。ある農業用用水路を整備したのだが水路の幅はせいぜい広いところでも1メートル程度。狭いところはいわゆる蓋付きの側溝で幅も50センチ程度。ここまで書いてきた捉え方でいけば「川」というよりは「用悪水路」がイメージし易い。打ち合わせの中でこの場合「川と言ってはいけないんでしょうね」と相手方の上司が言うのだが、同席した部下は盛んに「川」という言葉を使われる。なぜ「川と言ってはいけないんでしょうね」と言うかといえば、農業用用水路を整備したのに「川」を整備したと揚げ足を取られたら問題のネタにもなりかねないというわけだ。しかし、そもそもが農業用用水路も「川」であることに違いはない。「川」ではなければなんと呼ぶかといえば「水路」ということになるのだろうが、わたしは「川」と呼ぶ人にむしろ心引かれる。この時代では道が溢れるほどあってそこには側溝が当たり前のように付属する。その路面の排水専用なら「側溝」という人もいるだろうし、そこに絶えずどこからともなく水が流れてくれば「水路」という人もいる。その形態や利用方法によってそこに暮らしている人々もさまざまに捉えるだろう。きっと「川」を頻発した方も、道路側溝のようなものを「川」とは呼ばないかもしれない。
現代人は「川」と呼ばないこうした水路を「川」と呼ぶに値するようなかかわりを、かつての人々は体現していた。西天竜について最近文献をあさっている。ところが意外にも西天竜に関する記述はとても少ない。歴史的な部分では市町村誌や区誌といったものに記述をみるが、西天竜に関わる暮らし上のことはほとんど公なものには登場しない。そもそも郷土研究と言われる歴史だけではなく社会的な部分も扱っているようなものにも文献を探すのは難しいのである。この地域の郷土研究といえば上伊那郷土研究会がある。その発行雑誌『伊那路』に探してもほとんど「西天竜」というタイトルはなく、文中に記載があるかどうかという程度。西天竜よりは新しい時代に開発された三峰川総合開発に関わるものはあるものの、西天竜はほとんど対象にされてこなかったのだ。唯一タイトルにあったのが竹入弘元氏が昭和41年11月号に発表された「西天竜-その恩恵と哀話-」である。随想的なこの文の中には、とても興味深い体験談がたくさん記述されていて、こういうものが後に大きな財産になるとつくづく教えられたのである。このことは日を改めて書くことにする。
続く



















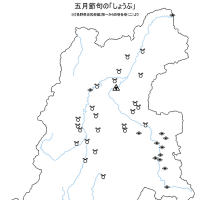







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます