わたしの仕事は、いわゆる「設計」にあたる。設計しているものは土木系。今でこそCADを利用し、手で線を引くことはほぼ皆無。考えてみれば、仕事についてしばらくの時代を思い出せば、今とは全く異なる環境だ。しかし、出来上がる図は、当時と変わらない。そもそもそれが今の時代に適しているかといえば、適していないのかもしれない。この構図が変われば、わたしの現役としての役目は終えるような気がする。最近は、そうした環境の進歩によって、依頼主から3D(スリーディー)で描いた図を求められることもある。いわゆる立体視できるものということになるのだろうが、座標がXとYだけではなくなる。もちろん、わたしはそうした図は今のところ描けない。
いまだ手書き時代と変わらない、というのは、図を描けば「平面図」「断面図」「側面図」といったそれぞれの方向から描いたもので校正する。ただしそれほど難しいものを対象にしていないから、「側面図」を省くことはよくある。「解かれば良い」レベルで、手を抜いていると言われればそうかもしれないが、無駄に時間を費やすことはしない。もちろん業務量が多いから、丁寧なことはしない。手書きであろうが、CADであろうが、この構成は変わっておらず、描かれた図面上の世界は、綺麗な手書きの図であれば、CADで引いた図と変わらない。だから、いまもって何も変わっていない、ということになる。しかし、そこに至までの作業は手書きとCADでは異なるのは当たり前。その世界に会社内でも、先駆けて手を出したわたしだが、もうそれから20年以上。もちろん世間のコンサルは、わたしが手を出したころには、とっくにCADを利用していたが・・・。
かつては線を引くといえば、メッシュの入った原図に線を引いた。真っ白い原図もあったが、それは平面図用で、構造物を描く際には、メッシュの入ったものを利用した。したがって1対4くらいの割合で、メッシュ入りの原図を利用した。そのメッシュとは、1ミリ単位のもので、1センチごと線は太くなっていた。さらに5センチ単位にさらに太い線が入っていた。実は、CADに変わった今も、メッシュを表示させると、手書き時代の原図と同じ世界に入れる。メッシュは、瞬時に1ミリを認識できるし、傾斜線がどのような割合で引かれているかも判断できる。ようは出来上がった図を瞬時にイメージすることができる。が、しかし、今はメッシュを表示して図を印刷して納品することはほとんどない。手書きからCADに変わっていく過程では、依頼主からメッシュがないとイメージできないといってメッシュを表示させていたが、今はメッシュがなくても、依頼主から「メッシュがない」と言われることは、めったにない。当たり前にメッシュなしの図を印刷しているのが、今である。
メッシュがあることによって、例えば水平線を1本引くといえば、メッシュに定規をあてて、横に鉛筆をスライドさせれば、容易に水平線が引けた。同じように垂直線を引こうとすれば、縦のメッシュに合わせて線を引けば容易なことだった。さらに、10分の1縮尺なら、1センチは1メートル、100分の1縮尺なら10メートルとすぐに判断できる。したがって10分の1縮尺で1メートル四方の正方形を描くには、原図と鉛筆、そして目印のない定規で簡単に描けたわけだ。同様に、CADにメッシュを表示させれば、鉛筆に代わったマウスでメッシュ上に線を引けば、同じ正方形が描けるわけで、鉛筆とマウスの違いはあっても、同じイメージで線を描いていることに違いはない、ということになる。ようは、メッシュはわたしたちの頭の中で図をイメージさせる際に、わかりやすいツール、ということになるだろう。
かつては原図を「青焼き」と称していたコピー機で印刷していた。いわゆる湿式コピーである。今では「青焼き」など見ることもなくなったが、20年前には現役だった。その機械を通して描いたものが印刷されるわけだが、濃く焼けばメッシュは強く表示され、薄く焼けば比例してメッシュは薄くなった。したがって、メッシュを薄くしたい場合は、薄く焼いたのだが、ここで人によって差異が生じる。自信のない線を引いた人の図は、比例してメッシュ以外の線も薄くなってしまう。ようは描いた線に、描いた人のこころが映りこんでしまう、というわけだ。したがって手書きの時代には、描かれた線に個人差があったことはいうまでもないし、もちろん線の引き方の上手、下手があったことも事実である。










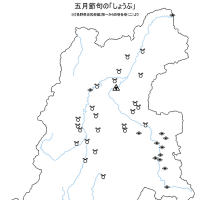
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます