
国道19号松本(南)方面、この先右手に犀川橋があり、大町へ続く

長野(北)方面、この先右手に「明科駅」がある。山裾を左手に行けば「木戸橋」
『安曇野市誌』にかかわる調査が滞っているのは、もちろん感染症のせい。このままでは何も書けないし、時だけが過ぎてしまうと思い、何でも良いから情報が欲しいし、自らその地を体感したいという思いがある。市内明科地区は、旧明科町にあたり、安曇野市の中では犀川右岸地域を主体とする、ちょっと雰囲気の違うところ。その街中を歩く催しがあったので、仲間とともに同行した。その催しの主旨は移住定住促進。今年、市には移住定住を進めるための新しい部署ができたという。とりわけ珍しい話でもないのだが、あらためて明科のマチを歩いて見て、驚きの光景を目にした。
明科といえば、国道19号線上にあり、この街中を知らない人はいないだろう、とは思うが、それは長野道が開通する前のこと。今は北信域との連絡は高速道路にとって代わられ、明科の印象も下がってしまった。もちろん国道19号への思い入れのあるわたしには、今もって「国道19号のマチ」という印象が強いが…。かつて「水郷の町」と冠していたほど、水に縁があるのは、その位置にもある。犀川へ高瀬川と穂高川が合流する位置に明科のマチはある。「水郷」とは「河川や湖沼が多くある景勝地」をいう。したがって明科の場合、河川の合流点にあるという意味で「水郷」を利用したのは言うまでもない。この先(下流)は山峡に入り、国道19号線沿いには繰り返し東電のダムが見られる。もちろんかつてはそのようなものはなかったから、犀川通船と呼ばれた水運があった。その口元にあたる明科は、千曲川でいう立ヶ花のような位置にある。この先は川幅が狭まり、長野市までの間には広い平地はない。独特な長野県らしい地形の連続。わたしにとってはこの山峡の道は、当初あまり良いイメージはなかった。初めてこの道を通ったのは、おそらく小学4年生の折の善光寺・県庁見学だっただろう。この曲がりくねった道は、車酔いをする者には好ましくない環境である。「長野は遠い」、そう思わせる原点でもある。その後この道を通るようになったのは、やはり社会人になって以降のこと。長野道が開通していなかった時代だったから、走っていて次のカーブが右か左かわかるほどだった。いまもってこの道を好んで走る理由は、そうした親しみがあるからだ。良い意味でも、悪い意味でもいろいろ経験させてもらった道である。北と南との往来だけの若いころの「明科」は通過点上にある里とヤマの境界域にあるマチという印象であったが、仕事でかかわるようになると、本城村(現築北村)や四賀村(現松本市)への分岐点であるということも知り、ますます頻繁に行き来する交差点のようなマチであることを体感したわけである。とりわけ犀川左岸側の押野や七貴、木戸橋の先の陸郷は頻繁に訪れている。そして当時の穂高や豊科といったいわゆる南安曇とは異なる、山間の過疎地のムラの姿を意識したのも、そのころ(平成10年前後)である。
さて、その明科において開かれた今回の催し「まちあるき空き家空き店舗見学会」は、既に14回を数えている。当初はまちづくり委員会による空き店舗への利用者の誘導が目的だったといい、今は積極的に行政が関わって表記の催しが行われている。その理由は、マチの中の空き家率の高さなのである。マチであったから、メインの道路の裏側に、人が通るほどの狭い路地が迷路のように錯綜している。もちろんそれほど広い範囲ではないものの、とはいえ裏路地がいまもって狭いままに存在する姿は、今回歩いてみて実感した。そしてそうした路地に表玄関を置く家がたくさんあり、そうした家々に生活感がない光景をたくさんみることができる。空き家がこれほど多いとは知らなったこと。いずれ、どこの地域でも起こりうることではあるが、とくに明科は空き家が多く、裏側の路地を歩いていると9割くらい空き家ではないのか、と思わせる。とはいえ、最後に訪れた龍門渕テラスが建つ国道ができるまでの旧道添いの本町に面した家々は、逆に空き家が1割くらいと印象を受け、結果的に車道のないところで空き家が目立っているということが実態だということはわかったが、もちろん車道が開いていても空き家がかなり存在するのも事実。わたしが盛んに役場を訪れていた平成10年ころとは、ずいぶん様子が違っているわけである。

















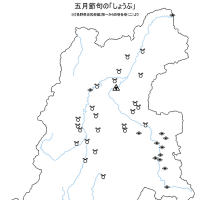









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます